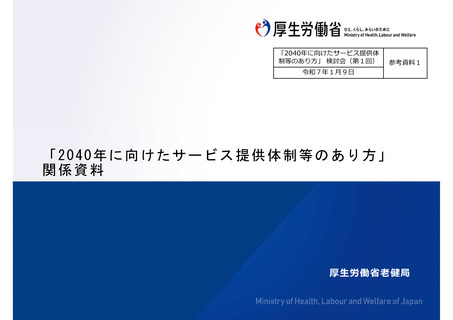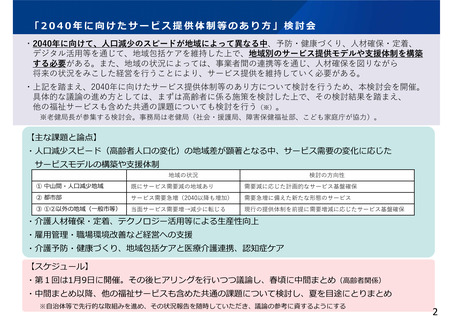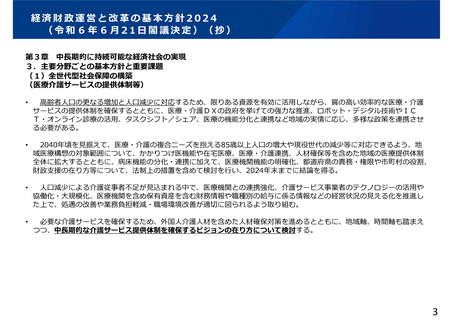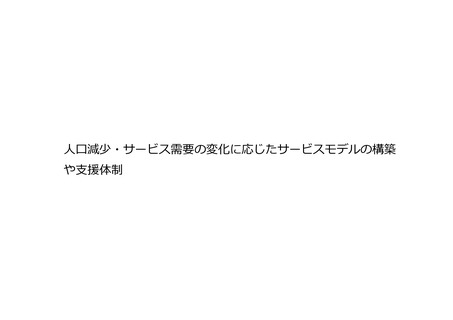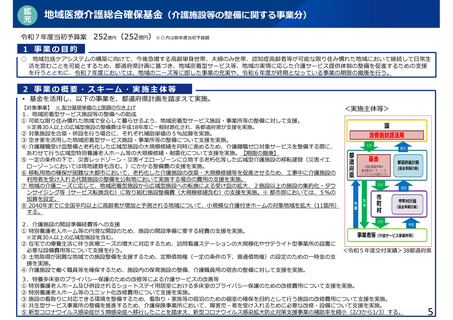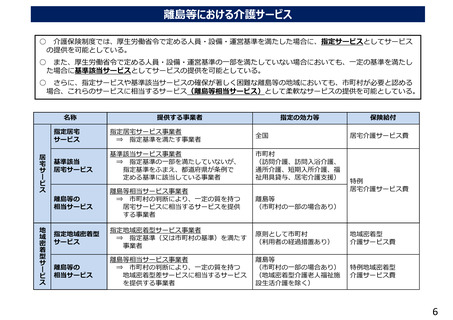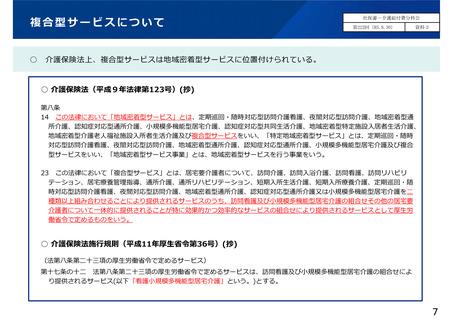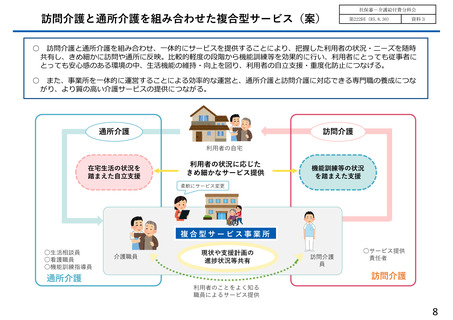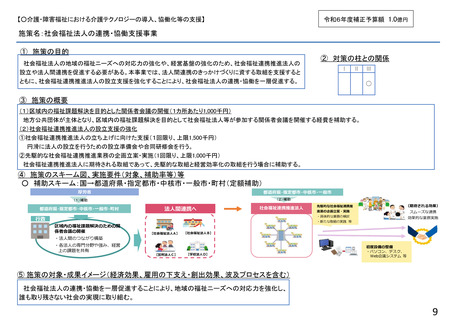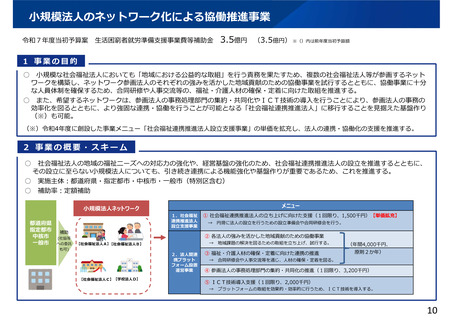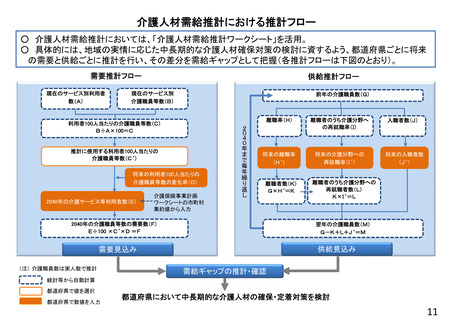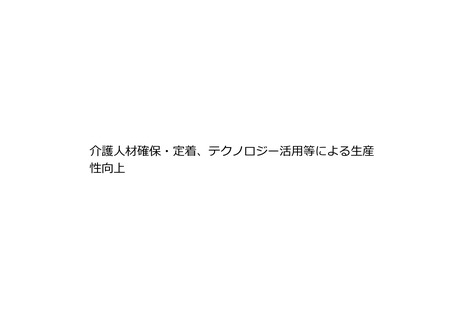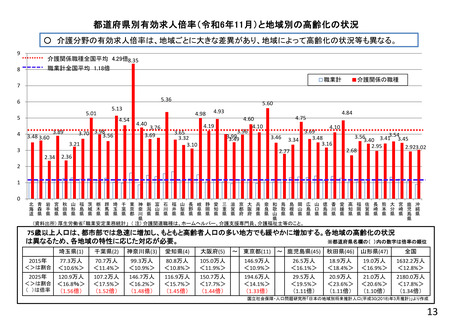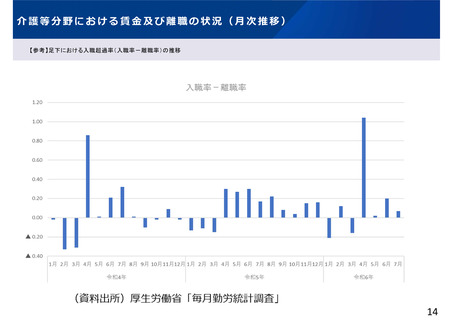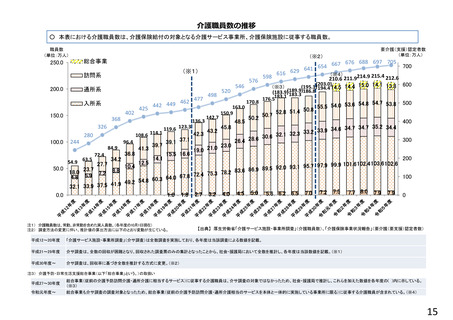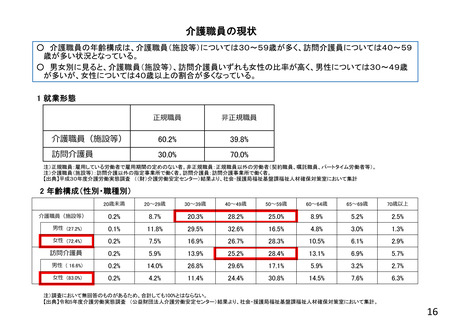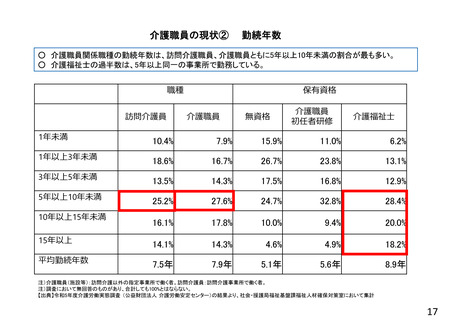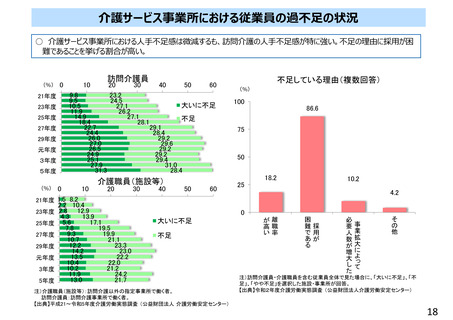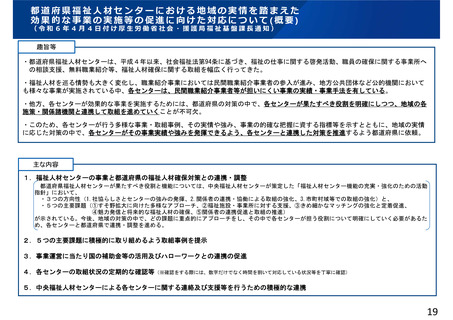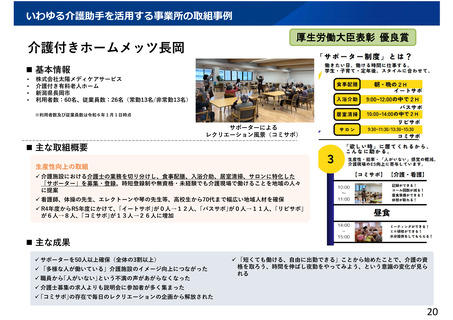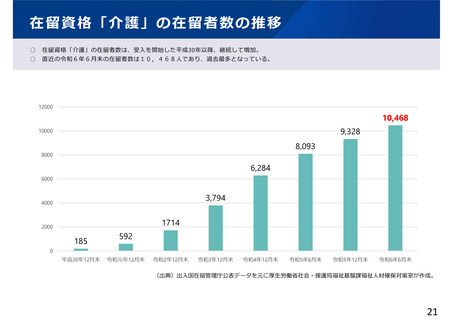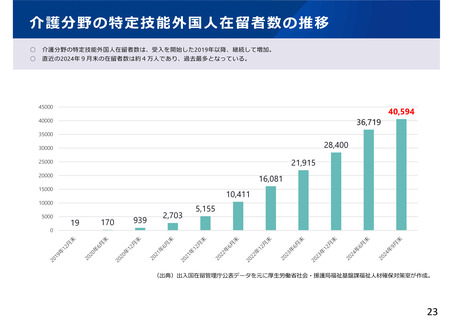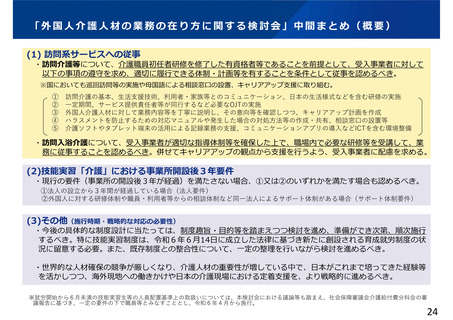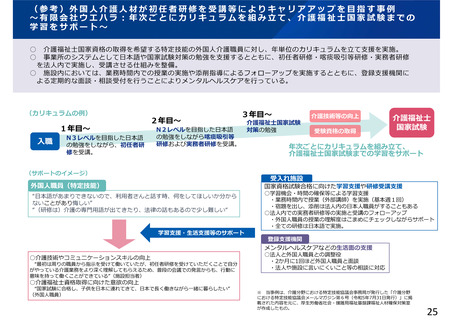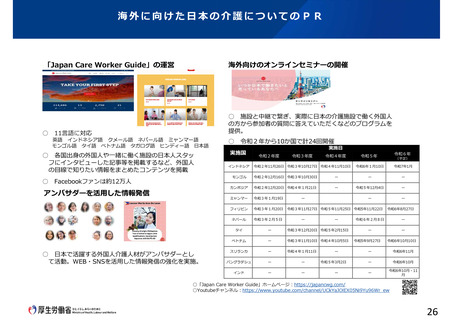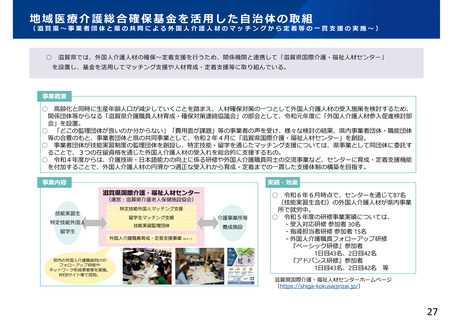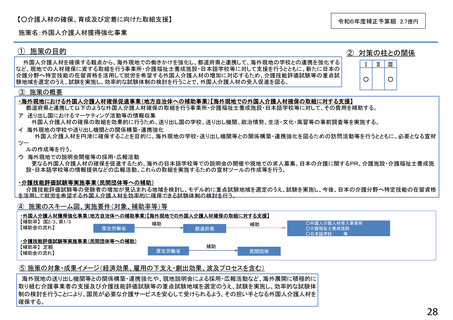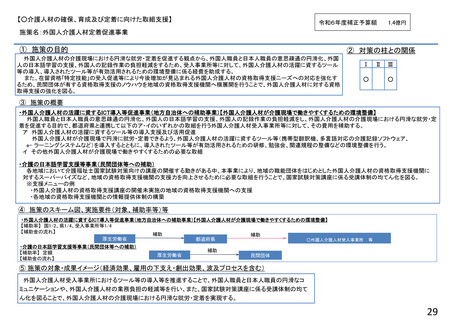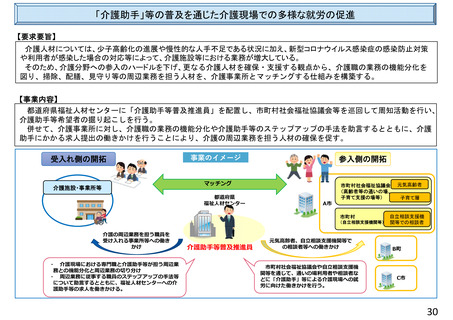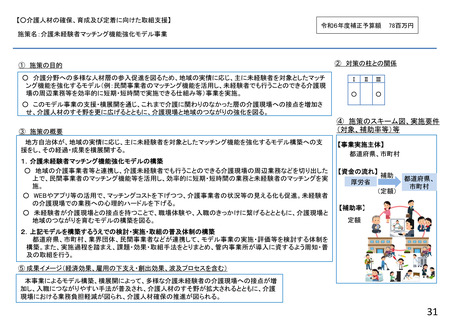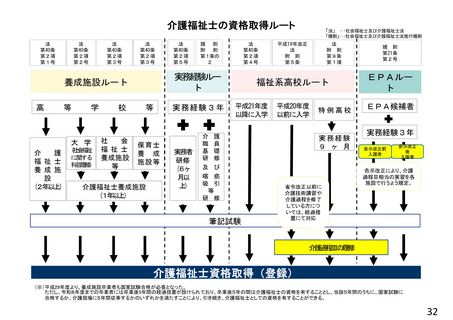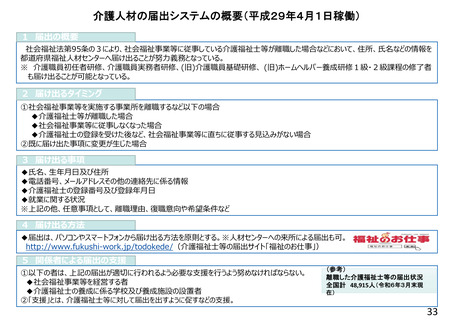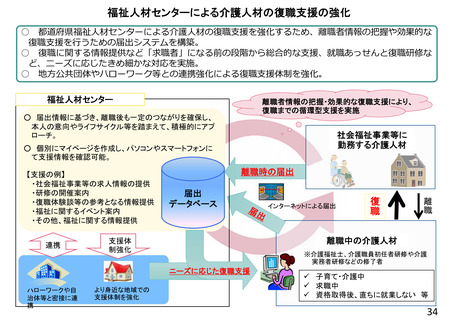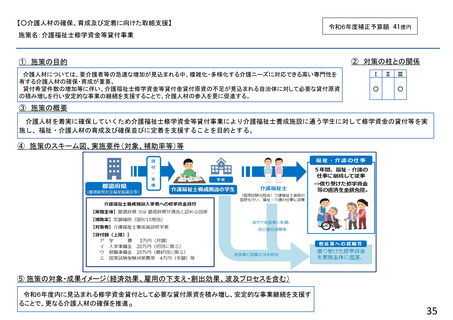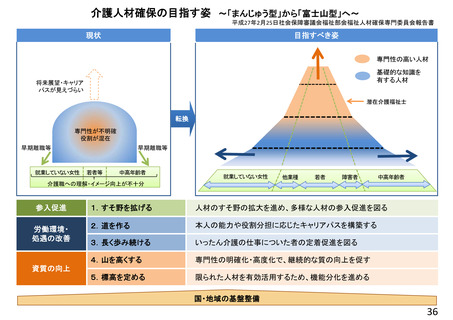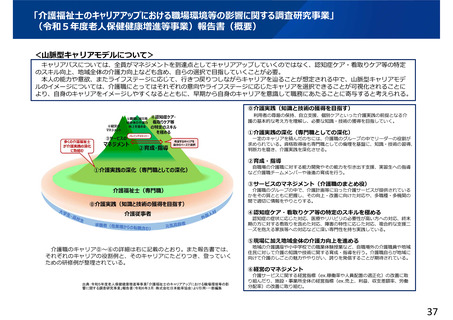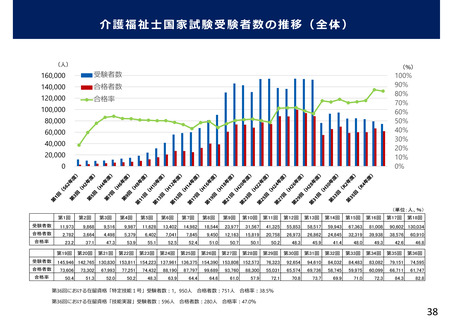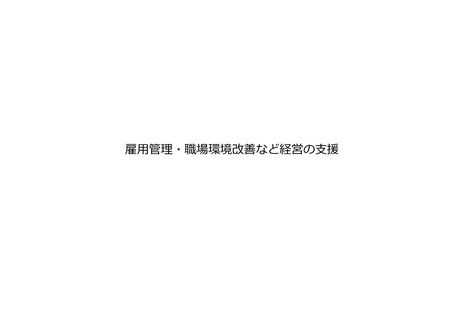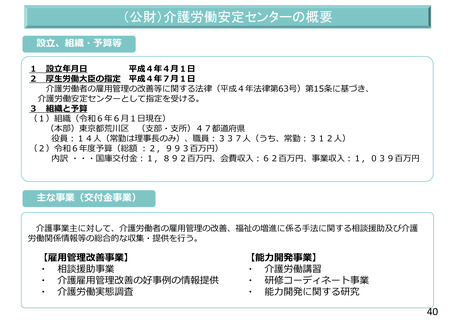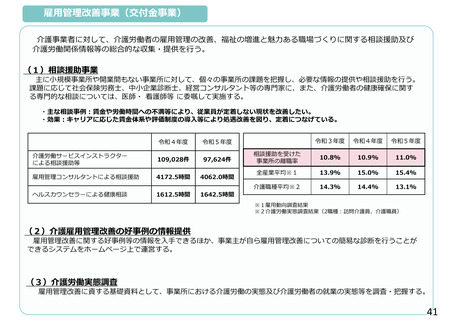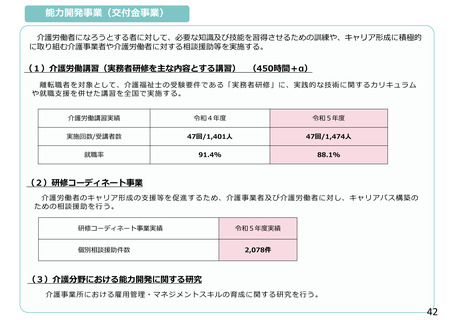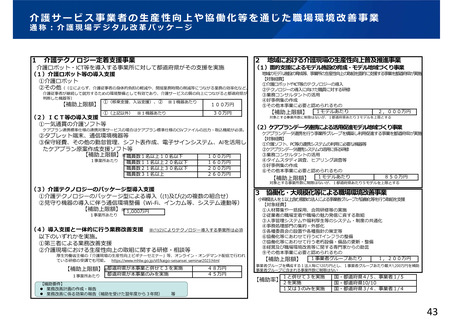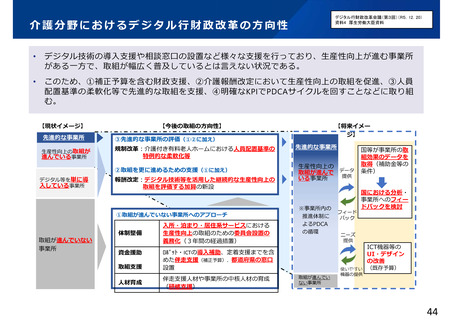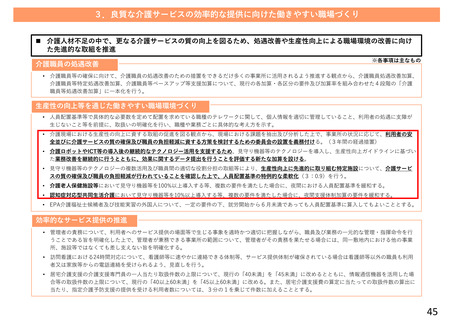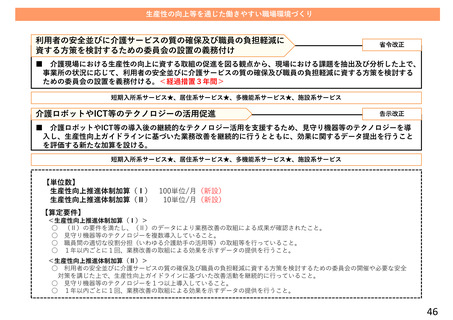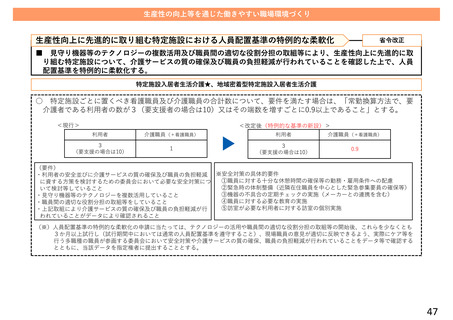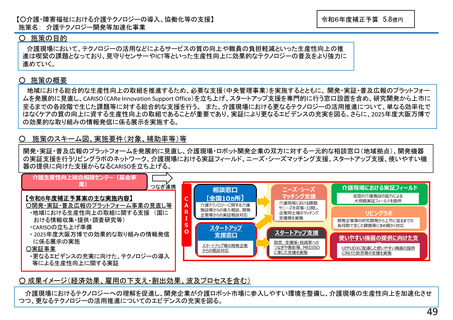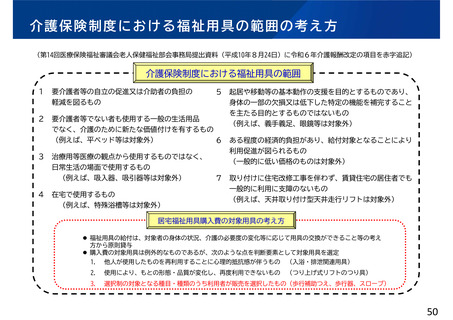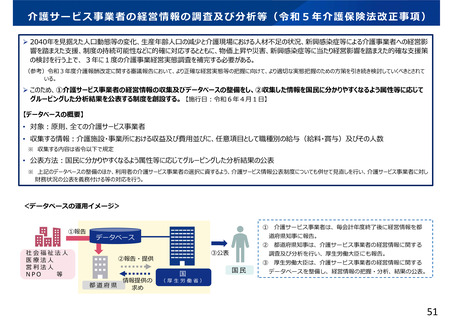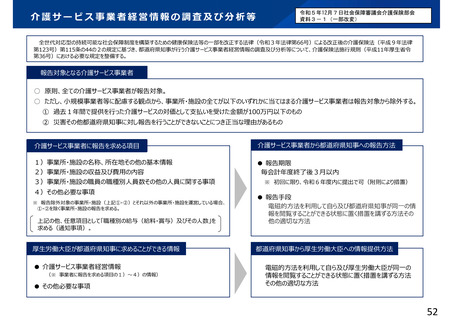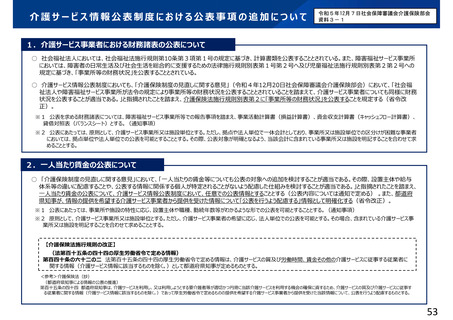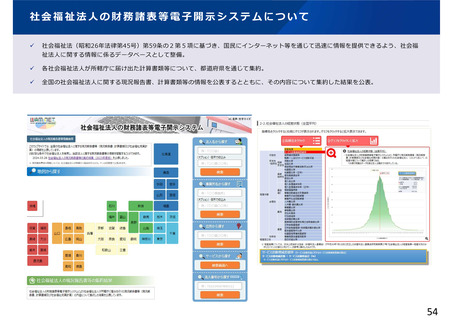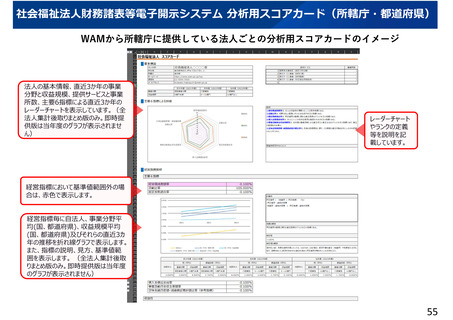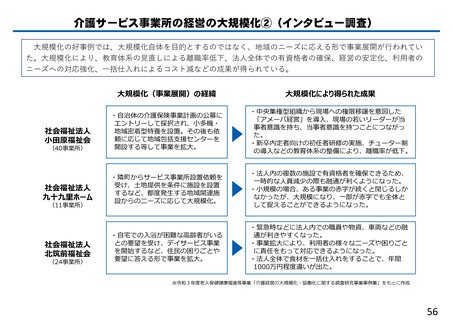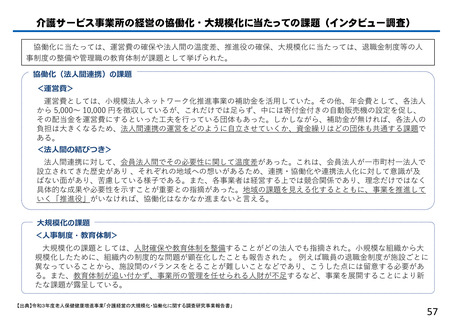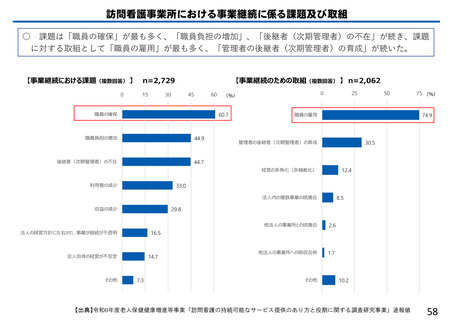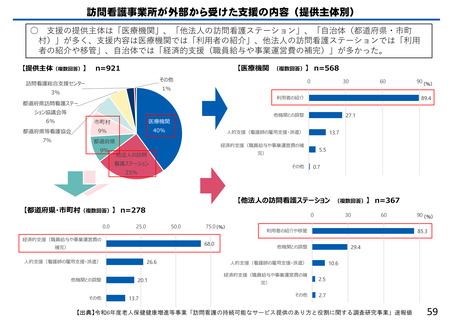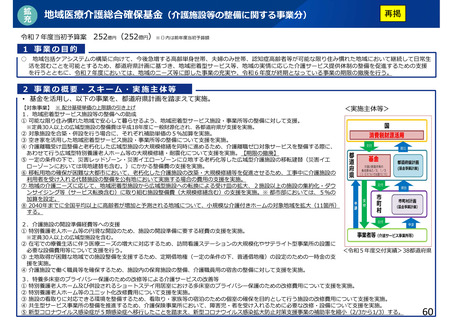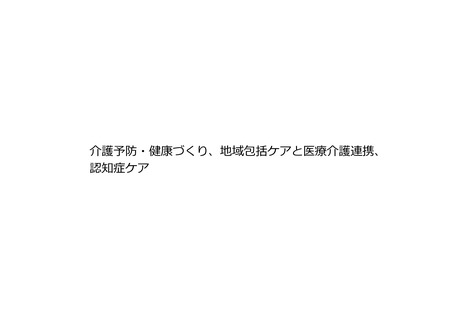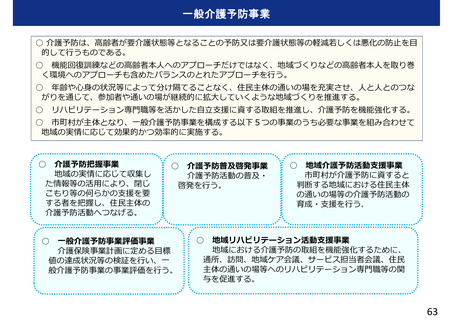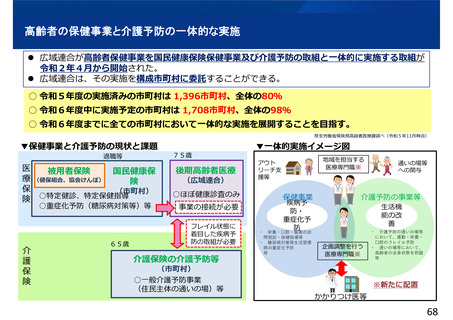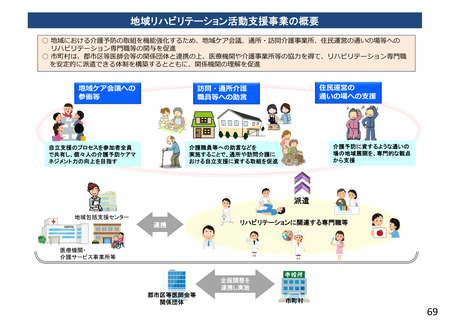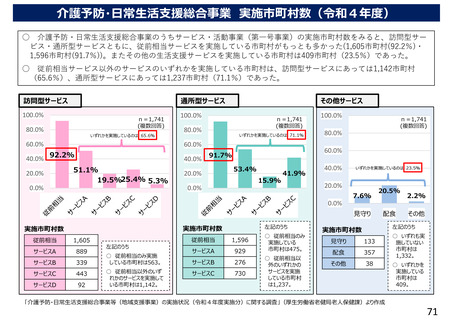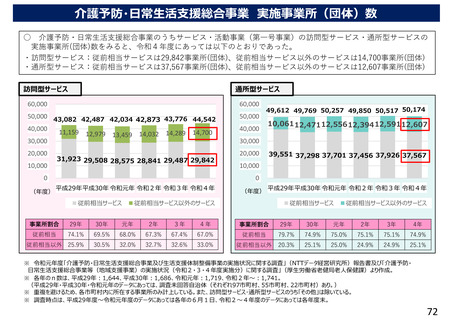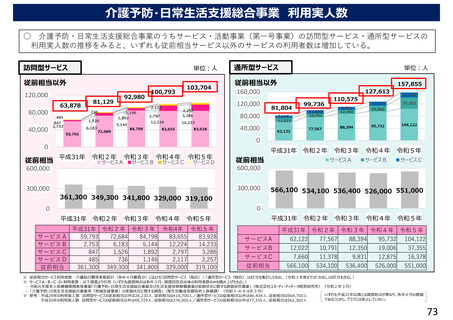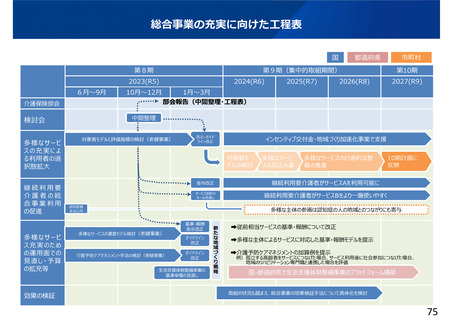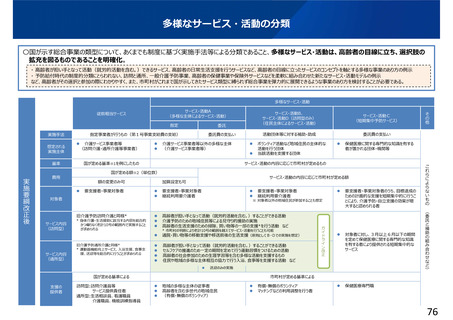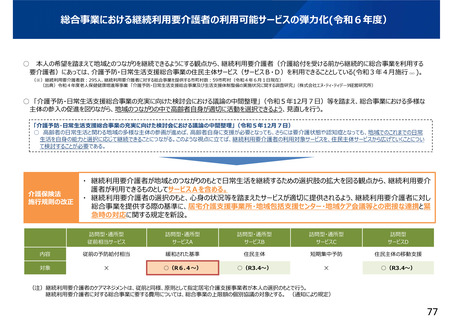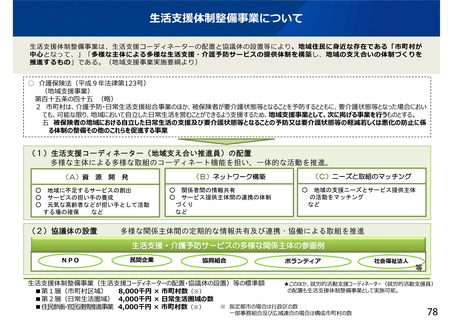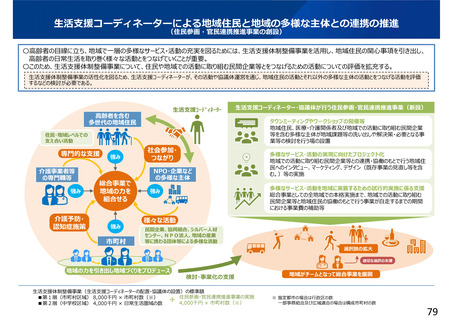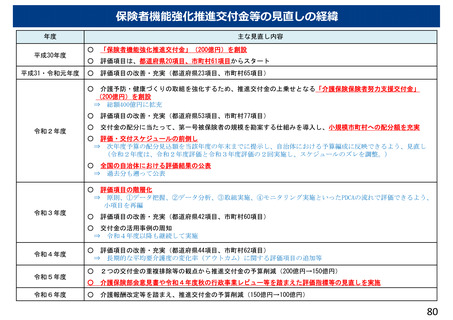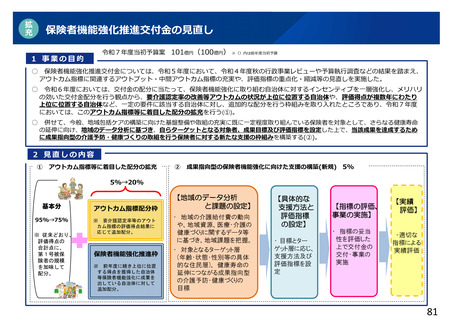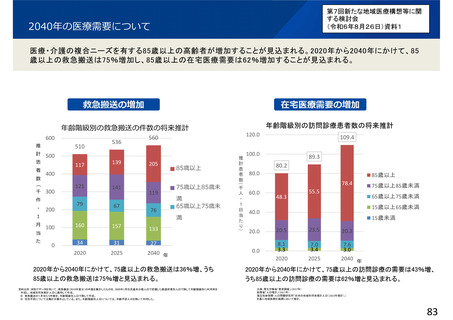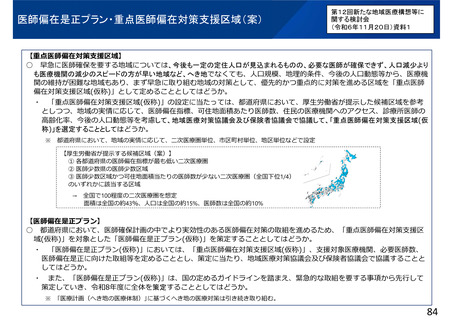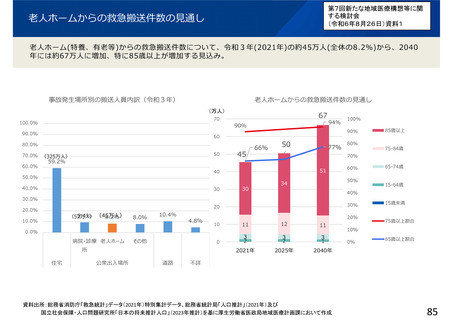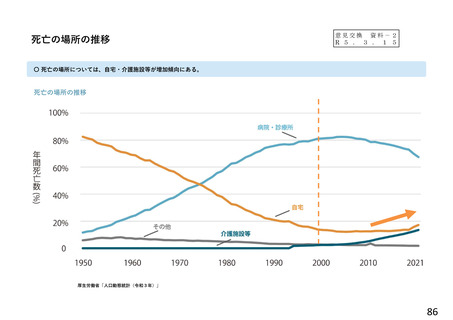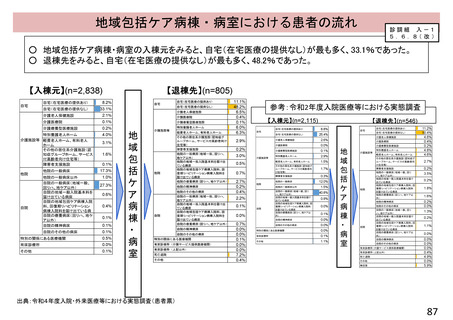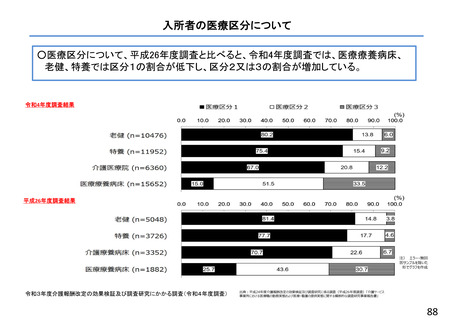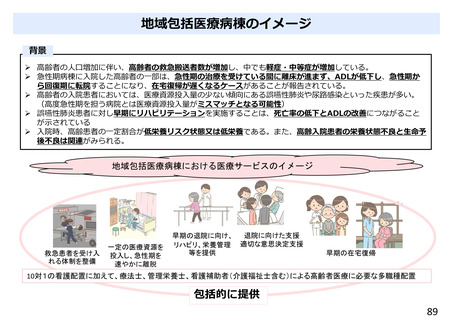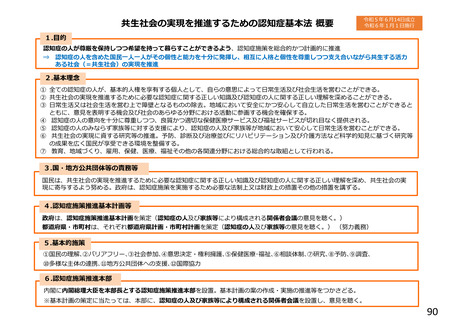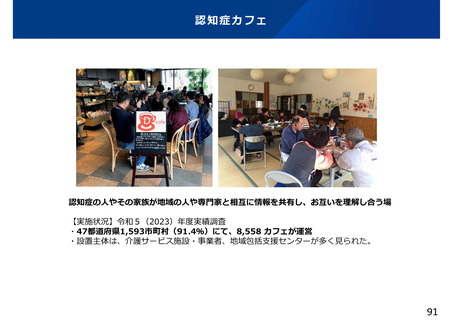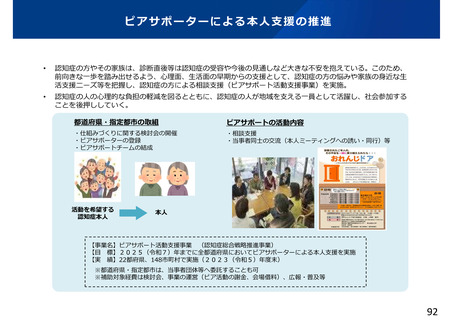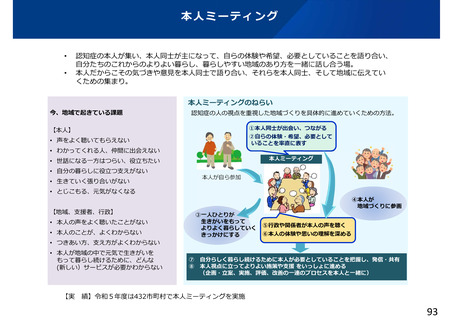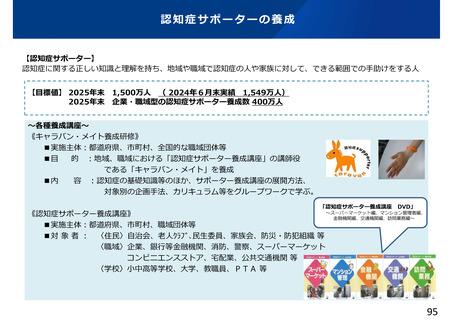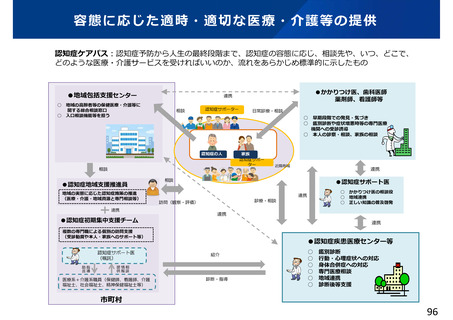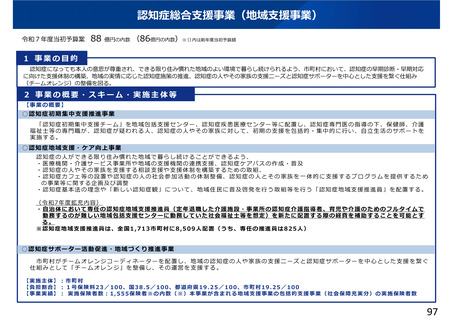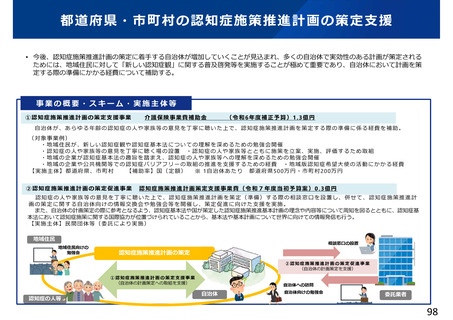よむ、つかう、まなぶ。
参考資料1 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」関係資料 (64 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48603.html |
| 出典情報 | 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会(第1回 1/9)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
運営
場所
住民団体
個人宅・空き家/公民館・自治会館・集会所/店
舗・空き店舗
体操(運動)/会食/茶話会/趣味活動/農
作業/多世代交流
内容
新潟県新潟市
誰もが気軽に集まり交流することができる 新潟市発祥の“地域の茶の間”
POINT
Data(2019年9月末日現在)
❶人と人、人と社会がつながり、自然な助け合いが生まれる「地域の茶の間」の取組みから、介護予防
と生活支援を一体的に推進。
❷地域の茶の間をさらに推進するために開設した「地域包括ケア推進モデルハウス」に定期的に専門
職を派遣し、相談・アドバイスを実施。介護予防と保健の連携がさらに推進。
❸地域の茶の間創設者のノウハウを学ぶ「茶の間の学校」で人材を育成。
新潟市発祥の「地域の茶の間」は、子どもから高齢者まで、障がいや認知症の有無にかかわらず、誰
もが気軽に集まり交流し、それぞれの生きがいや役割を持つことで、自発的な参加意欲が生まれる場で
あ
る。その「地域の茶の間」を土台とし、支え合う地域がつくられ、介護予防や健康寿命の延伸につながることを目指
している。
新潟市8区9か所に開設した「地域包括ケア推進モデルハウス」(以下「モデルハウス」)は地域包括ケアシステム
の要と位置づけされており、常設型の地域の茶の間としての場だけでなく、様々な役割を担う場となっている。
モデルハウスには、定期的に保健師や作業療法士等の専門職が派遣され、在宅での生活を支える取組も行わ
れている。また、地域の茶の間を運営する人材を育成する「茶の間の学校」では、基幹型モデルハウス「実家の茶
の間・紫竹」での実習を始め、必要性・理念、立ち上げや運営のノウハウを学ぶことができる。
「実家の茶の間・紫竹」は、多世代が参加し、それぞれが好きな時間を過ごしている。
初めての方でも利用しやすい居心地がよい場
であり続けているのは、お当番がさりげない配慮
をしながら、参加者がプライバシーを聞き出さな
いなどの「決まりごと」を守ることで、ほどよい距
離感が保たれていることが1つのポイントである。
この「決まりごと」を取り入れている地域の茶の
間も多数ある。
また、参加者のこれまでの経験や得意なこと
を生かし、役割をもつことで、「自分の居場所」
という確認ができ、特に男性の参加率が上がる。
そのほか、町内会主催による野菜作りや、ボ
ランティア団体が主催する併用住宅の店舗部
分にある空きスペースを活用した食事提供を
伴う場があるなど、地域の茶の間の主体・内
容・参加者は多様な広がりをみせている。
総人口
789,368人
高齢化率
29.1%
第7期介護保険料
基準額(月額)
6,353円
効果
概要
平成3年から新潟市内で始まった地域の茶の間は着
実に広がり続けており、市が補助・助成していない自主運
営の地域の茶の間を含めると市内総数は600を超えると
いう。視察も多く、新潟市から全国へ地域の茶の間の拡が
りをみせている。
また、「実家の茶の間・紫竹」では参加券を生活支援の
お礼として活用することができ、仲介役が必要のない住民
同士が互いに助けあえる関係が自然と生まれていることも
1つの効果といえる。
図:地域の茶の間設置数推移
(地域の茶の間に対する補助金実績のみ)
参考URL:http://www.city.niigata.lg.jp/iryo/korei/chiikihokatsucare/jikkanocyanoma.html(新潟市――「実家の茶の間・紫竹」)
64
場所
住民団体
個人宅・空き家/公民館・自治会館・集会所/店
舗・空き店舗
体操(運動)/会食/茶話会/趣味活動/農
作業/多世代交流
内容
新潟県新潟市
誰もが気軽に集まり交流することができる 新潟市発祥の“地域の茶の間”
POINT
Data(2019年9月末日現在)
❶人と人、人と社会がつながり、自然な助け合いが生まれる「地域の茶の間」の取組みから、介護予防
と生活支援を一体的に推進。
❷地域の茶の間をさらに推進するために開設した「地域包括ケア推進モデルハウス」に定期的に専門
職を派遣し、相談・アドバイスを実施。介護予防と保健の連携がさらに推進。
❸地域の茶の間創設者のノウハウを学ぶ「茶の間の学校」で人材を育成。
新潟市発祥の「地域の茶の間」は、子どもから高齢者まで、障がいや認知症の有無にかかわらず、誰
もが気軽に集まり交流し、それぞれの生きがいや役割を持つことで、自発的な参加意欲が生まれる場で
あ
る。その「地域の茶の間」を土台とし、支え合う地域がつくられ、介護予防や健康寿命の延伸につながることを目指
している。
新潟市8区9か所に開設した「地域包括ケア推進モデルハウス」(以下「モデルハウス」)は地域包括ケアシステム
の要と位置づけされており、常設型の地域の茶の間としての場だけでなく、様々な役割を担う場となっている。
モデルハウスには、定期的に保健師や作業療法士等の専門職が派遣され、在宅での生活を支える取組も行わ
れている。また、地域の茶の間を運営する人材を育成する「茶の間の学校」では、基幹型モデルハウス「実家の茶
の間・紫竹」での実習を始め、必要性・理念、立ち上げや運営のノウハウを学ぶことができる。
「実家の茶の間・紫竹」は、多世代が参加し、それぞれが好きな時間を過ごしている。
初めての方でも利用しやすい居心地がよい場
であり続けているのは、お当番がさりげない配慮
をしながら、参加者がプライバシーを聞き出さな
いなどの「決まりごと」を守ることで、ほどよい距
離感が保たれていることが1つのポイントである。
この「決まりごと」を取り入れている地域の茶の
間も多数ある。
また、参加者のこれまでの経験や得意なこと
を生かし、役割をもつことで、「自分の居場所」
という確認ができ、特に男性の参加率が上がる。
そのほか、町内会主催による野菜作りや、ボ
ランティア団体が主催する併用住宅の店舗部
分にある空きスペースを活用した食事提供を
伴う場があるなど、地域の茶の間の主体・内
容・参加者は多様な広がりをみせている。
総人口
789,368人
高齢化率
29.1%
第7期介護保険料
基準額(月額)
6,353円
効果
概要
平成3年から新潟市内で始まった地域の茶の間は着
実に広がり続けており、市が補助・助成していない自主運
営の地域の茶の間を含めると市内総数は600を超えると
いう。視察も多く、新潟市から全国へ地域の茶の間の拡が
りをみせている。
また、「実家の茶の間・紫竹」では参加券を生活支援の
お礼として活用することができ、仲介役が必要のない住民
同士が互いに助けあえる関係が自然と生まれていることも
1つの効果といえる。
図:地域の茶の間設置数推移
(地域の茶の間に対する補助金実績のみ)
参考URL:http://www.city.niigata.lg.jp/iryo/korei/chiikihokatsucare/jikkanocyanoma.html(新潟市――「実家の茶の間・紫竹」)
64