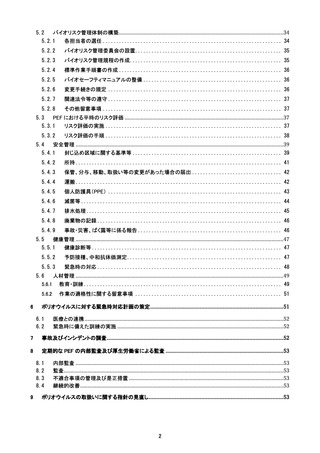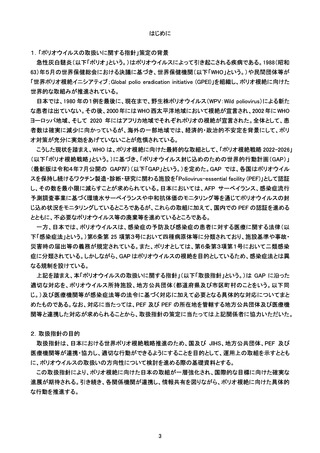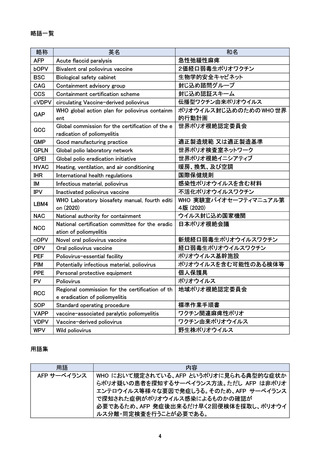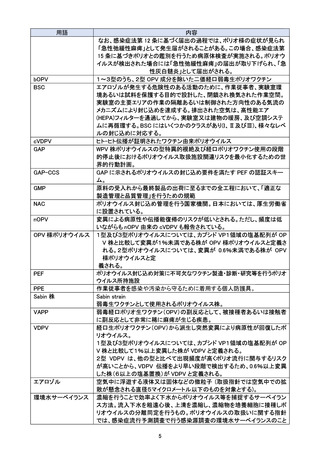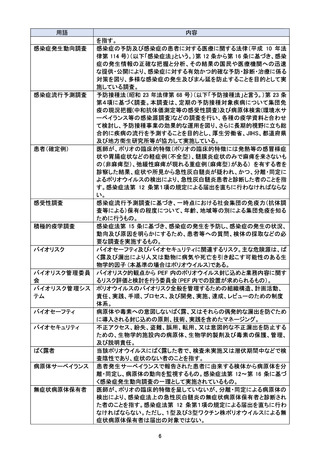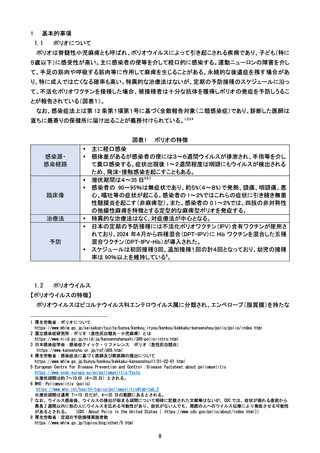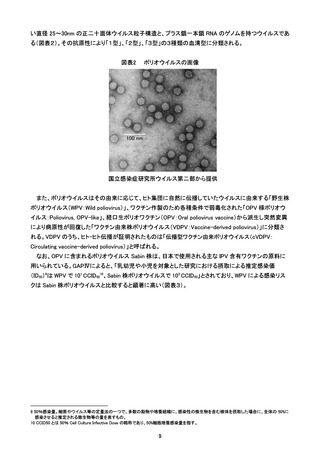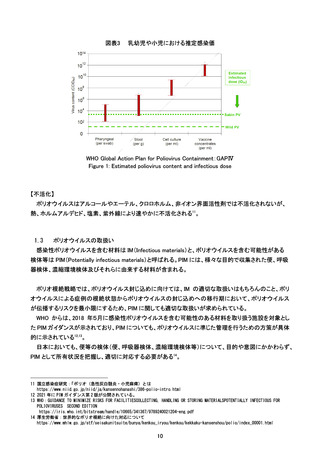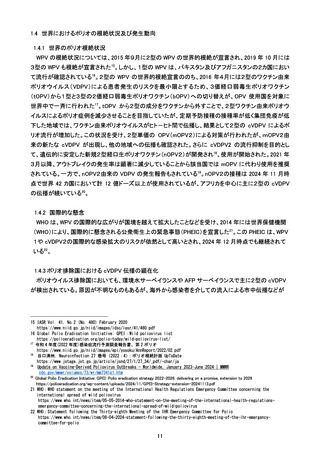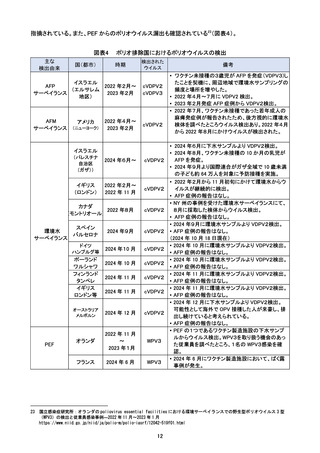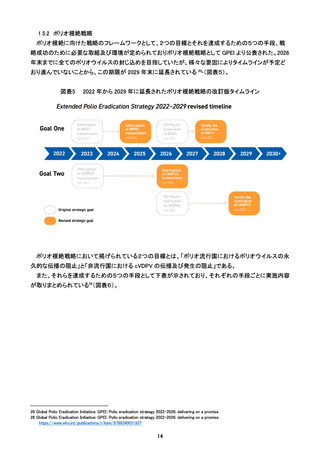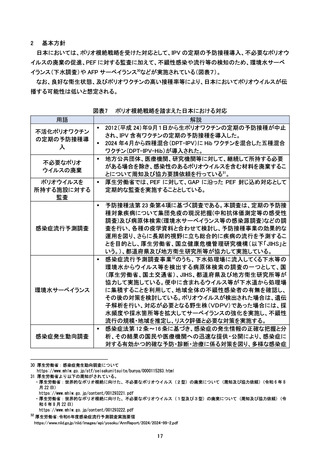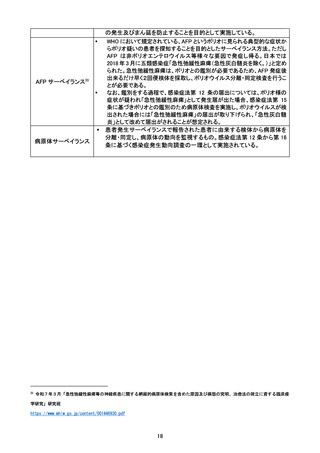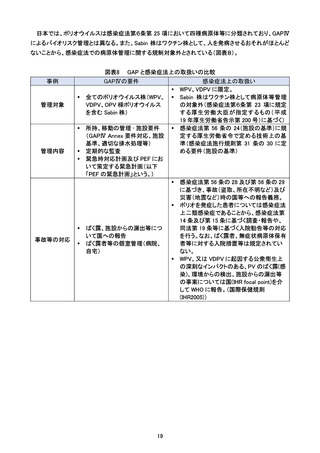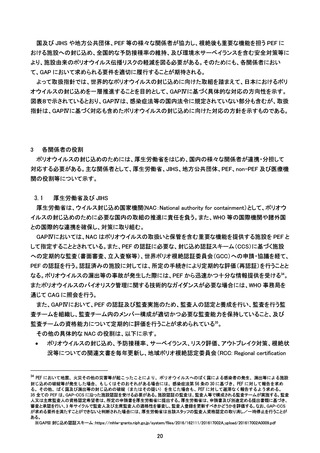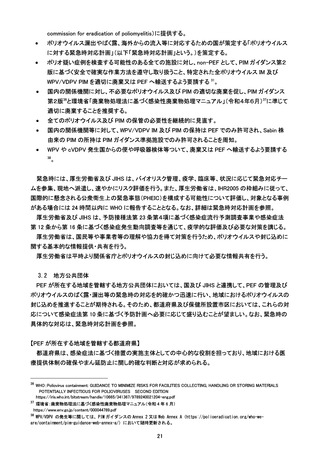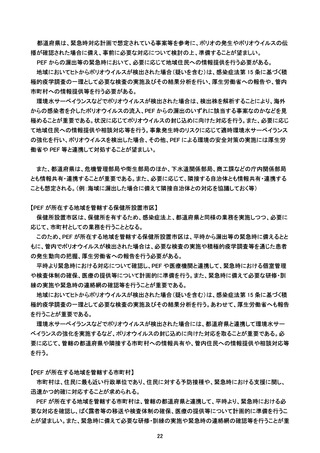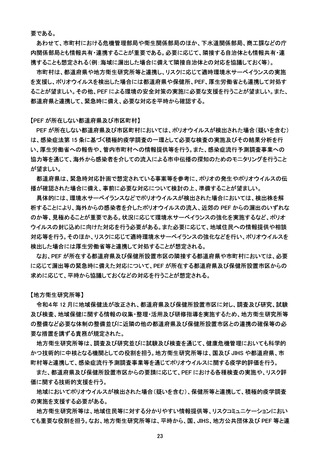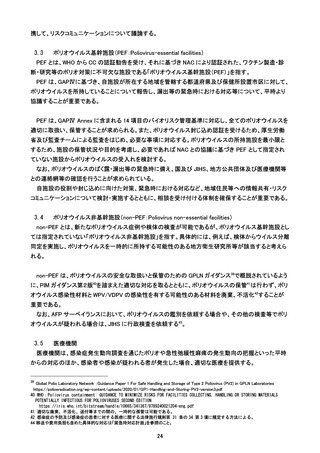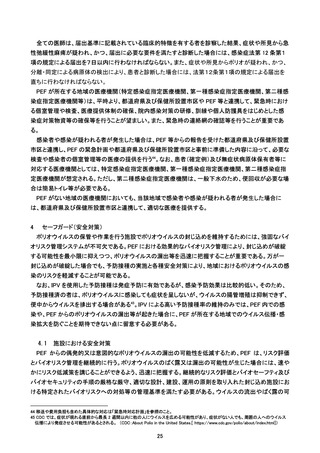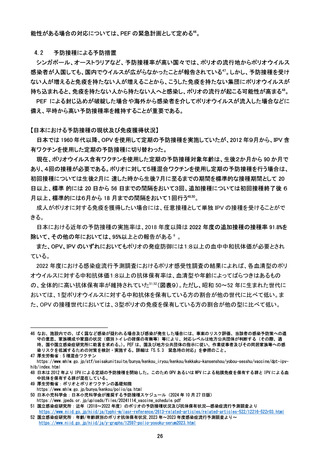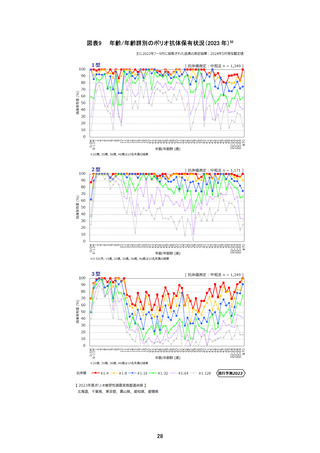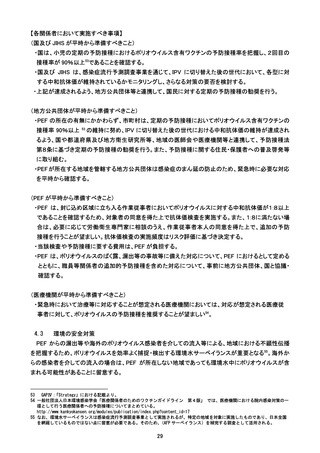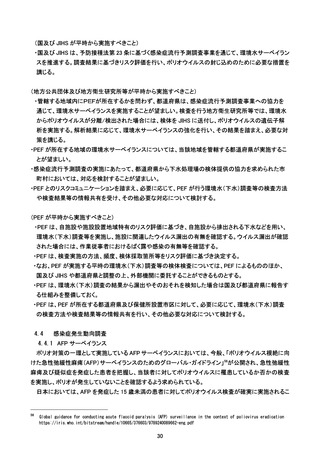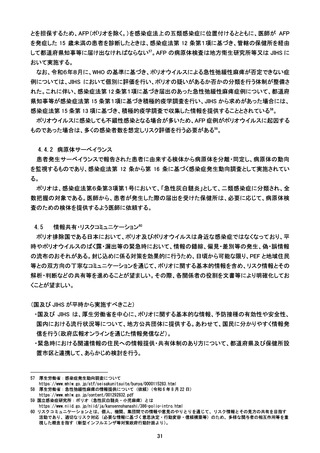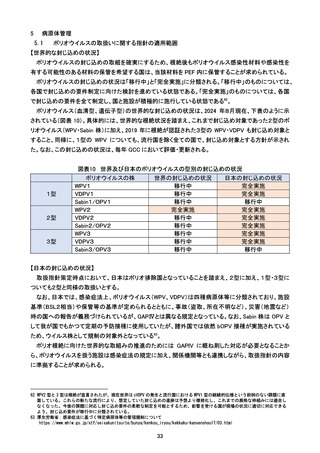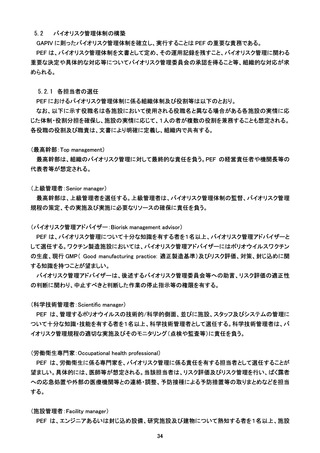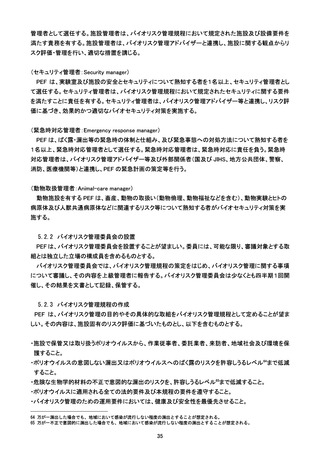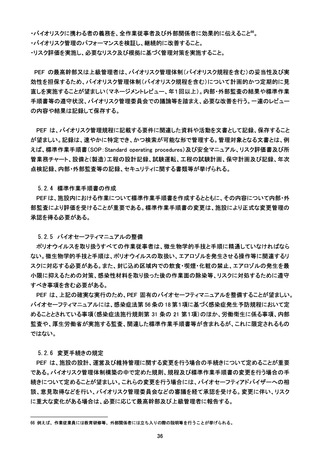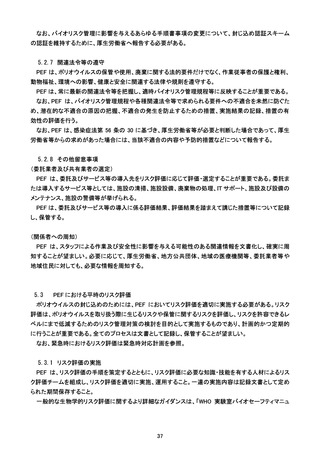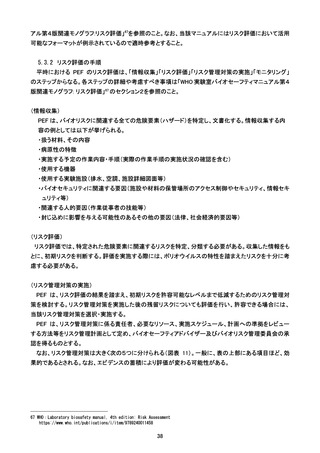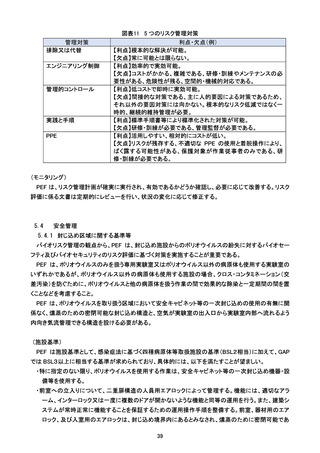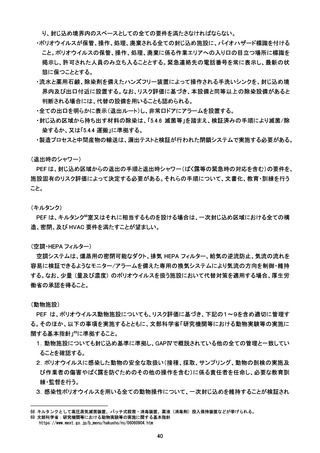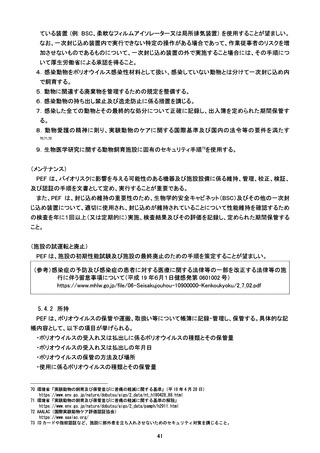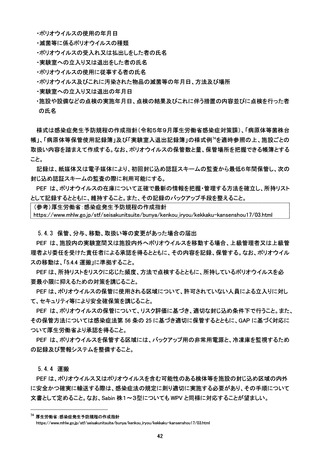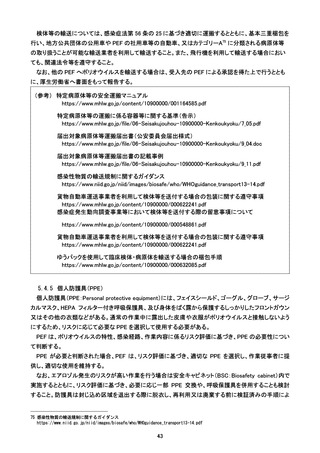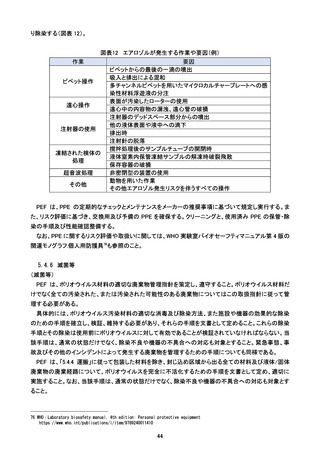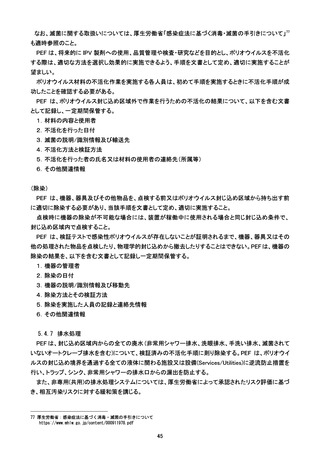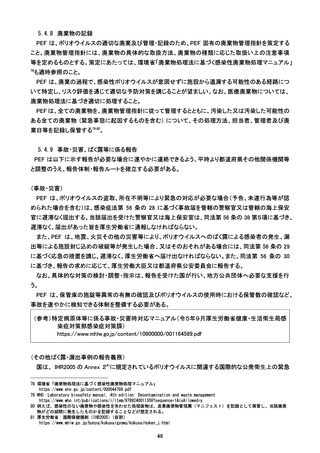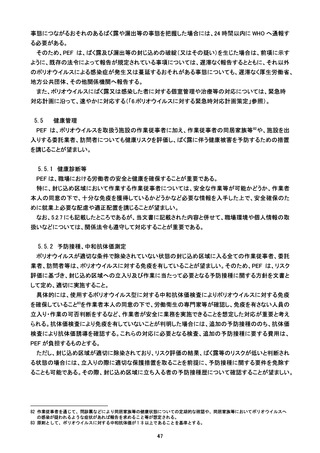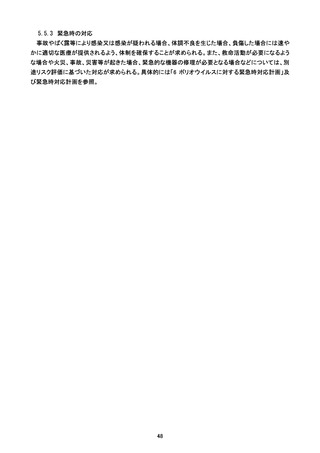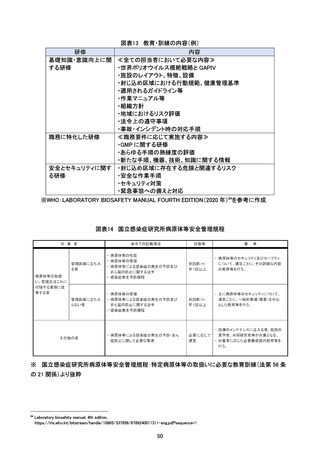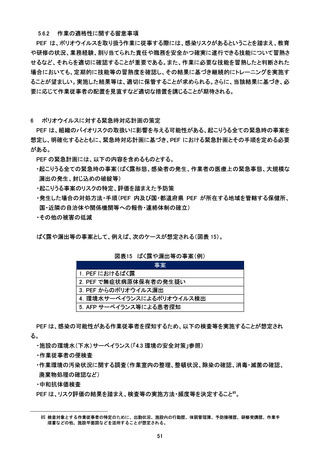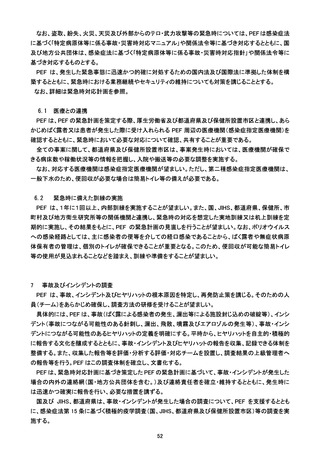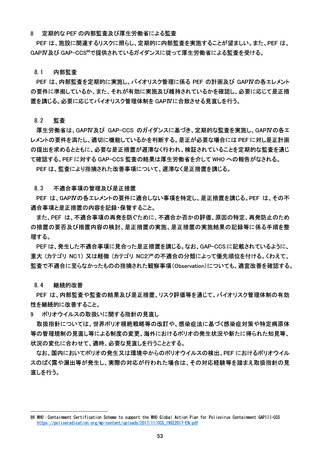よむ、つかう、まなぶ。
【参考資料3-1】ポリオウイルスの取扱いに関する指針(案)[1.7MB] (31 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54655.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第94回 3/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
とを担保するため、AFP(ポリオを除く。)を感染症法上の五類感染症に位置付けるとともに、医師が AFP
を発症した 15 歳未満の患者を診断したときは、感染症法第 12 条第1項に基づき、管轄の保健所を経由
して都道府県知事等に届け出なければならない57。AFP の病原体検査は地方衛生研究所等又は JIHS に
おいて実施する。
なお、令和6年8月に、WHO の基準に基づき、ポリオウイルスによる急性弛緩性麻痺が否定できない症
例については、JIHS において個別に評価を行い、ポリオの疑いがあるか否かの分類を行う体制が整備さ
れた。これに伴い、感染症法第 12 条第1項に基づき届出のあった急性弛緩性麻痺症例について、都道府
県知事等が感染症法第 15 条第1項に基づき積極的疫学調査を行い、JIHS から求めがあった場合には、
感染症法第 15 条第 13 項に基づき、積極的疫学調査で収集した情報を提供することとされている58。
ポリオウイルスに感染しても不顕性感染となる場合が多いため、AFP 症例がポリオウイルスに起因する
ものであった場合は、多くの感染者数を想定しリスク評価を行う必要がある59。
4.4.2 病原体サーベイランス
患者発生サーベイランスで報告された患者に由来する検体から病原体を分離・同定し、病原体の動向
を監視するものであり、感染症法第 12 条から第 16 条に基づく感染症発生動向調査として実施されてい
る。
ポリオは、感染症法第6条第3項第1号において、「急性灰白髄炎」として、二類感染症に分類され、全
数把握の対象である。医師から、患者が発生した際の届出を受けた保健所は、必要に応じて、病原体検
査のための検体を提供するよう医師に依頼する。
4.5
情報共有・リスクコミュニケーション60
ポリオ排除国である日本において、ポリオ及びポリオウイルスは身近な感染症ではなくなっており、平
時やポリオウイルスのばく露・漏出等の緊急時において、情報の錯綜、偏見・差別等の発生、偽・誤情報
の流布のおそれがある。封じ込めに係る対策を効果的に行うため、日頃から可能な限り、PEF と地域住民
等との双方向の丁寧なコミュニケーションを通じて、ポリオに関する基本的情報を含め、リスク情報とその
解析・判断などの共有等を進めることが望ましい。その際、各関係者の役割を文書等により明確化してお
くことが望ましい。
(国及び JIHS が平時から実施すべきこと)
・国及び JIHS は、厚生労働省を中心に、ポリオに関する基本的な情報、予防接種の有効性や安全性、
国内における流行状況等について、地方公共団体に提供する。あわせて、国民に分かりやすく情報発
信を行う(政府広報オンラインを通じた情報発信など)。
・緊急時における関連情報の住民への情報提供・共有体制のあり方について、都道府県及び保健所設
置市区と連携して、あらかじめ検討を行う。
57
厚生労働省:感染症発生動向調査について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115283.html
58 厚生労働省:急性弛緩性麻痺の情報提供について(依頼)
(令和 6 年 8 月 22 日)
https://www.mhlw.go.jp/content/001292832.pdf
59 国立感染症研究所:ポリオ(急性灰白髄炎・小児麻痺)とは
https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/386-polio-intro.html
60 リスクコミュニケーションとは、個人、機関、集団間での情報や意見のやりとりを通じて、リスク情報とその見方の共有を目指す
活動であり、適切なリスク対応(必要な情報に基づく意思決定・行動変容・信頼構築等)のため、多様な関与者の相互作用等を重
視した概念を指す(新型インフルエンザ等対策政府行動計画より)
。
31
を発症した 15 歳未満の患者を診断したときは、感染症法第 12 条第1項に基づき、管轄の保健所を経由
して都道府県知事等に届け出なければならない57。AFP の病原体検査は地方衛生研究所等又は JIHS に
おいて実施する。
なお、令和6年8月に、WHO の基準に基づき、ポリオウイルスによる急性弛緩性麻痺が否定できない症
例については、JIHS において個別に評価を行い、ポリオの疑いがあるか否かの分類を行う体制が整備さ
れた。これに伴い、感染症法第 12 条第1項に基づき届出のあった急性弛緩性麻痺症例について、都道府
県知事等が感染症法第 15 条第1項に基づき積極的疫学調査を行い、JIHS から求めがあった場合には、
感染症法第 15 条第 13 項に基づき、積極的疫学調査で収集した情報を提供することとされている58。
ポリオウイルスに感染しても不顕性感染となる場合が多いため、AFP 症例がポリオウイルスに起因する
ものであった場合は、多くの感染者数を想定しリスク評価を行う必要がある59。
4.4.2 病原体サーベイランス
患者発生サーベイランスで報告された患者に由来する検体から病原体を分離・同定し、病原体の動向
を監視するものであり、感染症法第 12 条から第 16 条に基づく感染症発生動向調査として実施されてい
る。
ポリオは、感染症法第6条第3項第1号において、「急性灰白髄炎」として、二類感染症に分類され、全
数把握の対象である。医師から、患者が発生した際の届出を受けた保健所は、必要に応じて、病原体検
査のための検体を提供するよう医師に依頼する。
4.5
情報共有・リスクコミュニケーション60
ポリオ排除国である日本において、ポリオ及びポリオウイルスは身近な感染症ではなくなっており、平
時やポリオウイルスのばく露・漏出等の緊急時において、情報の錯綜、偏見・差別等の発生、偽・誤情報
の流布のおそれがある。封じ込めに係る対策を効果的に行うため、日頃から可能な限り、PEF と地域住民
等との双方向の丁寧なコミュニケーションを通じて、ポリオに関する基本的情報を含め、リスク情報とその
解析・判断などの共有等を進めることが望ましい。その際、各関係者の役割を文書等により明確化してお
くことが望ましい。
(国及び JIHS が平時から実施すべきこと)
・国及び JIHS は、厚生労働省を中心に、ポリオに関する基本的な情報、予防接種の有効性や安全性、
国内における流行状況等について、地方公共団体に提供する。あわせて、国民に分かりやすく情報発
信を行う(政府広報オンラインを通じた情報発信など)。
・緊急時における関連情報の住民への情報提供・共有体制のあり方について、都道府県及び保健所設
置市区と連携して、あらかじめ検討を行う。
57
厚生労働省:感染症発生動向調査について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115283.html
58 厚生労働省:急性弛緩性麻痺の情報提供について(依頼)
(令和 6 年 8 月 22 日)
https://www.mhlw.go.jp/content/001292832.pdf
59 国立感染症研究所:ポリオ(急性灰白髄炎・小児麻痺)とは
https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/386-polio-intro.html
60 リスクコミュニケーションとは、個人、機関、集団間での情報や意見のやりとりを通じて、リスク情報とその見方の共有を目指す
活動であり、適切なリスク対応(必要な情報に基づく意思決定・行動変容・信頼構築等)のため、多様な関与者の相互作用等を重
視した概念を指す(新型インフルエンザ等対策政府行動計画より)
。
31