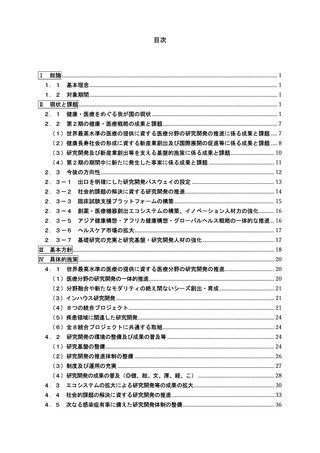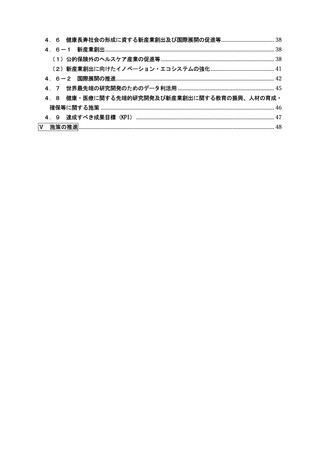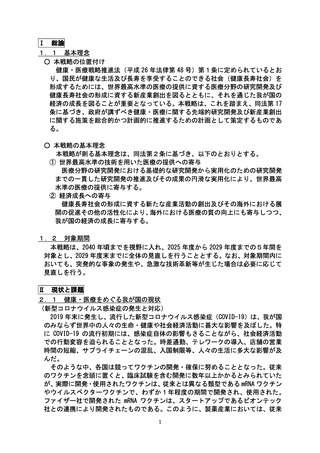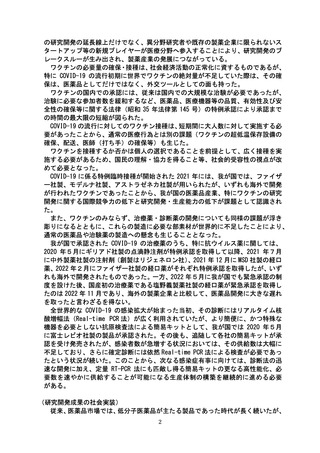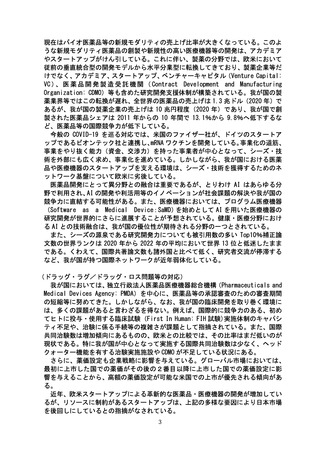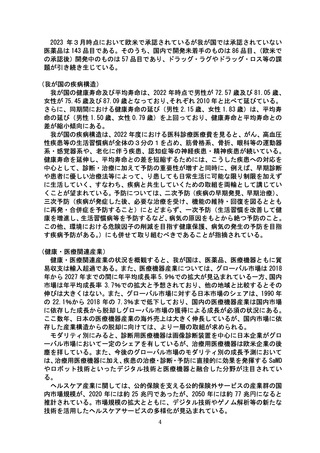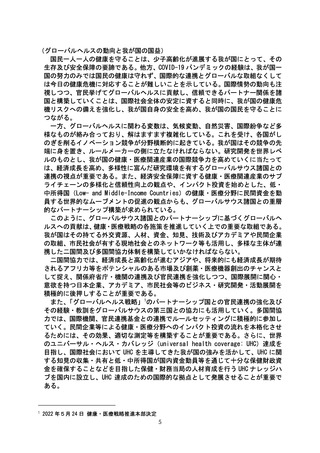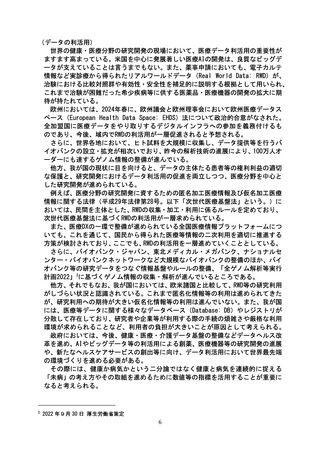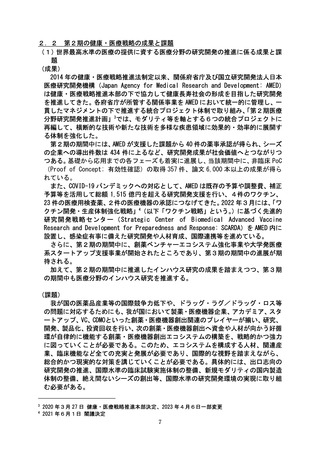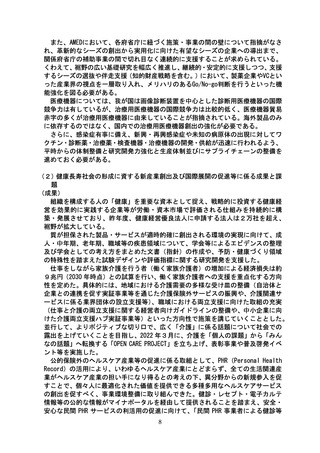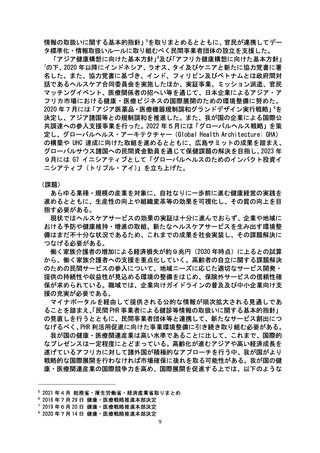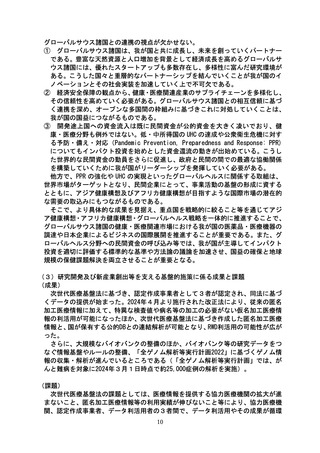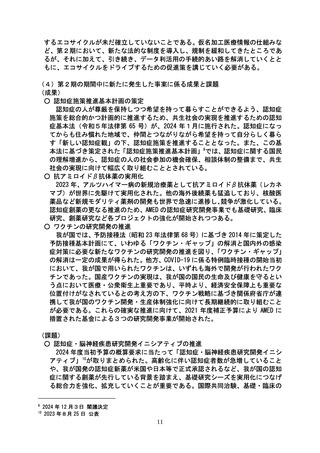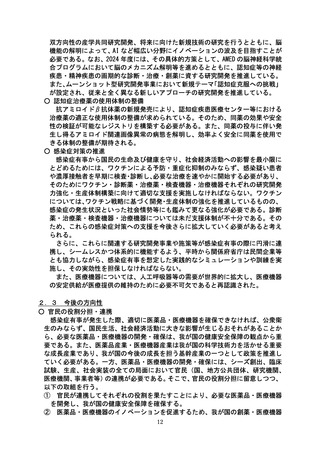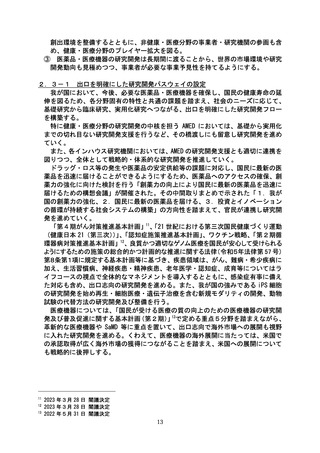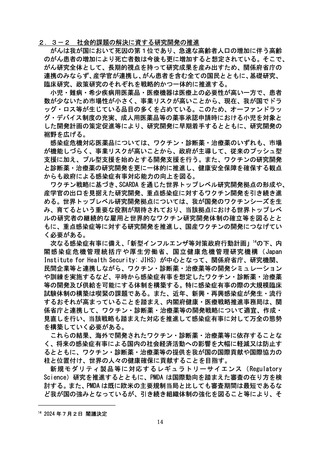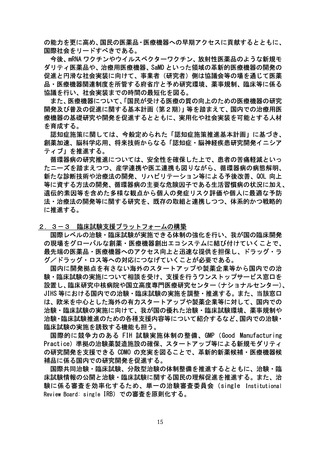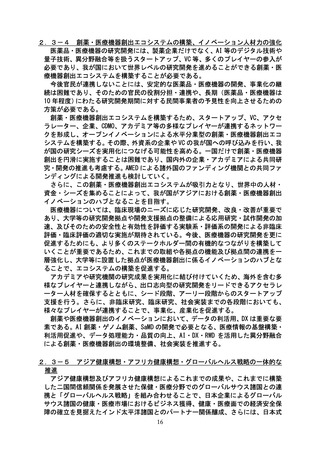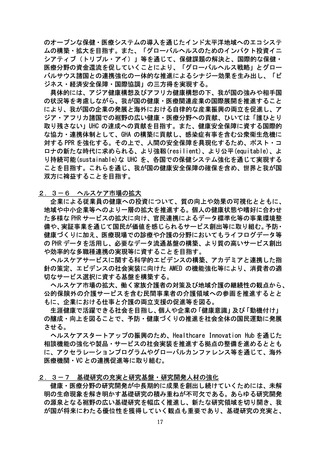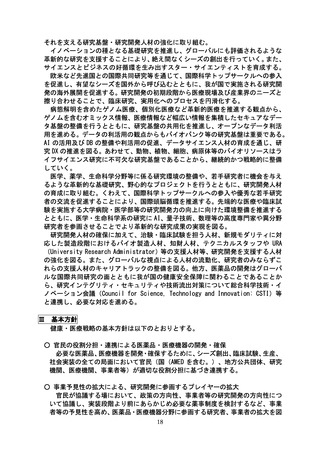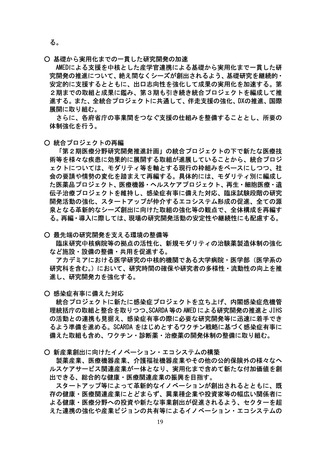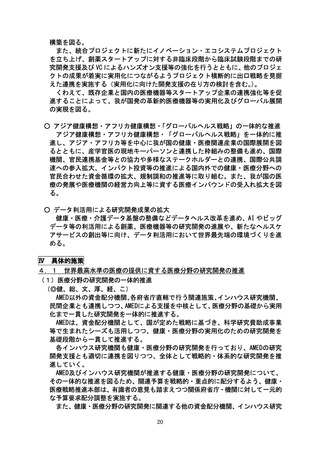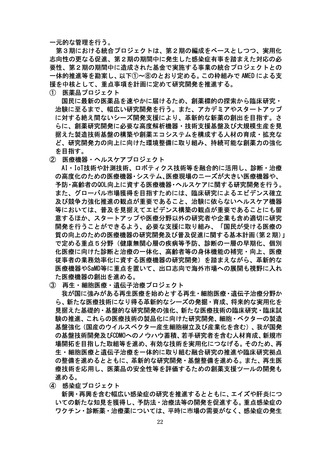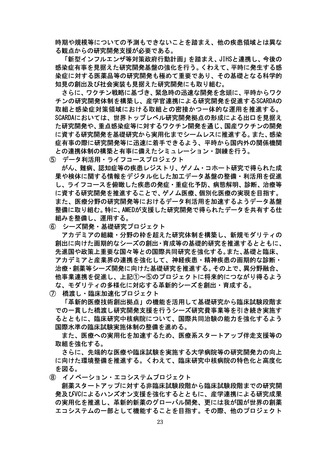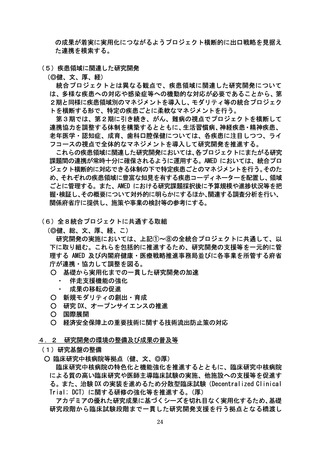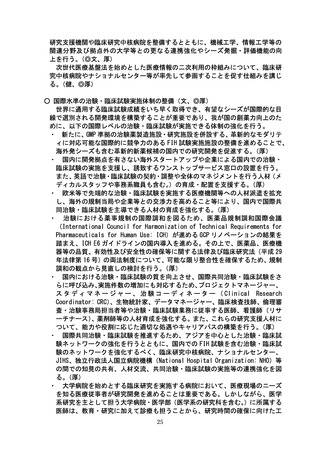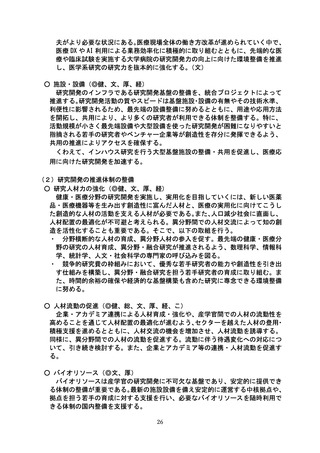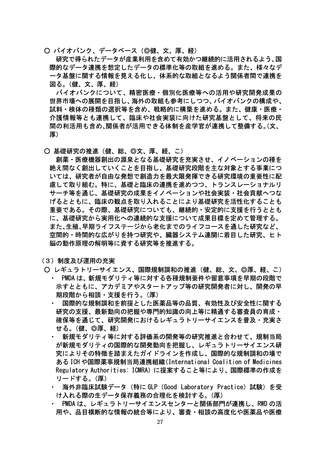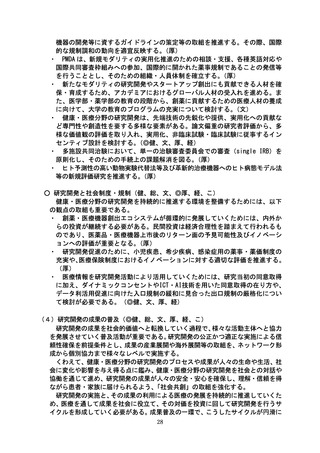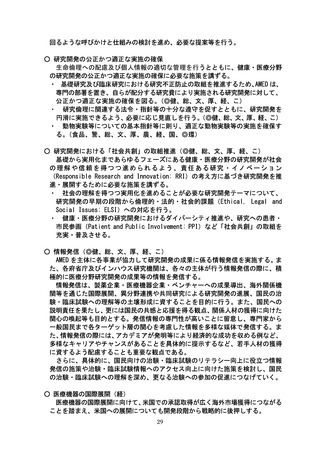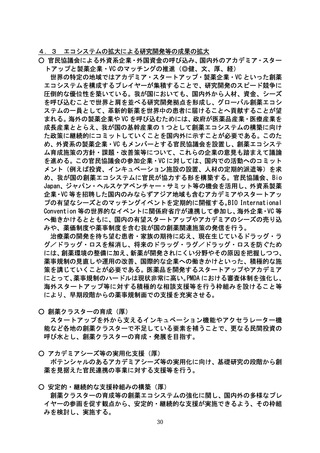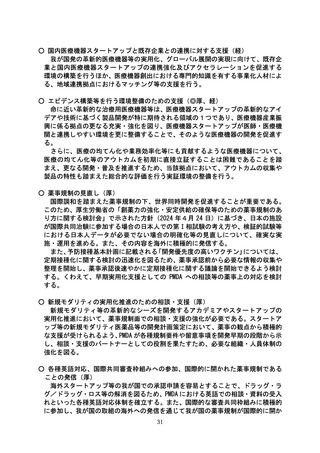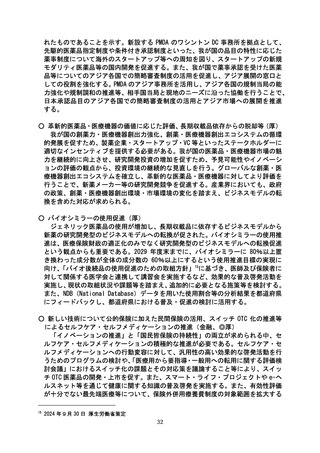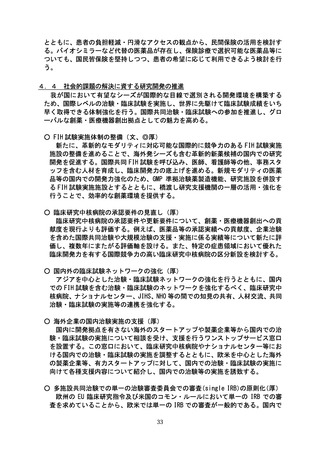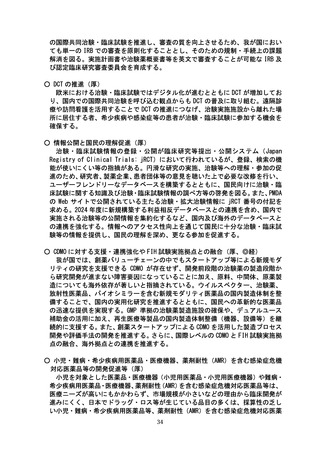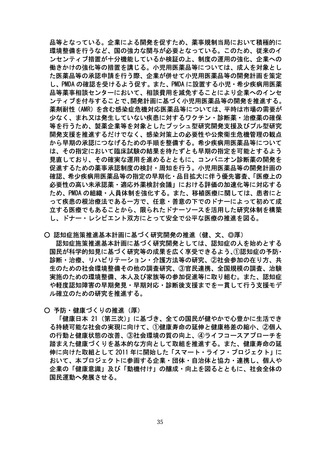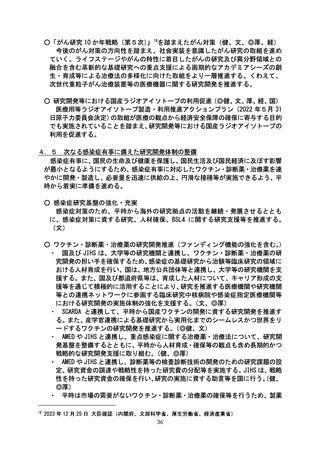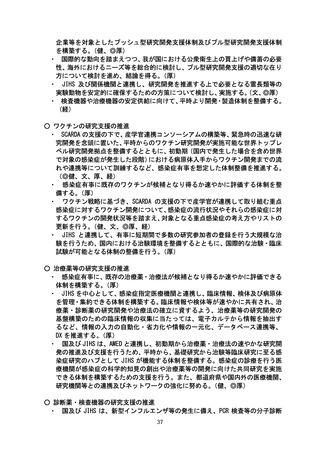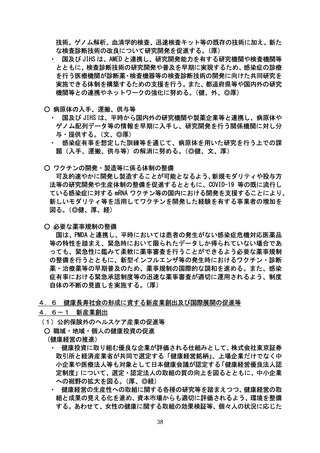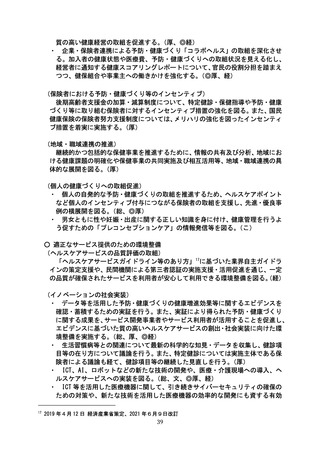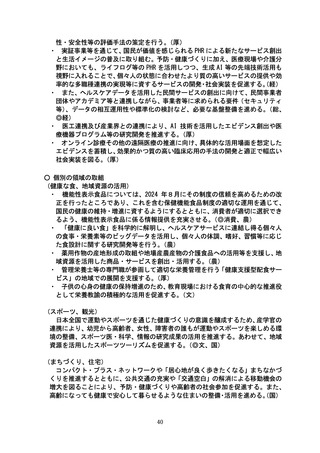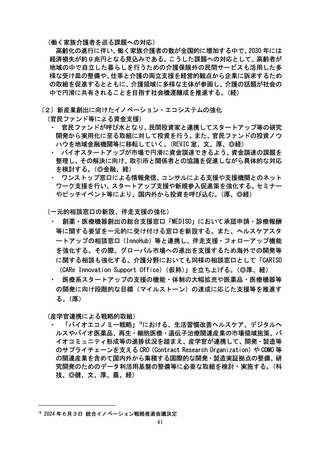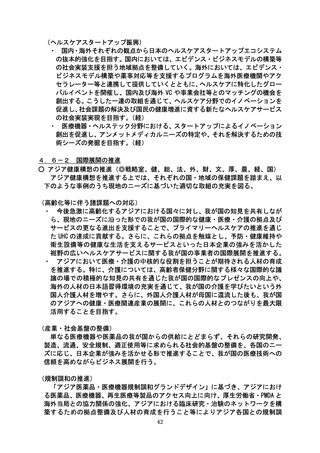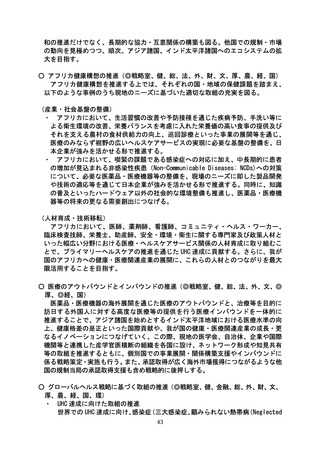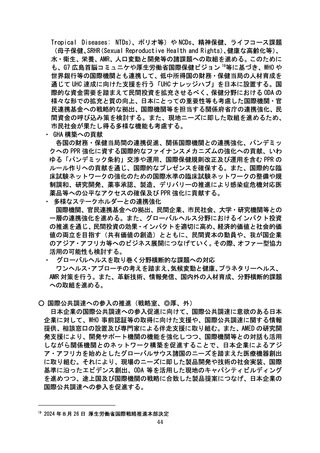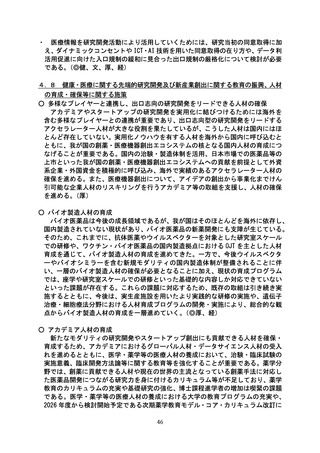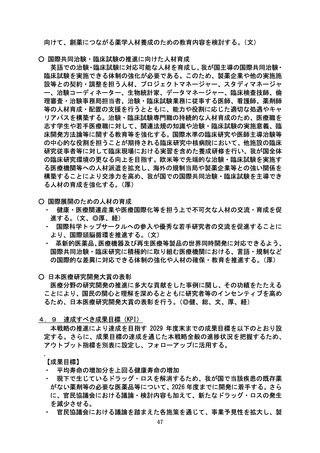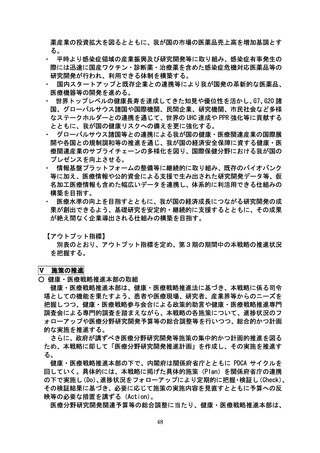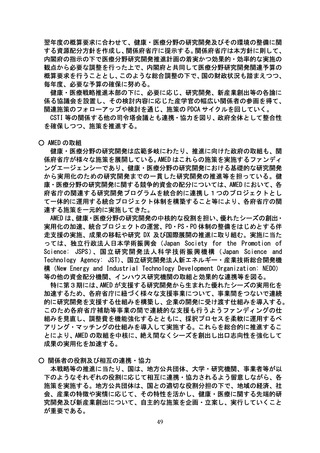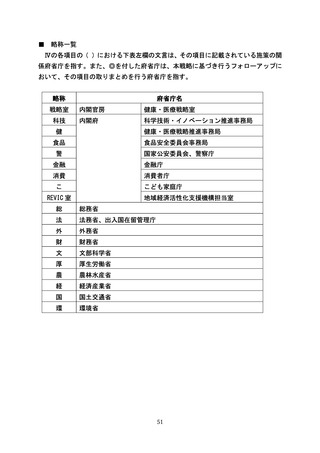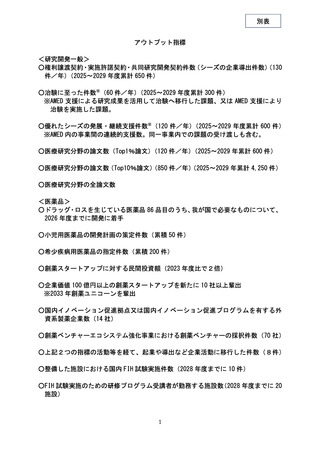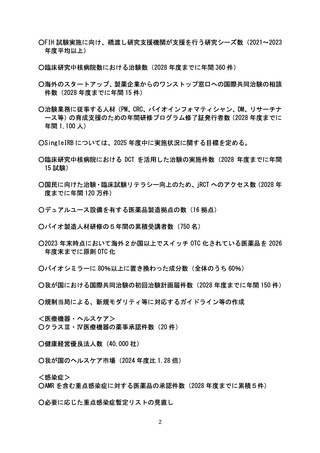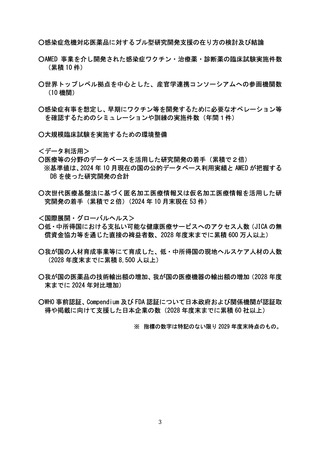よむ、つかう、まなぶ。
資料1-2 第3期健康・医療戦略(案) (50 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/suisin/suisin_dai49/gijisidai.html |
| 出典情報 | 健康・医療戦略推進本部(第49回 2/18)《首相官邸》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
・ 医療情報を研究開発活動により活用していくためには、研究当初の同意取得に加
え、ダイナミックコンセントや ICT・AI 技術を用いた同意取得の在り方や、データ利
活用促進に向けた入口規制の緩和に見合った出口規制の厳格化について検討が必要
である。
(◎健、文、厚、経)
4.8 健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出に関する教育の振興、人材
の育成・確保等に関する施策
○ 多様なプレイヤーと連携し、出口志向の研究開発をリードできる人材の確保
アカデミアやスタートアップの研究開発を実用化に結びつけるためには海外を
含む多様なプレイヤーとの連携が重要であり、出口志向型の研究開発をリードする
アクセラレーター人材が大きな役割を果たしているが、こうした人材は国内にはほ
とんど存在していない。実用化ノウハウを有する人材を海外から国内に呼び込むと
ともに、我が国の創薬・医療機器創出エコシステムの核となる国内人材の育成につ
なげることが重要である。国内の治験・製造体制を活用、日本市場での医薬品等の
上市といった我が国の創薬・医療機器創出エコシステムへの貢献を前提として外資
系企業・外国資金を積極的に呼び込み、海外で実績のあるアクセラレーター人材の
確保を進める。また、医療機器創出について、アイデアの創出から事業化までけん
引可能な企業人材のリスキリングを行うアカデミア等の取組を支援し、人材の確保
を進める。(厚)
○ バイオ製造人材の育成
バイオ医薬品は今後の成長領域であるが、我が国はそのほとんどを海外に依存し、
国内製造されていない現状があり、バイオ医薬品の新薬開発にも支障が生じている。
そのため、これまでに、抗体医薬やウイルスベクターを対象とした研究室スケール
での研修や、ワクチン・バイオ医薬品の国内製造拠点における OJT を主とした人材
育成を通じて、バイオ製造人材の育成を進めてきた。一方で、今後ウイルスベクタ
ーやバイオシミラーを含む新規モダリティの国内製造体制が整備されることに伴
い、一層のバイオ製造人材の確保が必要となることに加え、現状の育成プログラム
では、座学や研究室スケールでの研修といった基礎的な内容しか対応できていない
といった課題が存在する。これらの課題に対応するため、既存の取組は引き続き実
施するとともに、今後は、実生産施設を用いたより実践的な研修の実施や、遺伝子
治療・細胞療法分野における人材育成プログラムの開発・実施により、総合的な観
点からバイオ製造人材の育成を一層進めていく。(◎厚、経)
○ アカデミア人材の育成
新たなモダリティの研究開発やスタートアップ創出にも貢献できる人材を確保・
育成するため、アカデミアにおけるグローバル人材・データサイエンス人材の受入
れを進めるとともに、医学・薬学等の医療人材の養成において、治験・臨床試験の
実施意義、臨床開発方法論等に関する教育等を強化することが重要である。薬学分
野では、創薬に貢献できる人材や現在の世界の主流となっている創薬手法に対応し
た医薬品開発につながる研究力を身に付けるカリキュラム等が不足しており、薬学
教育のカリキュラムの充実や基礎研究の強化、博士課程進学者の増加は喫緊の課題
である。医学・薬学等の医療人材の養成における大学の教育プログラムの充実や、
2026 年度から検討開始予定である次期薬学教育モデル・コア・カリキュラム改訂に
46
え、ダイナミックコンセントや ICT・AI 技術を用いた同意取得の在り方や、データ利
活用促進に向けた入口規制の緩和に見合った出口規制の厳格化について検討が必要
である。
(◎健、文、厚、経)
4.8 健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出に関する教育の振興、人材
の育成・確保等に関する施策
○ 多様なプレイヤーと連携し、出口志向の研究開発をリードできる人材の確保
アカデミアやスタートアップの研究開発を実用化に結びつけるためには海外を
含む多様なプレイヤーとの連携が重要であり、出口志向型の研究開発をリードする
アクセラレーター人材が大きな役割を果たしているが、こうした人材は国内にはほ
とんど存在していない。実用化ノウハウを有する人材を海外から国内に呼び込むと
ともに、我が国の創薬・医療機器創出エコシステムの核となる国内人材の育成につ
なげることが重要である。国内の治験・製造体制を活用、日本市場での医薬品等の
上市といった我が国の創薬・医療機器創出エコシステムへの貢献を前提として外資
系企業・外国資金を積極的に呼び込み、海外で実績のあるアクセラレーター人材の
確保を進める。また、医療機器創出について、アイデアの創出から事業化までけん
引可能な企業人材のリスキリングを行うアカデミア等の取組を支援し、人材の確保
を進める。(厚)
○ バイオ製造人材の育成
バイオ医薬品は今後の成長領域であるが、我が国はそのほとんどを海外に依存し、
国内製造されていない現状があり、バイオ医薬品の新薬開発にも支障が生じている。
そのため、これまでに、抗体医薬やウイルスベクターを対象とした研究室スケール
での研修や、ワクチン・バイオ医薬品の国内製造拠点における OJT を主とした人材
育成を通じて、バイオ製造人材の育成を進めてきた。一方で、今後ウイルスベクタ
ーやバイオシミラーを含む新規モダリティの国内製造体制が整備されることに伴
い、一層のバイオ製造人材の確保が必要となることに加え、現状の育成プログラム
では、座学や研究室スケールでの研修といった基礎的な内容しか対応できていない
といった課題が存在する。これらの課題に対応するため、既存の取組は引き続き実
施するとともに、今後は、実生産施設を用いたより実践的な研修の実施や、遺伝子
治療・細胞療法分野における人材育成プログラムの開発・実施により、総合的な観
点からバイオ製造人材の育成を一層進めていく。(◎厚、経)
○ アカデミア人材の育成
新たなモダリティの研究開発やスタートアップ創出にも貢献できる人材を確保・
育成するため、アカデミアにおけるグローバル人材・データサイエンス人材の受入
れを進めるとともに、医学・薬学等の医療人材の養成において、治験・臨床試験の
実施意義、臨床開発方法論等に関する教育等を強化することが重要である。薬学分
野では、創薬に貢献できる人材や現在の世界の主流となっている創薬手法に対応し
た医薬品開発につながる研究力を身に付けるカリキュラム等が不足しており、薬学
教育のカリキュラムの充実や基礎研究の強化、博士課程進学者の増加は喫緊の課題
である。医学・薬学等の医療人材の養成における大学の教育プログラムの充実や、
2026 年度から検討開始予定である次期薬学教育モデル・コア・カリキュラム改訂に
46