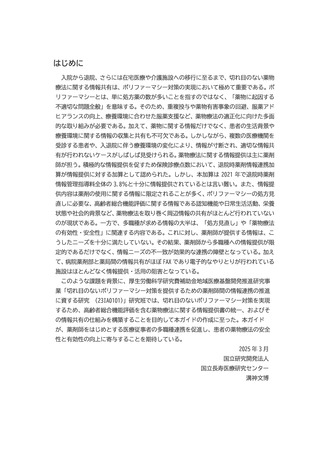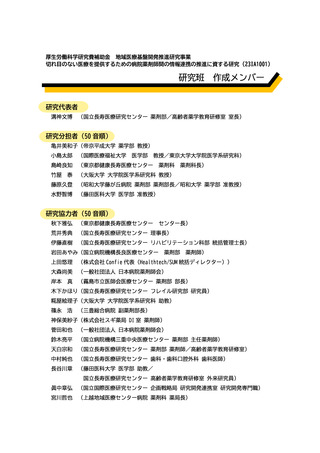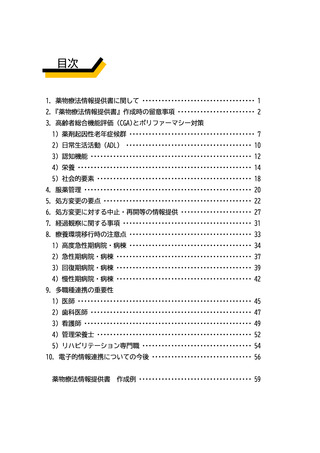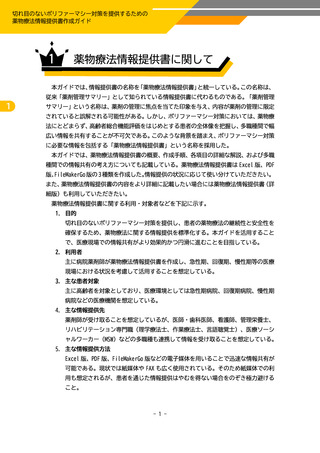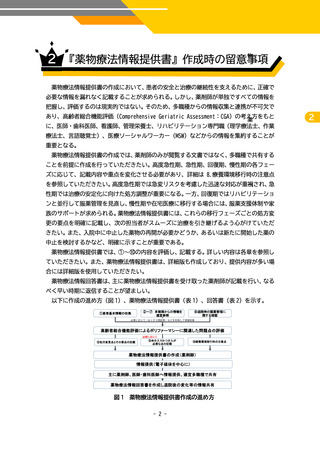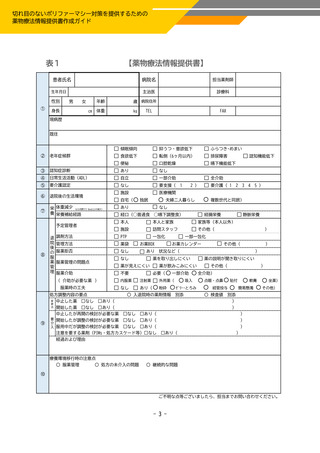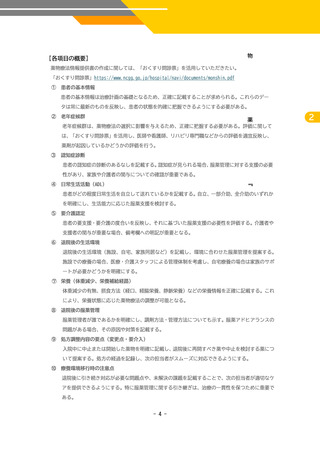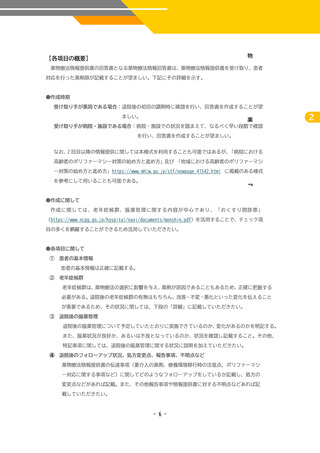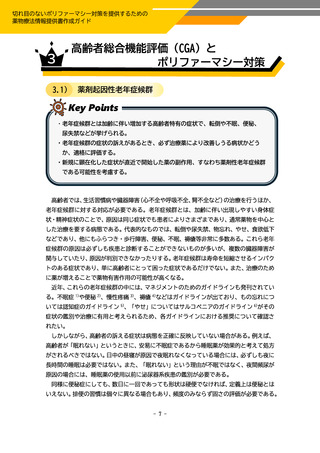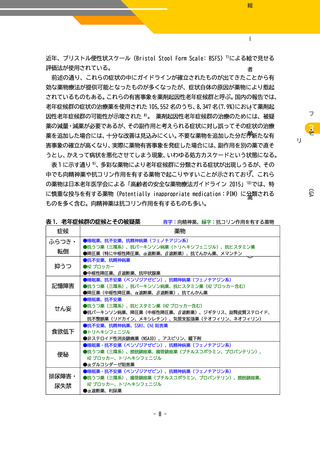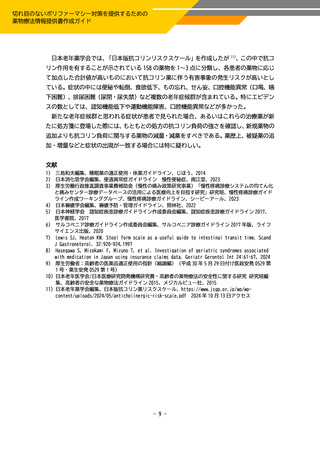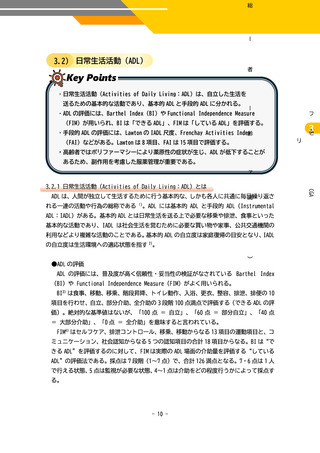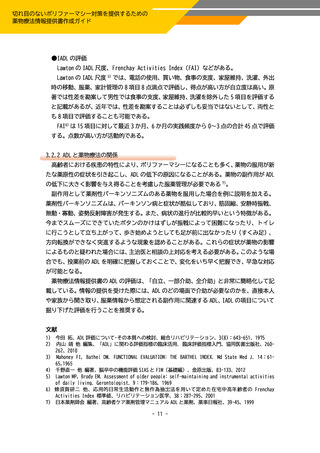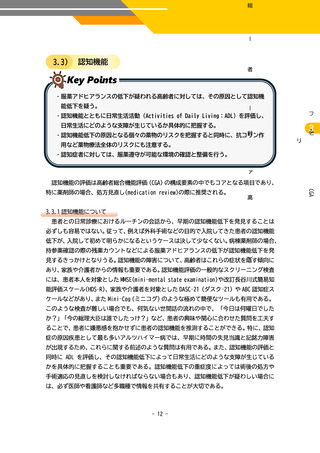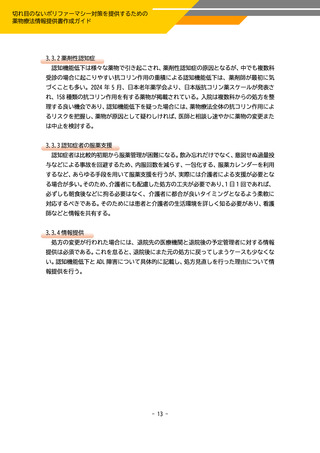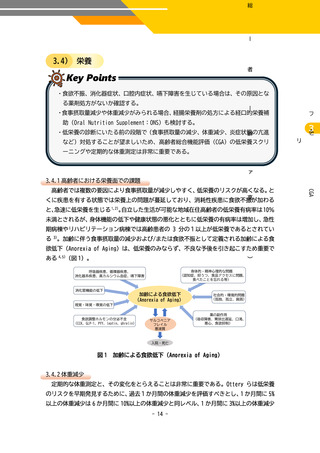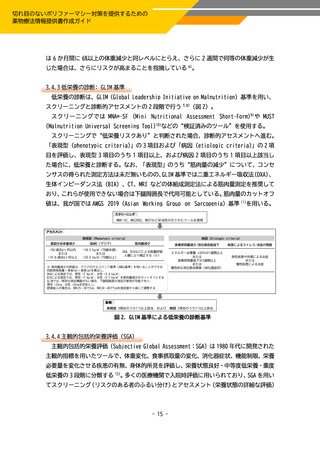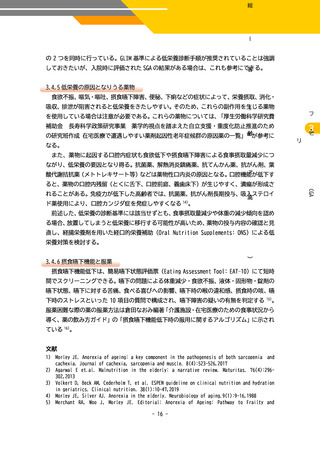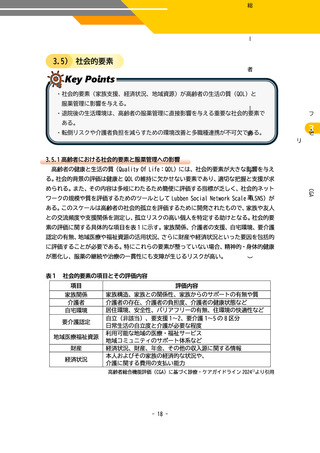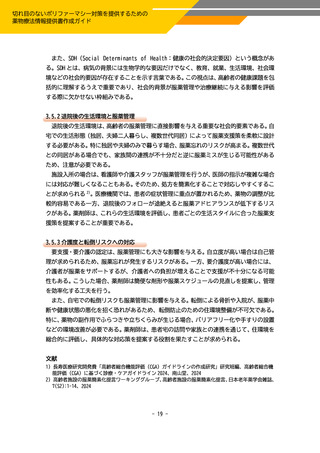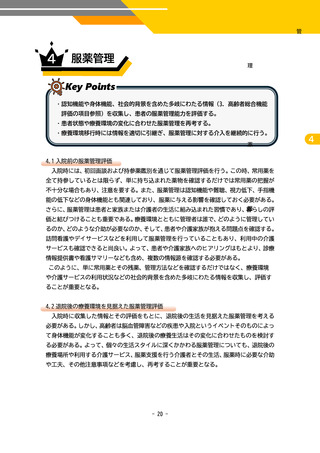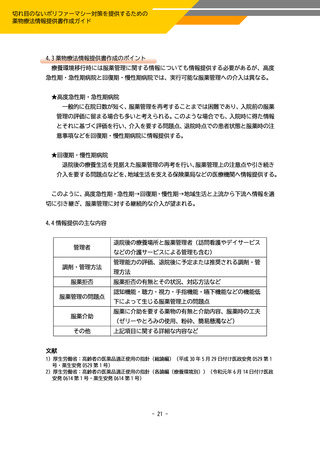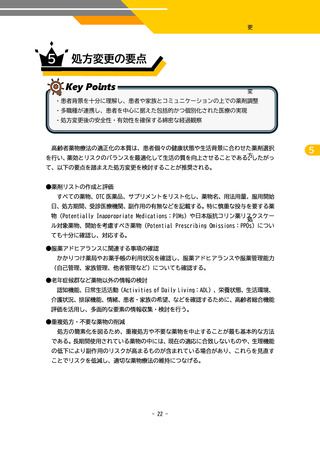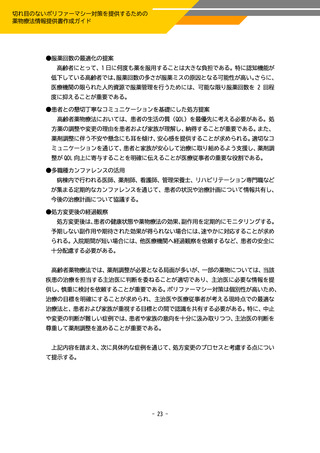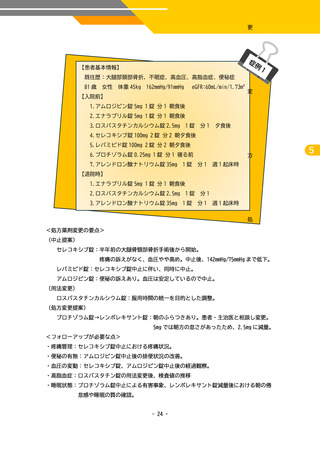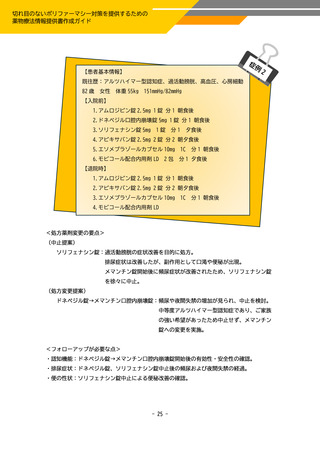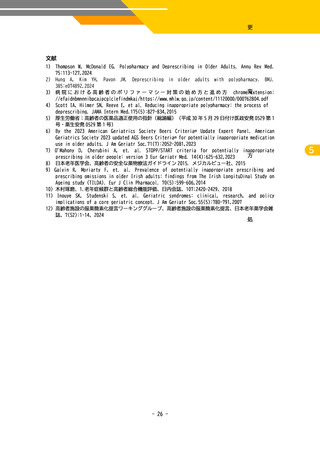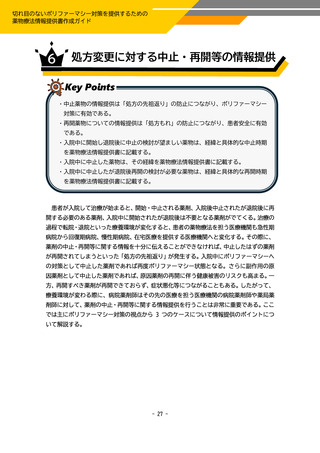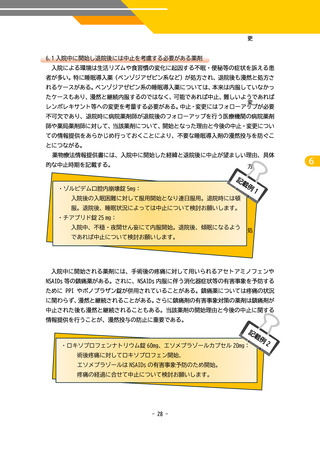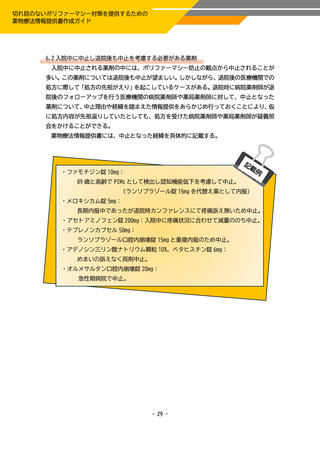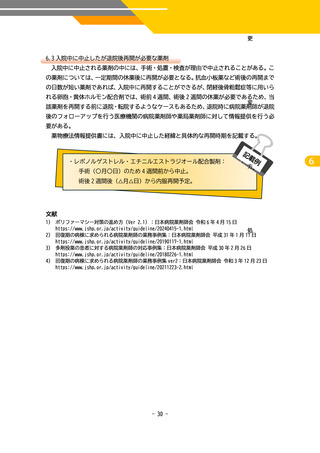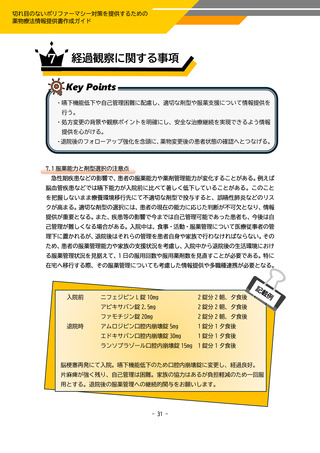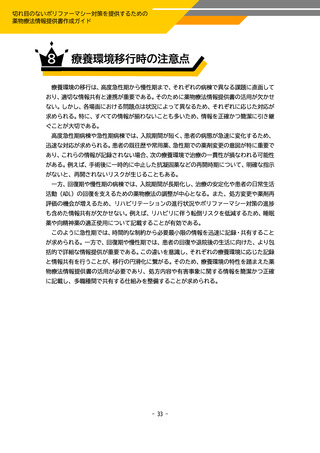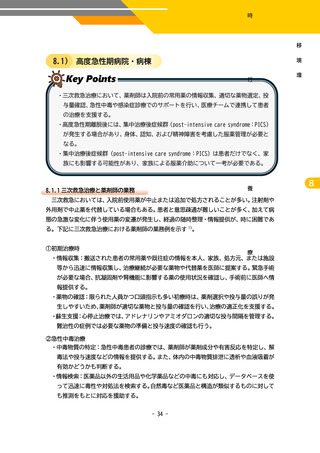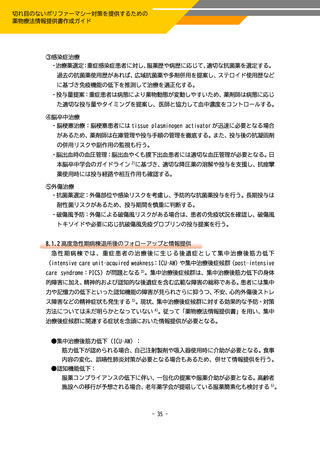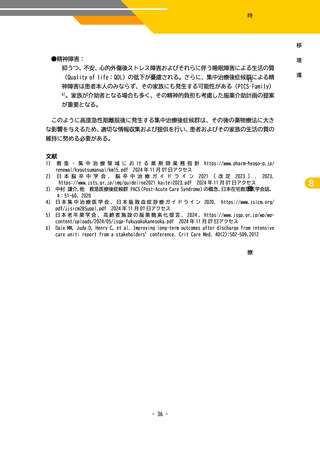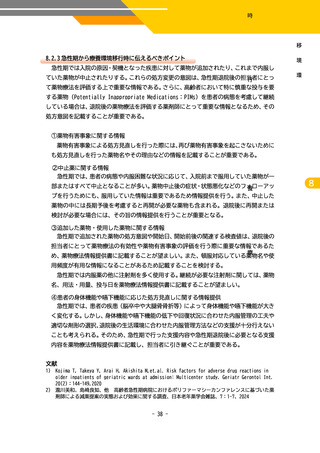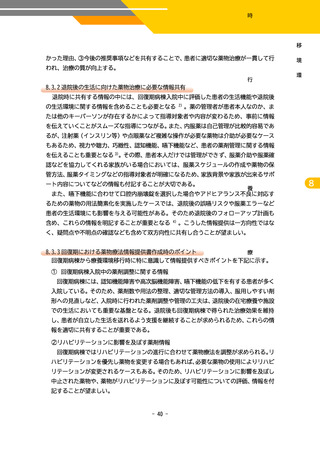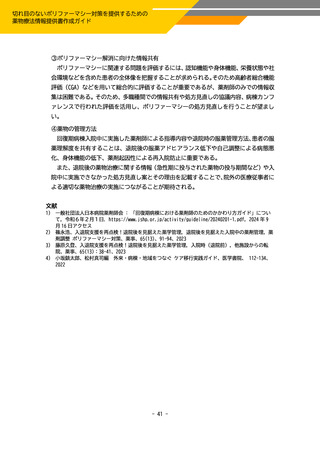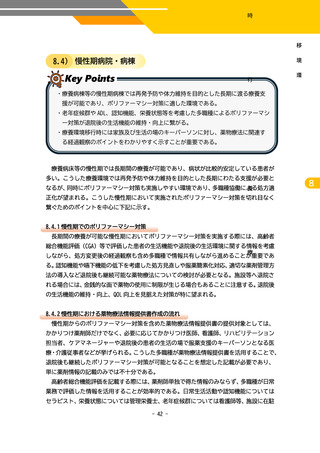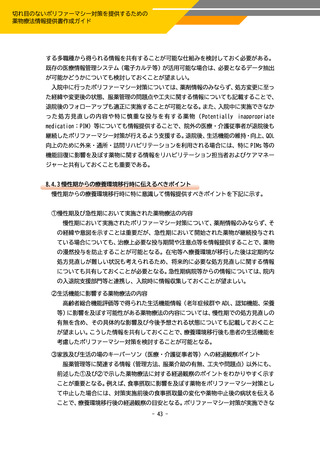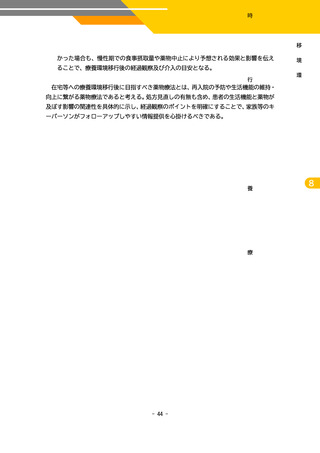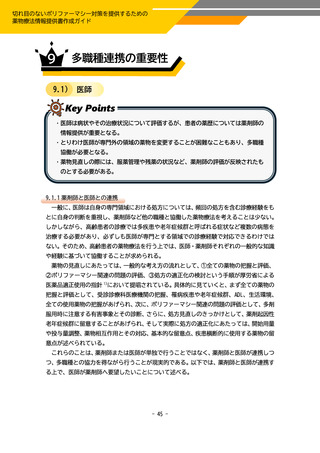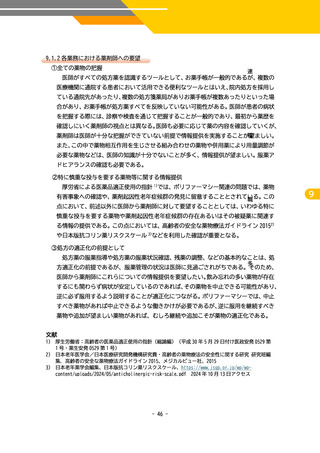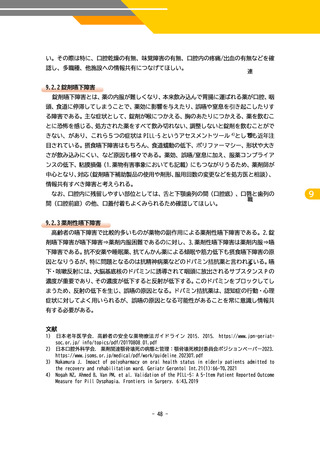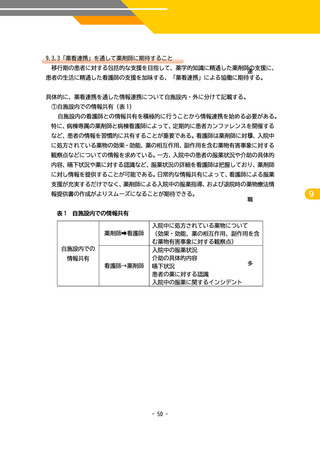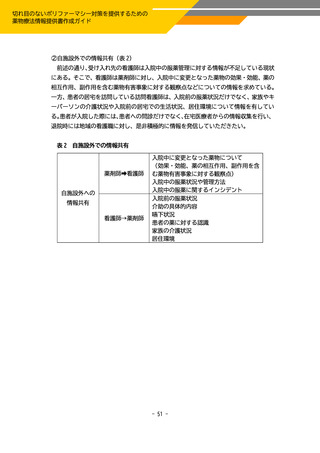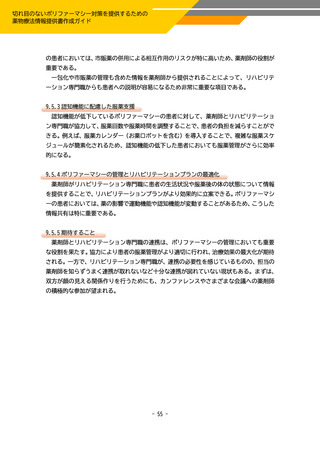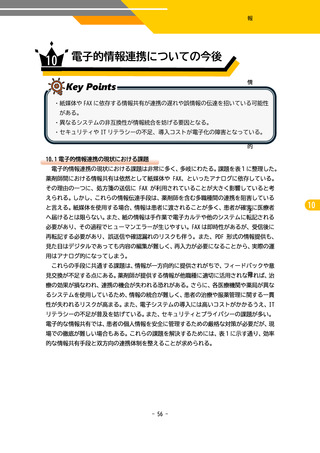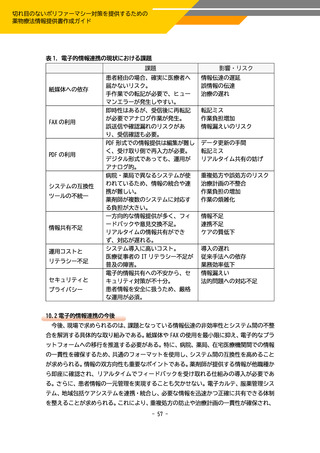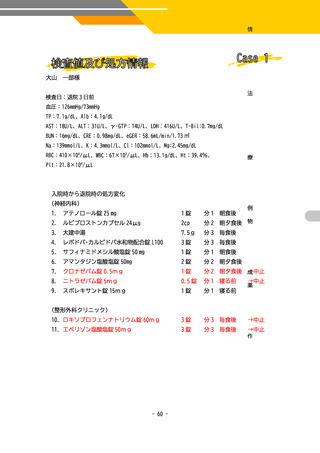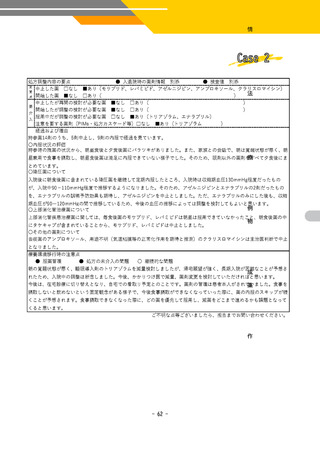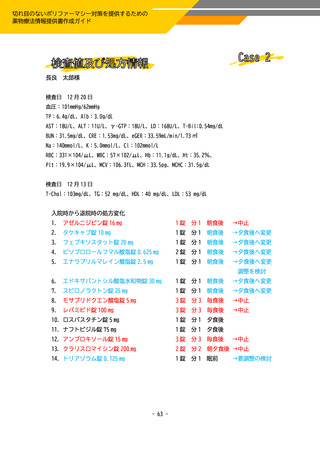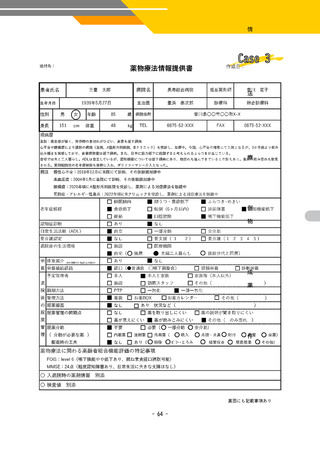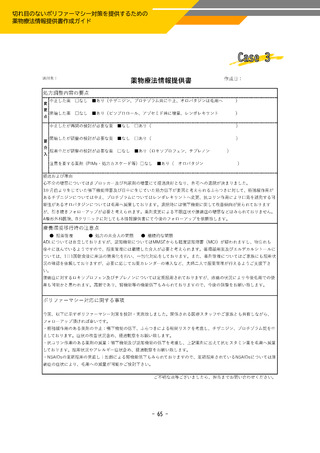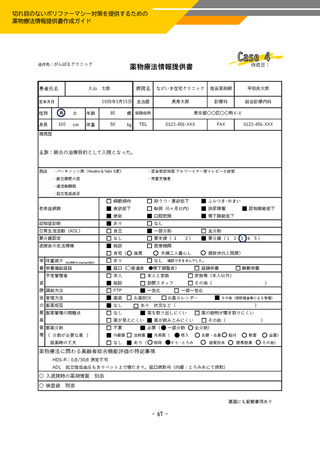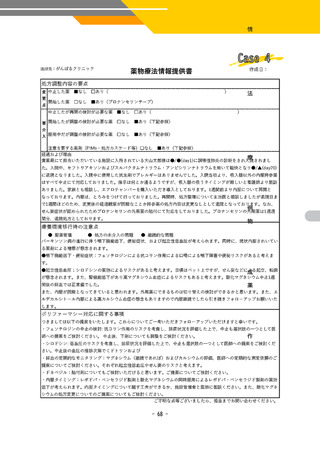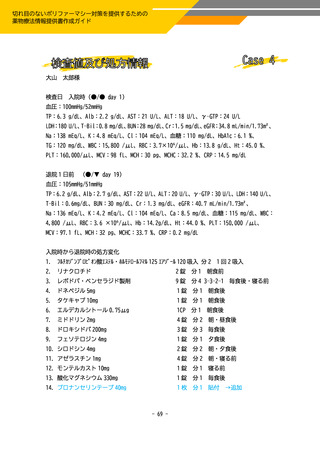よむ、つかう、まなぶ。
切れ目のないポリファーマシー対策を提供するための薬物療法情報提供書作成ガイド (25 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.ncgg.go.jp/hospital/kenshu/news/20250331.html |
| 出典情報 | 切れ目のないポリファーマシー対策を提供するための薬物療法情報提供書作成ガイド(3/31)《国立長寿医療研究センター》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
4
3
服薬管理
Key Points
・認知機能や身体機能、社会的背景を含めた多岐にわたる情報(3.高齢者総合機能
評価の項目参照)を収集し、患者の服薬管理能力を評価する。
・患者状態や療養環境の変化に合わせた服薬管理を再考する。
・療養環境移行時には情報を適切に引継ぎ、服薬管理に対する介入を継続的に行う。
入院時には、初回面談および持参薬鑑別を通じて服薬管理評価を行う。この時、常用薬を
全て持参しているとは限らず、単に持ち込まれた薬物を確認するだけでは常用薬の把握が
不十分な場合もあり、注意を要する。また、服薬管理は認知機能や難聴、視力低下、手指機
能の低下などの身体機能とも関連しており、服薬に与える影響を確認しておく必要がある。
さらに、服薬管理は患者と家族または介護者の生活に組み込まれた習慣であり、暮らしの評
価と結びつけることも重要である。療養環境とともに管理者は誰で、どのように管理してい
るのか、どのような介助が必要なのか、そして、患者や介護家族が抱える問題点を確認する。
訪問看護やデイサービスなどを利用して服薬管理を行っていることもあり、利用中の介護
サービスも確認できると尚良い。よって、患者や介護家族へのヒアリングはもとより、診療
情報提供書や看護サマリーなども含め、複数の情報源を確認する必要がある。
このように、単に常用薬とその残薬、管理方法などを確認するだけではなく、療養環境
や介護サービスの利用状況などの社会的背景を含めた多岐にわたる情報を収集し、評価す
ることが重要となる。
4.2 退院後の療養環境を見据えた服薬管理評価
入院時に収集した情報とその評価をもとに、退院後の生活を見据えた服薬管理を考える
必要がある。しかし、高齢者は脳血管障害などの疾患や入院というイベントそのものによっ
て身体機能が変化することも多く、退院後の療養生活はその変化に合わせたものを検討す
る必要がある。よって、個々の生活スタイルに深くかかわる服薬管理についても、退院後の
療養場所や利用する介護サービス、服薬支援を行う介護者とその生活、服薬時に必要な介助
や工夫、その他注意事項などを考慮し、再考することが重要となる。
- 20 -
服管
薬理
管理
服薬
4.1 入院前の服薬管理評価
4
4
3
服薬管理
Key Points
・認知機能や身体機能、社会的背景を含めた多岐にわたる情報(3.高齢者総合機能
評価の項目参照)を収集し、患者の服薬管理能力を評価する。
・患者状態や療養環境の変化に合わせた服薬管理を再考する。
・療養環境移行時には情報を適切に引継ぎ、服薬管理に対する介入を継続的に行う。
入院時には、初回面談および持参薬鑑別を通じて服薬管理評価を行う。この時、常用薬を
全て持参しているとは限らず、単に持ち込まれた薬物を確認するだけでは常用薬の把握が
不十分な場合もあり、注意を要する。また、服薬管理は認知機能や難聴、視力低下、手指機
能の低下などの身体機能とも関連しており、服薬に与える影響を確認しておく必要がある。
さらに、服薬管理は患者と家族または介護者の生活に組み込まれた習慣であり、暮らしの評
価と結びつけることも重要である。療養環境とともに管理者は誰で、どのように管理してい
るのか、どのような介助が必要なのか、そして、患者や介護家族が抱える問題点を確認する。
訪問看護やデイサービスなどを利用して服薬管理を行っていることもあり、利用中の介護
サービスも確認できると尚良い。よって、患者や介護家族へのヒアリングはもとより、診療
情報提供書や看護サマリーなども含め、複数の情報源を確認する必要がある。
このように、単に常用薬とその残薬、管理方法などを確認するだけではなく、療養環境
や介護サービスの利用状況などの社会的背景を含めた多岐にわたる情報を収集し、評価す
ることが重要となる。
4.2 退院後の療養環境を見据えた服薬管理評価
入院時に収集した情報とその評価をもとに、退院後の生活を見据えた服薬管理を考える
必要がある。しかし、高齢者は脳血管障害などの疾患や入院というイベントそのものによっ
て身体機能が変化することも多く、退院後の療養生活はその変化に合わせたものを検討す
る必要がある。よって、個々の生活スタイルに深くかかわる服薬管理についても、退院後の
療養場所や利用する介護サービス、服薬支援を行う介護者とその生活、服薬時に必要な介助
や工夫、その他注意事項などを考慮し、再考することが重要となる。
- 20 -
服管
薬理
管理
服薬
4.1 入院前の服薬管理評価
4
4