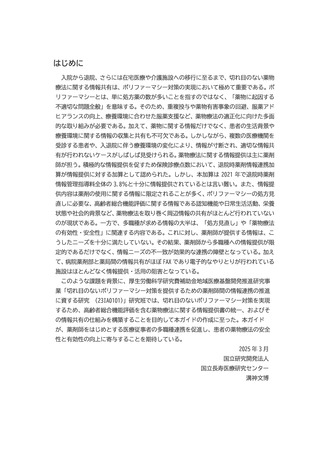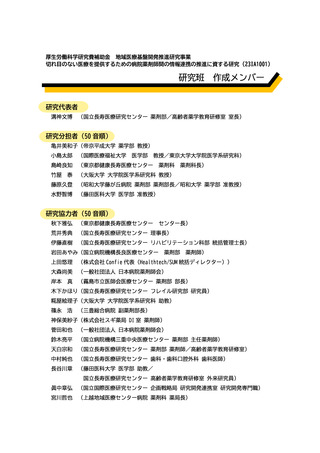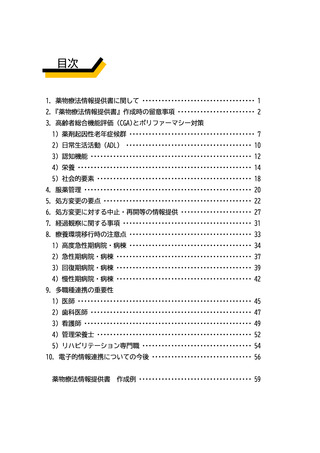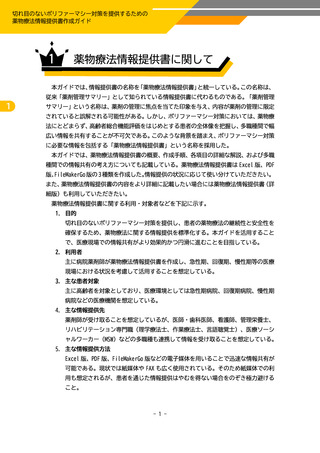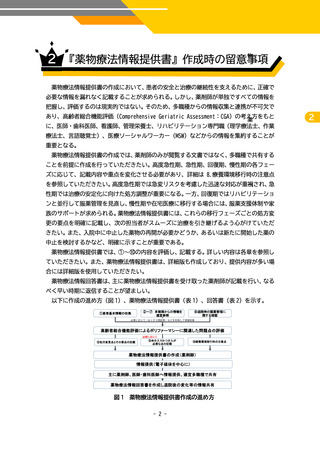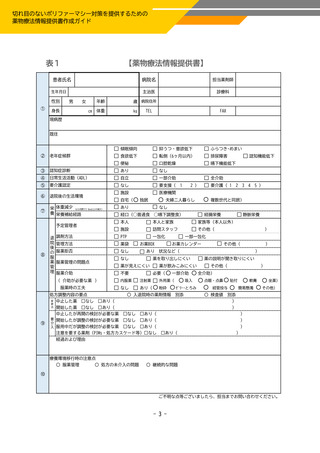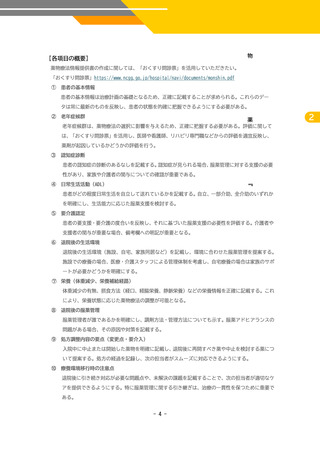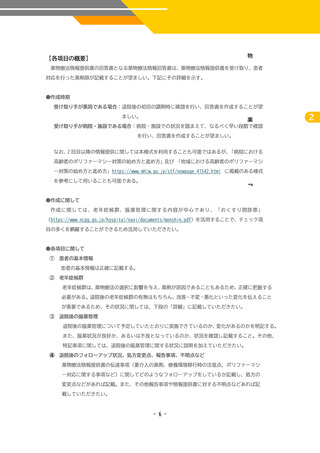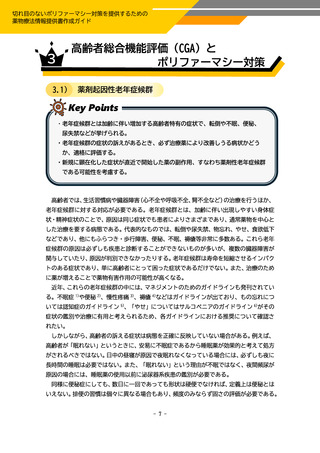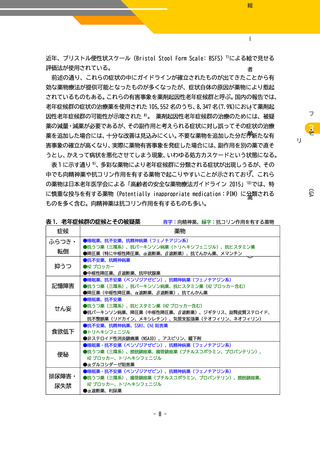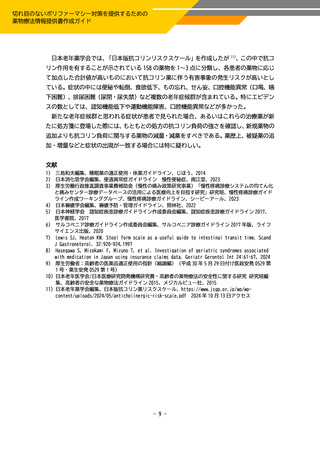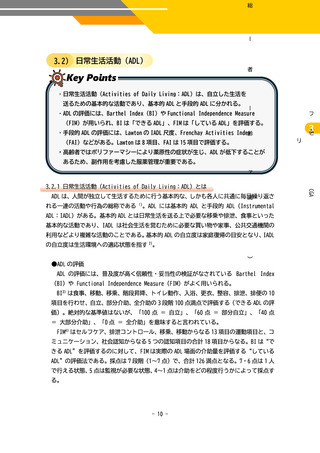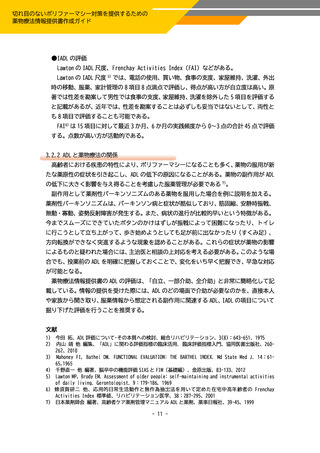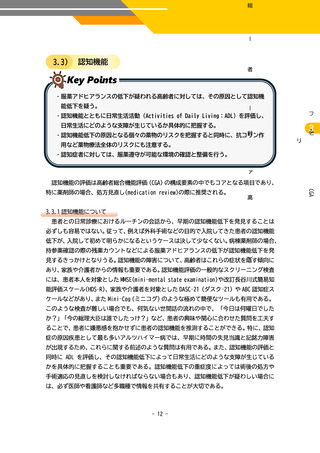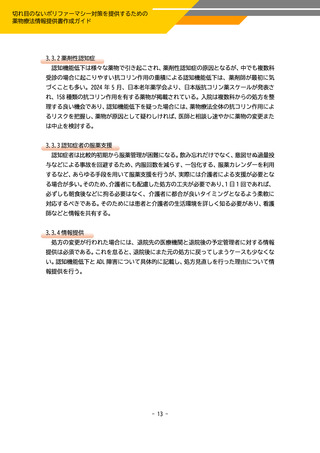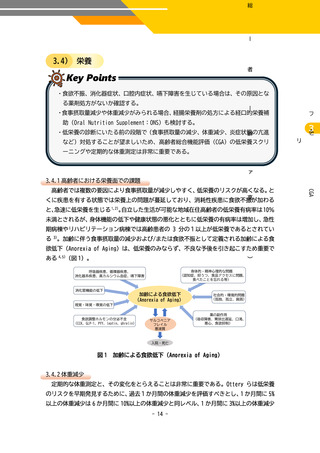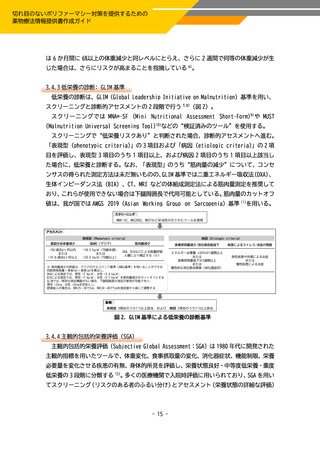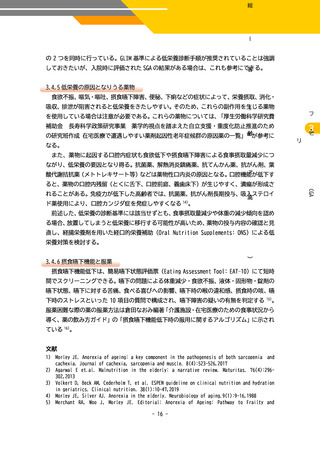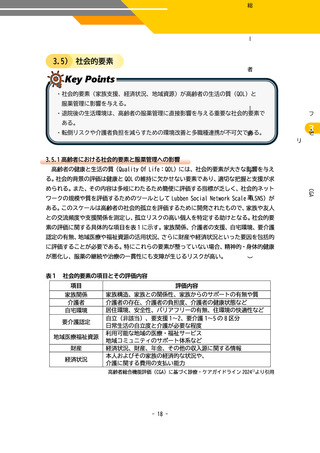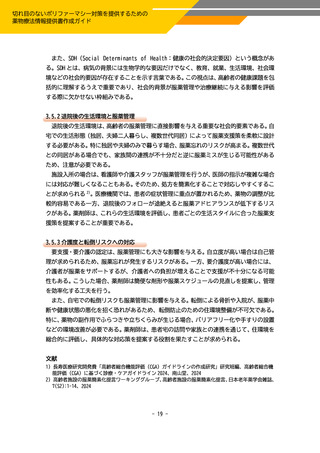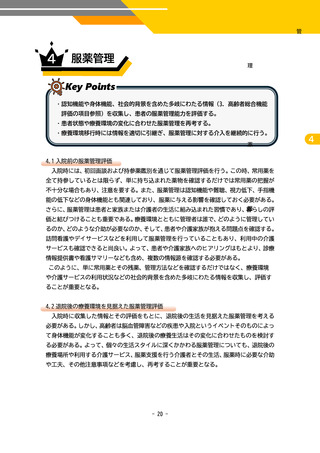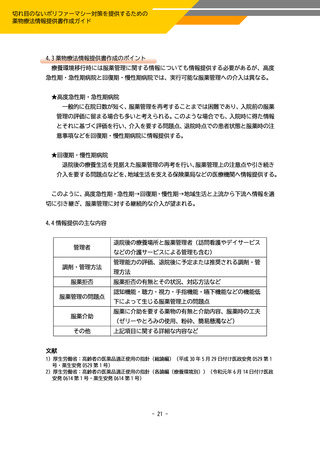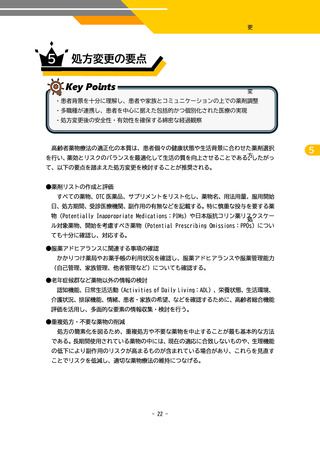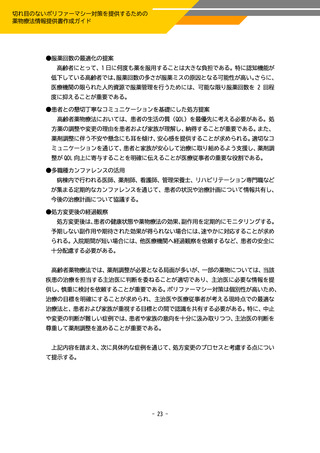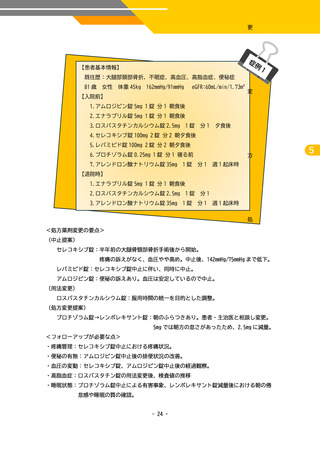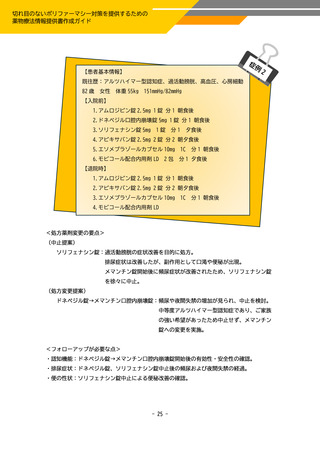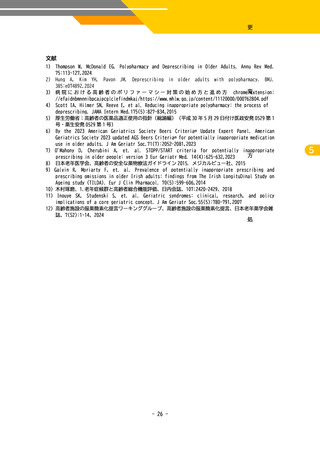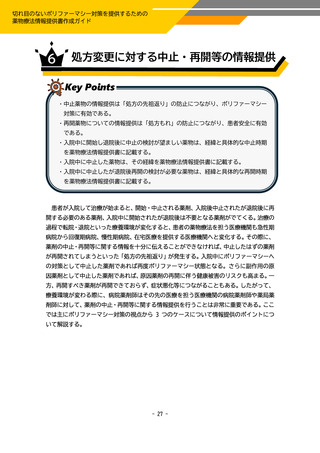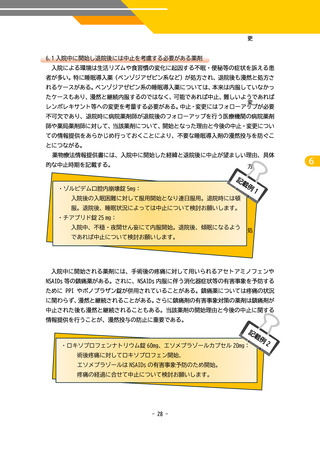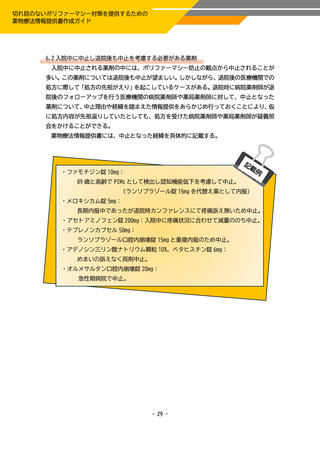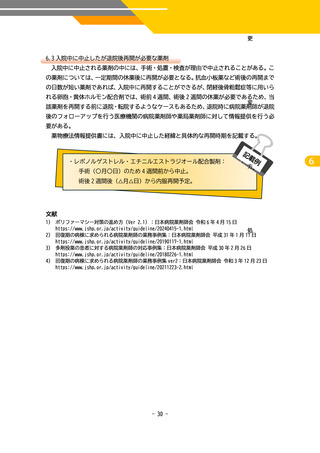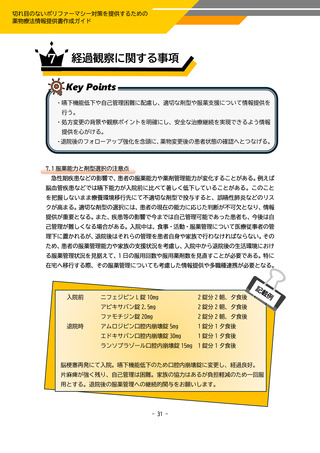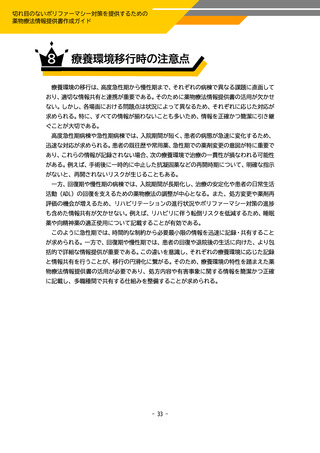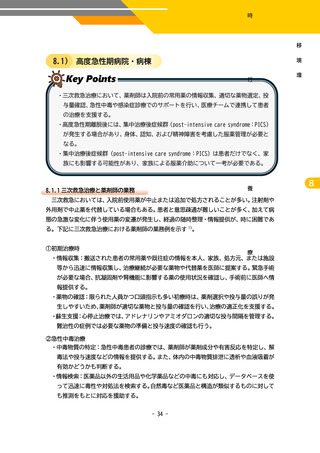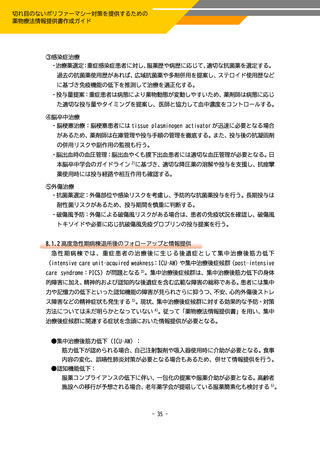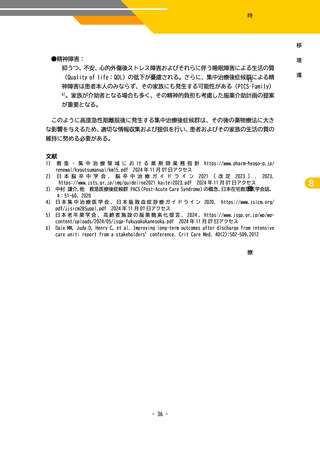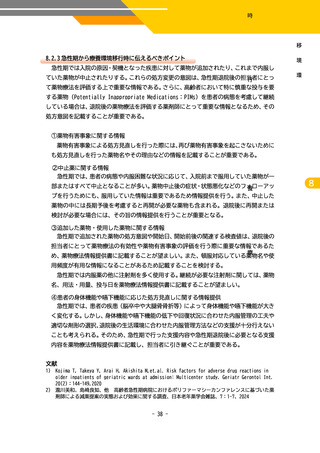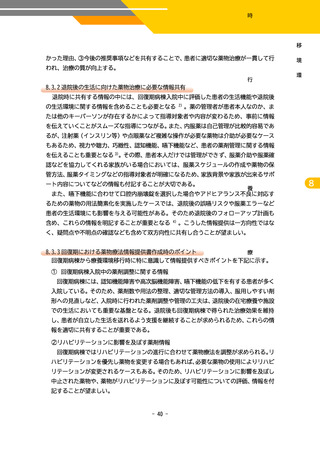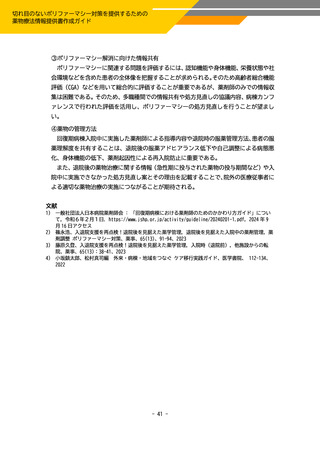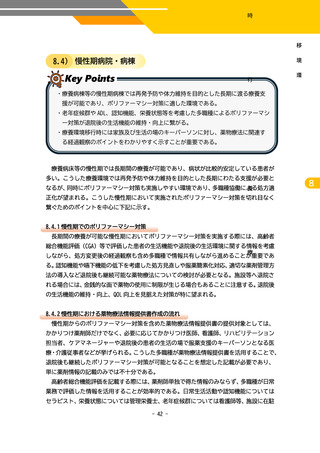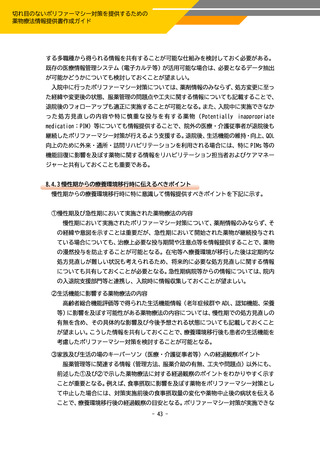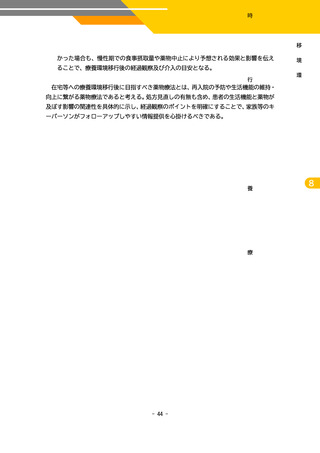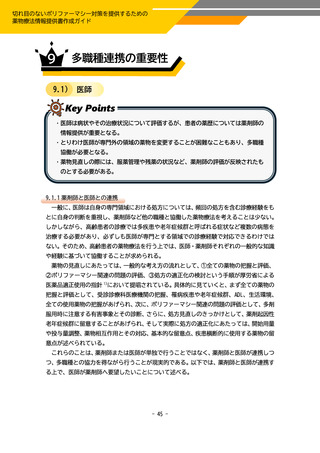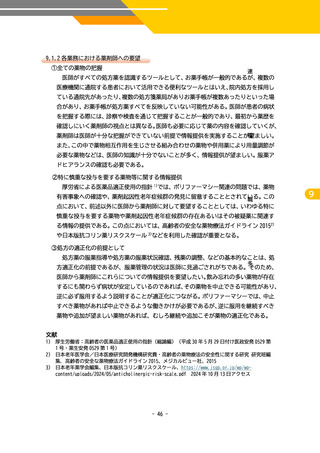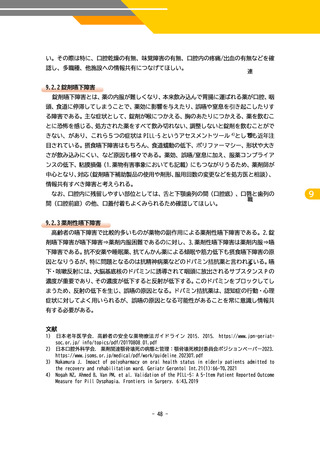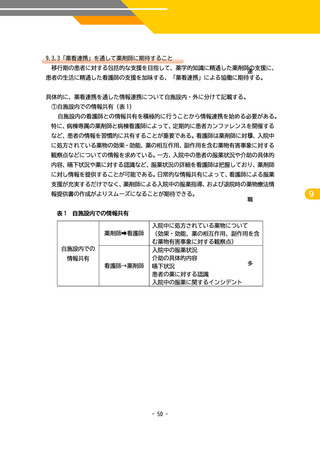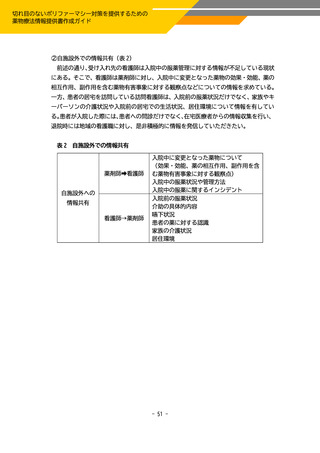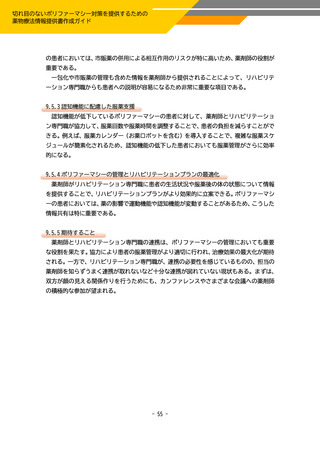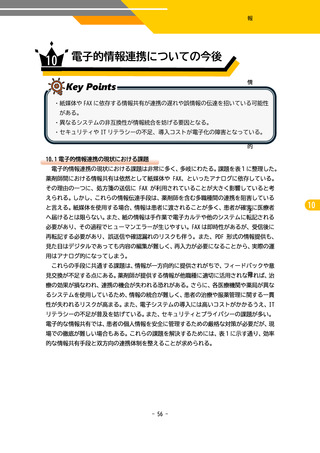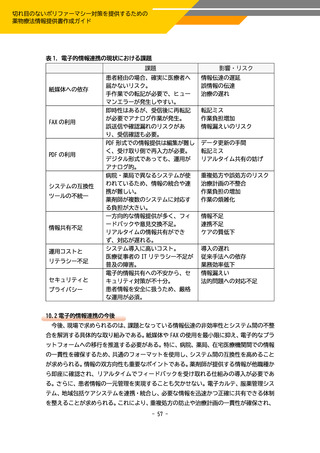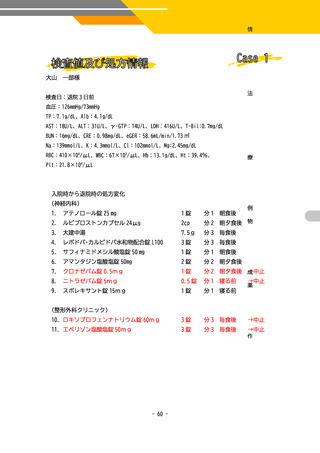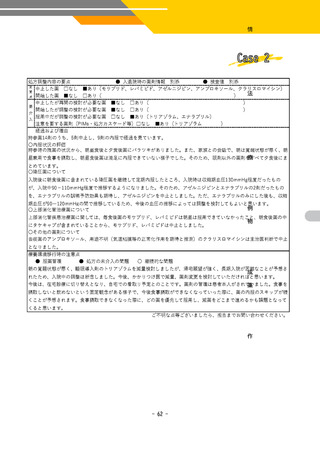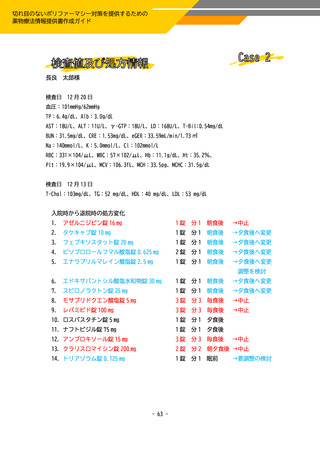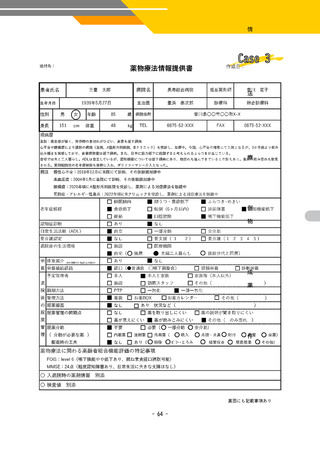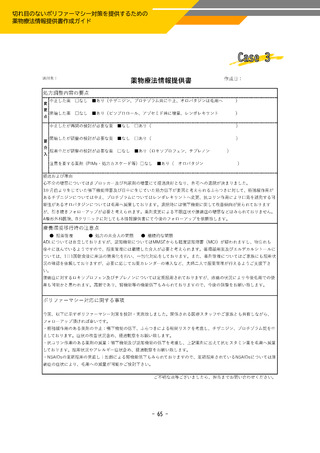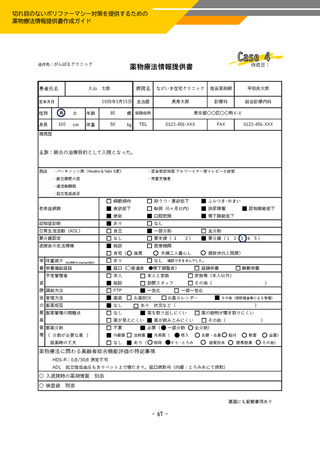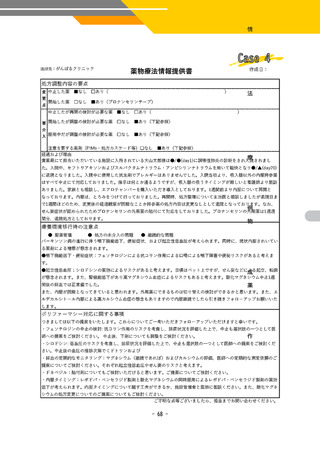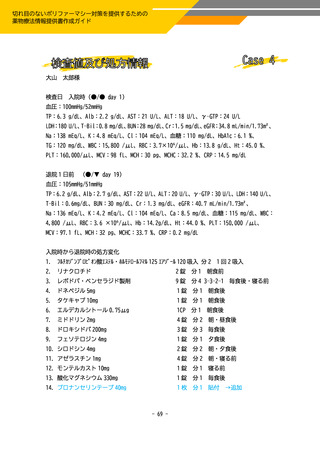よむ、つかう、まなぶ。
切れ目のないポリファーマシー対策を提供するための薬物療法情報提供書作成ガイド (51 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.ncgg.go.jp/hospital/kenshu/news/20250331.html |
| 出典情報 | 切れ目のないポリファーマシー対策を提供するための薬物療法情報提供書作成ガイド(3/31)《国立長寿医療研究センター》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
9.1.2 各業務における薬剤師への要望
①全ての薬物の把握
医師がすべての処方薬を認識するツールとして、お薬手帳が一般的であるが、複数の
医療機関に通院する患者において活用できる便利なツールとはいえ、院内処方を採用し
ている通院先があったり、複数の処方箋薬局がありお薬手帳が複数あったりといった場
合があり、お薬手帳が処方薬すべてを反映していない可能性がある。医師が患者の病状
を把握する際には、診察や検査を通じて把握することが一般的であり、最初から薬歴を
確認しにいく薬剤師の視点とは異なる。医師も必要に応じて薬の内容を確認していくが、
薬剤師は医師が十分な把握ができていない前提で情報提供を実施することが望ましい。
また、この中で薬物相互作用を生じさせる組み合わせの薬物や併用薬により用量調節が
必要な薬物などは、医師の知識が十分でないことが多く、情報提供が望ましい。服薬ア
ドヒアランスの確認も必要である。
②特に慎重な投与を要する薬物等に関する情報提供
厚労省による医薬品適正使用の指針 1)では、ポリファーマシー関連の問題では、薬物
点において、前述以外に医師から薬剤師に対して要望することとしては、いわゆる特に
慎重な投与を要する薬物や薬剤起因性老年症候群の存在あるいはその被疑薬に関連す
る情報の提供である。この点においては、高齢者の安全な薬物療法ガイドライン 20152)
や日本版抗コリン薬リスクスケール 3)などを利用した確認が重要となる。
③処方の適正化の前提として
処方薬の服薬指導や処方薬の服薬状況確認、残薬の調整、などの基本的なことは、処
方適正化の前提であるが、服薬管理の状況は医師に見過ごされがちである。そのため、
医師から薬剤師にこれらについての情報提供を要望したい。飲み忘れの多い薬物が存在
するにも関わらず病状が安定しているのであれば、その薬物を中止できる可能性があり、
逆に必ず服用するよう説明することが適正化につながる。ポリファーマシーでは、中止
すべき薬物があれば中止できるような働きかけが必要であるが、逆に服用を継続すべき
薬物や追加が望ましい薬物があれば、むしろ継続や追加こそが薬物の適正化である。
文献
1)
厚生労働省:高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編)(平成 30 年 5 月 29 日付け医政安発 0529 第
1 号・薬生安発 0529 第 1 号)
2) 日本老年医学会/日本医療研究開発機構研究費・高齢者の薬物療法の安全性に関する研究 研究班編
集.高齢者の安全な薬物療法ガイドライン 2015、メジカルビュー社、2015
3) 日本老年薬学会編集、日本版抗コリン薬リスクスケール、https://www.jsgp.or.jp/wp/wpcontent/uploads/2024/05/anticholinergic-risk-scale.pdf 2024 年 10 月 13 日アクセス
- 46 -
9
9
多職
職種
種連
連携
携の
の重
重要
要性
性
多
有害事象への確認や、薬剤起因性老年症候群の発見に留意することとされている。この
①全ての薬物の把握
医師がすべての処方薬を認識するツールとして、お薬手帳が一般的であるが、複数の
医療機関に通院する患者において活用できる便利なツールとはいえ、院内処方を採用し
ている通院先があったり、複数の処方箋薬局がありお薬手帳が複数あったりといった場
合があり、お薬手帳が処方薬すべてを反映していない可能性がある。医師が患者の病状
を把握する際には、診察や検査を通じて把握することが一般的であり、最初から薬歴を
確認しにいく薬剤師の視点とは異なる。医師も必要に応じて薬の内容を確認していくが、
薬剤師は医師が十分な把握ができていない前提で情報提供を実施することが望ましい。
また、この中で薬物相互作用を生じさせる組み合わせの薬物や併用薬により用量調節が
必要な薬物などは、医師の知識が十分でないことが多く、情報提供が望ましい。服薬ア
ドヒアランスの確認も必要である。
②特に慎重な投与を要する薬物等に関する情報提供
厚労省による医薬品適正使用の指針 1)では、ポリファーマシー関連の問題では、薬物
点において、前述以外に医師から薬剤師に対して要望することとしては、いわゆる特に
慎重な投与を要する薬物や薬剤起因性老年症候群の存在あるいはその被疑薬に関連す
る情報の提供である。この点においては、高齢者の安全な薬物療法ガイドライン 20152)
や日本版抗コリン薬リスクスケール 3)などを利用した確認が重要となる。
③処方の適正化の前提として
処方薬の服薬指導や処方薬の服薬状況確認、残薬の調整、などの基本的なことは、処
方適正化の前提であるが、服薬管理の状況は医師に見過ごされがちである。そのため、
医師から薬剤師にこれらについての情報提供を要望したい。飲み忘れの多い薬物が存在
するにも関わらず病状が安定しているのであれば、その薬物を中止できる可能性があり、
逆に必ず服用するよう説明することが適正化につながる。ポリファーマシーでは、中止
すべき薬物があれば中止できるような働きかけが必要であるが、逆に服用を継続すべき
薬物や追加が望ましい薬物があれば、むしろ継続や追加こそが薬物の適正化である。
文献
1)
厚生労働省:高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編)(平成 30 年 5 月 29 日付け医政安発 0529 第
1 号・薬生安発 0529 第 1 号)
2) 日本老年医学会/日本医療研究開発機構研究費・高齢者の薬物療法の安全性に関する研究 研究班編
集.高齢者の安全な薬物療法ガイドライン 2015、メジカルビュー社、2015
3) 日本老年薬学会編集、日本版抗コリン薬リスクスケール、https://www.jsgp.or.jp/wp/wpcontent/uploads/2024/05/anticholinergic-risk-scale.pdf 2024 年 10 月 13 日アクセス
- 46 -
9
9
多職
職種
種連
連携
携の
の重
重要
要性
性
多
有害事象への確認や、薬剤起因性老年症候群の発見に留意することとされている。この