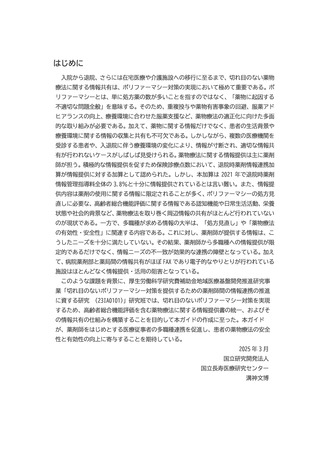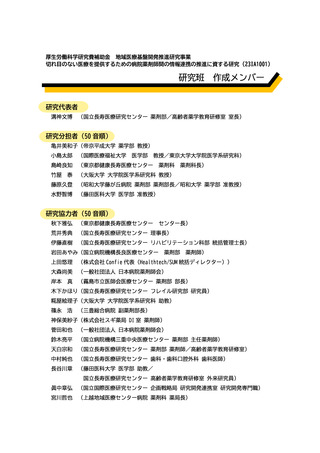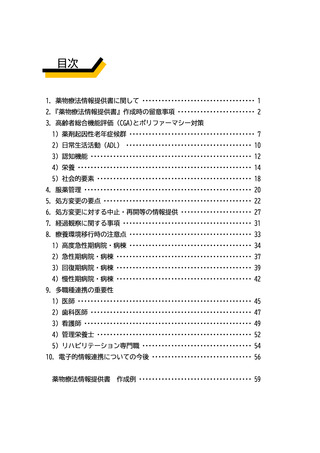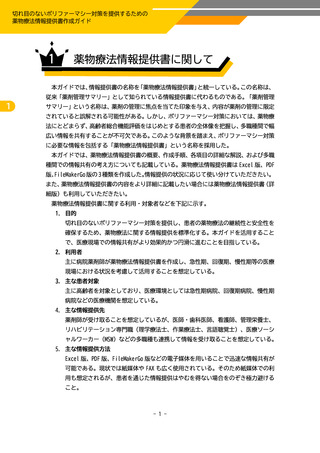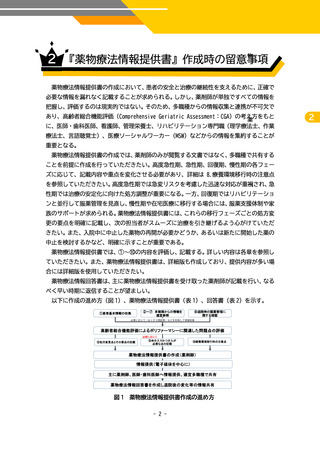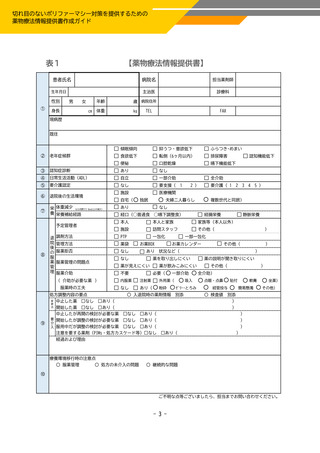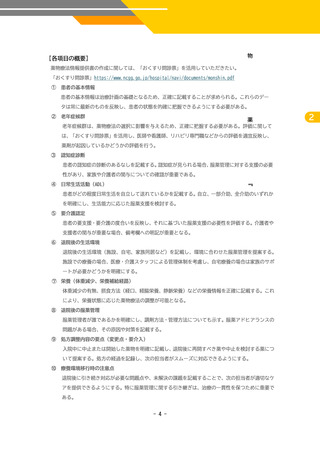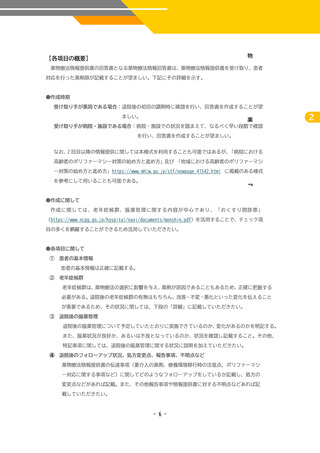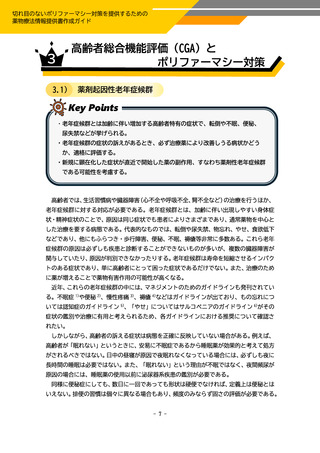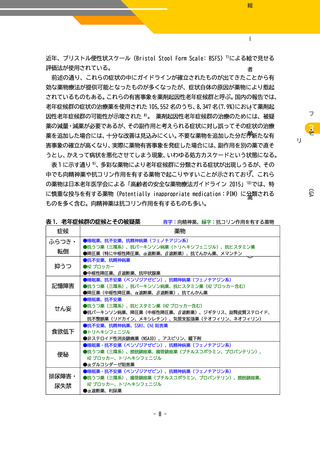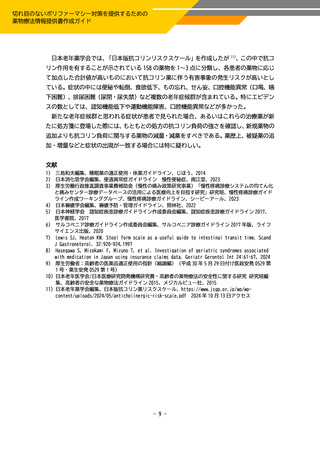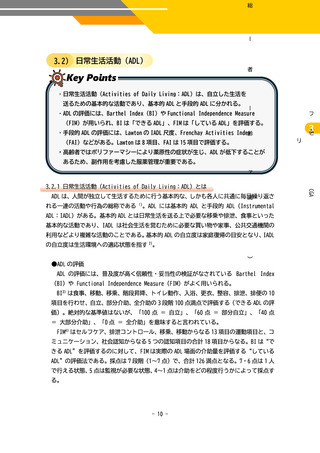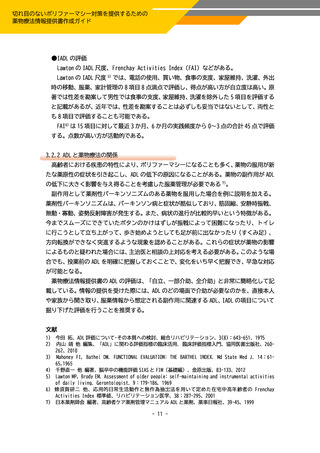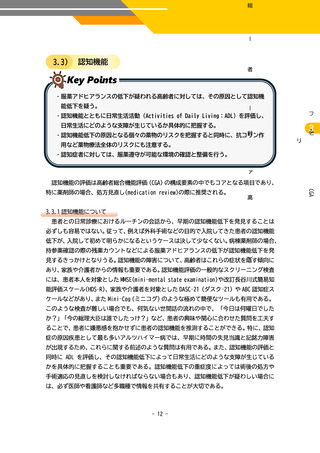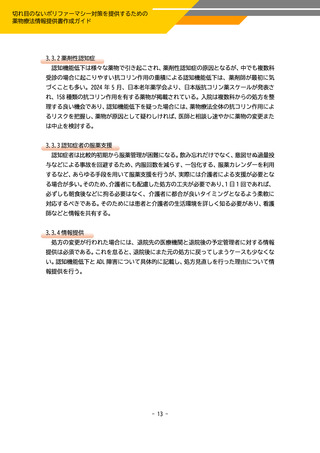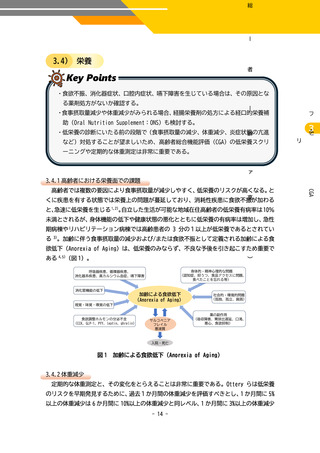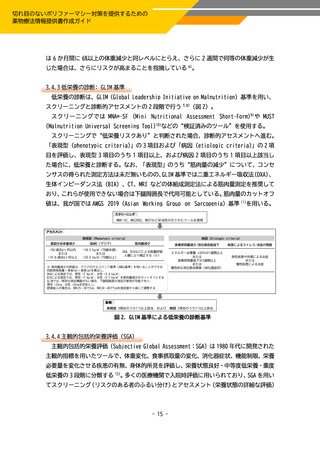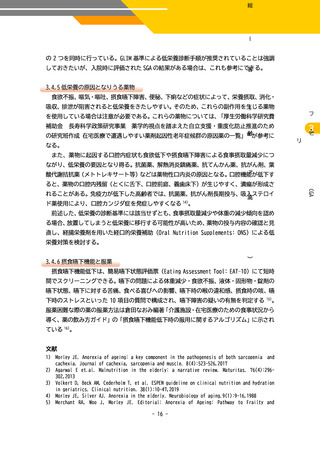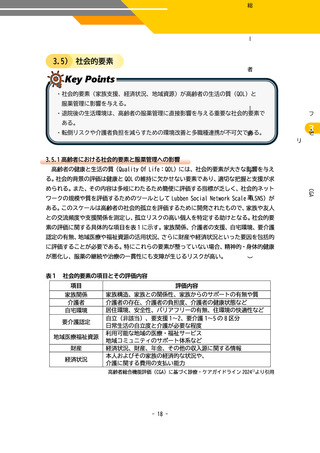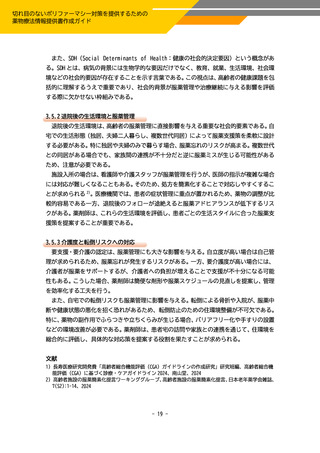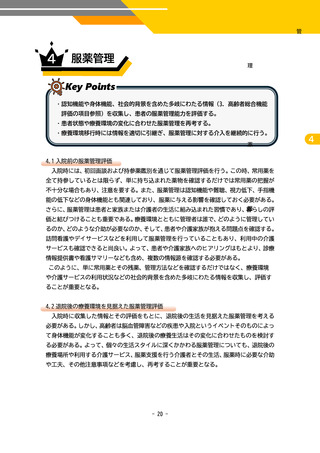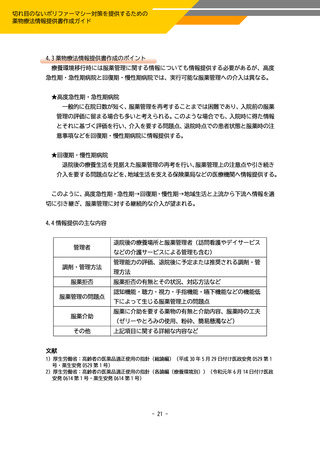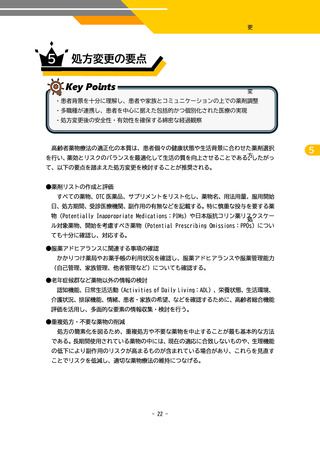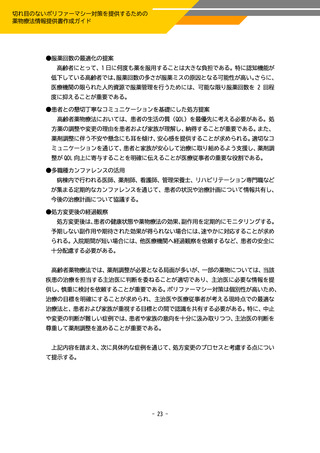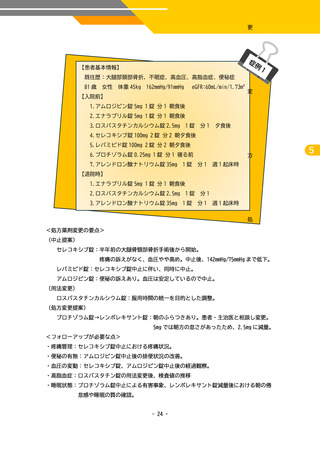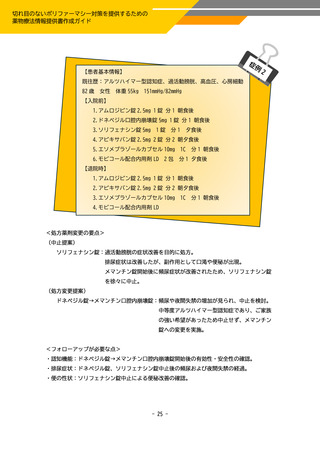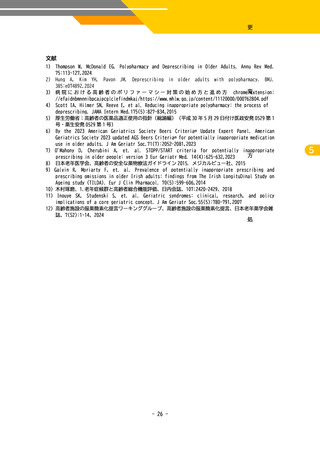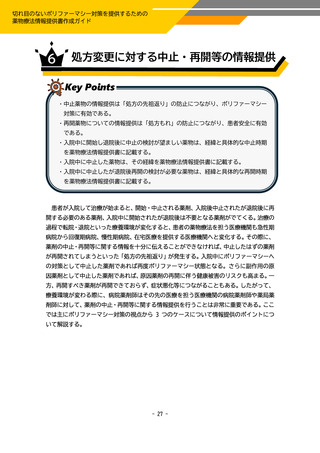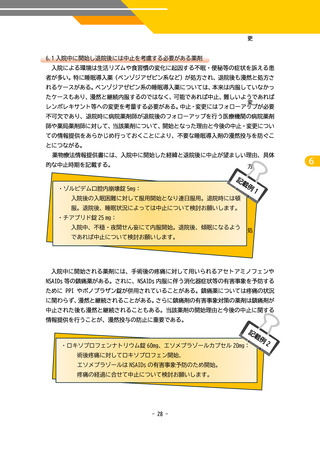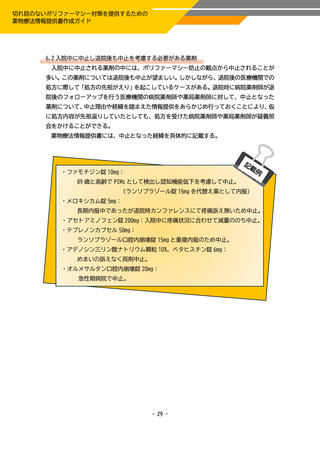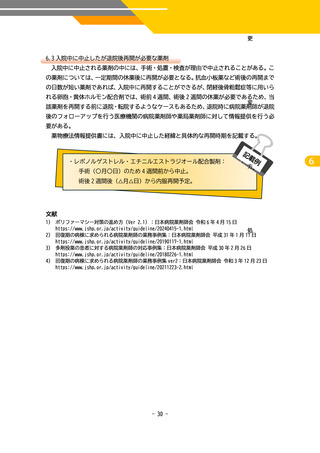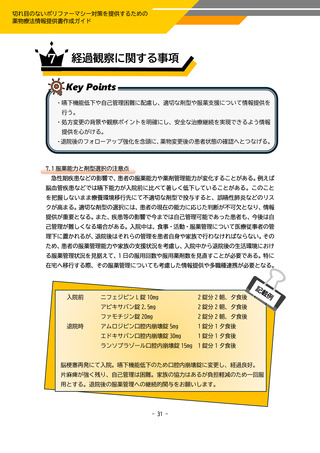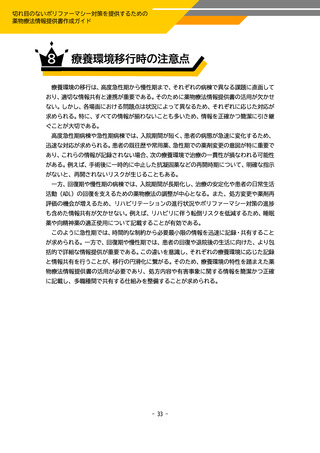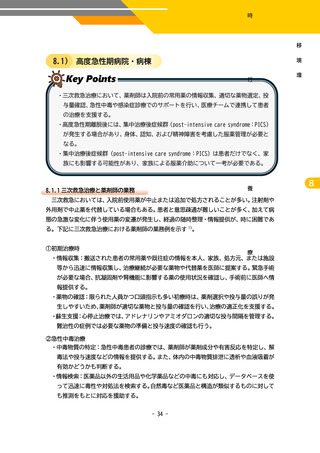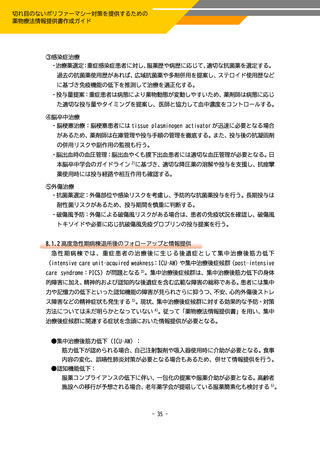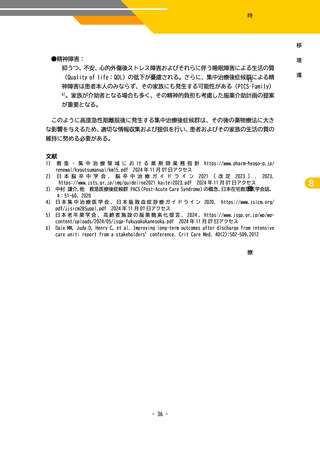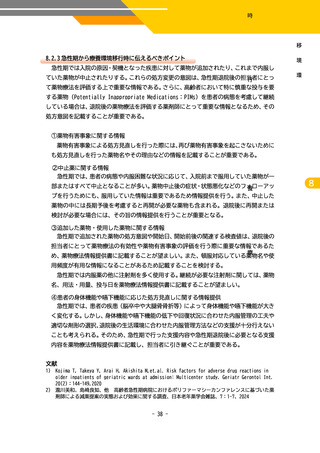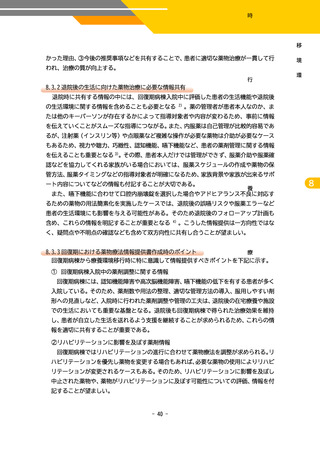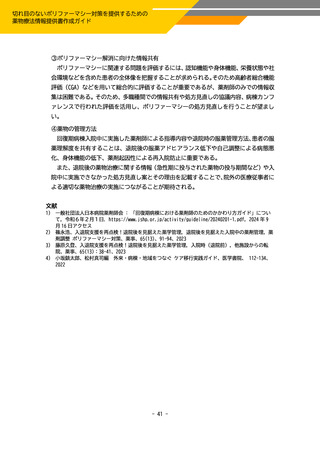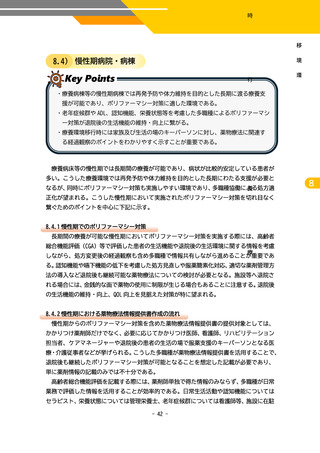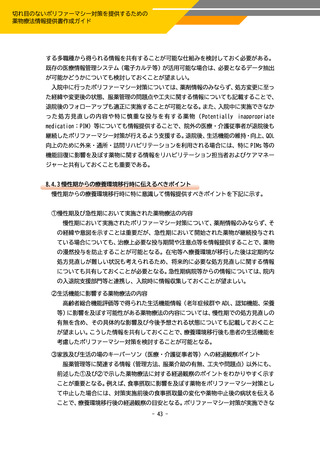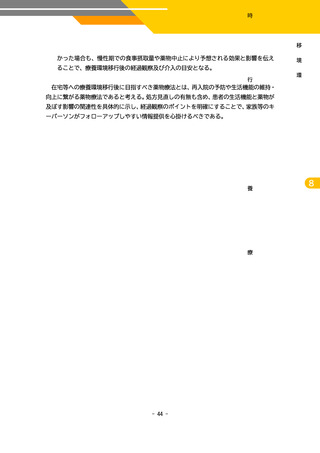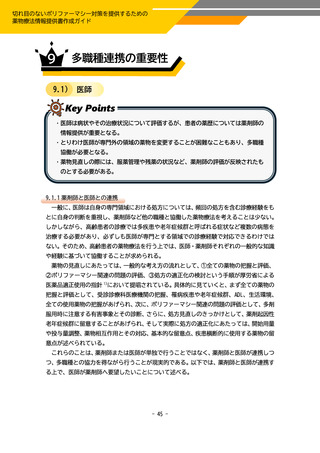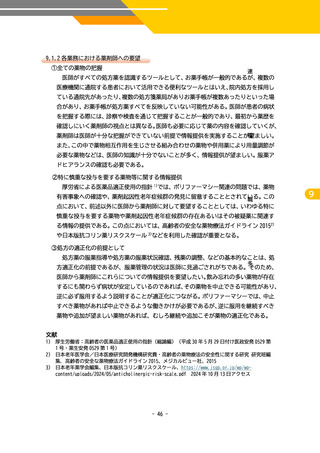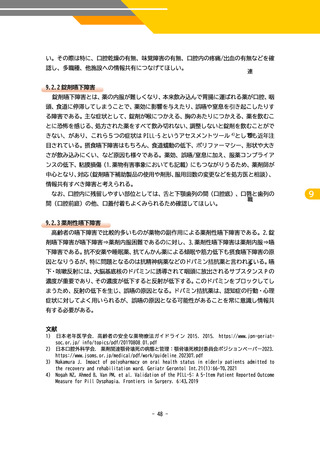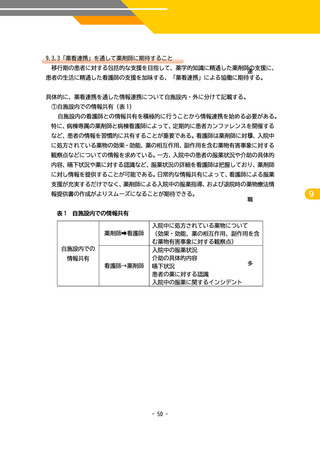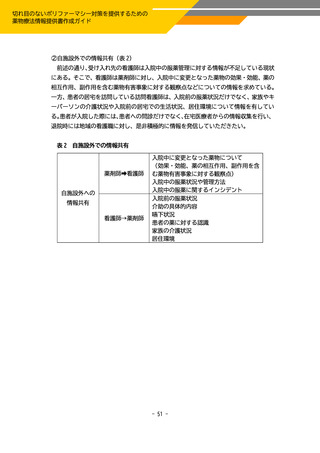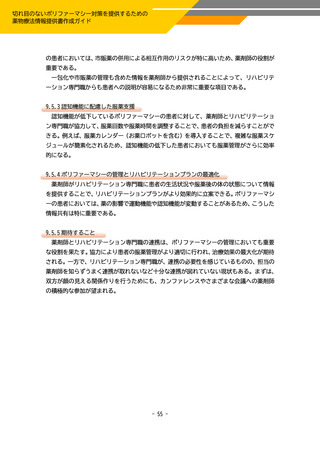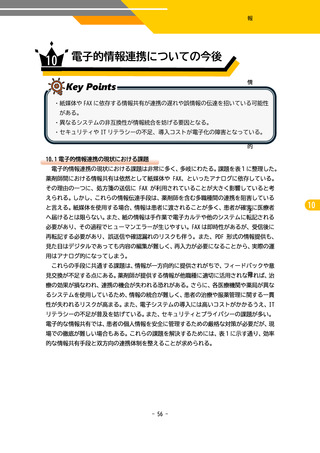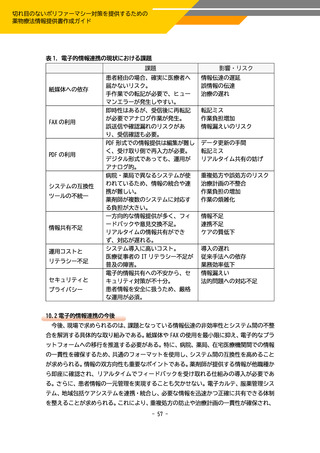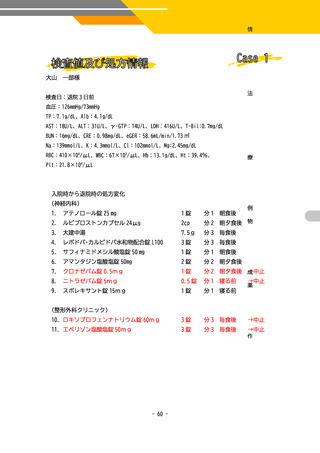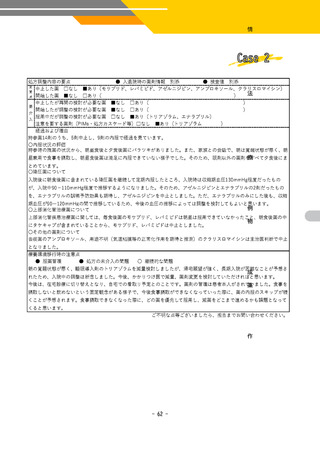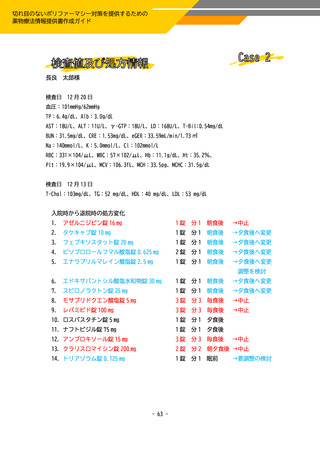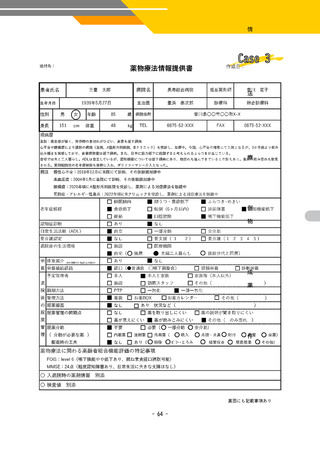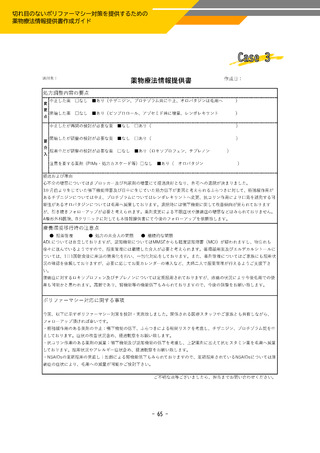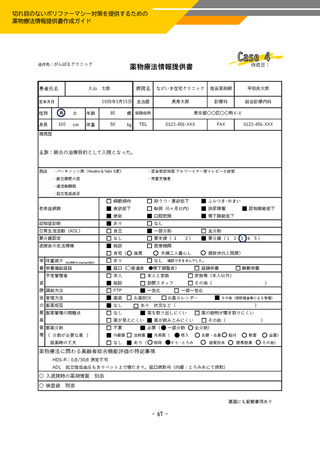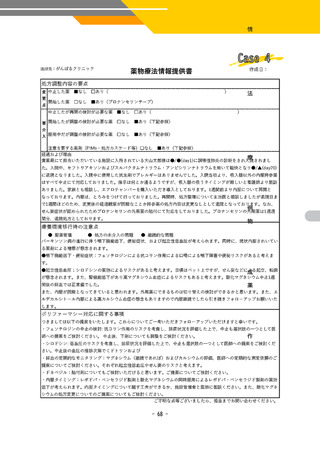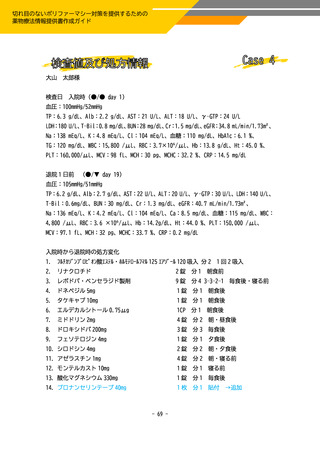よむ、つかう、まなぶ。
切れ目のないポリファーマシー対策を提供するための薬物療法情報提供書作成ガイド (48 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.ncgg.go.jp/hospital/kenshu/news/20250331.html |
| 出典情報 | 切れ目のないポリファーマシー対策を提供するための薬物療法情報提供書作成ガイド(3/31)《国立長寿医療研究センター》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
切れ目のないポリファーマシー対策を提供するための
薬物療法情報提供書作成ガイド
する多職種から得られる情報を共有することが可能な仕組みを検討しておく必要がある。
既存の医療情報管理システム(電子カルテ等)が活用可能な場合は、必要となるデータ抽出
が可能かどうかについても検討しておくことが望ましい。
入院中に行ったポリファーマシー対策については、薬剤情報のみならず、処方変更に至っ
た経緯や変更後の状態、服薬管理の問題点や工夫に関する情報についても記載することで、
退院後のフォローアップも適正に実施することが可能となる。また、入院中に実施できなか
っ た 処 方 見 直 しの 内 容や 特 に 慎 重 な 投与 を 有す る 薬 物 ( Potentially inappropriate
medication:PIM)等についても情報提供することで、院外の医療・介護従事者が退院後も
継続したポリファーマシー対策が行えるよう支援する。退院後、生活機能の維持・向上、QOL
向上のために外来・通所・訪問リハビリテーションを利用される場合には、特に PIMs 等の
機能回復に影響を及ぼす薬物に関する情報をリハビリテーション担当者およびケアマネー
ジャーと共有しておくことも重要である。
8.4.3 慢性期からの療養環境移行時に伝えるべきポイント
慢性期からの療養環境移行時に特に意識して情報提供すべきポイントを下記に示す。
①慢性期及び急性期において実施された薬物療法の内容
慢性期において実施されたポリファーマシー対策について、薬剤情報のみならず、そ
の経緯や意図を示すことは重要だが、急性期において開始された薬物が継続投与され
ている場合についても、治療上必要な投与期間や注意点等を情報提供することで、薬物
の漫然投与を防止することが可能となる。在宅等へ療養環境が移行した後は定期的な
処方見直しが難しい状況も考えられるため、将来的に必要な処方見直しに関する情報
についても共有しておくことが必要となる。急性期病院等からの情報については、院内
の入退院支援部門等と連携し、入院時に情報収集しておくことが望ましい。
②生活機能に影響する薬物療法の内容
高齢者総合機能評価等で得られた生活機能情報(老年症候群や ADL、認知機能、栄養
等)に影響を及ぼす可能性がある薬物療法の内容については、慢性期での処方見直しの
有無を含め、その具体的な影響及び今後予想される状態についても記載しておくこと
が望ましい。こうした情報を共有しておくことで、療養環境移行後も患者の生活機能を
考慮したポリファーマシー対策を検討することが可能となる。
③家族及び生活の場のキーパーソン(医療・介護従事者等)への経過観察ポイント
服薬管理等に関連する情報(管理方法、服薬介助の有無、工夫や問題点)以外にも、
前述した①及び②で示した薬物療法に対する経過観察のポイントをわかりやすく示す
ことが重要となる。例えば、食事摂取に影響を及ぼす薬物をポリファーマシー対策とし
て中止した場合には、対策実施前後の食事摂取量の変化や薬物中止後の病状を伝える
ことで、療養環境移行後の経過観察の目安となる。ポリファーマシー対策が実施できな
- 43 -
薬物療法情報提供書作成ガイド
する多職種から得られる情報を共有することが可能な仕組みを検討しておく必要がある。
既存の医療情報管理システム(電子カルテ等)が活用可能な場合は、必要となるデータ抽出
が可能かどうかについても検討しておくことが望ましい。
入院中に行ったポリファーマシー対策については、薬剤情報のみならず、処方変更に至っ
た経緯や変更後の状態、服薬管理の問題点や工夫に関する情報についても記載することで、
退院後のフォローアップも適正に実施することが可能となる。また、入院中に実施できなか
っ た 処 方 見 直 しの 内 容や 特 に 慎 重 な 投与 を 有す る 薬 物 ( Potentially inappropriate
medication:PIM)等についても情報提供することで、院外の医療・介護従事者が退院後も
継続したポリファーマシー対策が行えるよう支援する。退院後、生活機能の維持・向上、QOL
向上のために外来・通所・訪問リハビリテーションを利用される場合には、特に PIMs 等の
機能回復に影響を及ぼす薬物に関する情報をリハビリテーション担当者およびケアマネー
ジャーと共有しておくことも重要である。
8.4.3 慢性期からの療養環境移行時に伝えるべきポイント
慢性期からの療養環境移行時に特に意識して情報提供すべきポイントを下記に示す。
①慢性期及び急性期において実施された薬物療法の内容
慢性期において実施されたポリファーマシー対策について、薬剤情報のみならず、そ
の経緯や意図を示すことは重要だが、急性期において開始された薬物が継続投与され
ている場合についても、治療上必要な投与期間や注意点等を情報提供することで、薬物
の漫然投与を防止することが可能となる。在宅等へ療養環境が移行した後は定期的な
処方見直しが難しい状況も考えられるため、将来的に必要な処方見直しに関する情報
についても共有しておくことが必要となる。急性期病院等からの情報については、院内
の入退院支援部門等と連携し、入院時に情報収集しておくことが望ましい。
②生活機能に影響する薬物療法の内容
高齢者総合機能評価等で得られた生活機能情報(老年症候群や ADL、認知機能、栄養
等)に影響を及ぼす可能性がある薬物療法の内容については、慢性期での処方見直しの
有無を含め、その具体的な影響及び今後予想される状態についても記載しておくこと
が望ましい。こうした情報を共有しておくことで、療養環境移行後も患者の生活機能を
考慮したポリファーマシー対策を検討することが可能となる。
③家族及び生活の場のキーパーソン(医療・介護従事者等)への経過観察ポイント
服薬管理等に関連する情報(管理方法、服薬介助の有無、工夫や問題点)以外にも、
前述した①及び②で示した薬物療法に対する経過観察のポイントをわかりやすく示す
ことが重要となる。例えば、食事摂取に影響を及ぼす薬物をポリファーマシー対策とし
て中止した場合には、対策実施前後の食事摂取量の変化や薬物中止後の病状を伝える
ことで、療養環境移行後の経過観察の目安となる。ポリファーマシー対策が実施できな
- 43 -