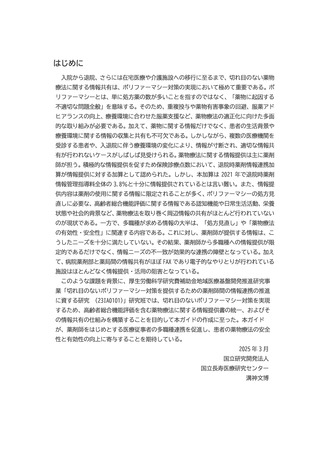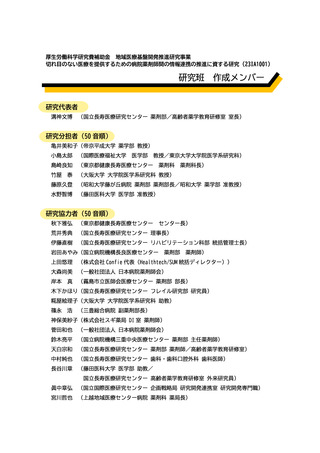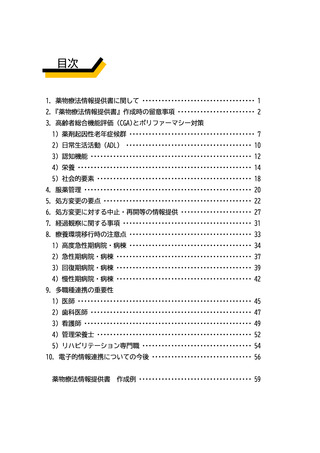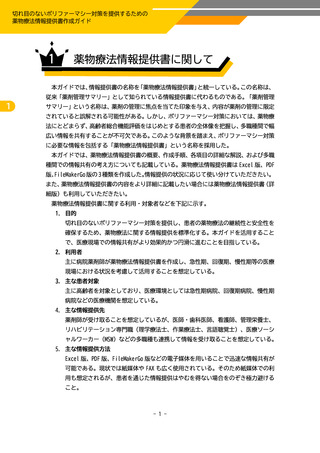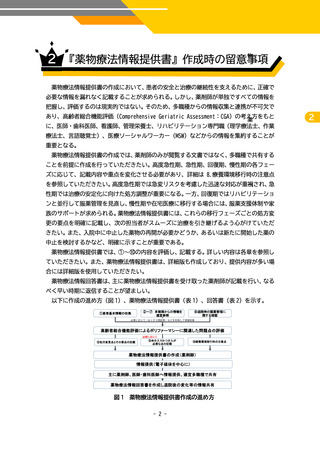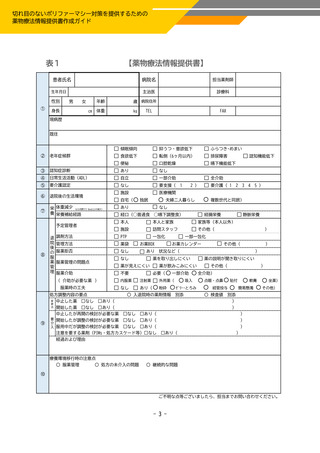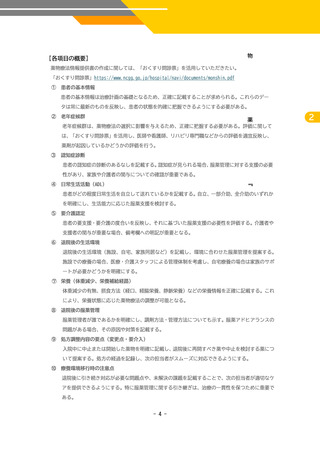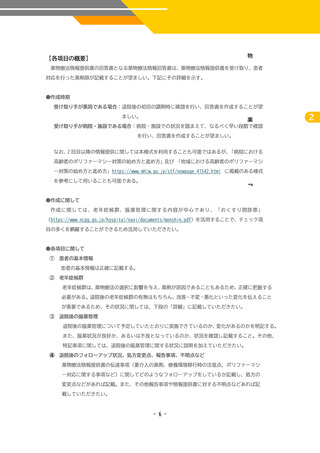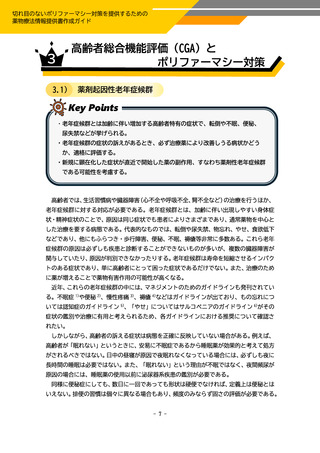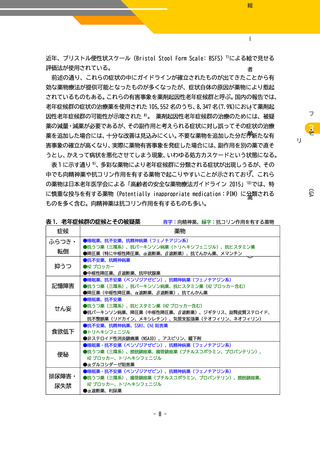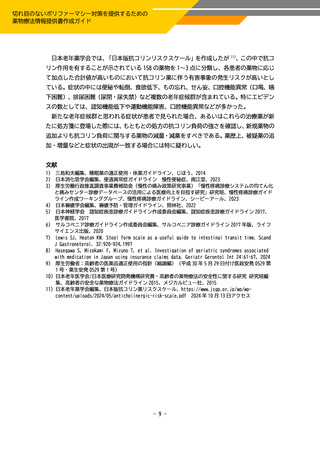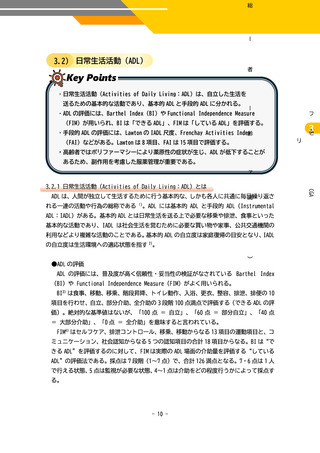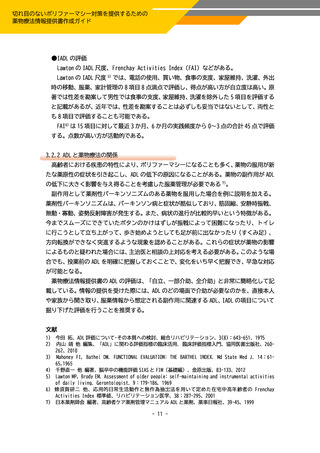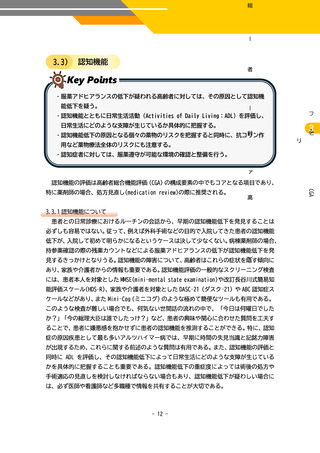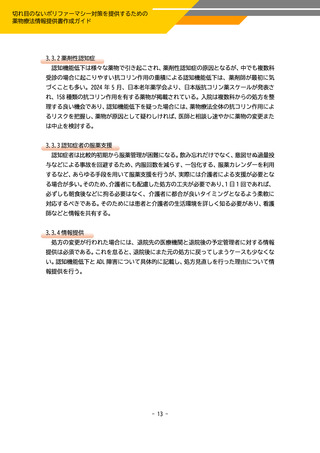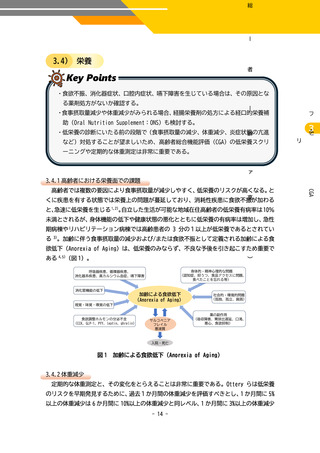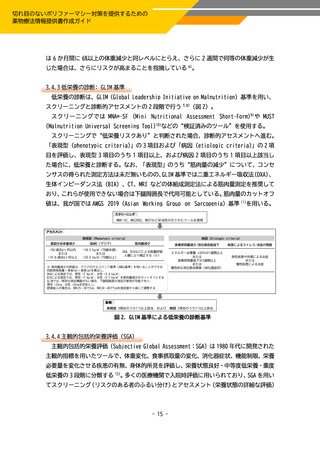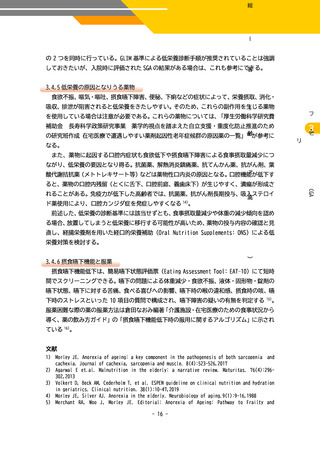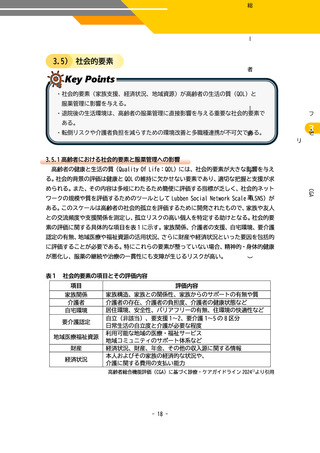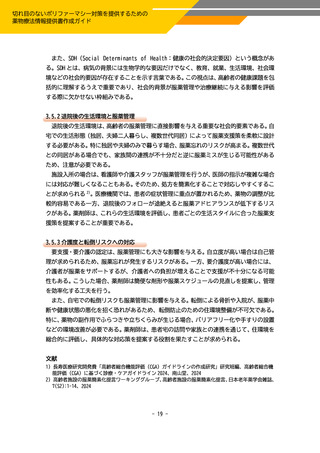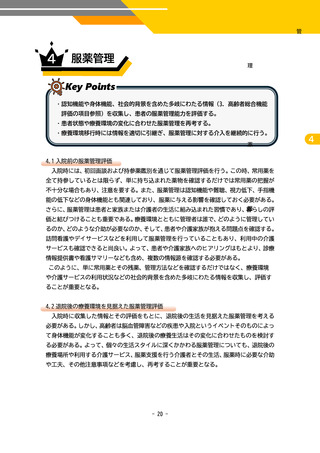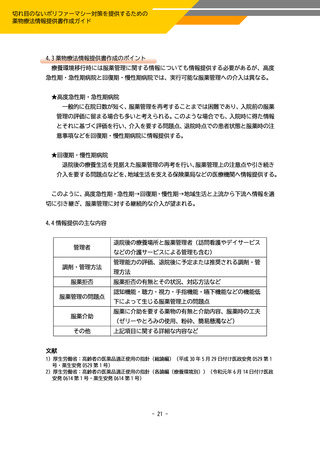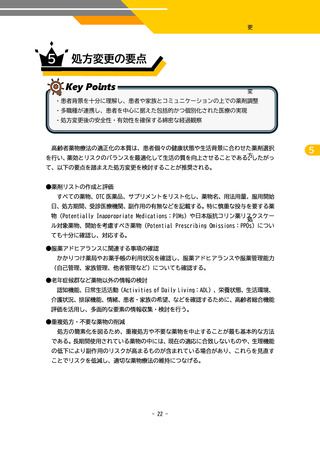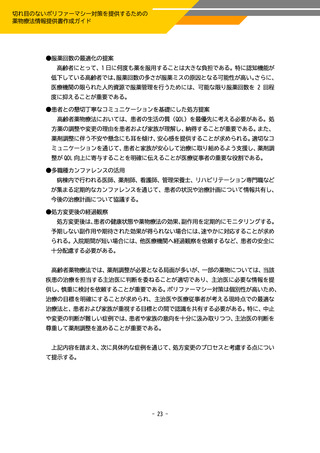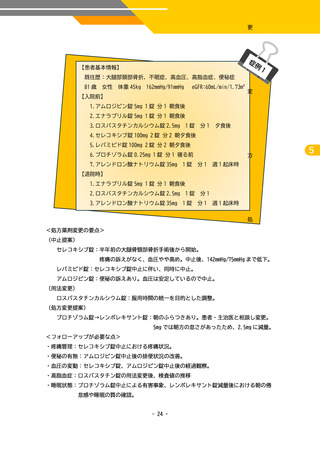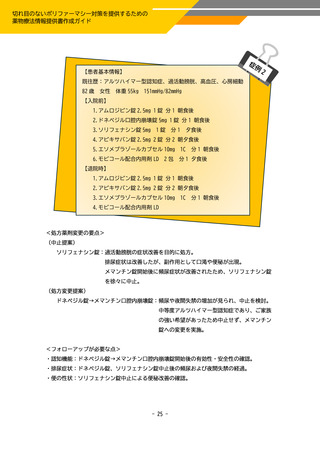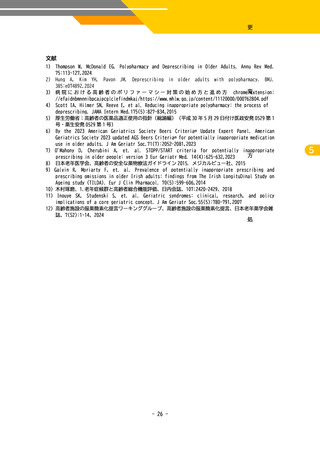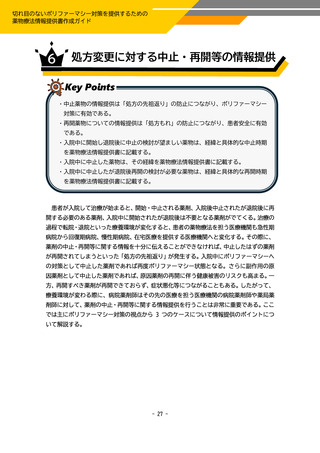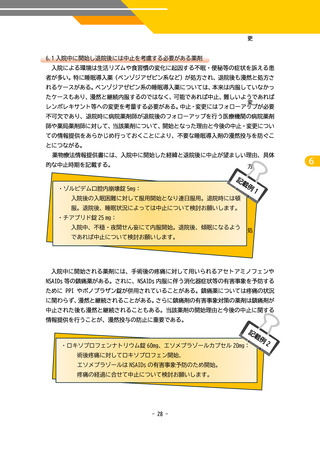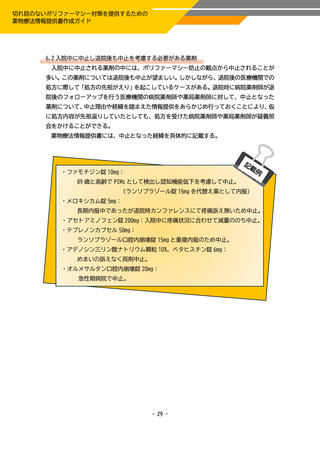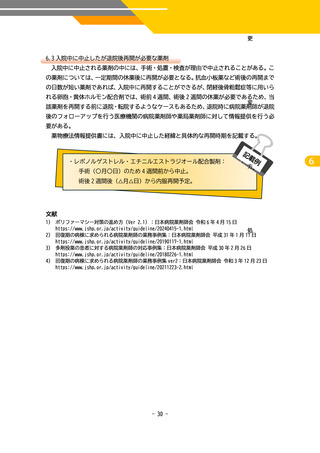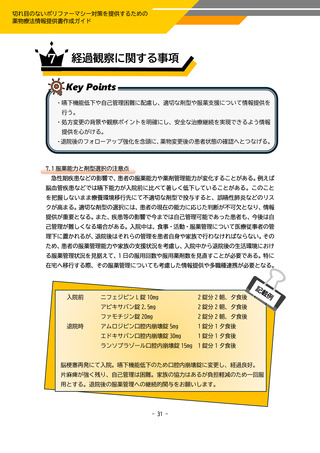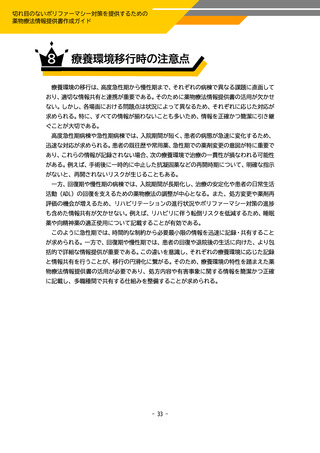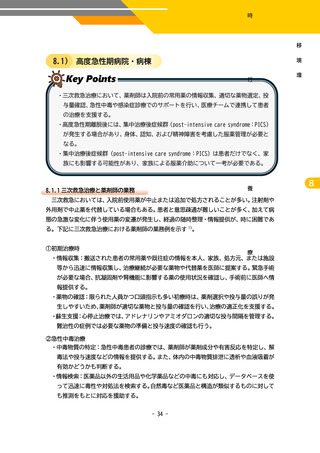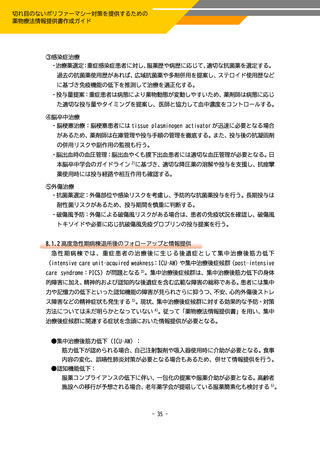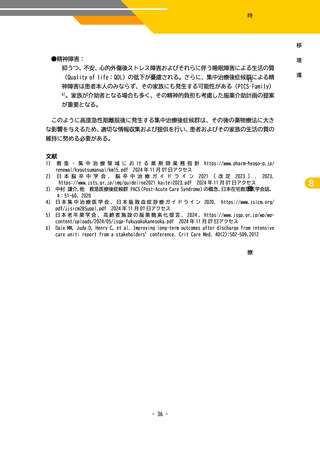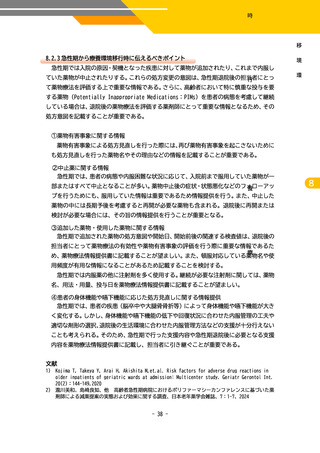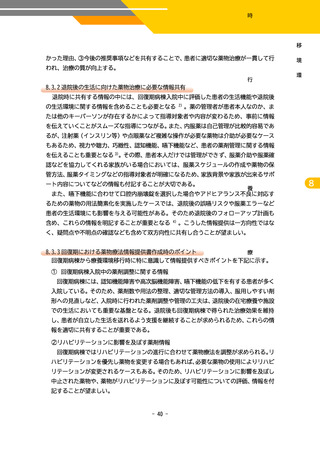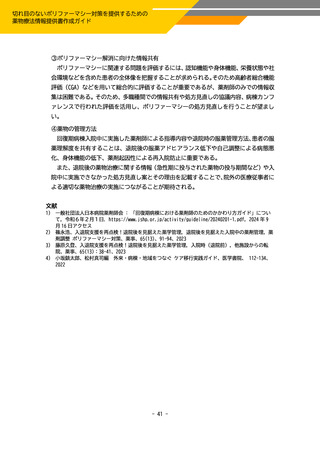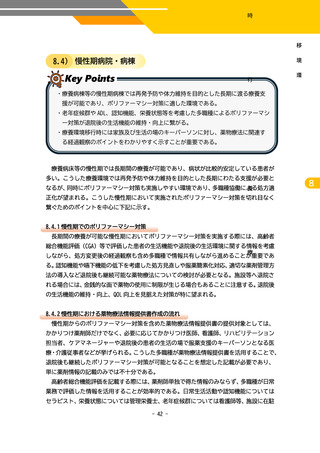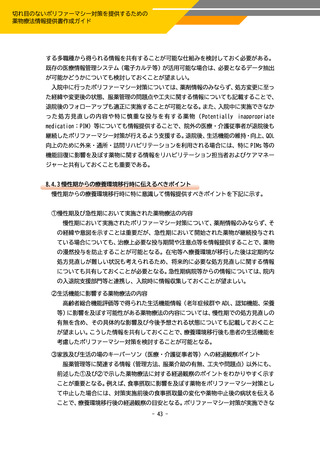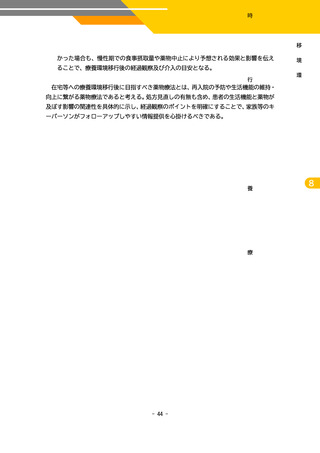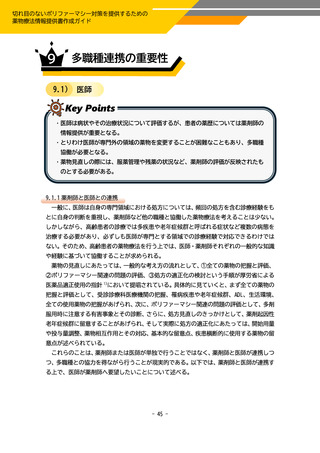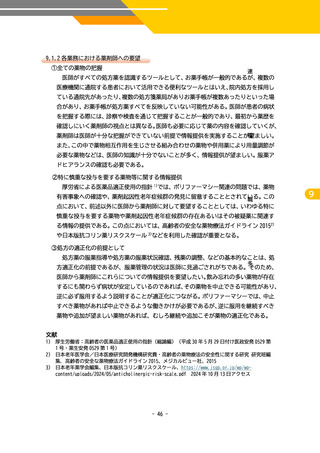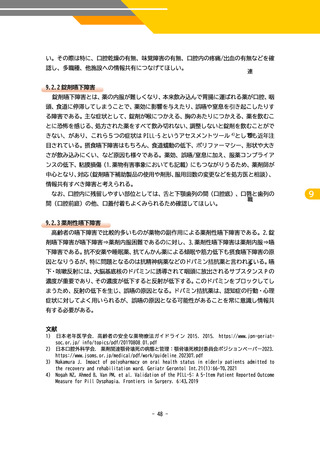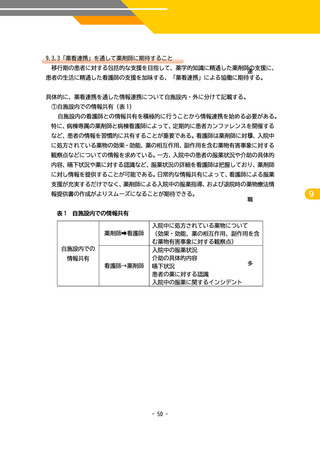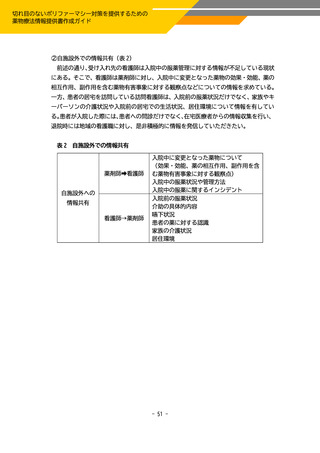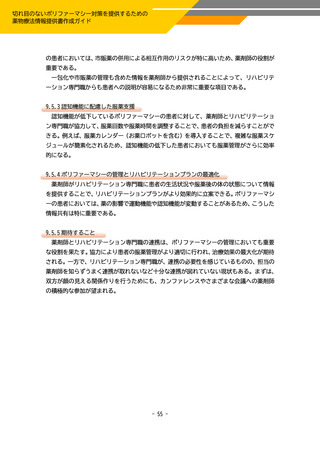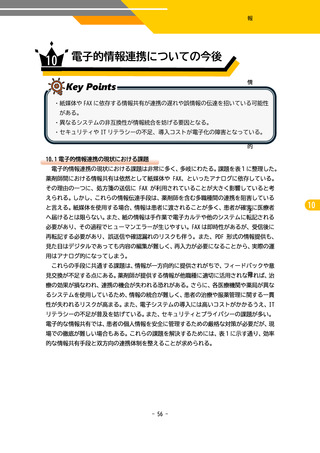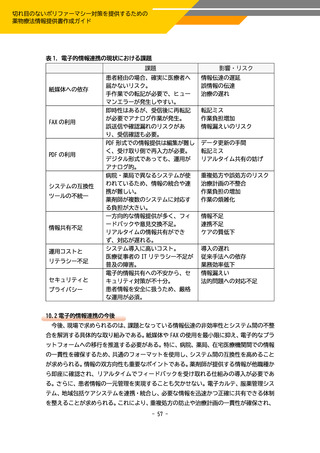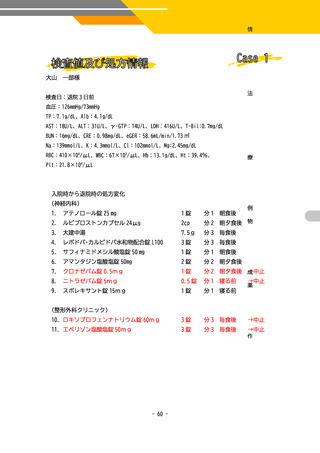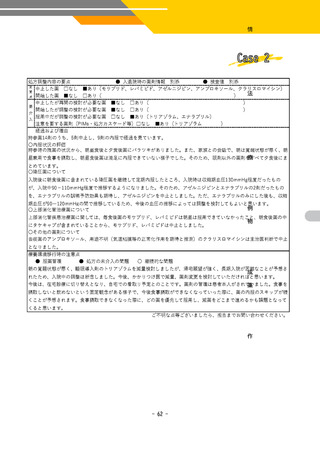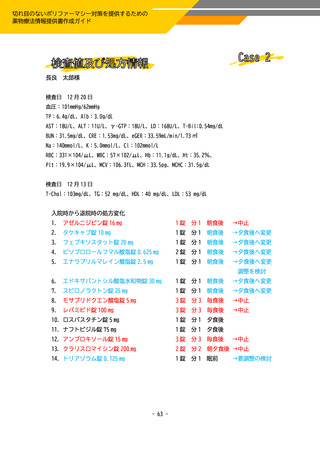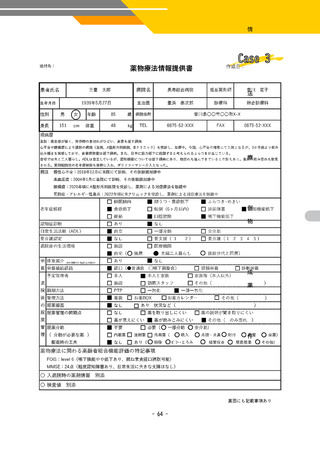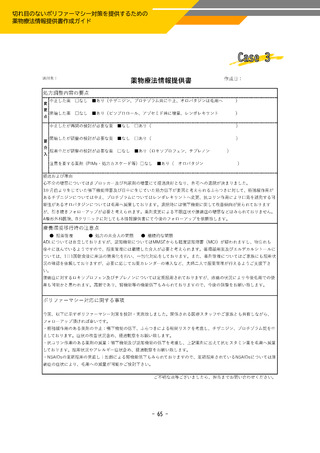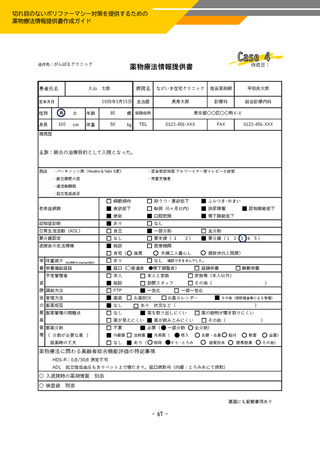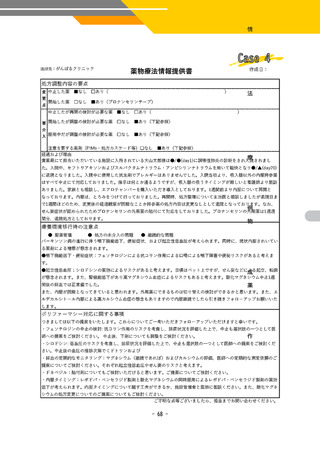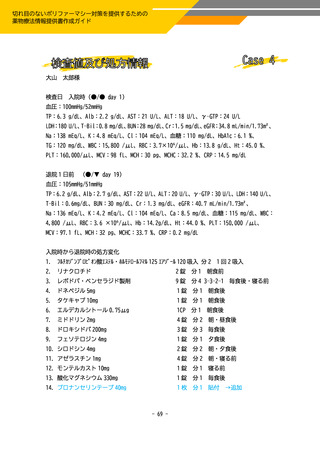よむ、つかう、まなぶ。
切れ目のないポリファーマシー対策を提供するための薬物療法情報提供書作成ガイド (47 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.ncgg.go.jp/hospital/kenshu/news/20250331.html |
| 出典情報 | 切れ目のないポリファーマシー対策を提供するための薬物療法情報提供書作成ガイド(3/31)《国立長寿医療研究センター》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
8.4) 慢性期病院・病棟
Key Points
・療養病棟等の慢性期病棟では再発予防や体力維持を目的とした長期に渡る療養支
援が可能であり、ポリファーマシー対策に適した環境である。
・老年症候群や ADL、認知機能、栄養状態等を考慮した多職種によるポリファーマシ
ー対策が退院後の生活機能の維持・向上に繋がる。
・療養環境移行時には家族及び生活の場のキーパーソンに対し、薬物療法に関連す
る経過観察のポイントをわかりやすく示すことが重要である。
療養病床等の慢性期では長期間の療養が可能であり、病状が比較的安定している患者が
多い。こうした療養環境では再発予防や体力維持を目的とした長期にわたる支援が必要と
正化が望まれる。こうした慢性期において実施されたポリファーマシー対策を切れ目なく
繋ぐためのポイントを中心に下記に示す。
8.4.1 慢性期でのポリファーマシー対策
長期間の療養が可能な慢性期においてポリファーマシー対策を実施する際には、高齢者
総合機能評価(CGA)等で評価した患者の生活機能や退院後の生活環境に関する情報を考慮
しながら、処方変更後の経過観察も含め多職種で情報共有しながら進めることが重要であ
る。認知機能や嚥下機能の低下を考慮した処方見直しや服薬簡素化対応、適切な薬剤管理方
法の導入など退院後も継続可能な薬物療法についての検討が必要となる。施設等へ退院さ
れる場合には、金銭的な面で薬物の使用に制限が生じる場合もあることに注意する。退院後
の生活機能の維持・向上、QOL 向上を見据えた対策が特に望まれる。
8.4.2 慢性期における薬物療法情報提供書作成の流れ
慢性期からのポリファーマシー対策を含めた薬物療法情報提供書の提供対象としては、
かかりつけ薬剤師だけでなく、必要に応じてかかりつけ医師、看護師、リハビリテーション
担当者、ケアマネージャーや退院後の患者の生活の場で服薬支援のキーパーソンとなる医
療・介護従事者などが挙げられる。こうした多職種が薬物療法情報提供書を活用することで、
退院後も継続したポリファーマシー対策が可能となることを想定した記載が必要であり、
単に薬剤情報の記載のみでは不十分である。
高齢者総合機能評価を記載する際には、薬剤師単独で得た情報のみならず、多職種が日常
業務で評価した情報を活用することが効率的である。日常生活活動や認知機能については
セラピスト、栄養状態については管理栄養士、老年症候群については看護師等、施設に在駐
- 42 -
8
8
療養
養環
環境
境移
移行
行時
時の
の注
注意
意点
点
療
なるが、同時にポリファーマシー対策も実施しやすい環境であり、多職種協働による処方適
Key Points
・療養病棟等の慢性期病棟では再発予防や体力維持を目的とした長期に渡る療養支
援が可能であり、ポリファーマシー対策に適した環境である。
・老年症候群や ADL、認知機能、栄養状態等を考慮した多職種によるポリファーマシ
ー対策が退院後の生活機能の維持・向上に繋がる。
・療養環境移行時には家族及び生活の場のキーパーソンに対し、薬物療法に関連す
る経過観察のポイントをわかりやすく示すことが重要である。
療養病床等の慢性期では長期間の療養が可能であり、病状が比較的安定している患者が
多い。こうした療養環境では再発予防や体力維持を目的とした長期にわたる支援が必要と
正化が望まれる。こうした慢性期において実施されたポリファーマシー対策を切れ目なく
繋ぐためのポイントを中心に下記に示す。
8.4.1 慢性期でのポリファーマシー対策
長期間の療養が可能な慢性期においてポリファーマシー対策を実施する際には、高齢者
総合機能評価(CGA)等で評価した患者の生活機能や退院後の生活環境に関する情報を考慮
しながら、処方変更後の経過観察も含め多職種で情報共有しながら進めることが重要であ
る。認知機能や嚥下機能の低下を考慮した処方見直しや服薬簡素化対応、適切な薬剤管理方
法の導入など退院後も継続可能な薬物療法についての検討が必要となる。施設等へ退院さ
れる場合には、金銭的な面で薬物の使用に制限が生じる場合もあることに注意する。退院後
の生活機能の維持・向上、QOL 向上を見据えた対策が特に望まれる。
8.4.2 慢性期における薬物療法情報提供書作成の流れ
慢性期からのポリファーマシー対策を含めた薬物療法情報提供書の提供対象としては、
かかりつけ薬剤師だけでなく、必要に応じてかかりつけ医師、看護師、リハビリテーション
担当者、ケアマネージャーや退院後の患者の生活の場で服薬支援のキーパーソンとなる医
療・介護従事者などが挙げられる。こうした多職種が薬物療法情報提供書を活用することで、
退院後も継続したポリファーマシー対策が可能となることを想定した記載が必要であり、
単に薬剤情報の記載のみでは不十分である。
高齢者総合機能評価を記載する際には、薬剤師単独で得た情報のみならず、多職種が日常
業務で評価した情報を活用することが効率的である。日常生活活動や認知機能については
セラピスト、栄養状態については管理栄養士、老年症候群については看護師等、施設に在駐
- 42 -
8
8
療養
養環
環境
境移
移行
行時
時の
の注
注意
意点
点
療
なるが、同時にポリファーマシー対策も実施しやすい環境であり、多職種協働による処方適