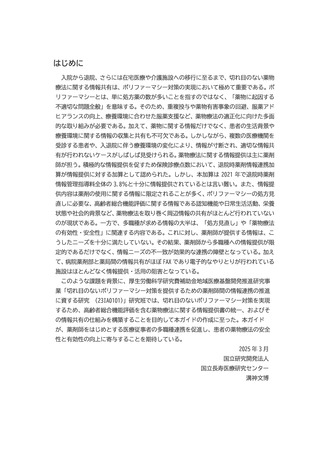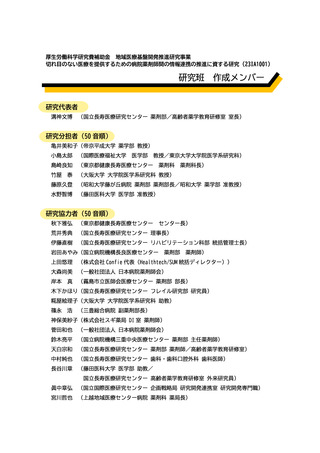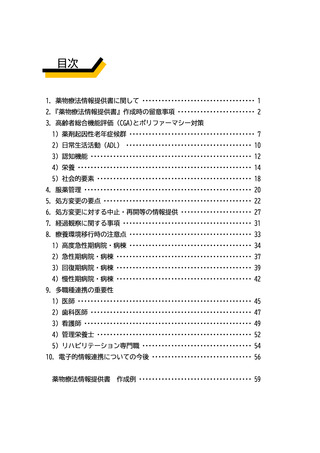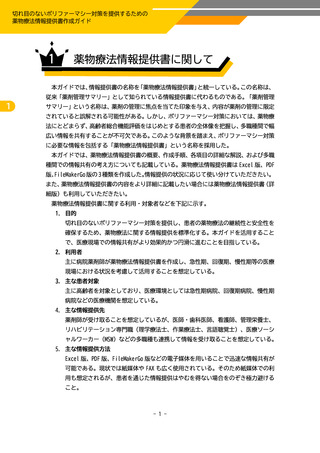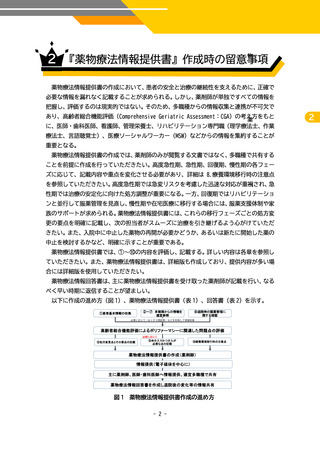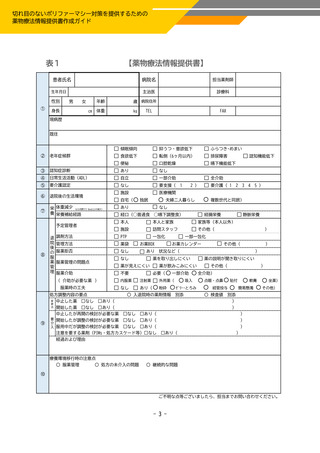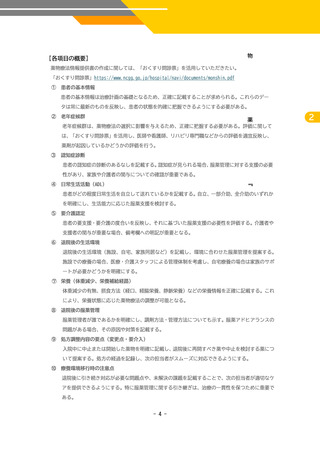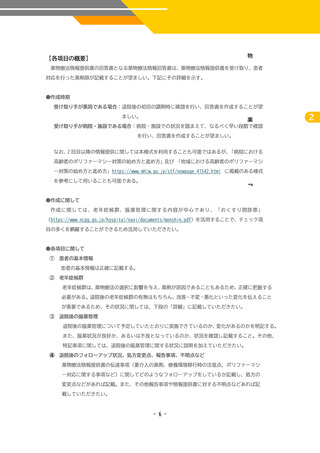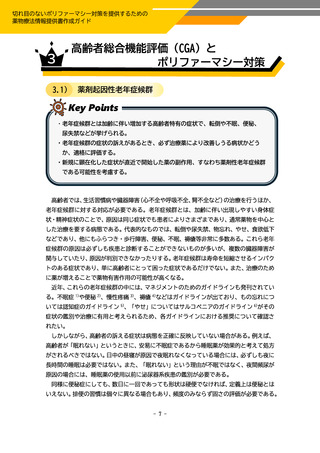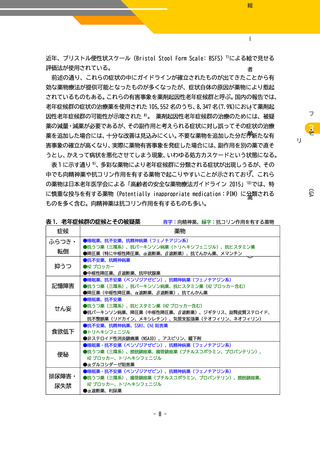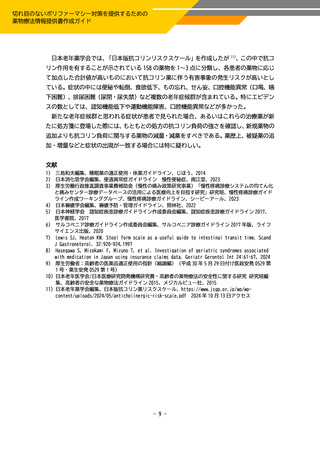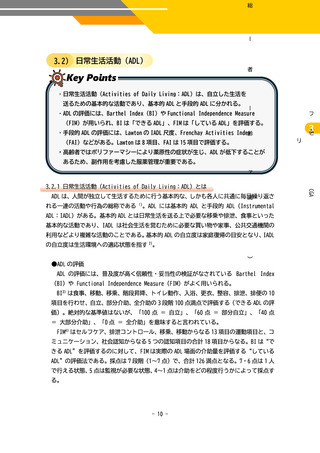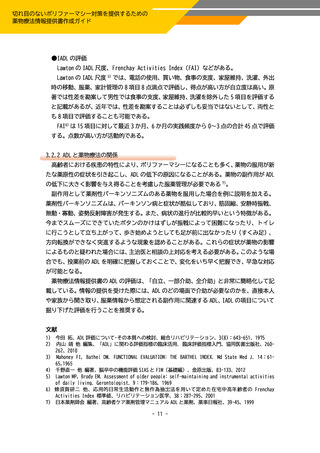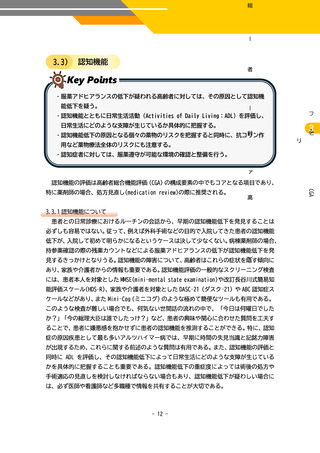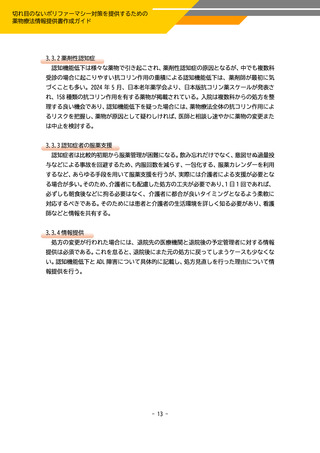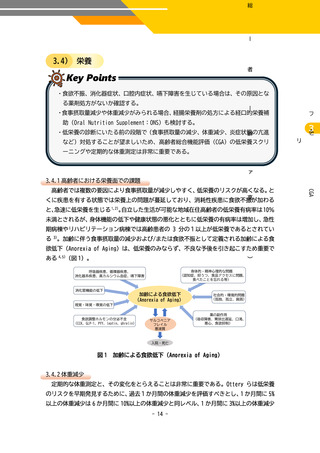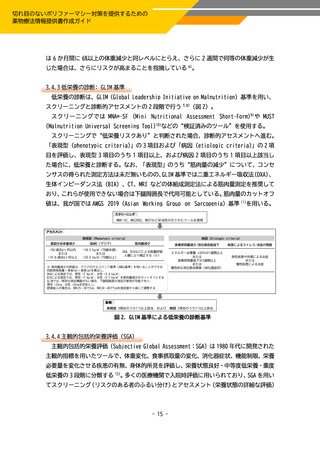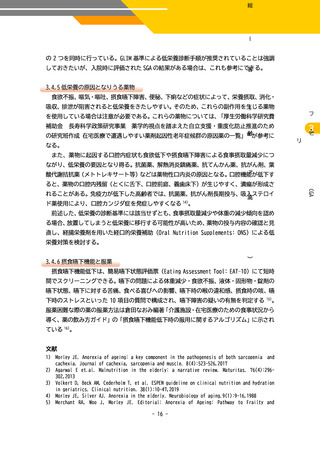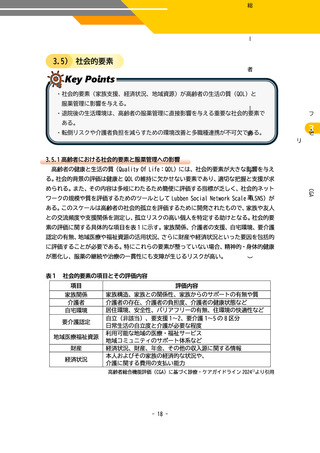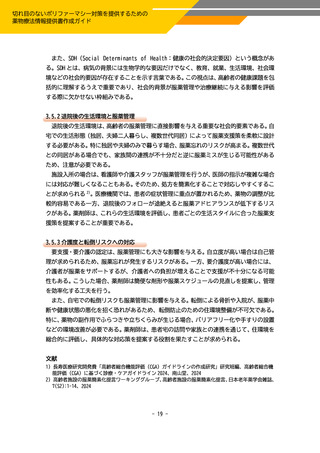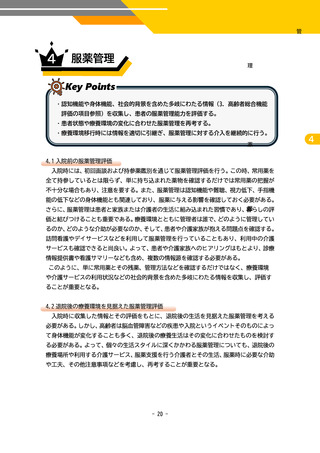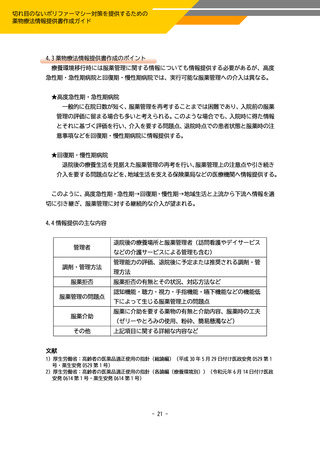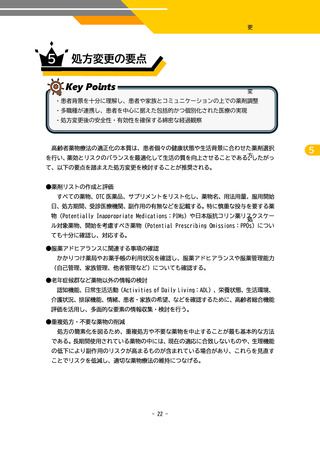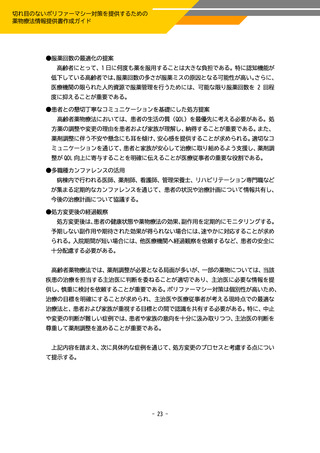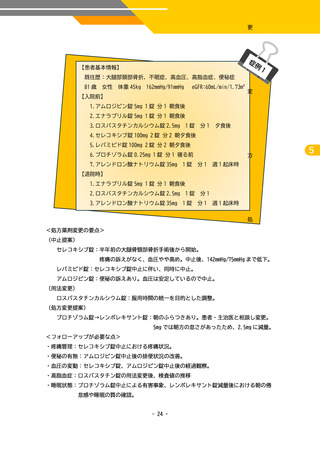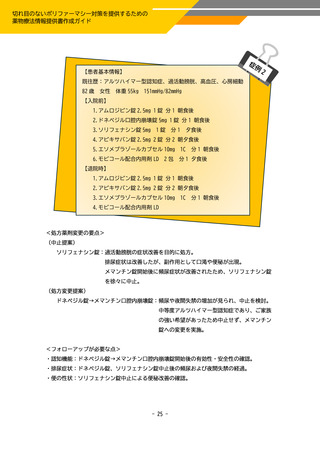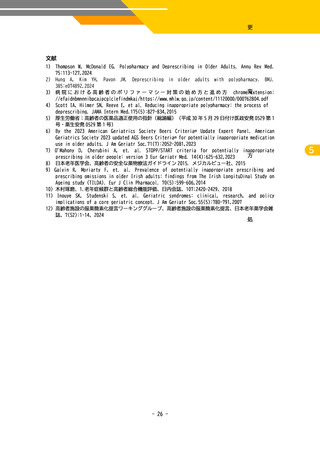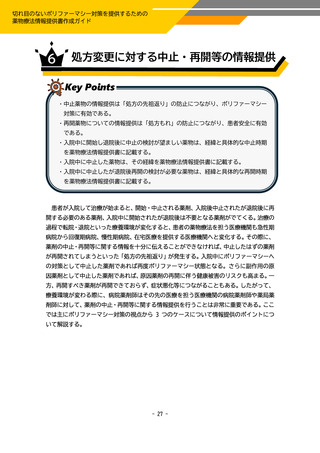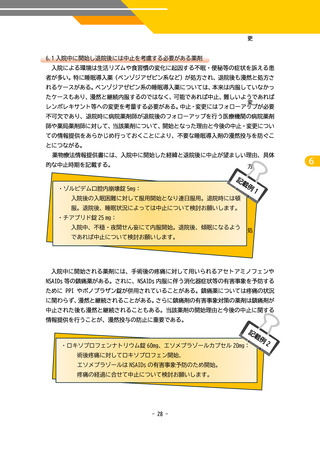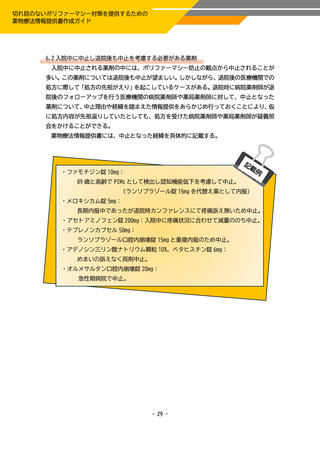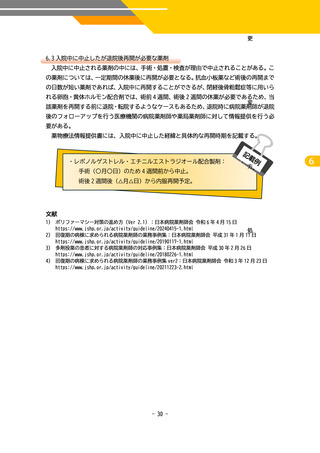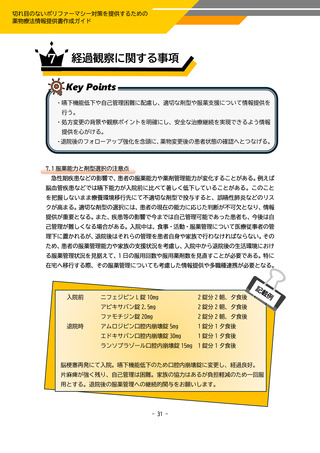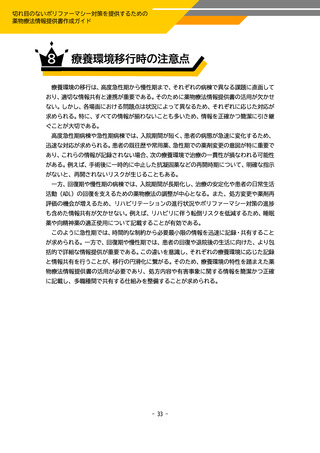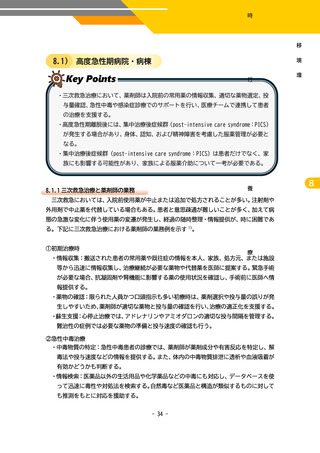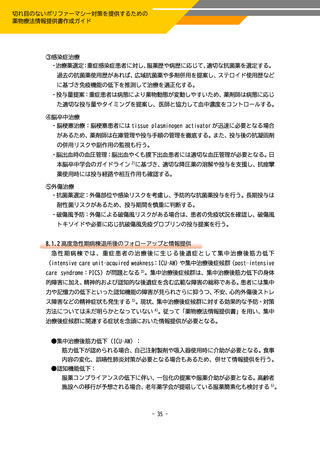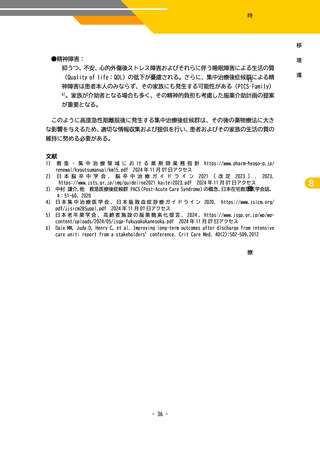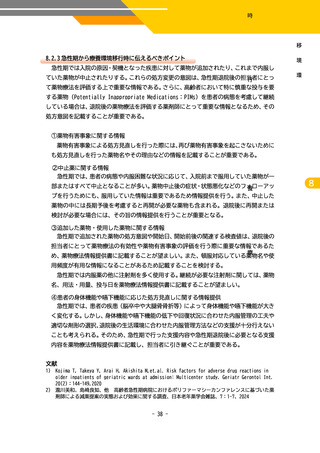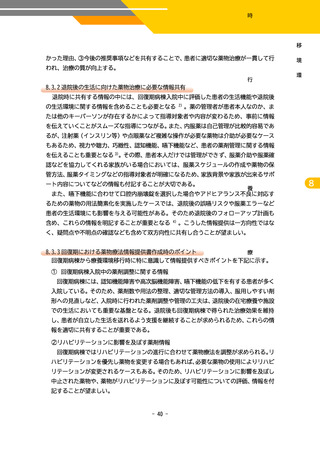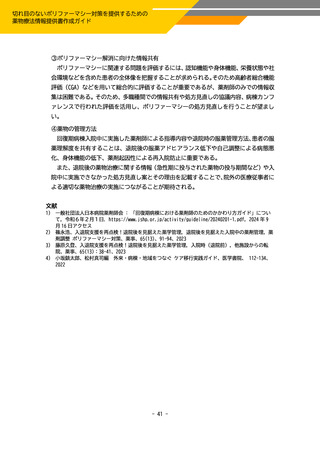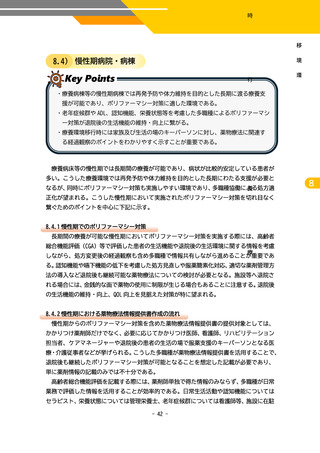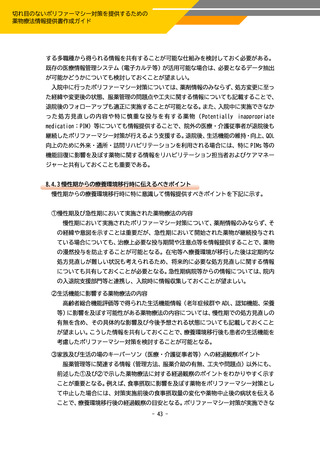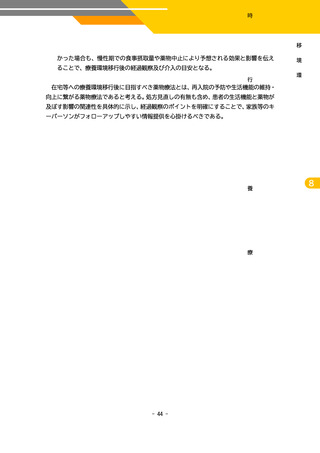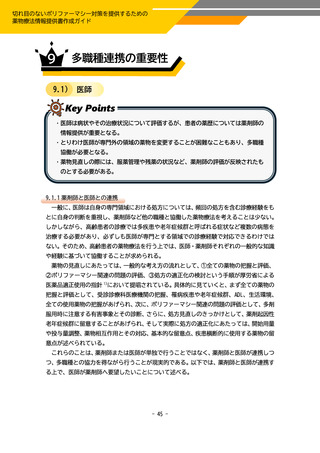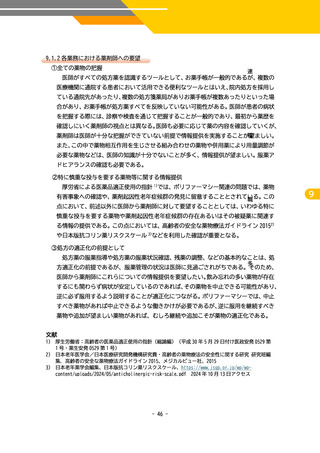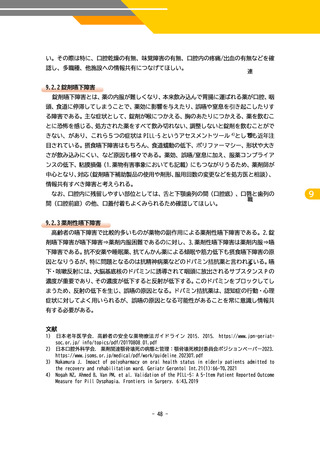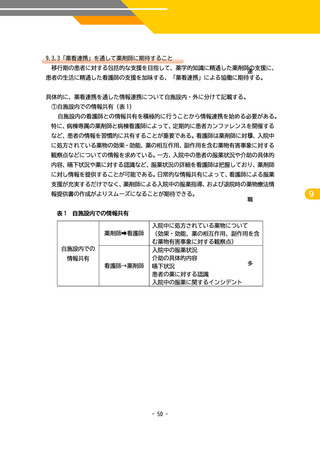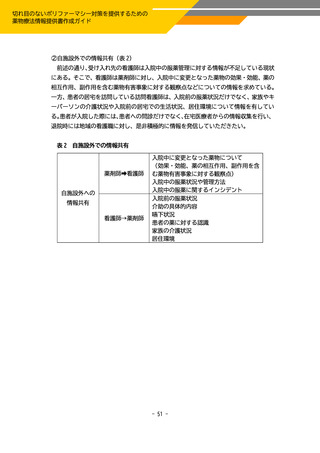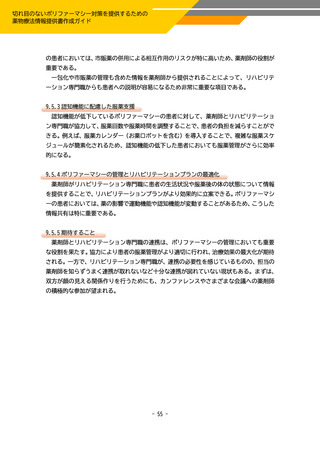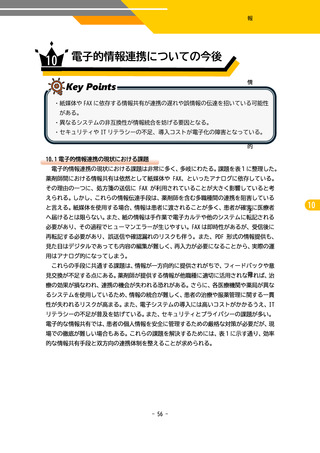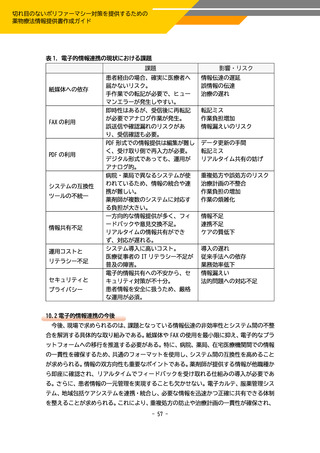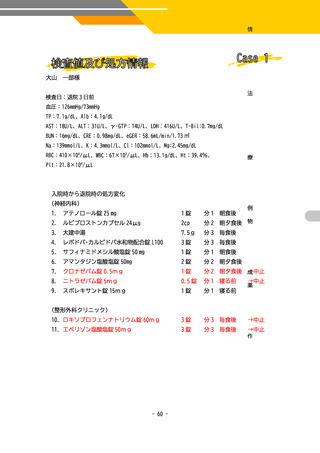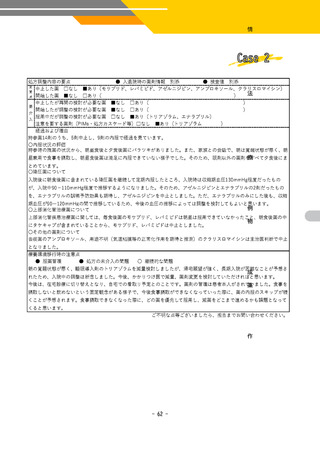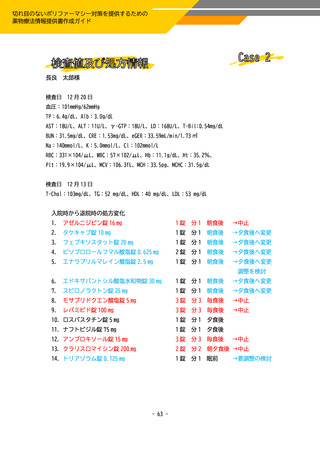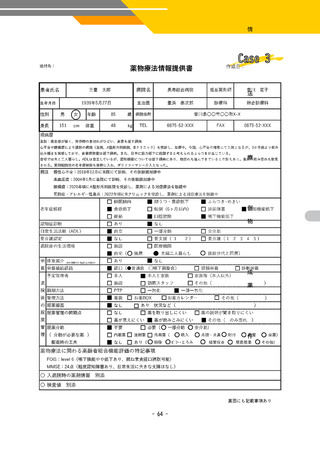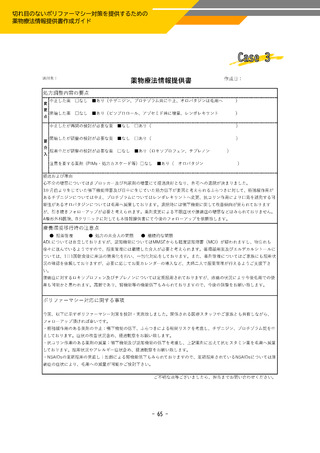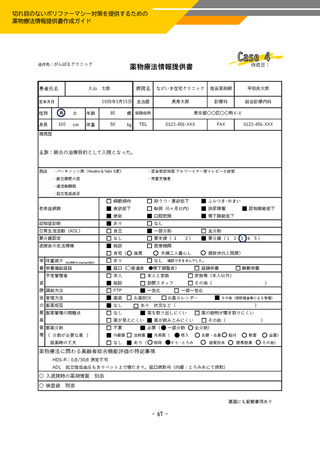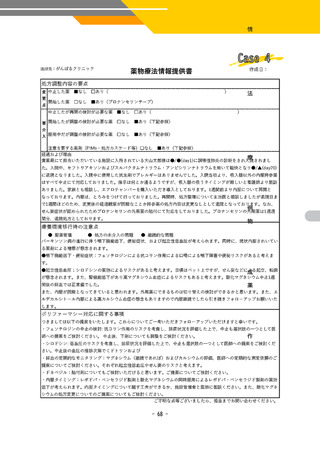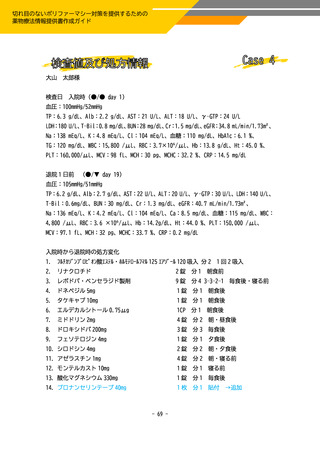よむ、つかう、まなぶ。
切れ目のないポリファーマシー対策を提供するための薬物療法情報提供書作成ガイド (53 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.ncgg.go.jp/hospital/kenshu/news/20250331.html |
| 出典情報 | 切れ目のないポリファーマシー対策を提供するための薬物療法情報提供書作成ガイド(3/31)《国立長寿医療研究センター》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
い。その際は特に、口腔乾燥の有無、味覚障害の有無、口腔内の疼痛/出血の有無などを確
認し、多職種、他施設への情報共有につなげてほしい。
9.2.2 錠剤嚥下障害
錠剤嚥下障害とは、薬の内服が難しくなり、本来飲み込んで胃腸に運ばれる薬が口腔、咽
頭、食道に停滞してしまうことで、薬効に影響を与えたり、誤嚥や窒息を引き起こしたりす
る障害である。主な症状として、錠剤が喉につかえる、胸のあたりにつかえる、薬を飲むこ
とに恐怖を感じる、処方された薬をすべて飲み切れない、調整しないと錠剤を飲むことがで
きない、があり、これら5つの症状は PILL-5 というアセスメントツール 4)としても近年注
目されている。摂食嚥下障害はもちろん、食道蠕動の低下、ポリファーマシー、形状や大き
さが飲み込みにくい、など原因も様々である。薬効、誤嚥/窒息に加え、服薬コンプライア
ンスの低下、粘膜損傷(1.薬物有害事象においても記載)にもつながりうるため、薬剤師が
中心となり、対応(錠剤嚥下補助製品の使用や剤形、服用回数の変更などを処方医と相談)、
情報共有すべき障害と考えられる。
間(口腔前庭)の他、口蓋付着もよくみられるため確認してほしい。
9.2.3 薬剤性嚥下障害
高齢者の嚥下障害で比較的多いものが薬物の副作用による薬剤性嚥下障害である。2.錠
剤嚥下障害が嚥下障害⇒薬剤内服困難であるのに対し、3.薬剤性嚥下障害は薬剤内服⇒嚥
下障害である。抗不安薬や睡眠薬、抗てんかん薬による傾眠や筋力低下も摂食嚥下障害の原
因となりうるが、特に問題となるのは抗精神病薬などのドパミン拮抗薬と言われている。嚥
下・咳嗽反射には、大脳基底核のドパミンに誘導されて咽頭に放出されるサブスタンス P の
濃度が重要であり、その濃度が低下すると反射が低下する。このドパミンをブロックしてし
まうため、反射の低下を生じ、誤嚥の原因となる。ドパミン拮抗薬は、認知症の行動・心理
症状に対してよく用いられるが、誤嚥の原因となる可能性があることを常に意識し情報共
有する必要がある。
文献
1)
日本老年医学会.高齢者の安全な薬物療法ガイドライン 2015.2015. https://www.jpn-geriatsoc.or.jp/ info/topics/pdf/20170808_01.pdf
2) 日本口腔外科学会. 薬剤関連顎骨壊死の病態と管理:顎骨壊死検討委員会ポジションペーパー2023.
https://www.jsoms.or.jp/medical/pdf/work/guideline_202307.pdf
3) Nakamura J. Impact of polypharmacy on oral health status in elderly patients admitted to
the recovery and rehabilitation ward. Geriatr Gerontol Int.21(1):66-70,2021
4) Nogah NZ, Ahmed B, Van PM, et al. Validation of the PILL-5: A 5-Item Patient Reported Outcome
Measure for Pill Dysphagia. Frontiers in Surgery. 6:43,2019
- 48 -
9
9
多多
職職
種種
連連
携携
のの
重重
要要
性性
なお、口腔内に残留しやすい部位としては、舌と下顎歯列の間(口腔底)、口唇と歯列の
認し、多職種、他施設への情報共有につなげてほしい。
9.2.2 錠剤嚥下障害
錠剤嚥下障害とは、薬の内服が難しくなり、本来飲み込んで胃腸に運ばれる薬が口腔、咽
頭、食道に停滞してしまうことで、薬効に影響を与えたり、誤嚥や窒息を引き起こしたりす
る障害である。主な症状として、錠剤が喉につかえる、胸のあたりにつかえる、薬を飲むこ
とに恐怖を感じる、処方された薬をすべて飲み切れない、調整しないと錠剤を飲むことがで
きない、があり、これら5つの症状は PILL-5 というアセスメントツール 4)としても近年注
目されている。摂食嚥下障害はもちろん、食道蠕動の低下、ポリファーマシー、形状や大き
さが飲み込みにくい、など原因も様々である。薬効、誤嚥/窒息に加え、服薬コンプライア
ンスの低下、粘膜損傷(1.薬物有害事象においても記載)にもつながりうるため、薬剤師が
中心となり、対応(錠剤嚥下補助製品の使用や剤形、服用回数の変更などを処方医と相談)、
情報共有すべき障害と考えられる。
間(口腔前庭)の他、口蓋付着もよくみられるため確認してほしい。
9.2.3 薬剤性嚥下障害
高齢者の嚥下障害で比較的多いものが薬物の副作用による薬剤性嚥下障害である。2.錠
剤嚥下障害が嚥下障害⇒薬剤内服困難であるのに対し、3.薬剤性嚥下障害は薬剤内服⇒嚥
下障害である。抗不安薬や睡眠薬、抗てんかん薬による傾眠や筋力低下も摂食嚥下障害の原
因となりうるが、特に問題となるのは抗精神病薬などのドパミン拮抗薬と言われている。嚥
下・咳嗽反射には、大脳基底核のドパミンに誘導されて咽頭に放出されるサブスタンス P の
濃度が重要であり、その濃度が低下すると反射が低下する。このドパミンをブロックしてし
まうため、反射の低下を生じ、誤嚥の原因となる。ドパミン拮抗薬は、認知症の行動・心理
症状に対してよく用いられるが、誤嚥の原因となる可能性があることを常に意識し情報共
有する必要がある。
文献
1)
日本老年医学会.高齢者の安全な薬物療法ガイドライン 2015.2015. https://www.jpn-geriatsoc.or.jp/ info/topics/pdf/20170808_01.pdf
2) 日本口腔外科学会. 薬剤関連顎骨壊死の病態と管理:顎骨壊死検討委員会ポジションペーパー2023.
https://www.jsoms.or.jp/medical/pdf/work/guideline_202307.pdf
3) Nakamura J. Impact of polypharmacy on oral health status in elderly patients admitted to
the recovery and rehabilitation ward. Geriatr Gerontol Int.21(1):66-70,2021
4) Nogah NZ, Ahmed B, Van PM, et al. Validation of the PILL-5: A 5-Item Patient Reported Outcome
Measure for Pill Dysphagia. Frontiers in Surgery. 6:43,2019
- 48 -
9
9
多多
職職
種種
連連
携携
のの
重重
要要
性性
なお、口腔内に残留しやすい部位としては、舌と下顎歯列の間(口腔底)、口唇と歯列の