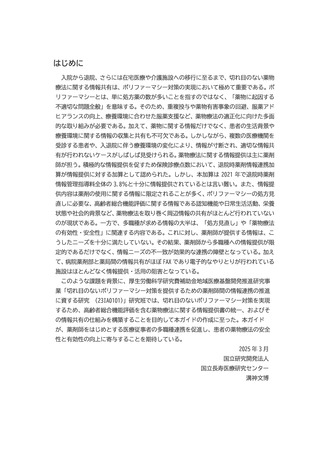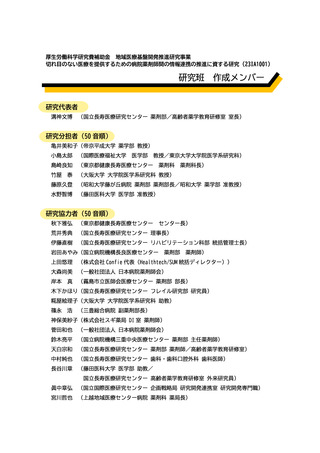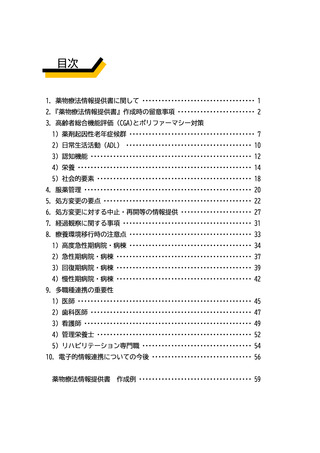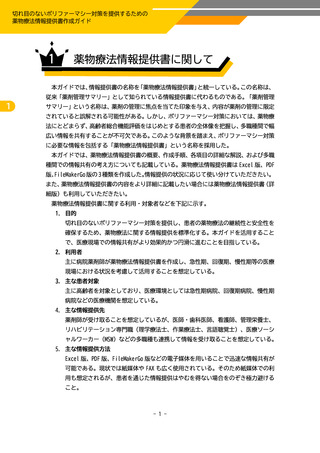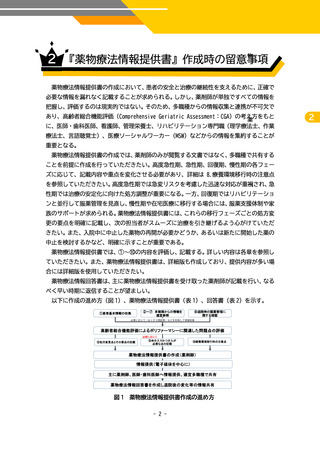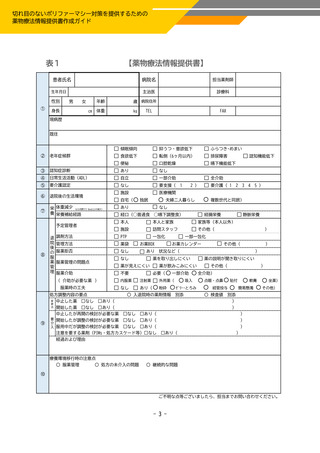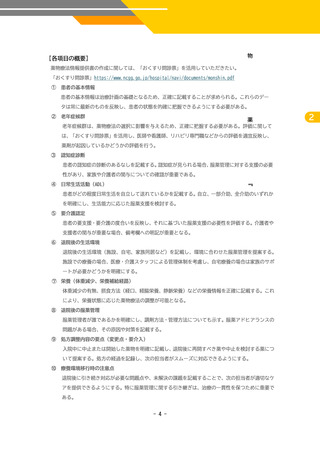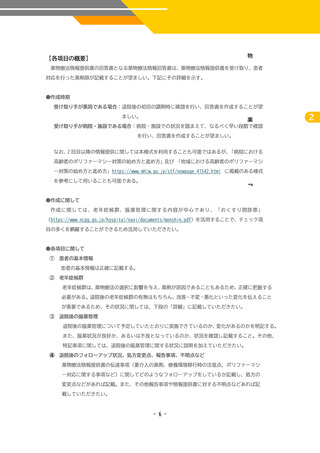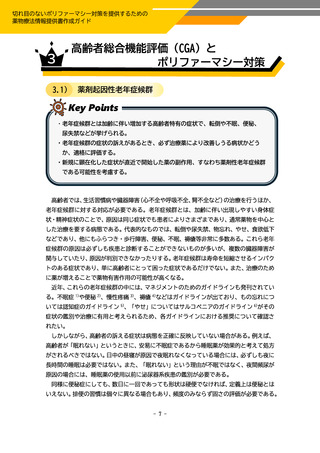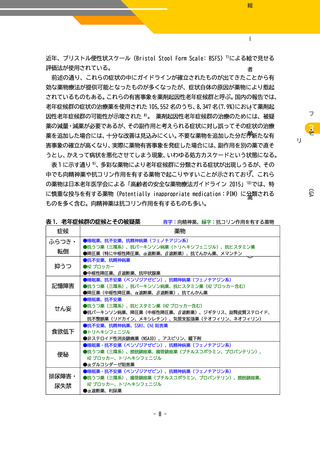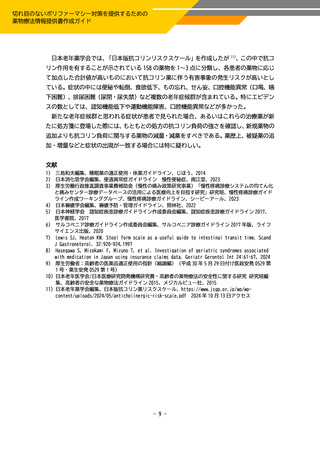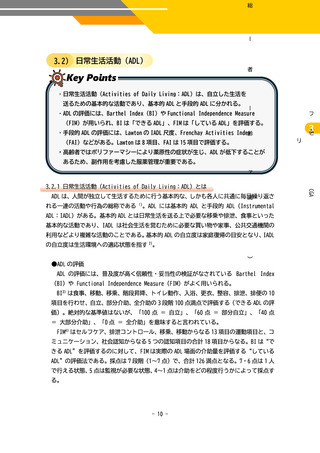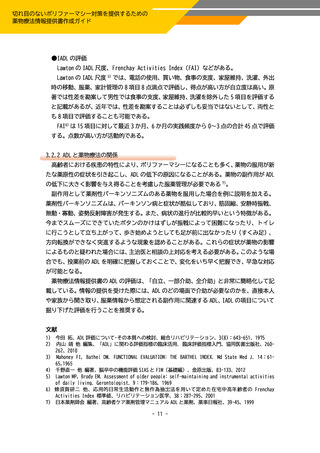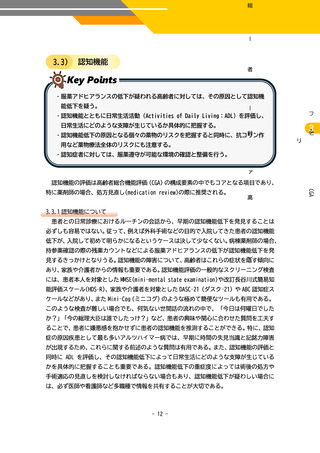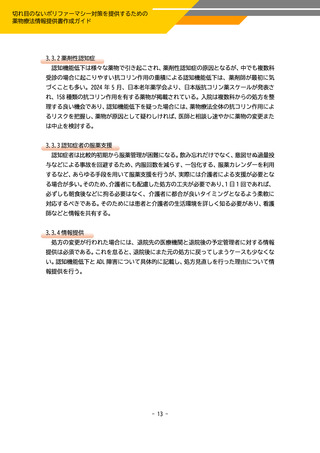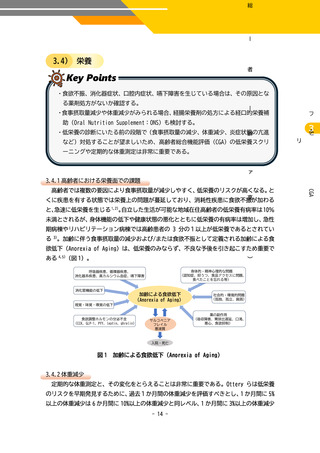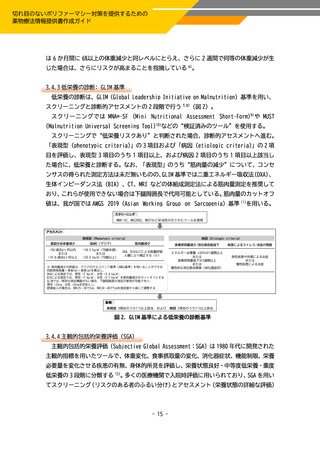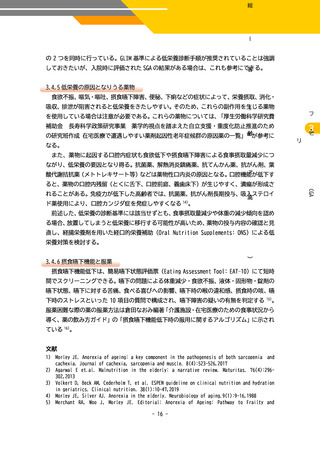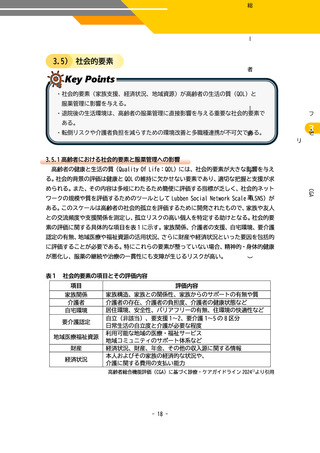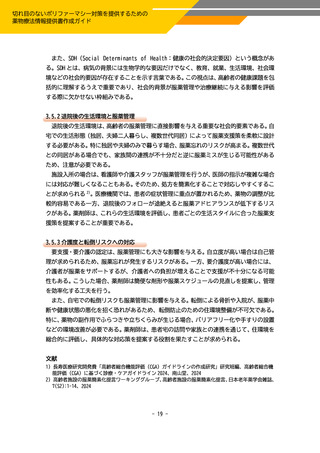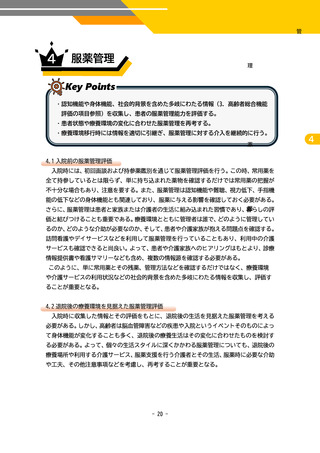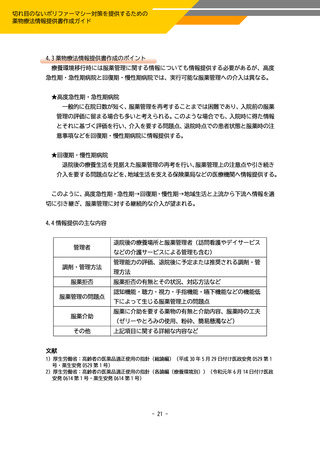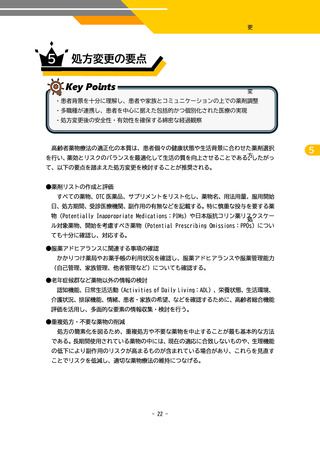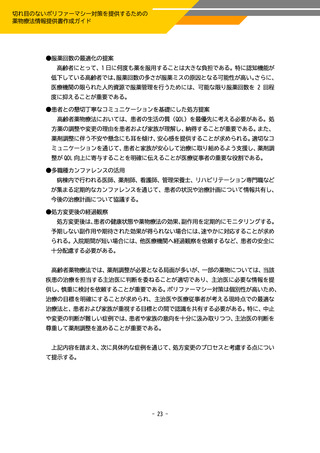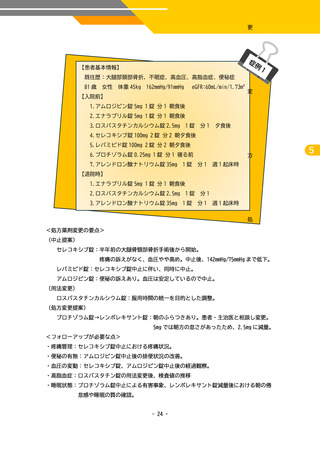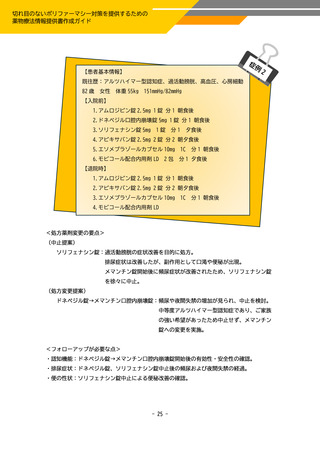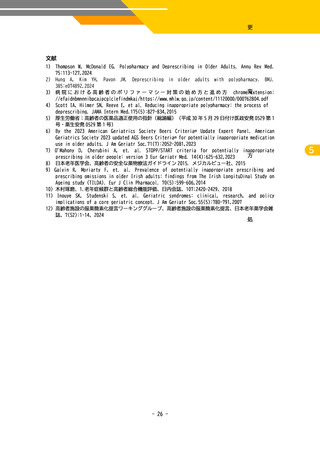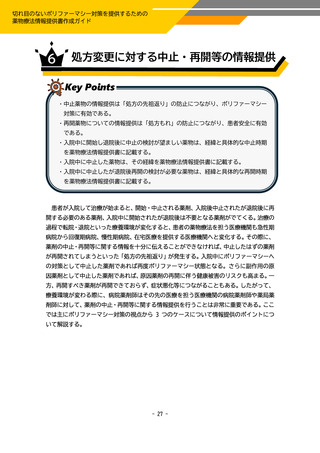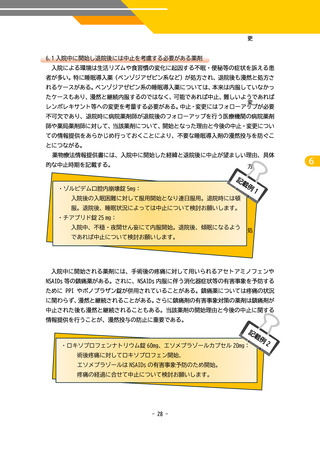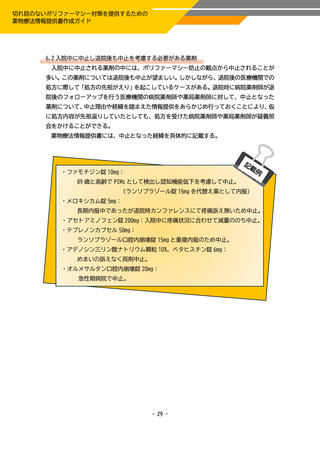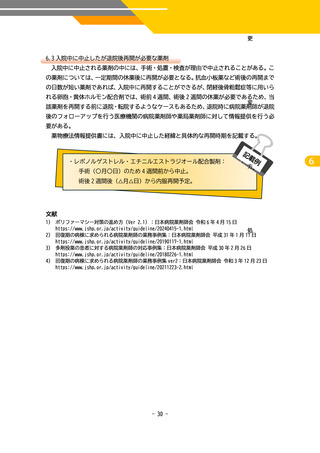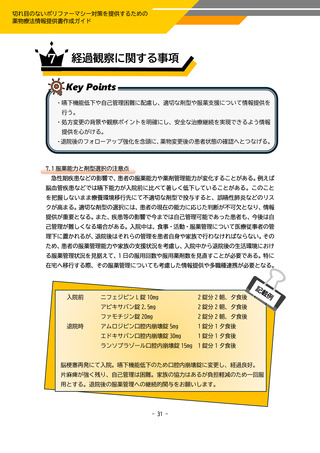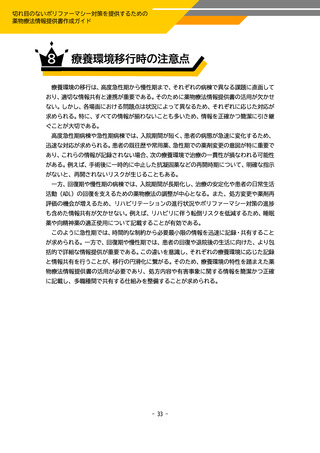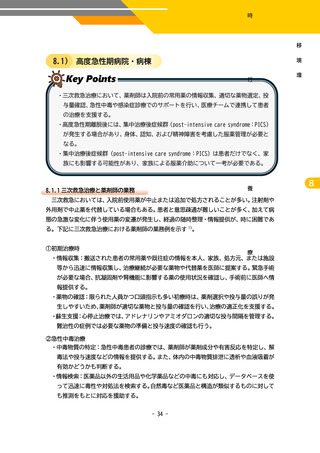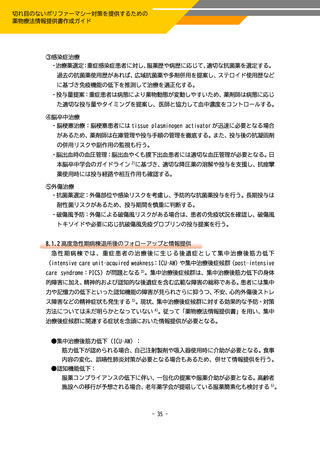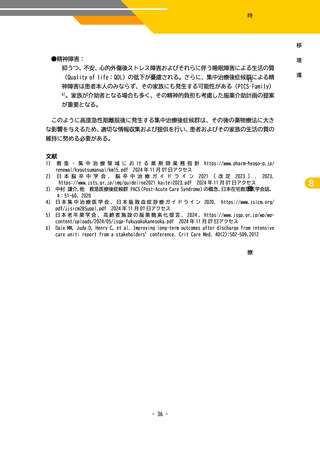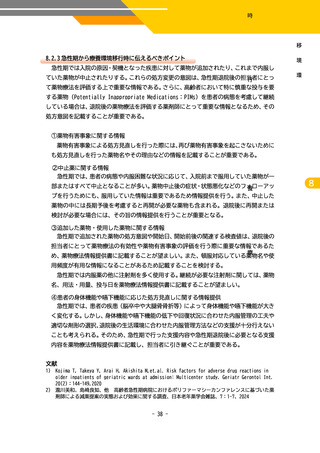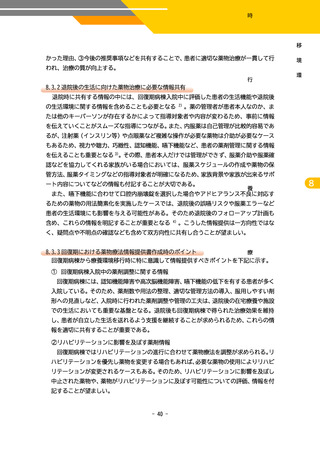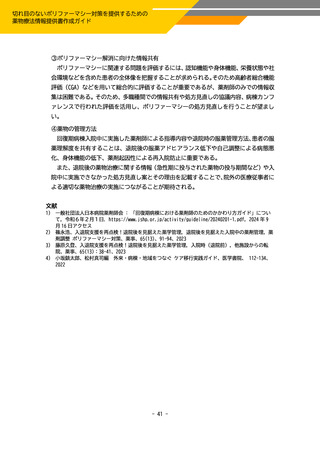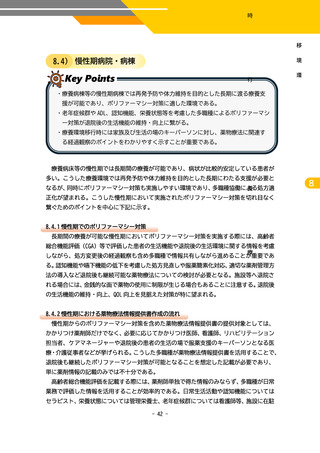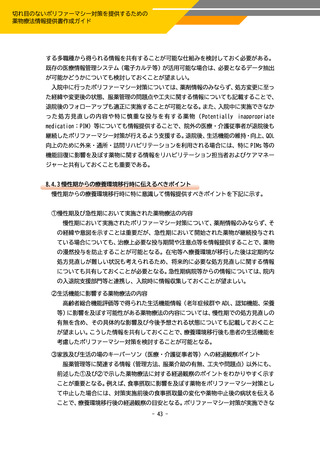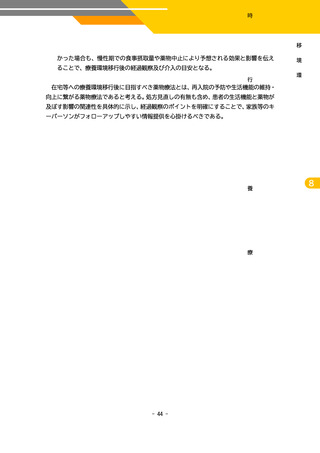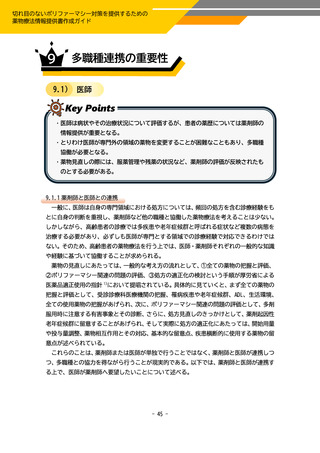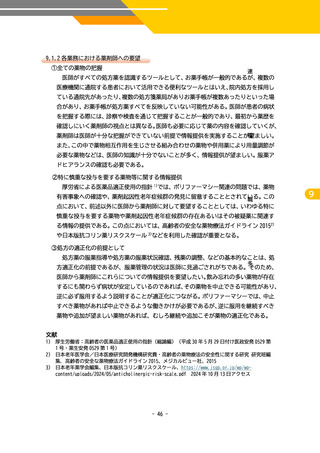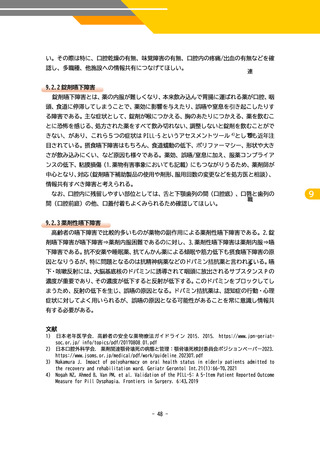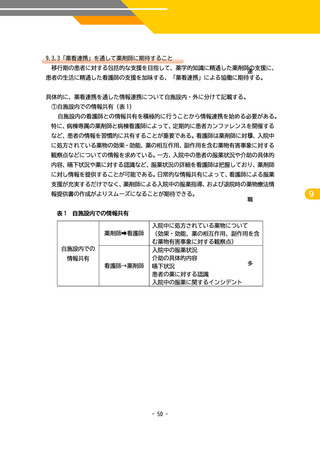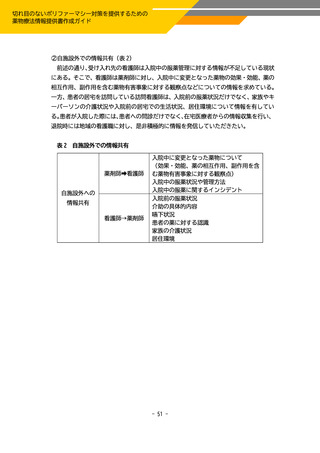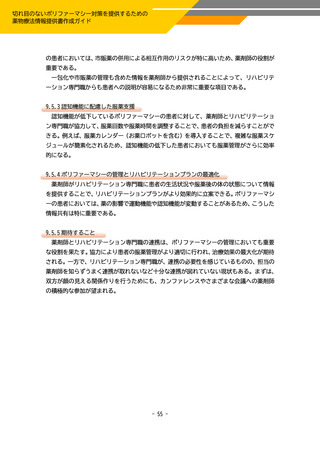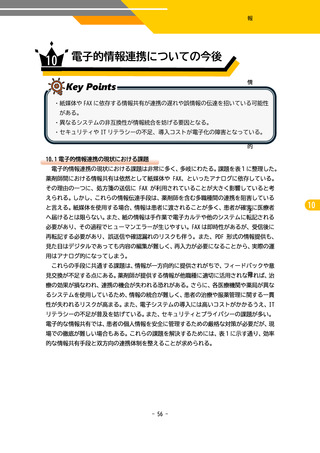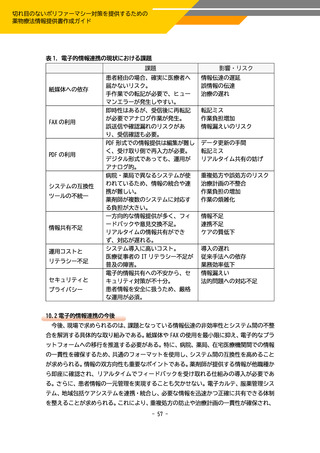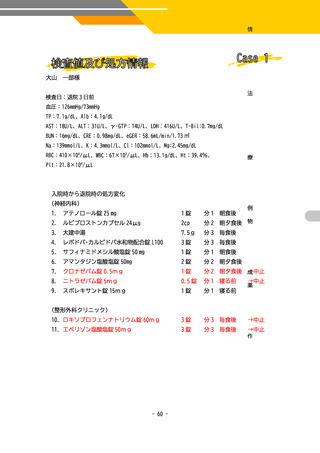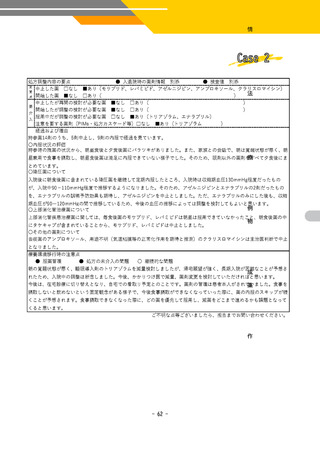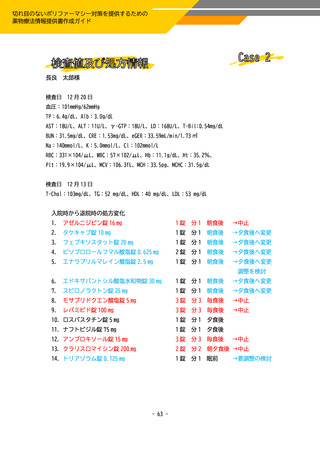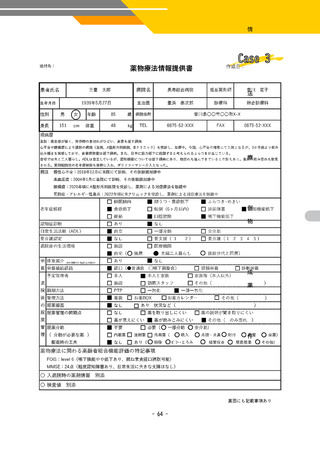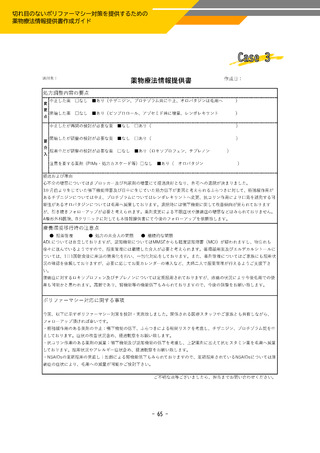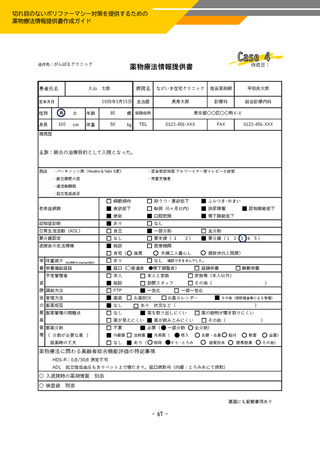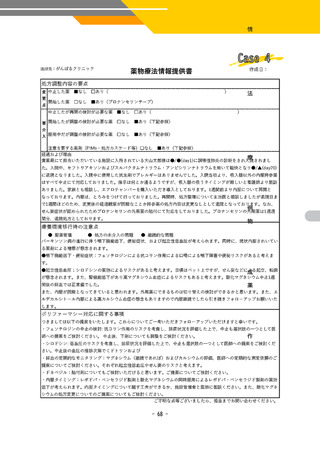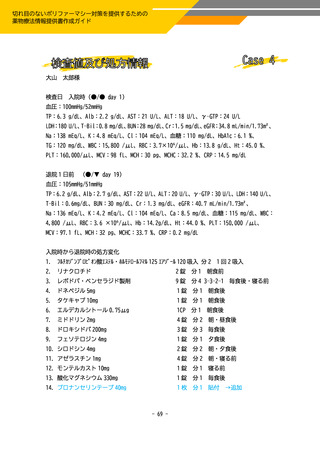よむ、つかう、まなぶ。
切れ目のないポリファーマシー対策を提供するための薬物療法情報提供書作成ガイド (43 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.ncgg.go.jp/hospital/kenshu/news/20250331.html |
| 出典情報 | 切れ目のないポリファーマシー対策を提供するための薬物療法情報提供書作成ガイド(3/31)《国立長寿医療研究センター》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
8.2.3 急性期から療養環境移行時に伝えるべきポイント
急性期では入院の原因・契機となった疾患に対して薬物が追加されたり、これまで内服し
ていた薬物が中止されたりする。これらの処方変更の意図は、急性期退院後の担当者にとっ
て薬物療法を評価する上で重要な情報である。さらに、高齢者において特に慎重な投与を要
する薬物(Potentially Inappropriate Medications:PIMs)を患者の病態を考慮して継続
している場合は、退院後の薬物療法を評価する薬剤師にとって重要な情報となるため、その
処方意図を記載することが重要である。
①薬物有害事象に関する情報
薬物有害事象による処方見直しを行った際には、再び薬物有害事象を起こさないために
も処方見直しを行った薬物名やその理由などの情報を記載することが重要である。
②中止薬に関する情報
急性期では、患者の病態や内服困難な状況に応じて、入院前まで服用していた薬物が一
プを行うためにも、服用していた情報は重要であるため情報提供を行う。また、中止した
薬物の中には長期予後を考慮すると再開が必要な薬物も含まれる。退院後に再開または
検討が必要な場合には、その旨の情報提供を行うことが重要となる。
③追加した薬物・使用した薬物に関する情報
急性期で追加された薬物の処方意図や開始日、開始前後の関連する検査値は、退院後の
担当者にとって薬物療法の有効性や薬物有害事象の評価を行う際に重要な情報であるた
め、薬物療法情報提供書に記載することが望ましい。また、頓服対応している薬物名や使
用頻度が有用な情報になることがあるため記載することを検討する。
急性期では内服薬の他に注射剤を多く使用する。継続が必要な注射剤に関しては、薬物
名、用法・用量、投与日を薬物療法情報提供書に記載することが望ましい。
④患者の身体機能や嚥下機能に応じた処方見直しに関する情報提供
急性期では、患者の疾患(脳卒中や大腿骨骨折等)によって身体機能や嚥下機能が大き
く変化する。しかし、身体機能や嚥下機能の低下や回復状況に合わせた内服管理の工夫や
適切な剤形の選択、退院後の生活環境に合わせた内服管理方法などの支援が十分行えない
ことも考えられる。そのため、急性期で行った支援内容や急性期退院後に必要となる支援
内容を薬物療法情報提供書に記載し、担当者に引き継ぐことが重要である。
文献
1)
Kojima T, Takeya Y, Arai H, Akishita M,et.al. Risk factors for adverse drug reactions in
older inpatients of geriatric wards at admission: Multicenter study. Geriatr Gerontol Int.
20(2):144-149,2020
2) 瀧川美和、島﨑良知、他 高齢者急性期病院におけるポリファーマシーカンファレンスに基づいた薬
剤師による減薬提案の実態および効果に関する調査、日本老年薬学会雑誌、7:1-7、2024
- 38 -
8
8
療療
養養
環環
境境
移移
行行
時時
のの
注注
意意
点点
部またはすべて中止となることが多い。薬物中止後の症状・状態悪化などのフォローアッ
急性期では入院の原因・契機となった疾患に対して薬物が追加されたり、これまで内服し
ていた薬物が中止されたりする。これらの処方変更の意図は、急性期退院後の担当者にとっ
て薬物療法を評価する上で重要な情報である。さらに、高齢者において特に慎重な投与を要
する薬物(Potentially Inappropriate Medications:PIMs)を患者の病態を考慮して継続
している場合は、退院後の薬物療法を評価する薬剤師にとって重要な情報となるため、その
処方意図を記載することが重要である。
①薬物有害事象に関する情報
薬物有害事象による処方見直しを行った際には、再び薬物有害事象を起こさないために
も処方見直しを行った薬物名やその理由などの情報を記載することが重要である。
②中止薬に関する情報
急性期では、患者の病態や内服困難な状況に応じて、入院前まで服用していた薬物が一
プを行うためにも、服用していた情報は重要であるため情報提供を行う。また、中止した
薬物の中には長期予後を考慮すると再開が必要な薬物も含まれる。退院後に再開または
検討が必要な場合には、その旨の情報提供を行うことが重要となる。
③追加した薬物・使用した薬物に関する情報
急性期で追加された薬物の処方意図や開始日、開始前後の関連する検査値は、退院後の
担当者にとって薬物療法の有効性や薬物有害事象の評価を行う際に重要な情報であるた
め、薬物療法情報提供書に記載することが望ましい。また、頓服対応している薬物名や使
用頻度が有用な情報になることがあるため記載することを検討する。
急性期では内服薬の他に注射剤を多く使用する。継続が必要な注射剤に関しては、薬物
名、用法・用量、投与日を薬物療法情報提供書に記載することが望ましい。
④患者の身体機能や嚥下機能に応じた処方見直しに関する情報提供
急性期では、患者の疾患(脳卒中や大腿骨骨折等)によって身体機能や嚥下機能が大き
く変化する。しかし、身体機能や嚥下機能の低下や回復状況に合わせた内服管理の工夫や
適切な剤形の選択、退院後の生活環境に合わせた内服管理方法などの支援が十分行えない
ことも考えられる。そのため、急性期で行った支援内容や急性期退院後に必要となる支援
内容を薬物療法情報提供書に記載し、担当者に引き継ぐことが重要である。
文献
1)
Kojima T, Takeya Y, Arai H, Akishita M,et.al. Risk factors for adverse drug reactions in
older inpatients of geriatric wards at admission: Multicenter study. Geriatr Gerontol Int.
20(2):144-149,2020
2) 瀧川美和、島﨑良知、他 高齢者急性期病院におけるポリファーマシーカンファレンスに基づいた薬
剤師による減薬提案の実態および効果に関する調査、日本老年薬学会雑誌、7:1-7、2024
- 38 -
8
8
療療
養養
環環
境境
移移
行行
時時
のの
注注
意意
点点
部またはすべて中止となることが多い。薬物中止後の症状・状態悪化などのフォローアッ