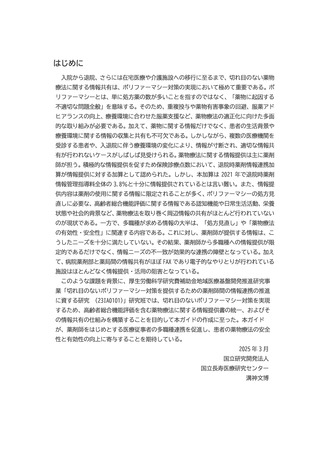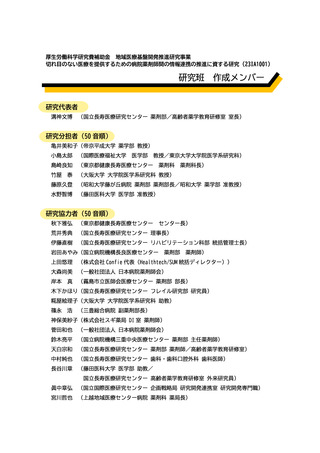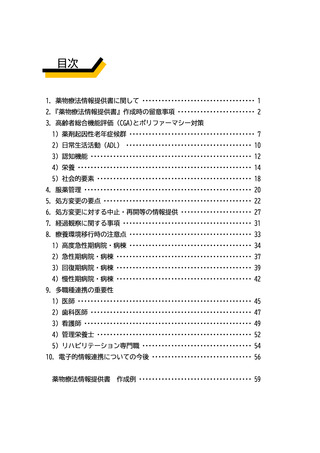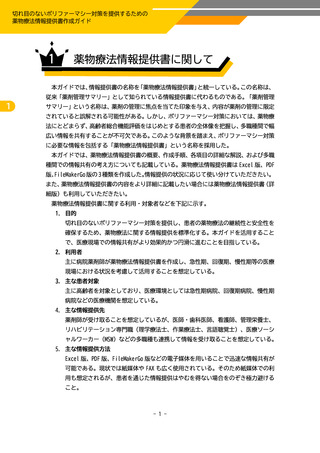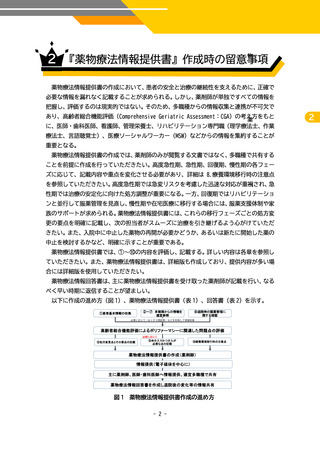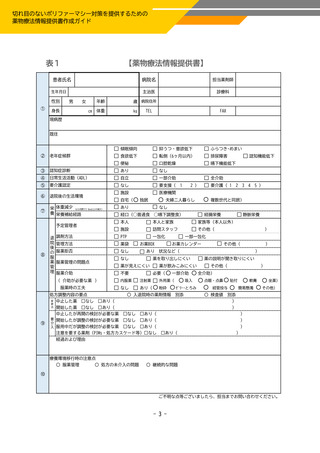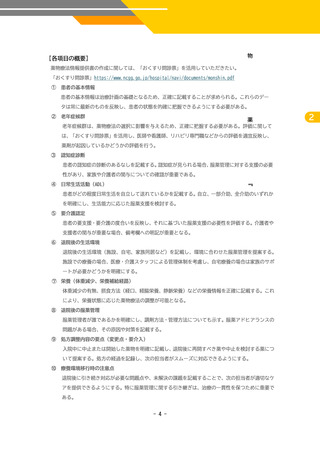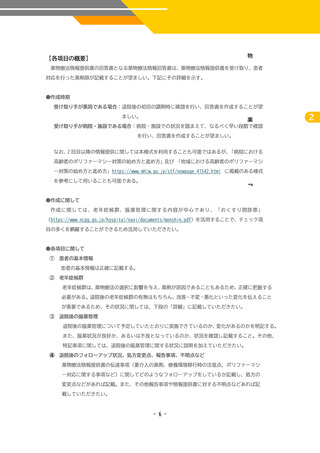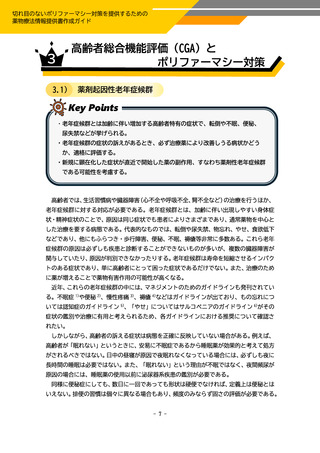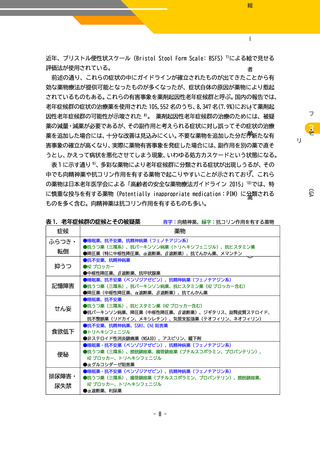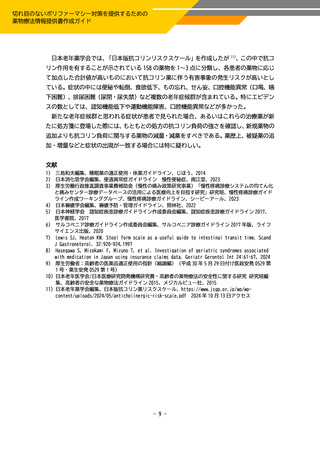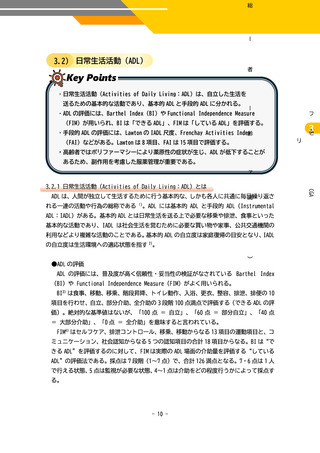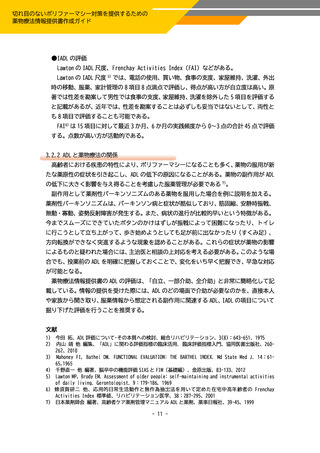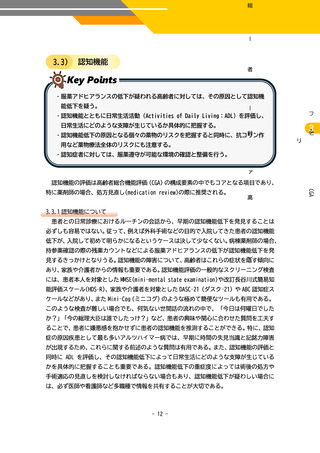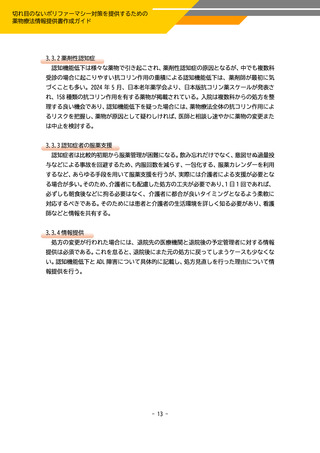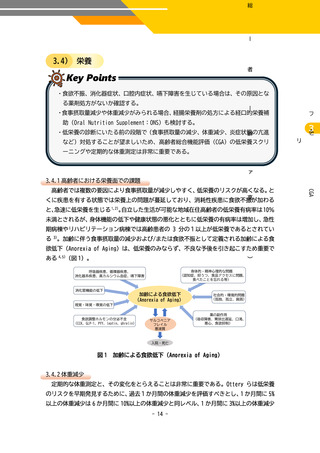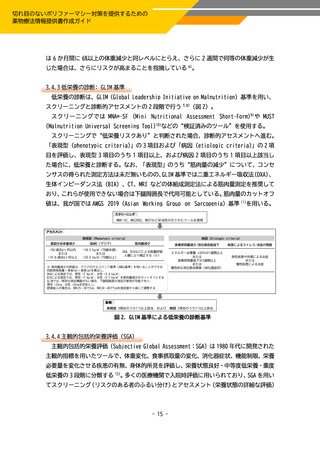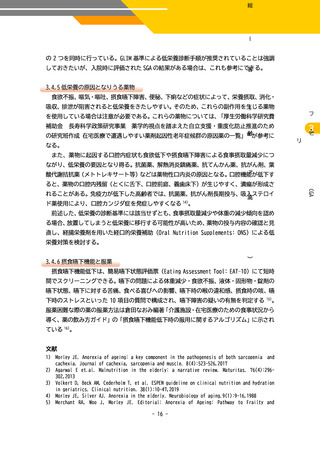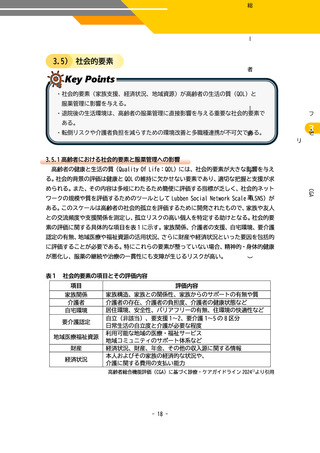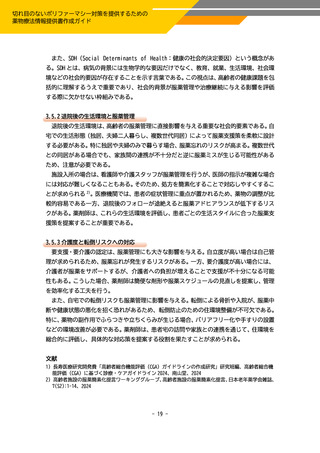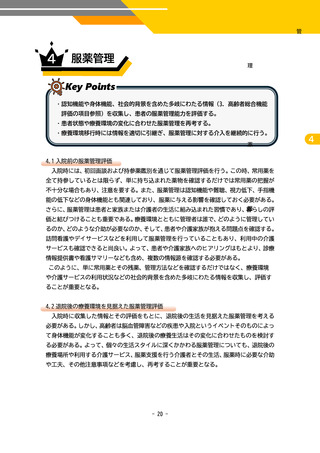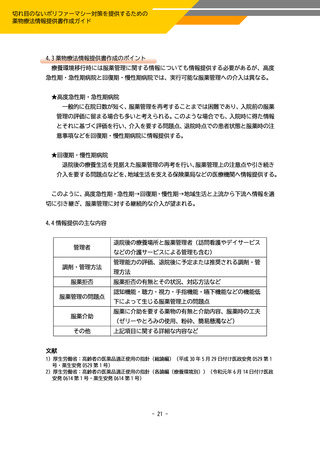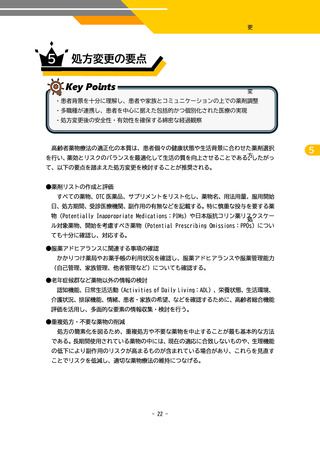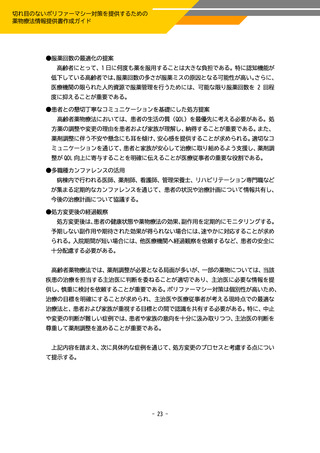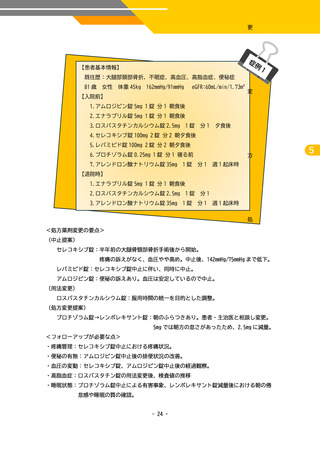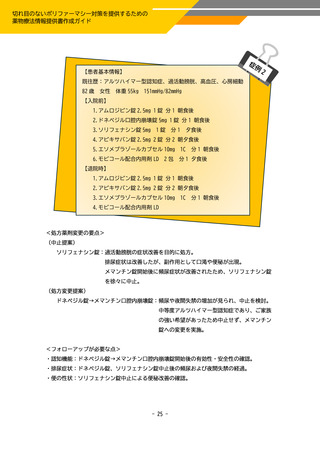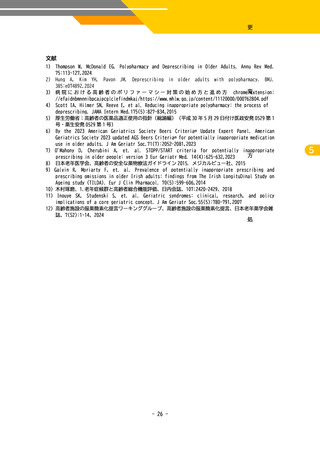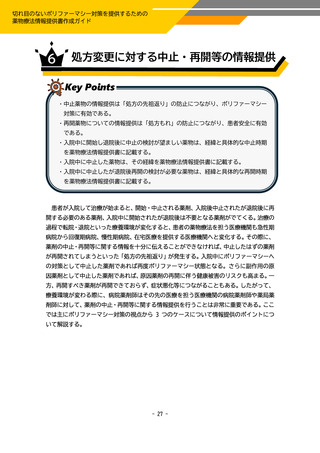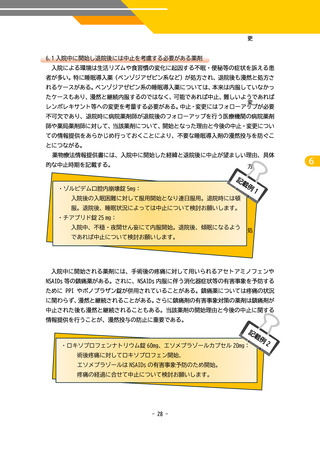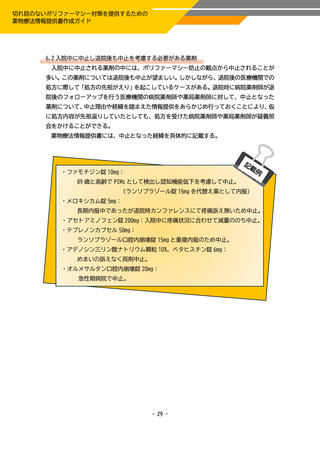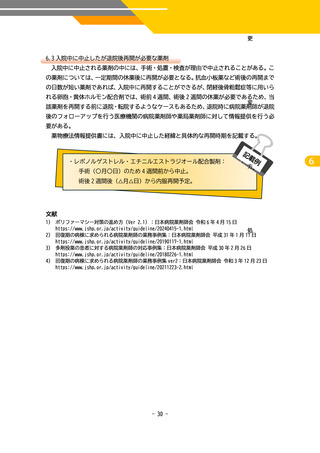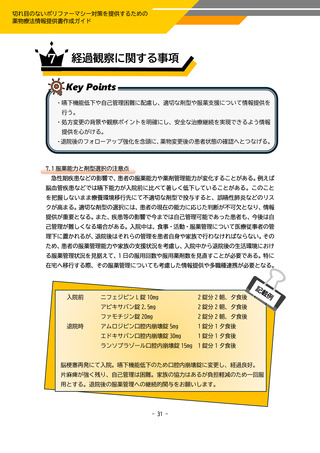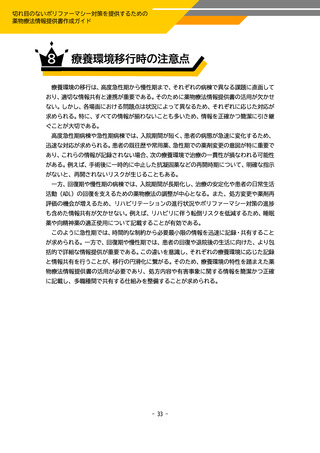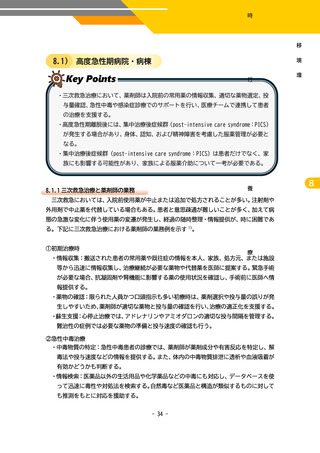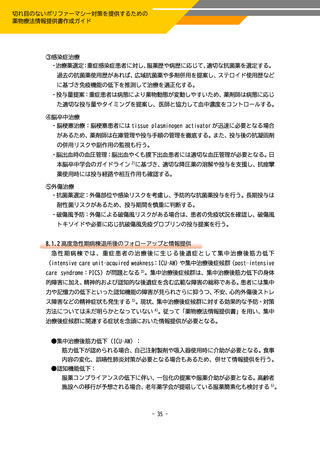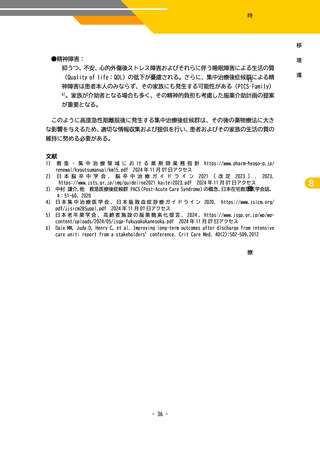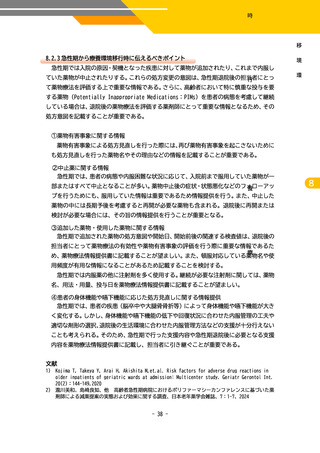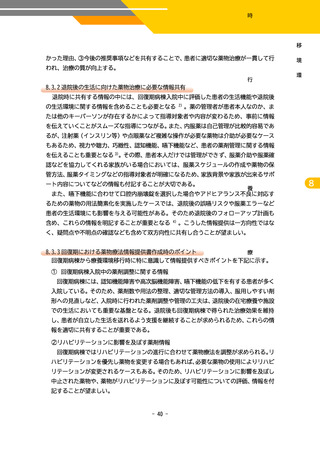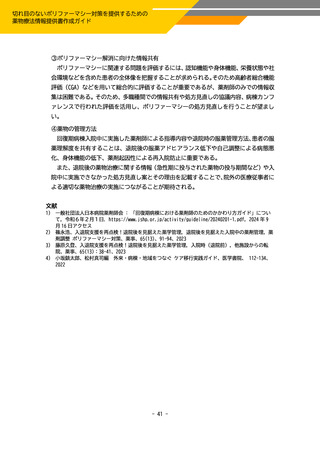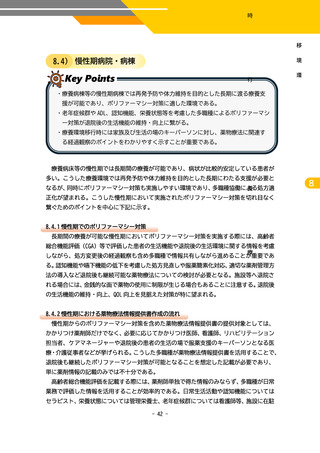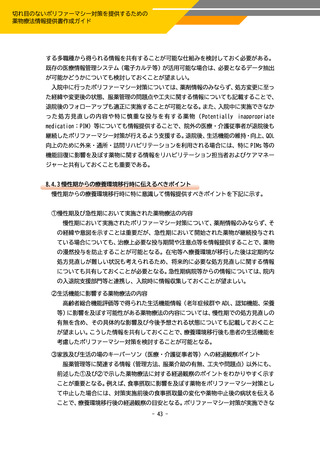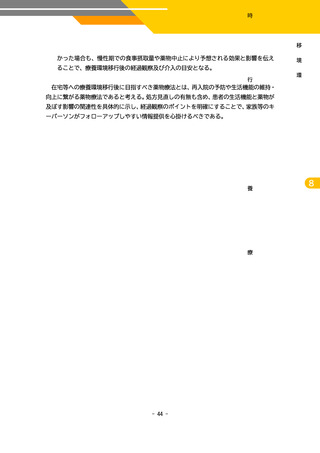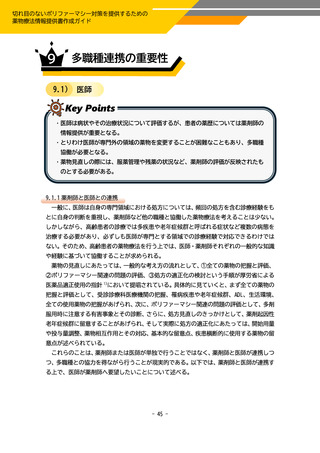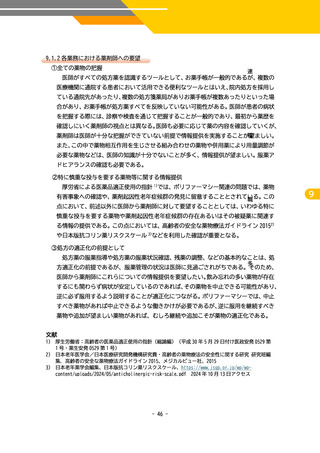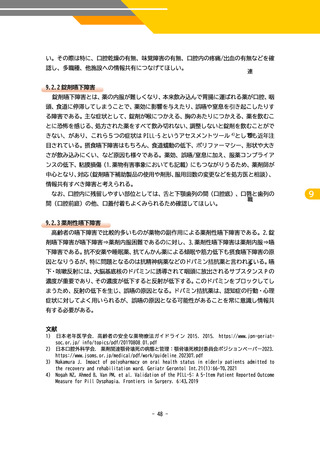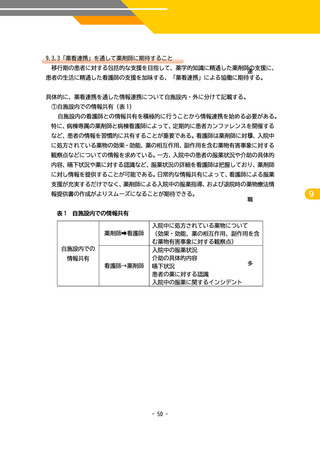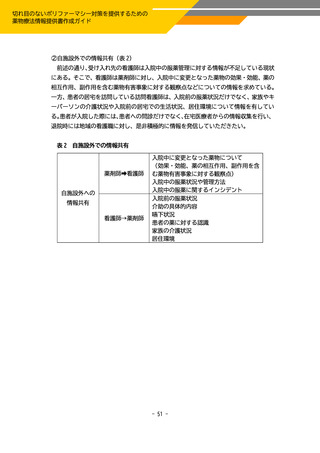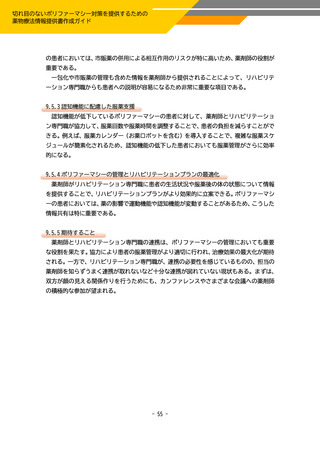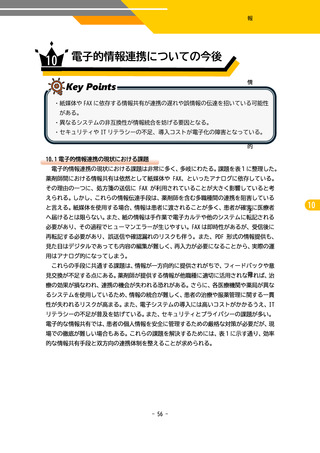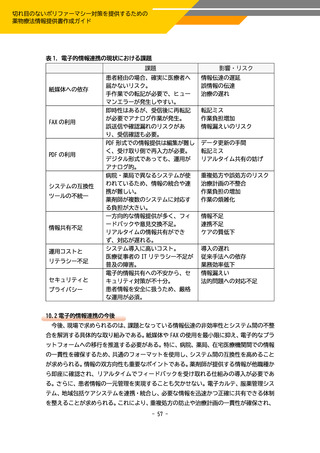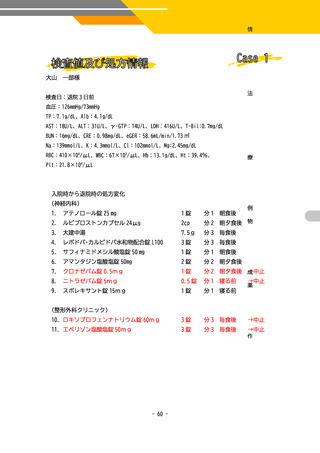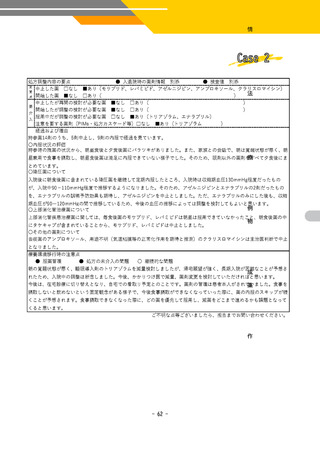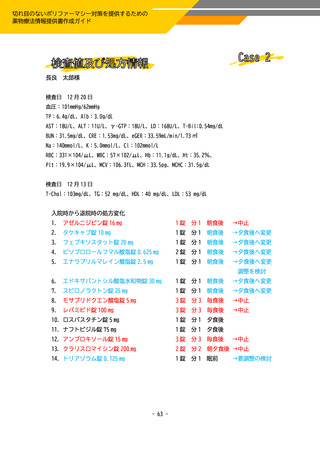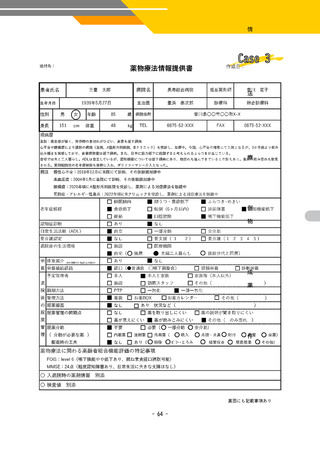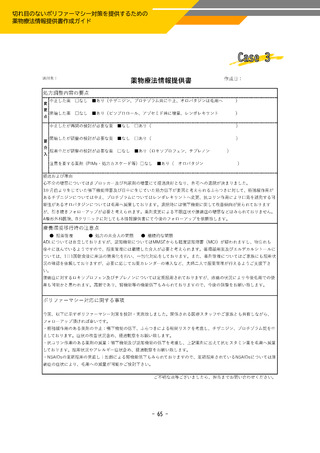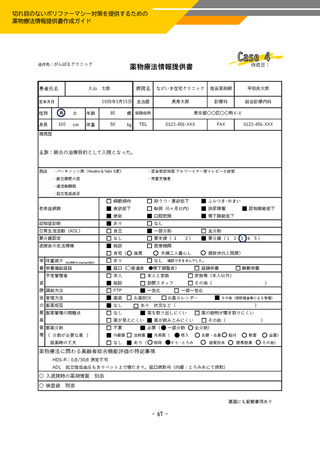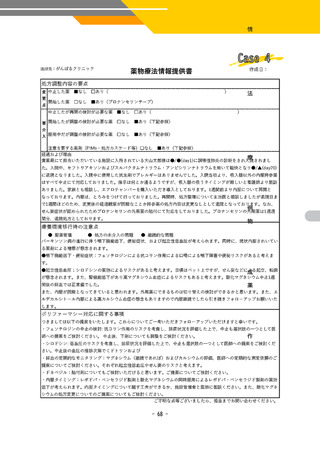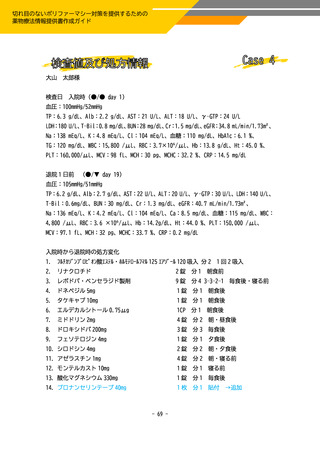よむ、つかう、まなぶ。
切れ目のないポリファーマシー対策を提供するための薬物療法情報提供書作成ガイド (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.ncgg.go.jp/hospital/kenshu/news/20250331.html |
| 出典情報 | 切れ目のないポリファーマシー対策を提供するための薬物療法情報提供書作成ガイド(3/31)《国立長寿医療研究センター》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
はじめに
入院から退院、さらには在宅医療や介護施設への移行に至るまで、切れ目のない薬物
療法に関する情報共有は、ポリファーマシー対策の実現において極めて重要である。ポ
リファーマシーとは、単に処方薬の数が多いことを指すのではなく、「薬物に起因する
不適切な問題全般」を意味する。そのため、重複投与や薬物有害事象の回避、服薬アド
ヒアランスの向上、療養環境に合わせた服薬支援など、薬物療法の適正化に向けた多面
的な取り組みが必要である。加えて、薬物に関する情報だけでなく、患者の生活背景や
療養環境に関する情報の収集と共有も不可欠である。しかしながら、複数の医療機関を
受診する患者や、入退院に伴う療養環境の変化により、情報が寸断され、適切な情報共
有が行われないケースがしばしば見受けられる。薬物療法に関する情報提供は主に薬剤
師が担う。積極的な情報提供を促すため保険診療点数において、退院時薬剤情報連携加
算が情報提供に対する加算として認められた。しかし、本加算は 2021 年で退院時薬剤
情報管理指導料全体の 3.8%と十分に情報提供されているとは言い難い。また、情報提
供内容は薬剤の使用に関する情報に限定されることが多く、ポリファーマシーの処方見
直しに必要な、高齢者総合機能評価に関する情報である認知機能や日常生活活動、栄養
状態や社会的背景など、薬物療法を取り巻く周辺情報の共有がほとんど行われていない
のが現状である。一方で、多職種が求める情報の大半は、「処方見直し」や「薬物療法
の有効性・安全性」に関連する内容である。これに対し、薬剤師が提供する情報は、こ
うしたニーズを十分に満たしていない。その結果、薬剤師から多職種への情報提供が限
定的であるだけでなく、情報ニーズの不一致が効果的な連携の障壁となっている。加え
て、病院薬剤部と薬局間の情報共有がほぼ FAX であり電子的なやりとりが行われている
施設はほとんどなく情報提供・活用の阻害となっている。
このような課題を背景に、厚生労働科学研究費補助金地域医療基盤開発推進研究事
業「切れ目のないポリファーマシー対策を提供するための薬剤師間の情報連携の推進
に資する研究 (23IA0101)」研究班では、切れ目のないポリファーマシー対策を実現
するため、高齢者総合機能評価を含む薬物療法に関する情報提供書の統一、およびそ
の情報共有の仕組みを構築することを目的して本ガイドの作成に至った。本ガイド
が、薬剤師をはじめとする医療従事者の多職種連携を促進し、患者の薬物療法の安全
性と有効性の向上に寄与することを期待している。
2025 年 3 月
国立研究開発法人
国立長寿医療研究センター
溝神文博
入院から退院、さらには在宅医療や介護施設への移行に至るまで、切れ目のない薬物
療法に関する情報共有は、ポリファーマシー対策の実現において極めて重要である。ポ
リファーマシーとは、単に処方薬の数が多いことを指すのではなく、「薬物に起因する
不適切な問題全般」を意味する。そのため、重複投与や薬物有害事象の回避、服薬アド
ヒアランスの向上、療養環境に合わせた服薬支援など、薬物療法の適正化に向けた多面
的な取り組みが必要である。加えて、薬物に関する情報だけでなく、患者の生活背景や
療養環境に関する情報の収集と共有も不可欠である。しかしながら、複数の医療機関を
受診する患者や、入退院に伴う療養環境の変化により、情報が寸断され、適切な情報共
有が行われないケースがしばしば見受けられる。薬物療法に関する情報提供は主に薬剤
師が担う。積極的な情報提供を促すため保険診療点数において、退院時薬剤情報連携加
算が情報提供に対する加算として認められた。しかし、本加算は 2021 年で退院時薬剤
情報管理指導料全体の 3.8%と十分に情報提供されているとは言い難い。また、情報提
供内容は薬剤の使用に関する情報に限定されることが多く、ポリファーマシーの処方見
直しに必要な、高齢者総合機能評価に関する情報である認知機能や日常生活活動、栄養
状態や社会的背景など、薬物療法を取り巻く周辺情報の共有がほとんど行われていない
のが現状である。一方で、多職種が求める情報の大半は、「処方見直し」や「薬物療法
の有効性・安全性」に関連する内容である。これに対し、薬剤師が提供する情報は、こ
うしたニーズを十分に満たしていない。その結果、薬剤師から多職種への情報提供が限
定的であるだけでなく、情報ニーズの不一致が効果的な連携の障壁となっている。加え
て、病院薬剤部と薬局間の情報共有がほぼ FAX であり電子的なやりとりが行われている
施設はほとんどなく情報提供・活用の阻害となっている。
このような課題を背景に、厚生労働科学研究費補助金地域医療基盤開発推進研究事
業「切れ目のないポリファーマシー対策を提供するための薬剤師間の情報連携の推進
に資する研究 (23IA0101)」研究班では、切れ目のないポリファーマシー対策を実現
するため、高齢者総合機能評価を含む薬物療法に関する情報提供書の統一、およびそ
の情報共有の仕組みを構築することを目的して本ガイドの作成に至った。本ガイド
が、薬剤師をはじめとする医療従事者の多職種連携を促進し、患者の薬物療法の安全
性と有効性の向上に寄与することを期待している。
2025 年 3 月
国立研究開発法人
国立長寿医療研究センター
溝神文博