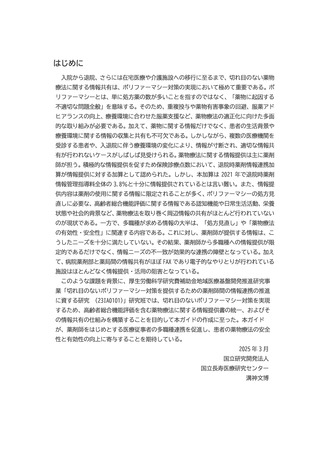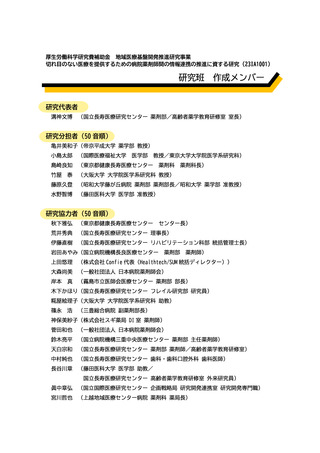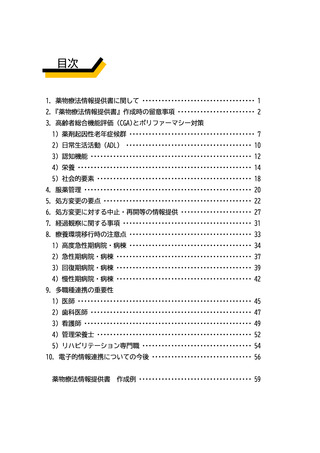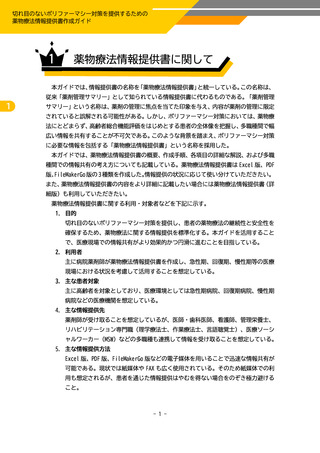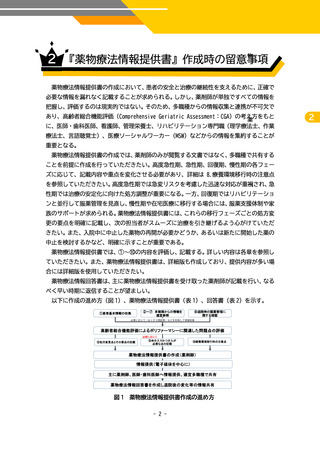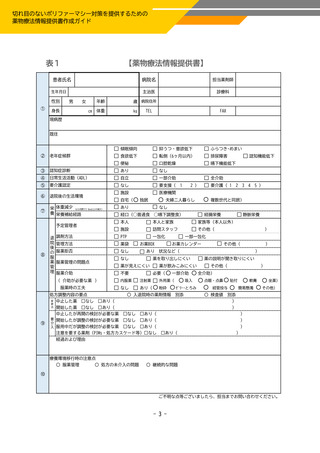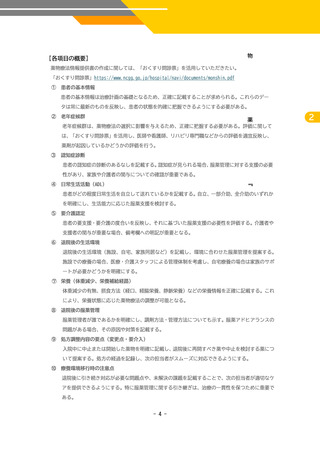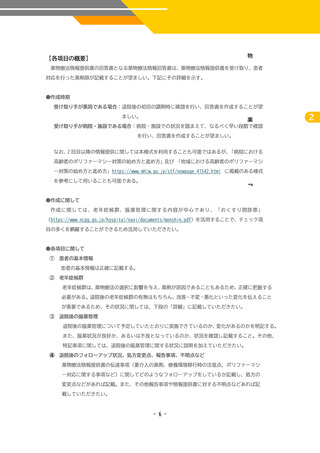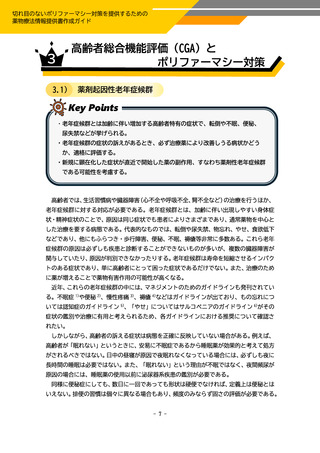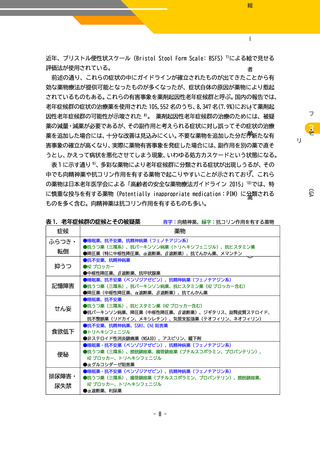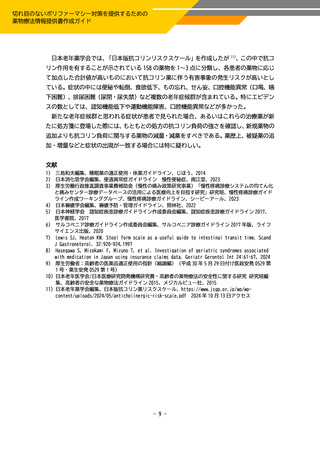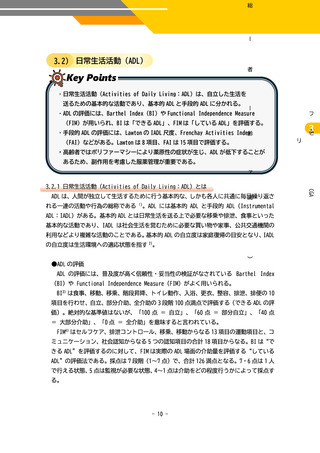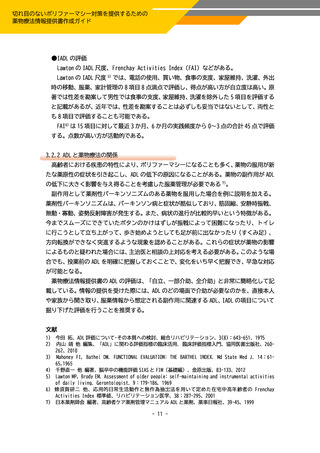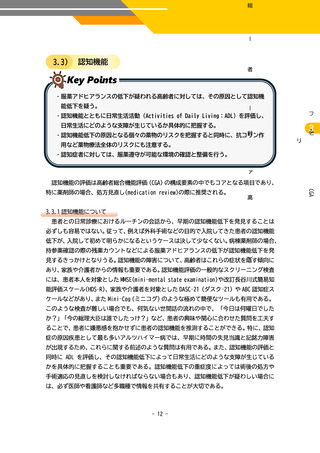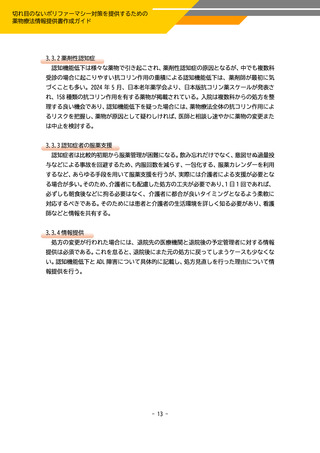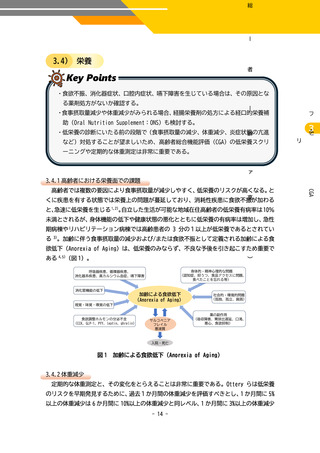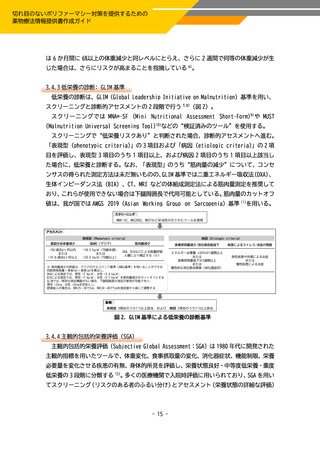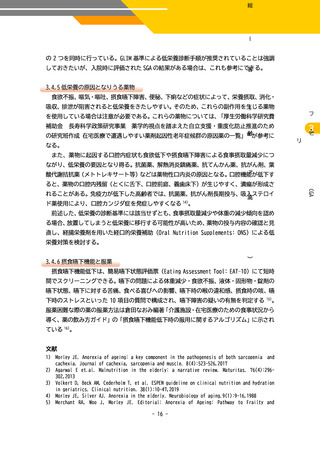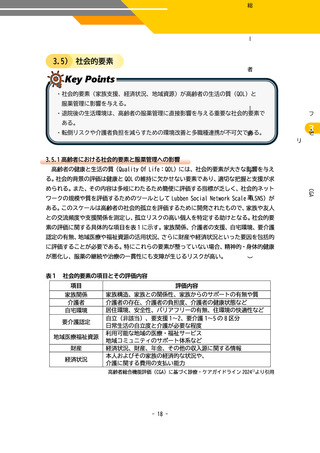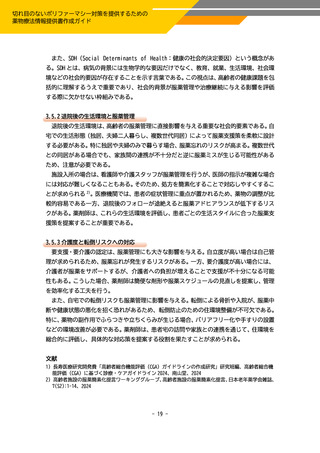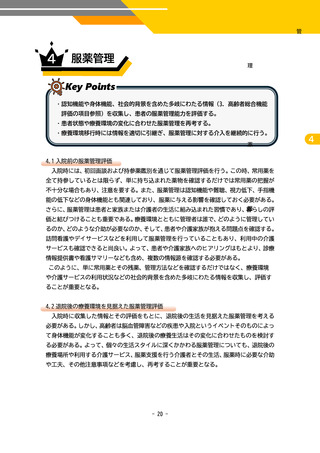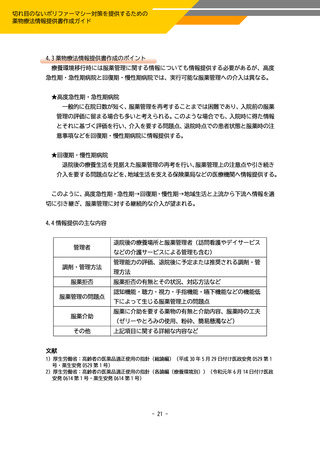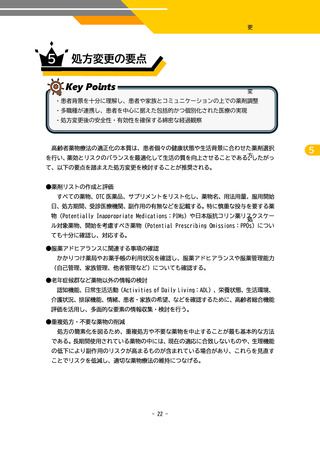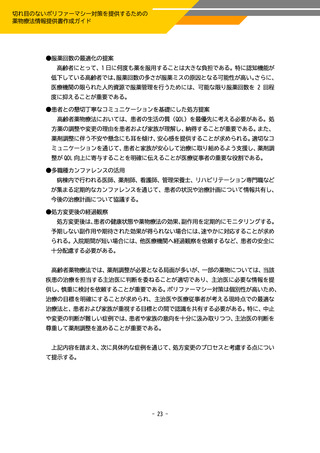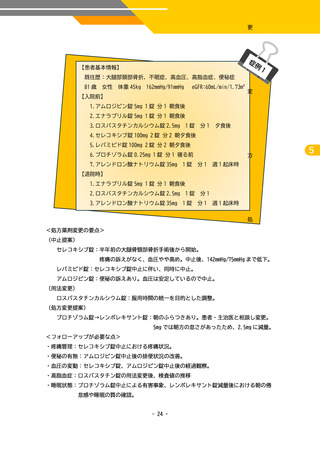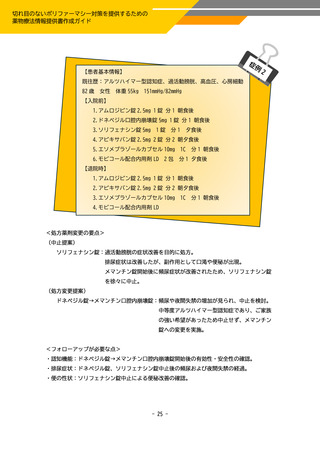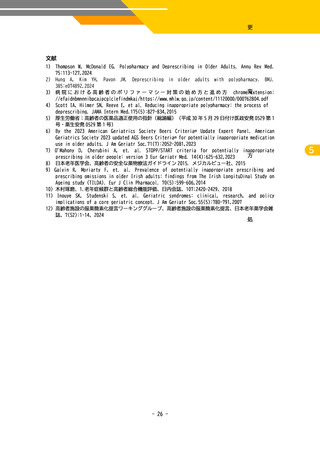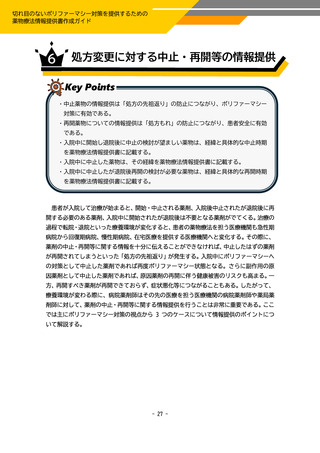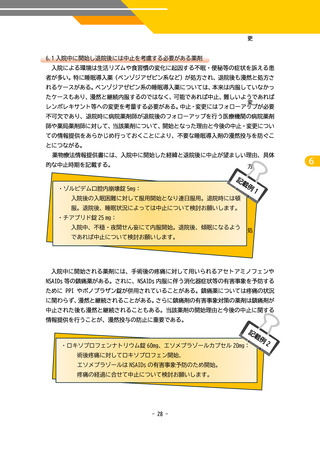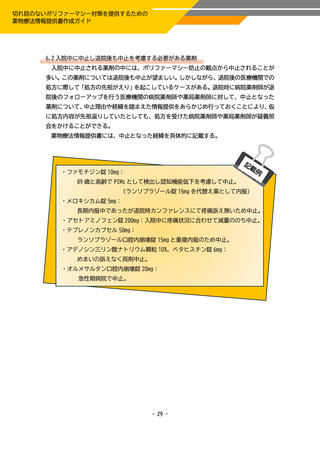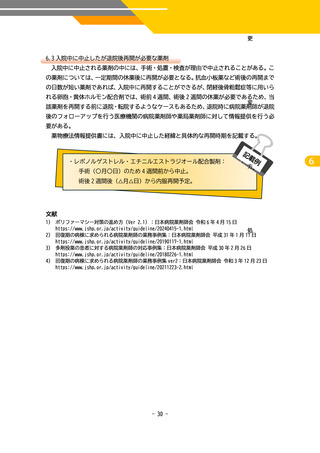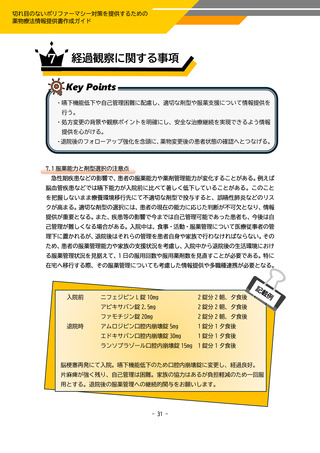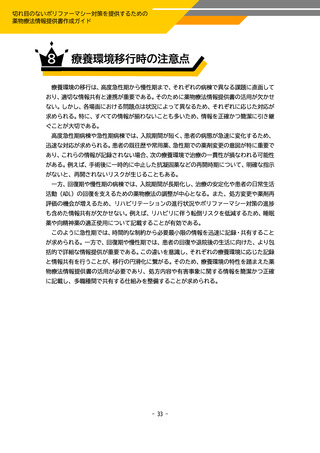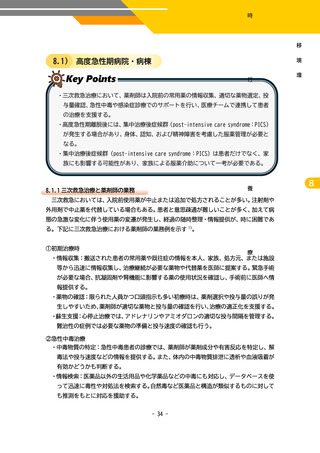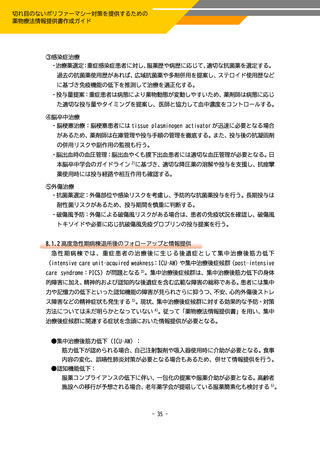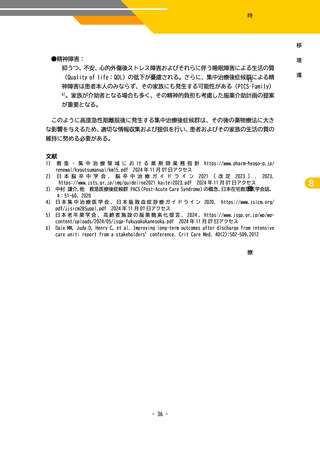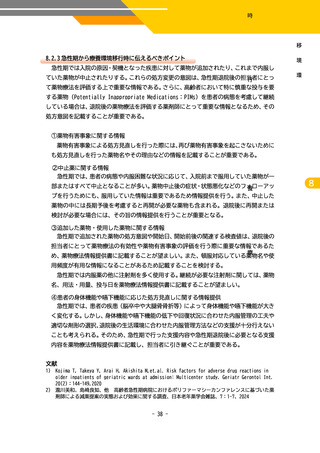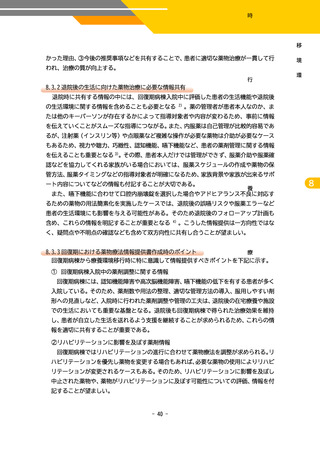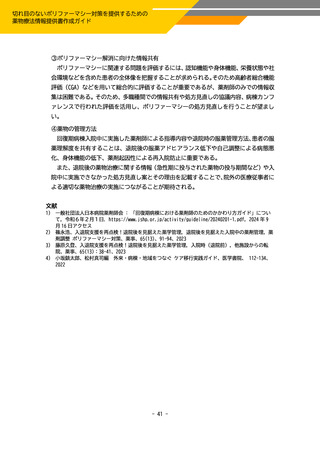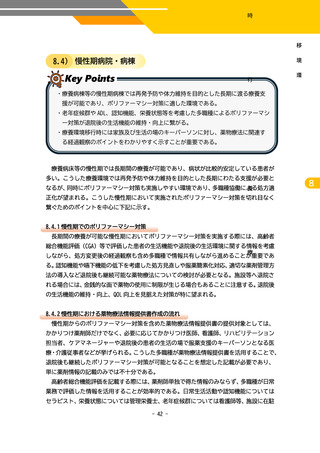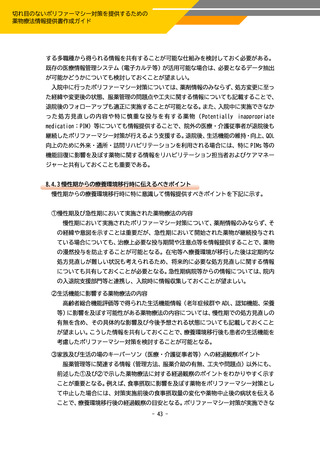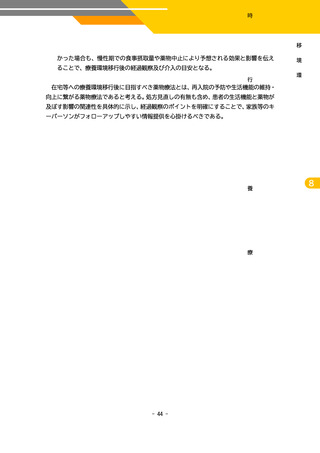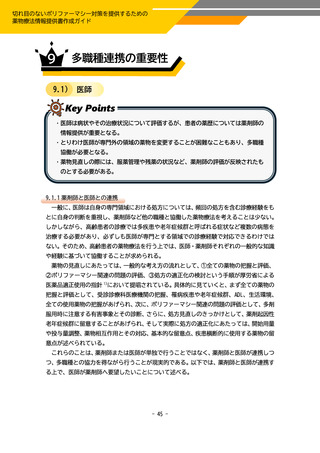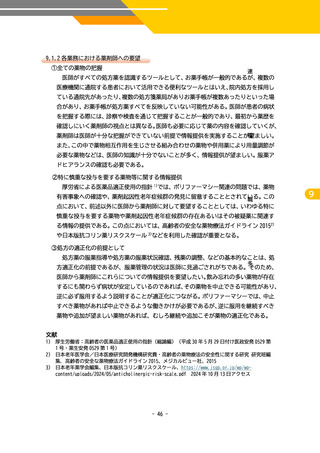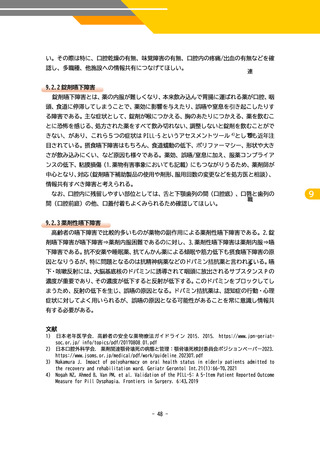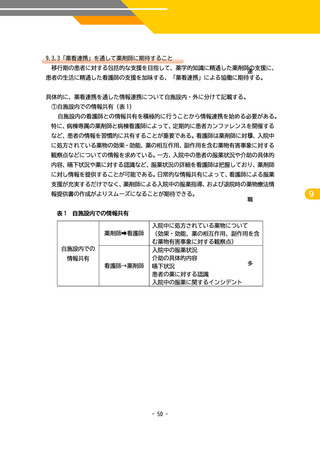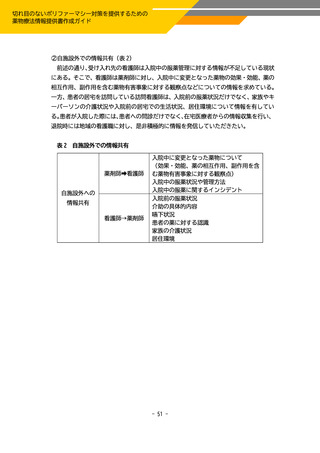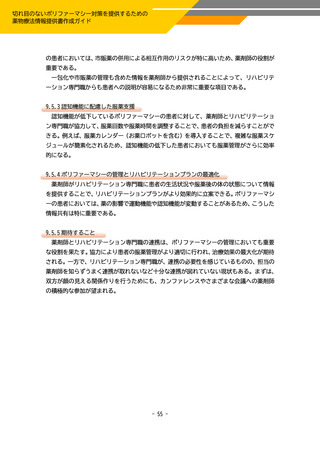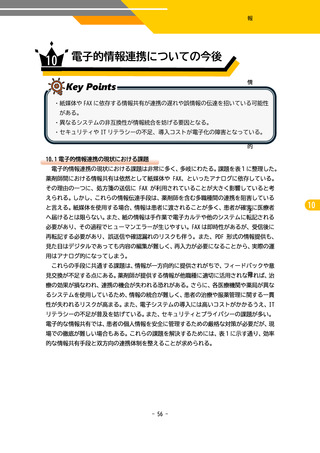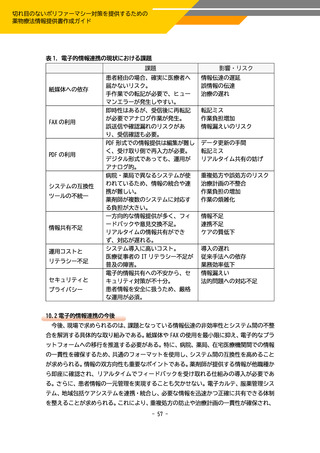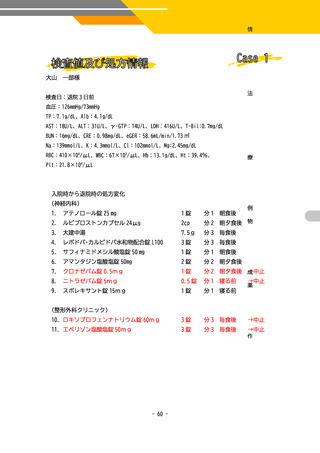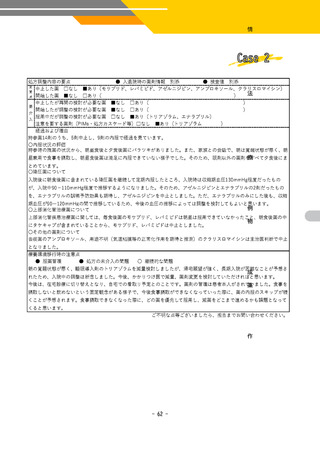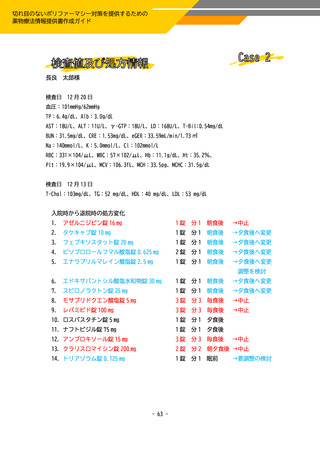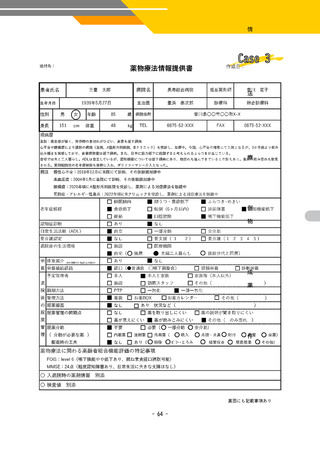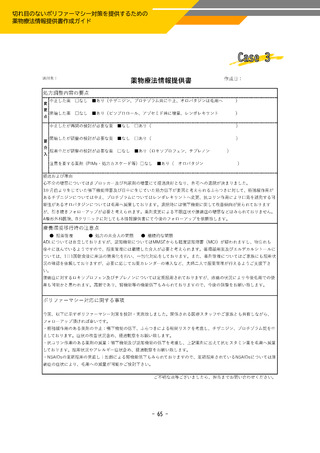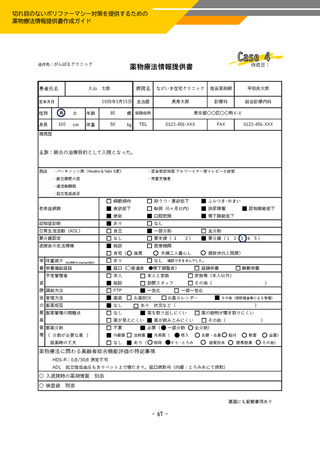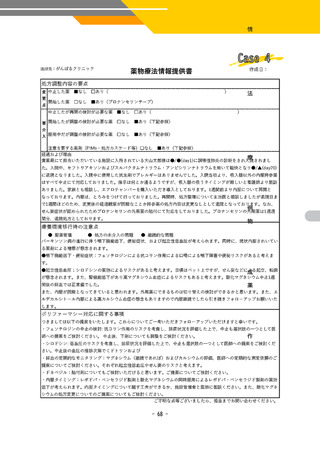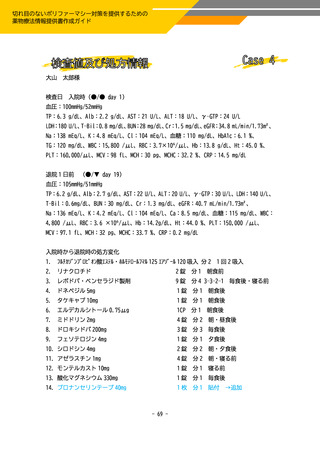よむ、つかう、まなぶ。
切れ目のないポリファーマシー対策を提供するための薬物療法情報提供書作成ガイド (32 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.ncgg.go.jp/hospital/kenshu/news/20250331.html |
| 出典情報 | 切れ目のないポリファーマシー対策を提供するための薬物療法情報提供書作成ガイド(3/31)《国立長寿医療研究センター》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
切れ目のないポリファーマシー対策を提供するための
薬物療法情報提供書作成ガイド
6
3
処方変更に対する中止・再開等の情報提供
Key Points
・中止薬物の情報提供は「処方の先祖返り」の防止につながり、ポリファーマシー
対策に有効である。
・再開薬物についての情報提供は「処方もれ」の防止につながり、患者安全に有効
である。
・入院中に開始し退院後に中止の検討が望ましい薬物は、経緯と具体的な中止時期
を薬物療法情報提供書に記載する。
・入院中に中止した薬物は、その経緯を薬物療法情報提供書に記載する。
・入院中に中止したが退院後再開の検討が必要な薬物は、経緯と具体的な再開時期
を薬物療法情報提供書に記載する。
患者が入院して治療が始まると、開始・中止される薬剤、入院後中止されたが退院後に再
開する必要のある薬剤、入院中に開始されたが退院後は不要となる薬剤がでてくる。治療の
過程で転院・退院といった療養環境が変化すると、患者の薬物療法を担う医療機関も急性期
病院から回復期病院、慢性期病院、在宅医療を提供する医療機関へと変化する。その際に、
薬剤の中止・再開等に関する情報を十分に伝えることができなければ、中止したはずの薬剤
が再開されてしまうといった「処方の先祖返り」が発生する。入院中にポリファーマシーへ
の対策として中止した薬剤であれば再度ポリファーマシー状態となる。さらに副作用の原
因薬剤として中止した薬剤であれば、原因薬剤の再開に伴う健康被害のリスクも高まる。一
方、再開すべき薬剤が再開できておらず、症状悪化等につながることもある。したがって、
療養環境が変わる際に、病院薬剤師はその先の医療を担う医療機関の病院薬剤師や薬局薬
剤師に対して、薬剤の中止・再開等に関する情報提供を行うことは非常に重要である。ここ
では主にポリファーマシー対策の視点から 3 つのケースについて情報提供のポイントにつ
いて解説する。
- 27 -
薬物療法情報提供書作成ガイド
6
3
処方変更に対する中止・再開等の情報提供
Key Points
・中止薬物の情報提供は「処方の先祖返り」の防止につながり、ポリファーマシー
対策に有効である。
・再開薬物についての情報提供は「処方もれ」の防止につながり、患者安全に有効
である。
・入院中に開始し退院後に中止の検討が望ましい薬物は、経緯と具体的な中止時期
を薬物療法情報提供書に記載する。
・入院中に中止した薬物は、その経緯を薬物療法情報提供書に記載する。
・入院中に中止したが退院後再開の検討が必要な薬物は、経緯と具体的な再開時期
を薬物療法情報提供書に記載する。
患者が入院して治療が始まると、開始・中止される薬剤、入院後中止されたが退院後に再
開する必要のある薬剤、入院中に開始されたが退院後は不要となる薬剤がでてくる。治療の
過程で転院・退院といった療養環境が変化すると、患者の薬物療法を担う医療機関も急性期
病院から回復期病院、慢性期病院、在宅医療を提供する医療機関へと変化する。その際に、
薬剤の中止・再開等に関する情報を十分に伝えることができなければ、中止したはずの薬剤
が再開されてしまうといった「処方の先祖返り」が発生する。入院中にポリファーマシーへ
の対策として中止した薬剤であれば再度ポリファーマシー状態となる。さらに副作用の原
因薬剤として中止した薬剤であれば、原因薬剤の再開に伴う健康被害のリスクも高まる。一
方、再開すべき薬剤が再開できておらず、症状悪化等につながることもある。したがって、
療養環境が変わる際に、病院薬剤師はその先の医療を担う医療機関の病院薬剤師や薬局薬
剤師に対して、薬剤の中止・再開等に関する情報提供を行うことは非常に重要である。ここ
では主にポリファーマシー対策の視点から 3 つのケースについて情報提供のポイントにつ
いて解説する。
- 27 -