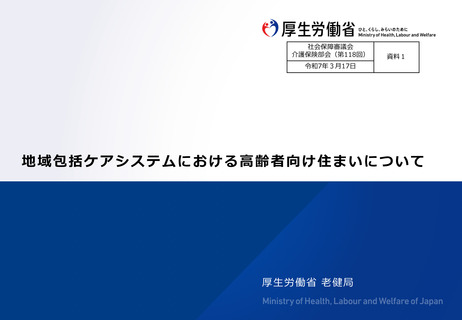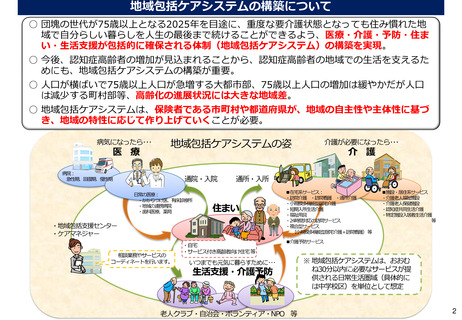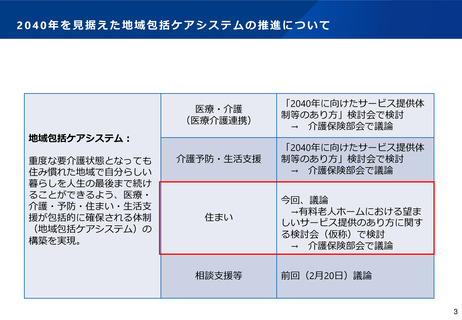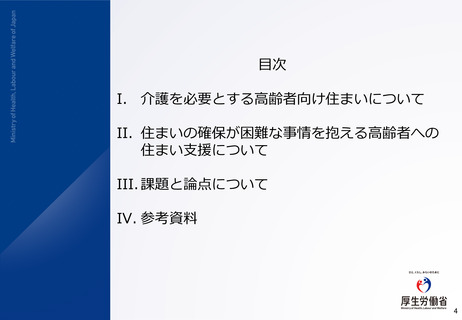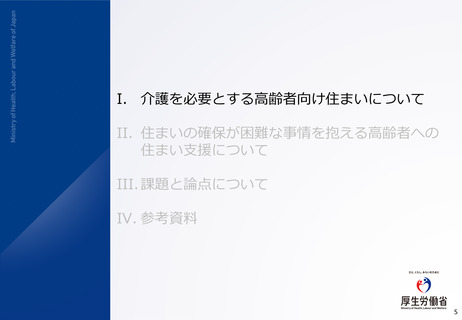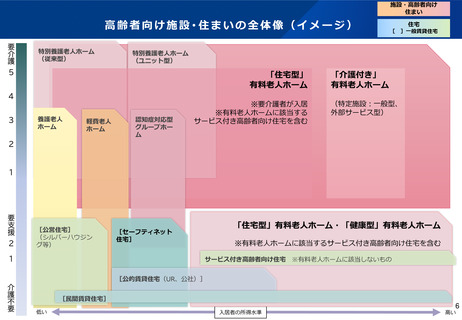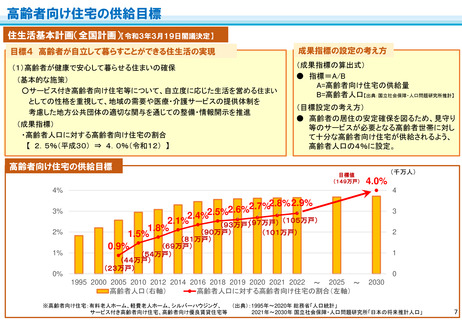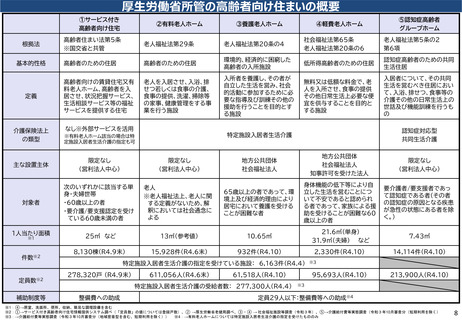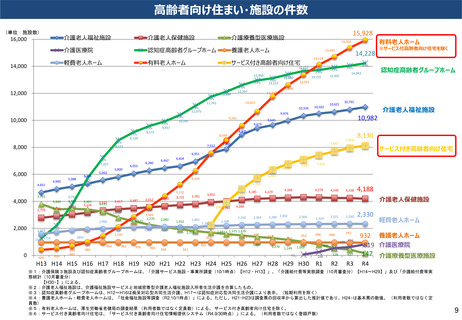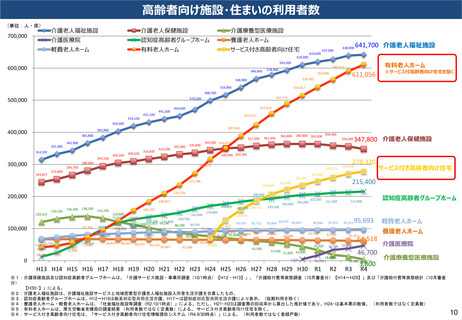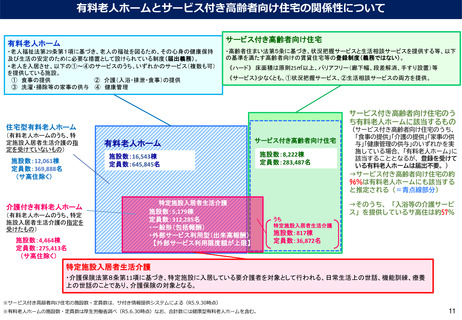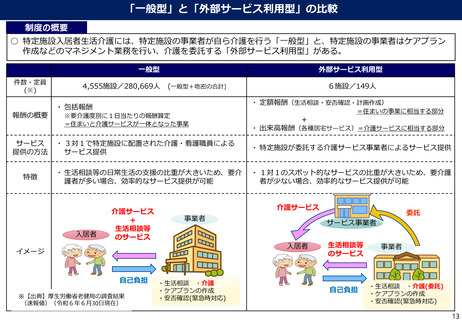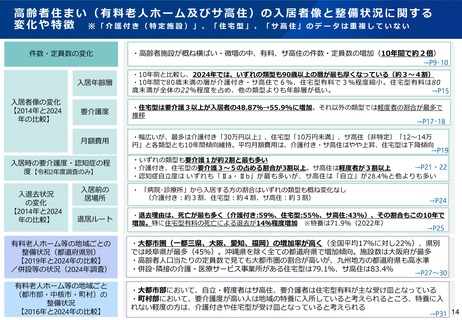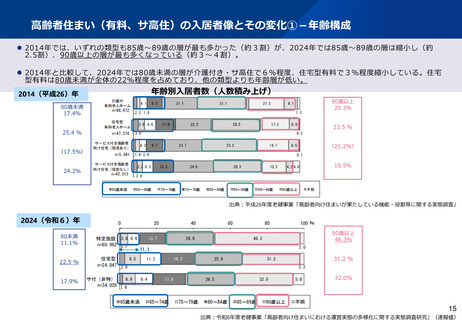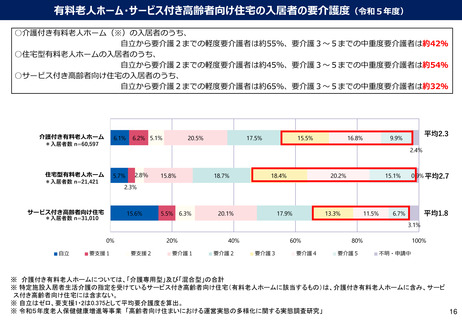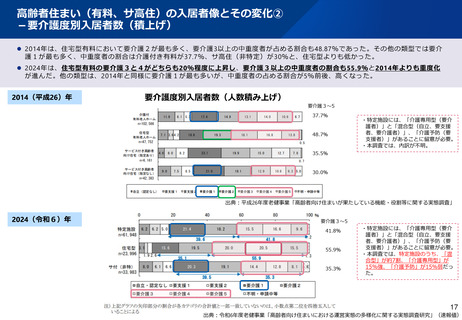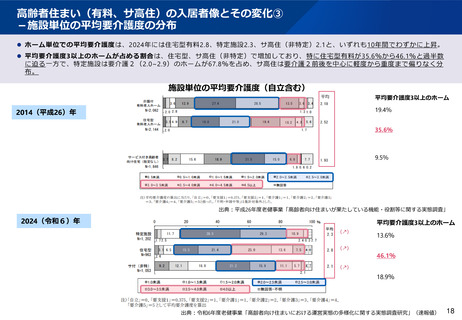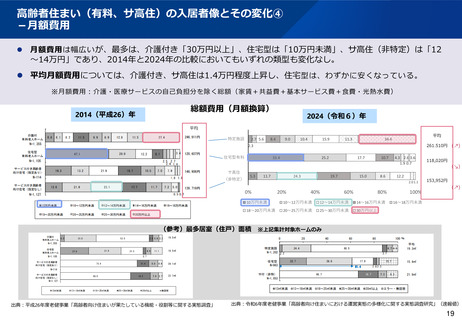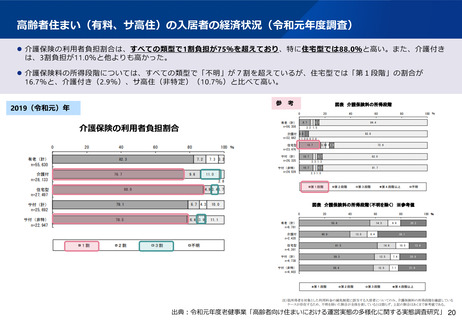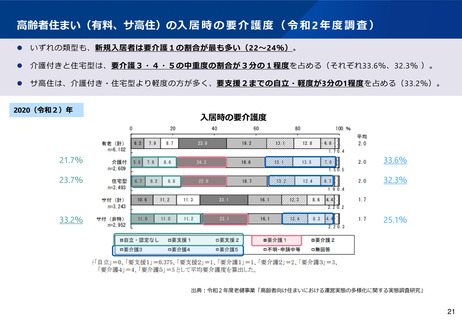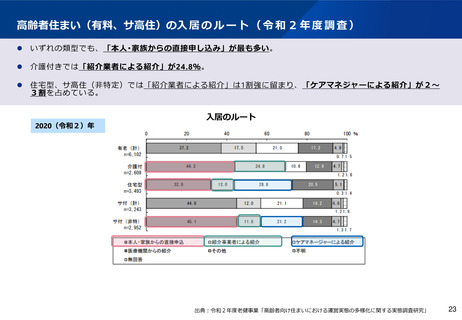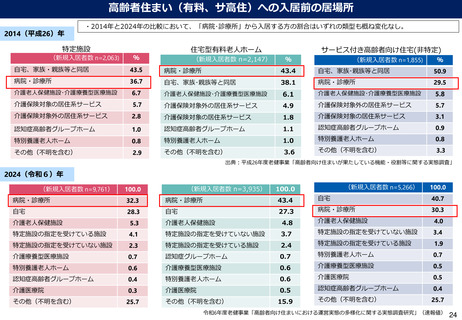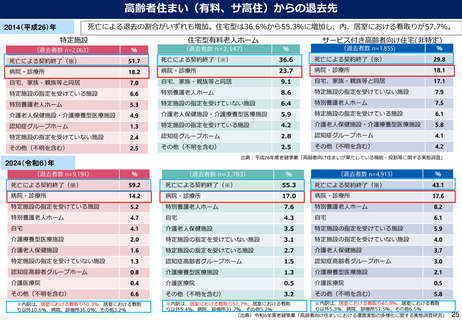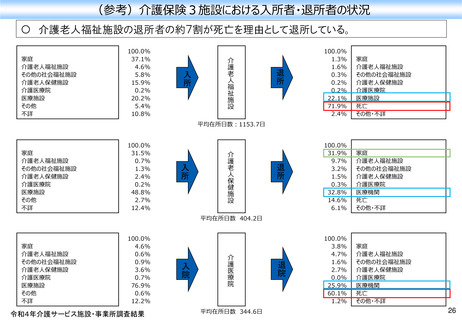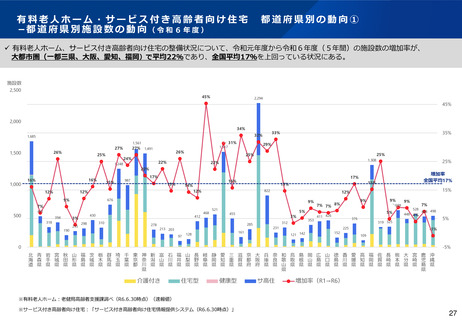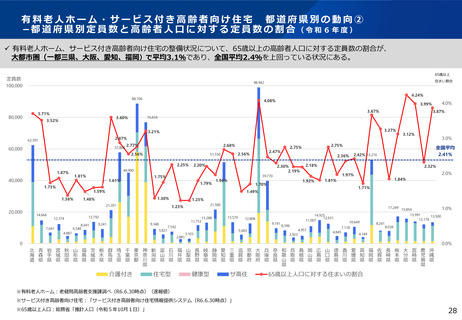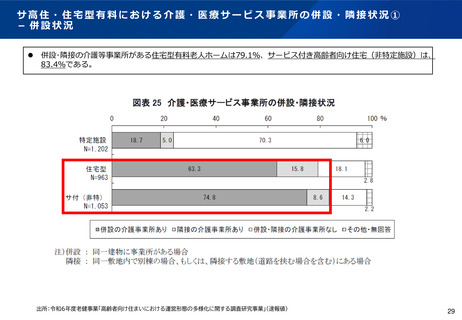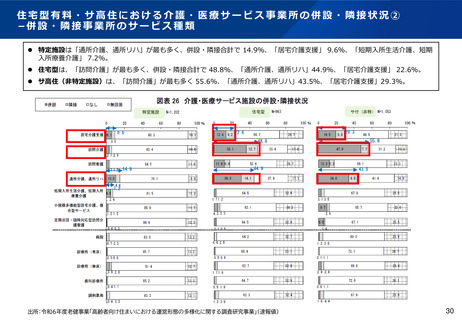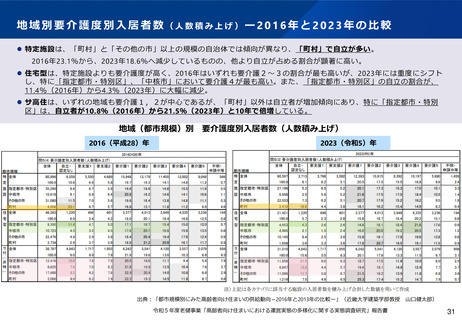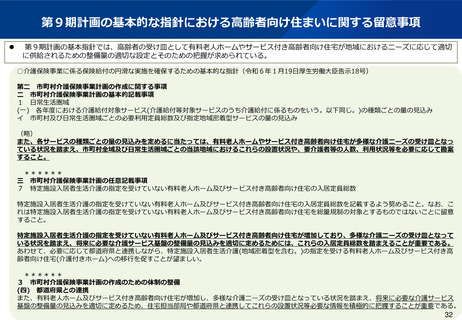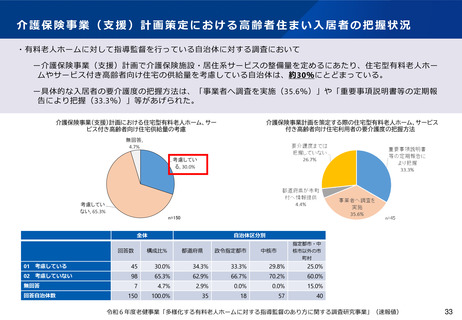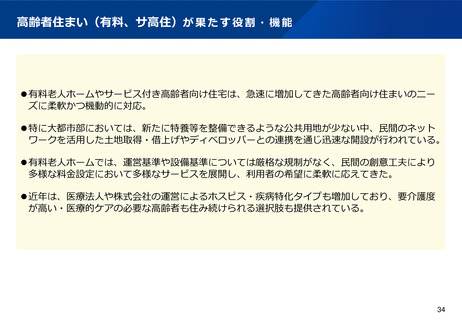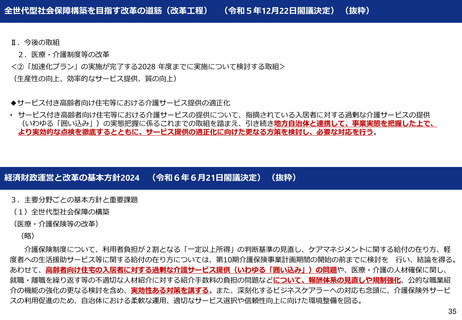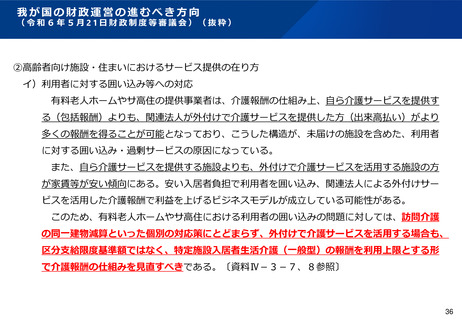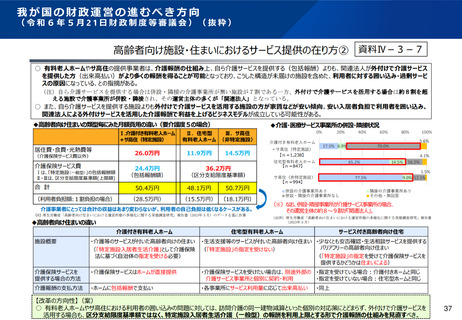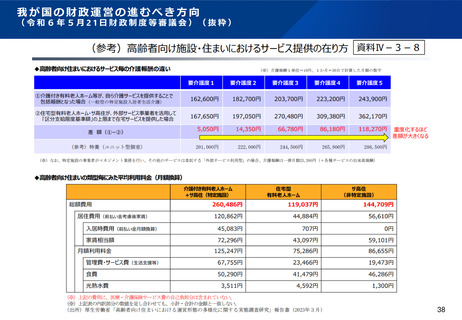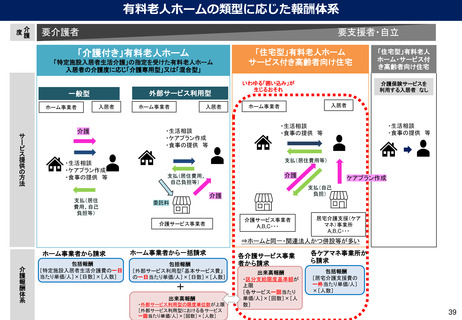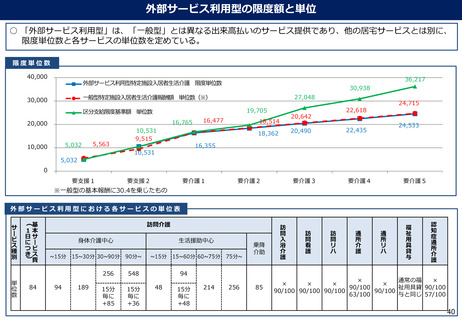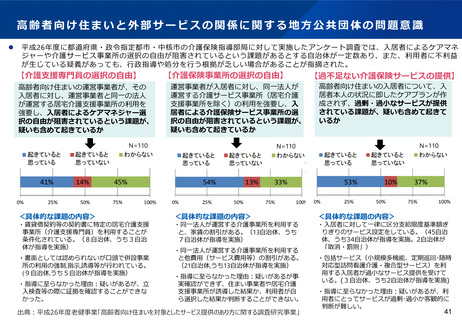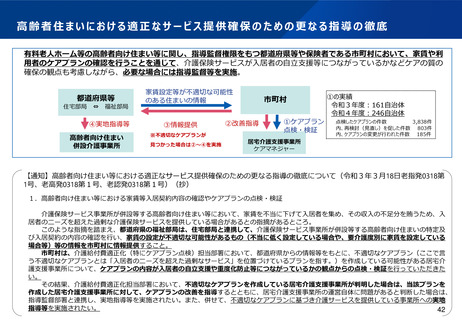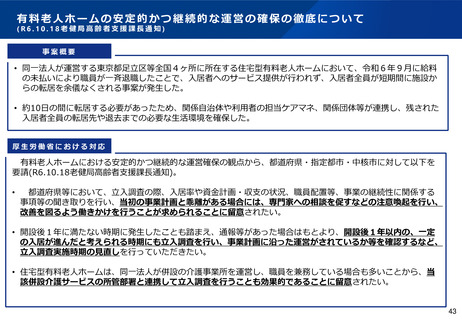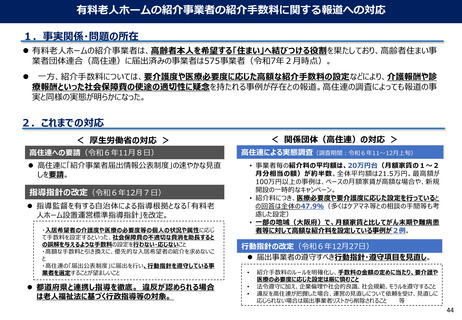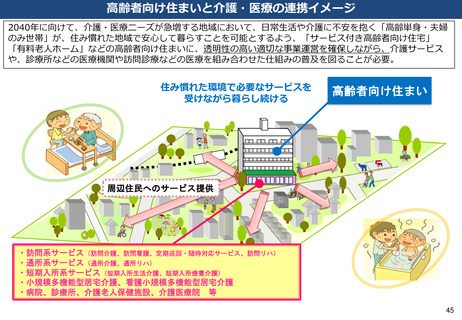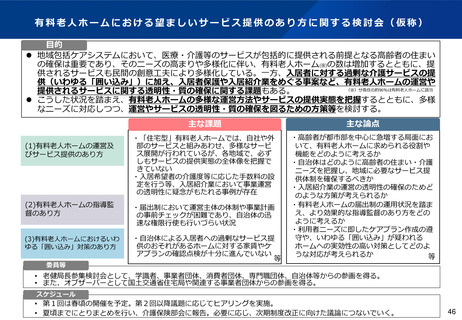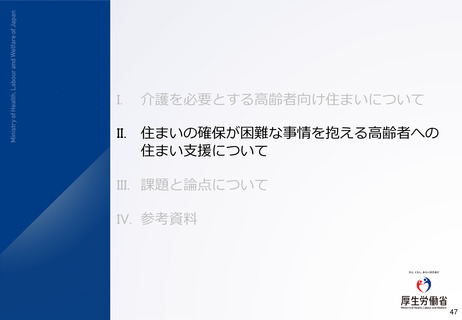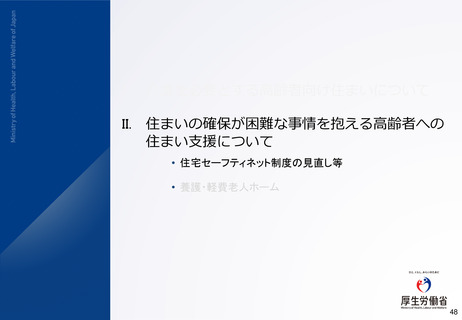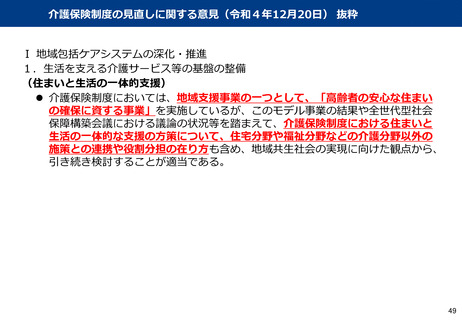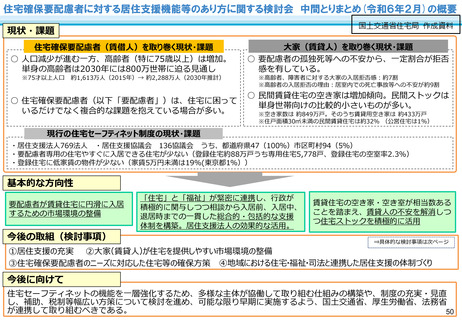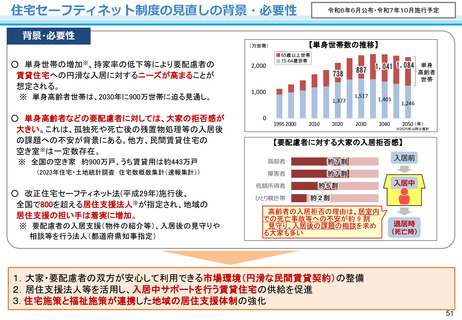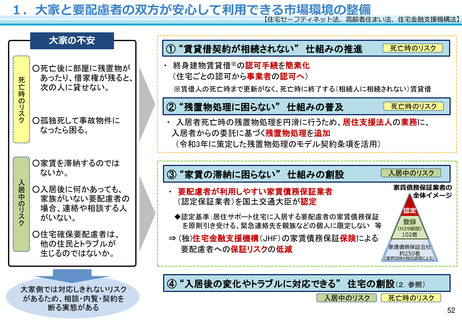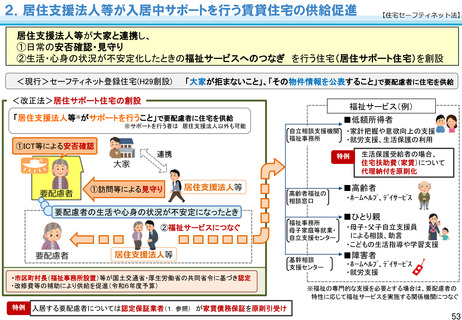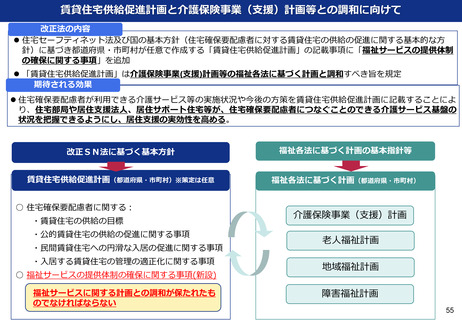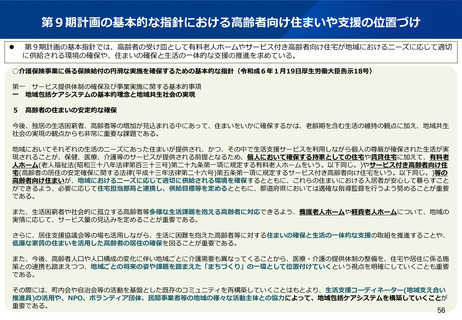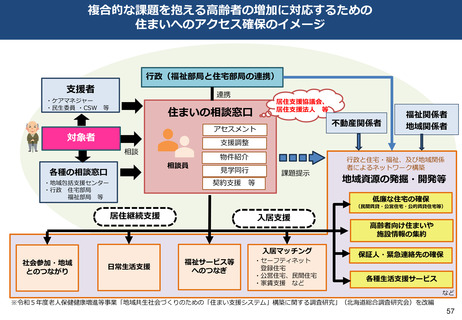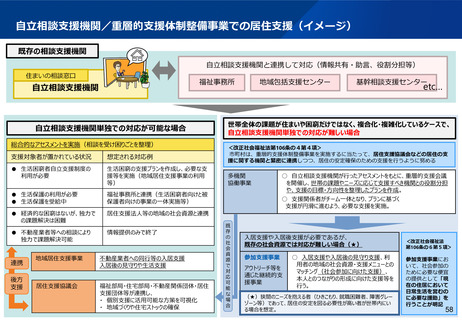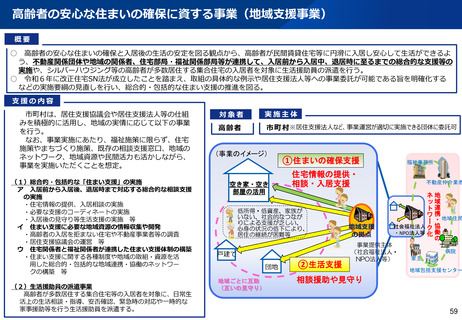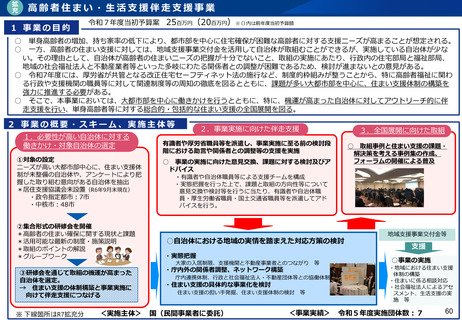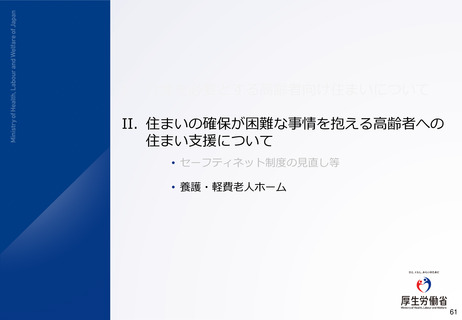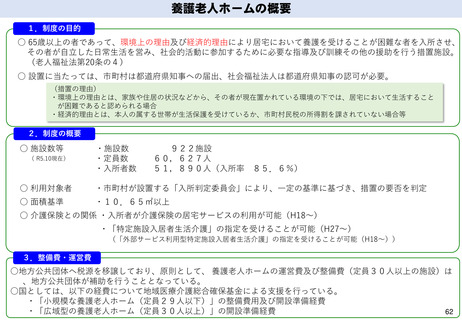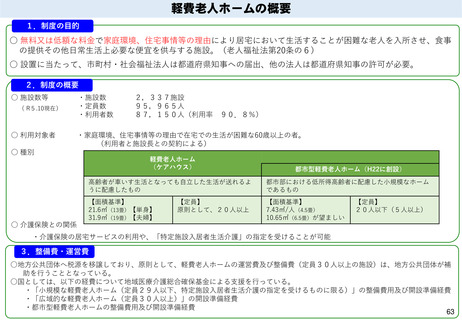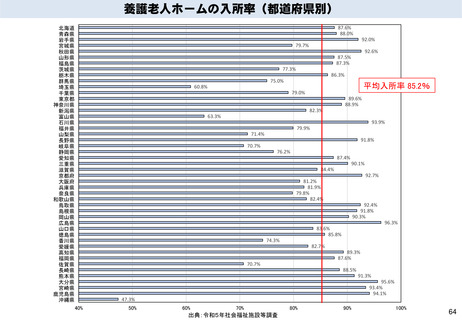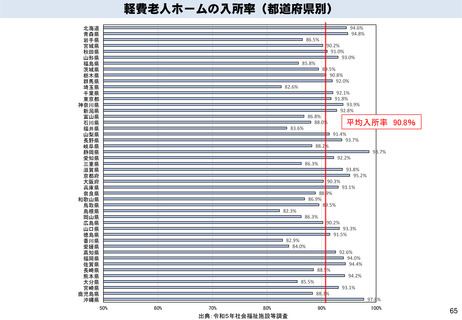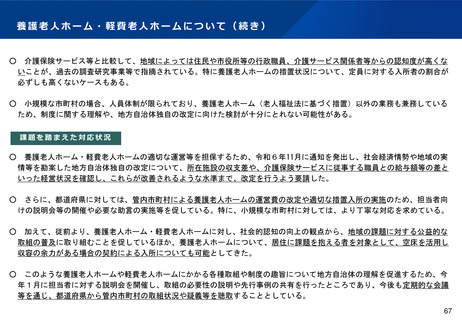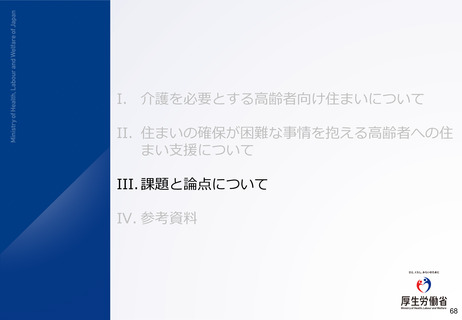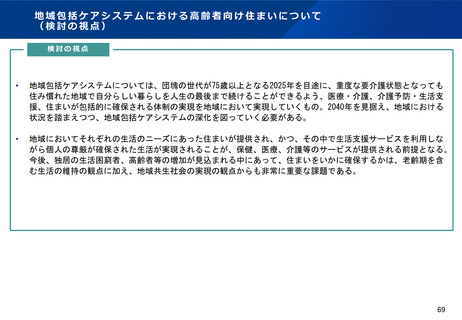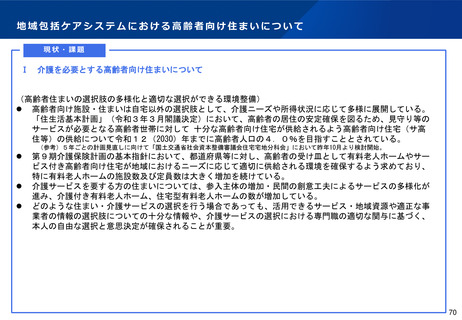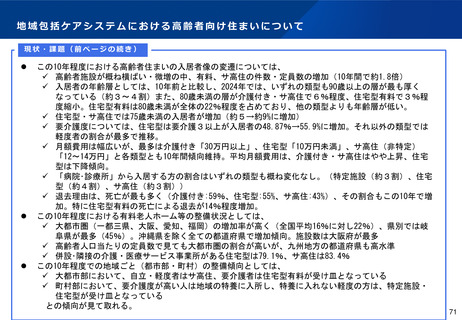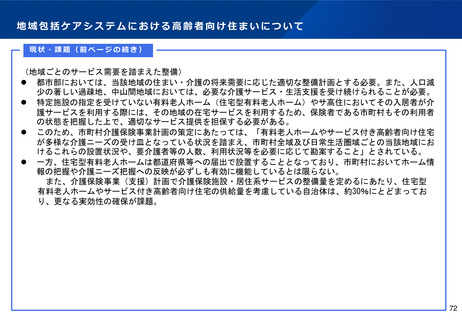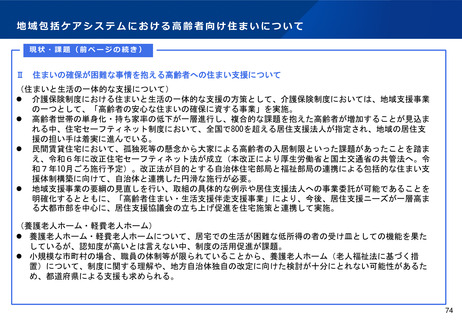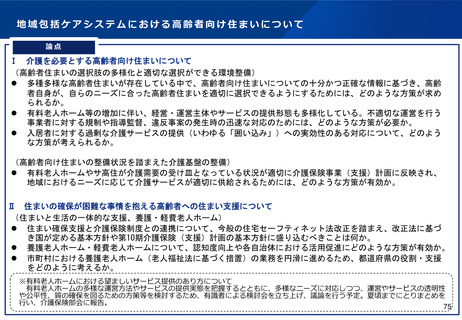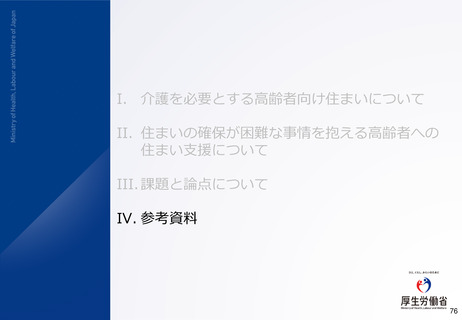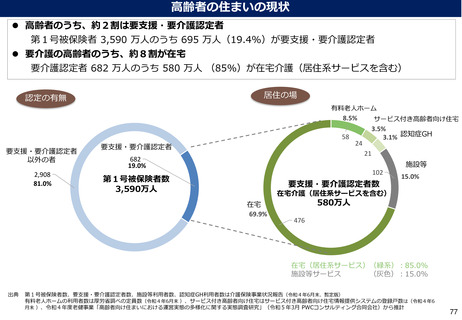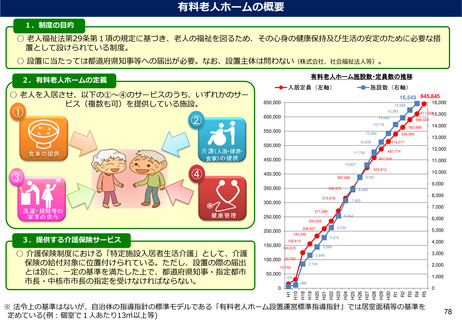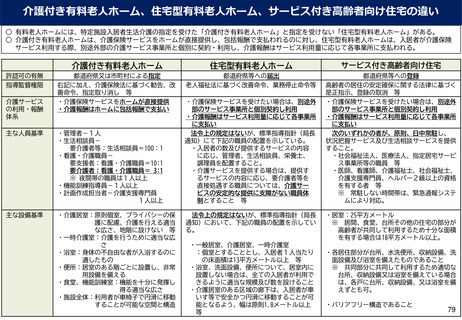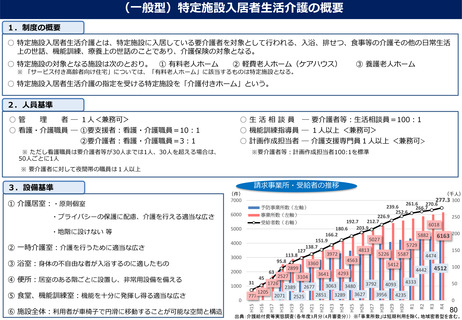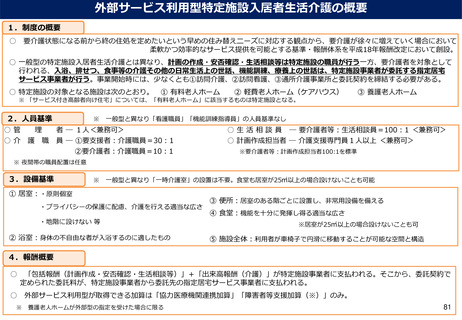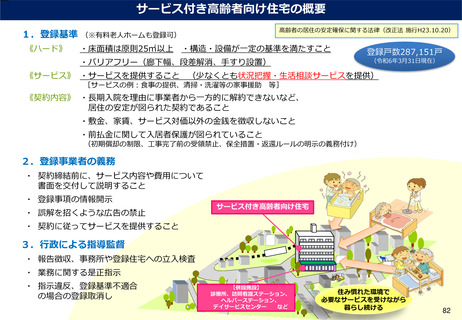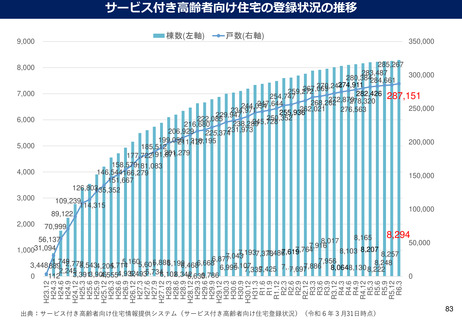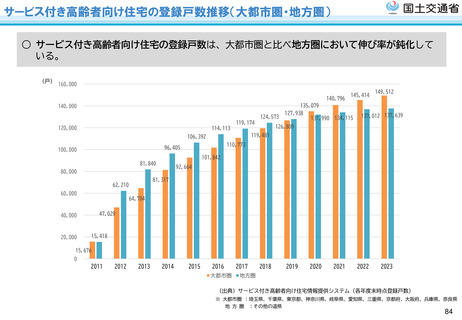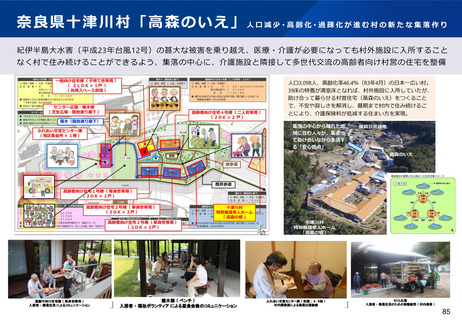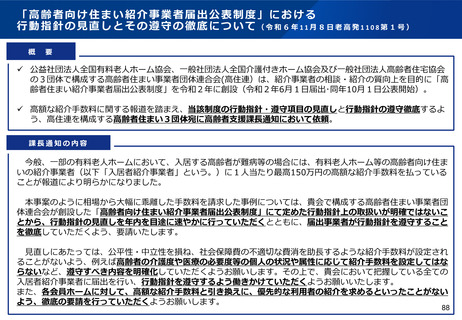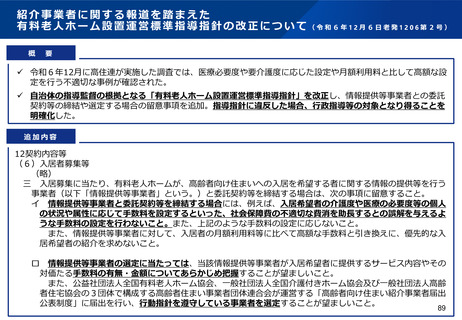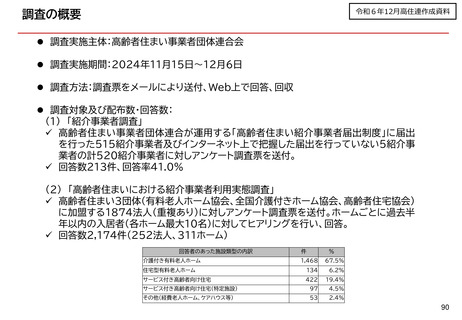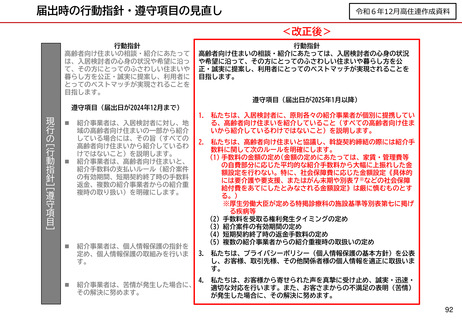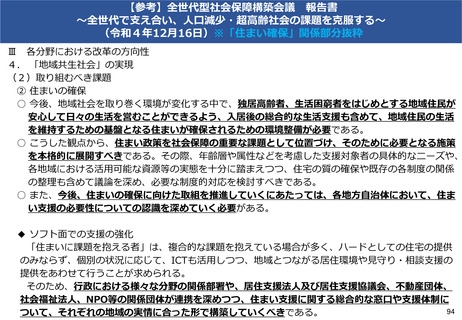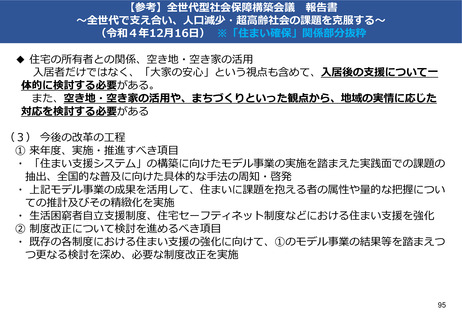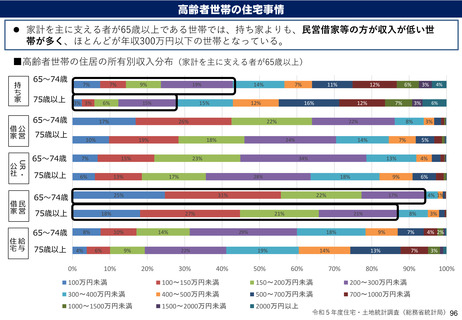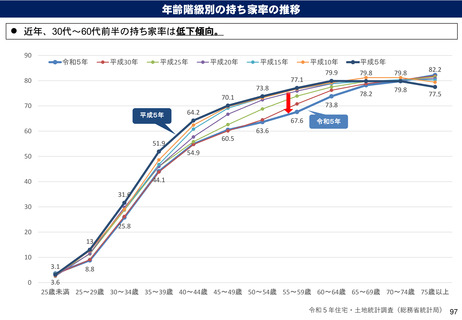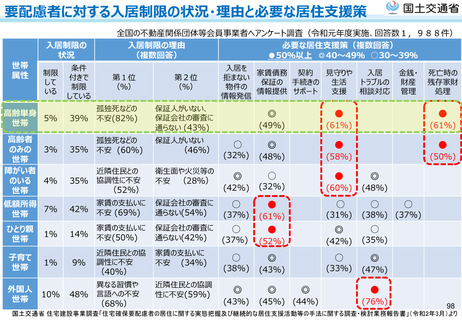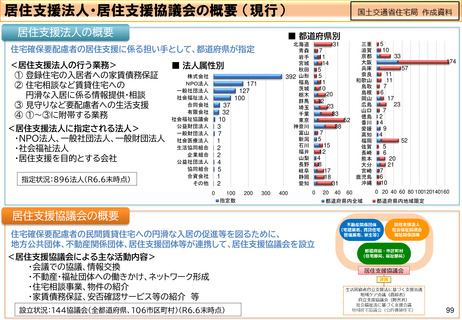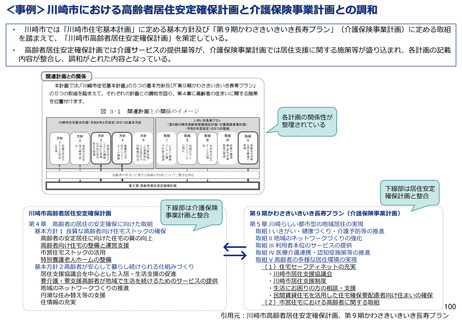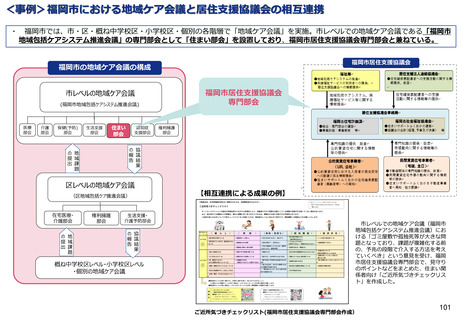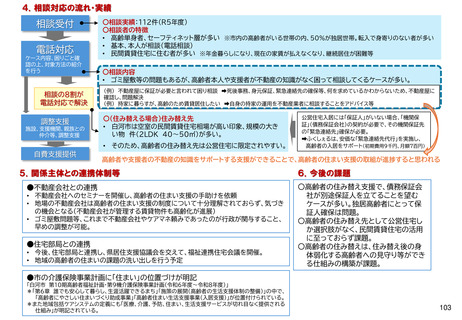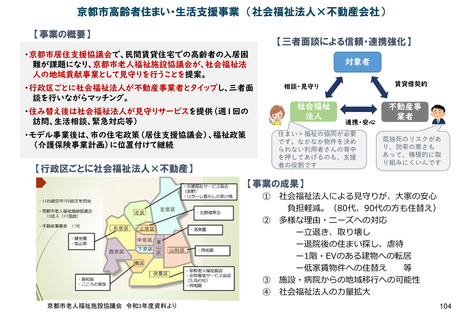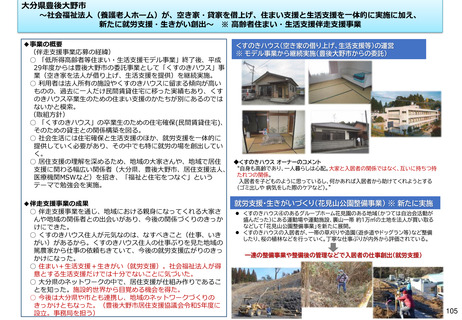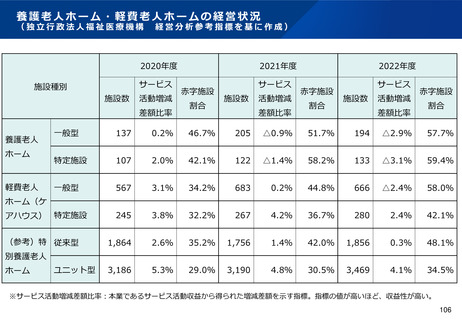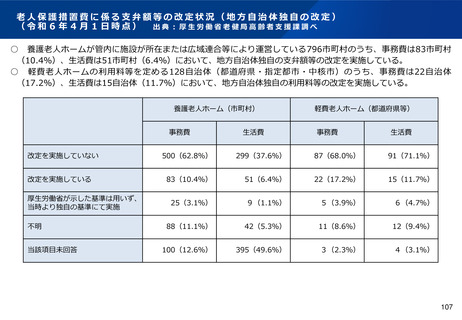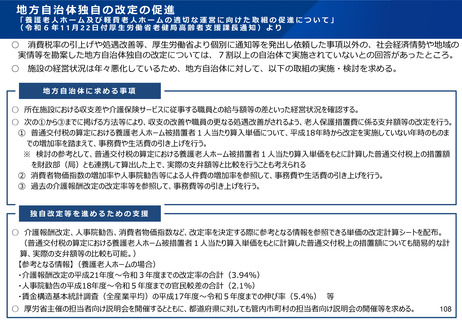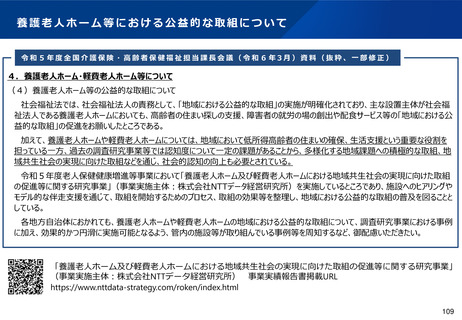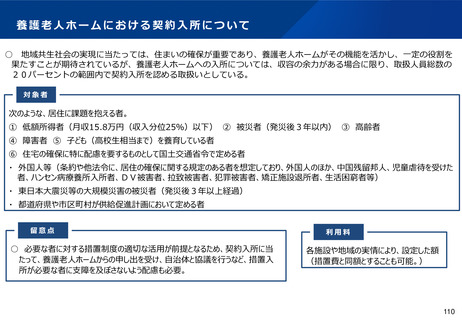資料1 地域包括ケアシステムにおける高齢者向け住まいについて (54 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53593.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第118回 3/17)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
【住宅セーフティネット法】
居住支援法人等が大家と連携し、
①日常の安否確認・見守り
②生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎ を行う住宅(居住サポート住宅)を創設
<現行>セーフティネット登録住宅(H29創設)
「大家が拒まないこと」、「その物件情報を公表すること」で要配慮者に住宅を供給
<改正法>居住サポート住宅の創設
福祉サービス(例)
「居住支援法人等※がサポートを行うこと」で要配慮者に住宅を供給
※サポートを行う者は 居住支援法人以外も可能
■低額所得者
自立相談支援機関
福祉事務所
①ICT等による安否確認
連携
特例
大家
要配慮者
①訪問等による見守り
居住支援法人等
高齢者福祉の
相談窓口
要配慮者の生活や心身の状況が不安定になったとき
②福祉サービスにつなぐ
要配慮者
居住支援法人等
・市区町村長(福祉事務所設置)等が国土交通省・厚生労働省の共同省令に基づき認定
・改修費等の補助により供給を促進(令和6年度予算)
特例
・家計把握や意欲向上の支援
・就労支援、生活保護の利用
福祉事務所
母子家庭等就業・
自立支援センター
基幹相談
支援センター
生活保護受給者の場合、
住宅扶助費(家賃)について
代理納付を原則化
■高齢者
・ホームヘルプ、デイサービス
■ひとり親
・母子・父子自立支援員
による相談、助言
・こどもの生活指導や学習支援
■障害者
・ホームヘルプ、デイサービス
・就労支援
※福祉の専門的な支援を必要とする場合は、要配慮者の
特性に応じて福祉サービスを実施する関係機関につなぐ
入居する要配慮者については認定保証業者(1.参照) が家賃債務保証を原則引受け
53