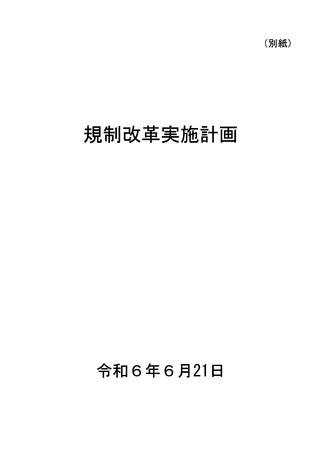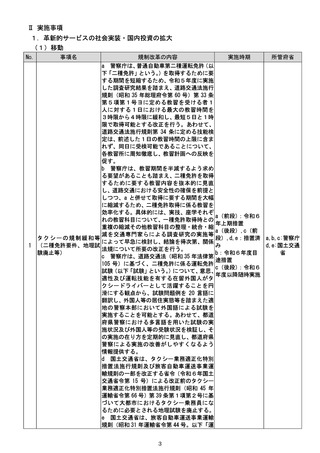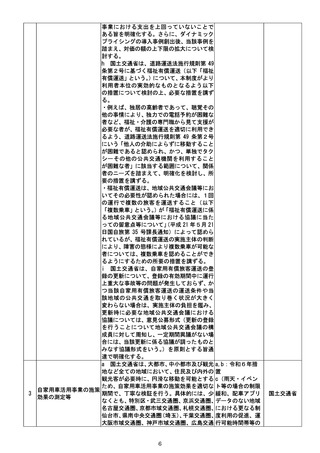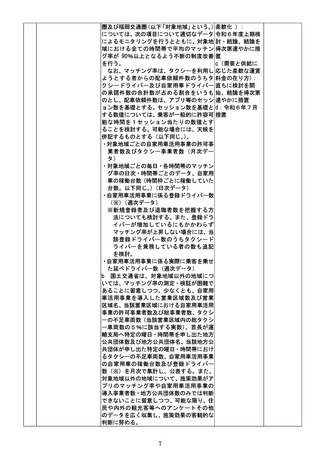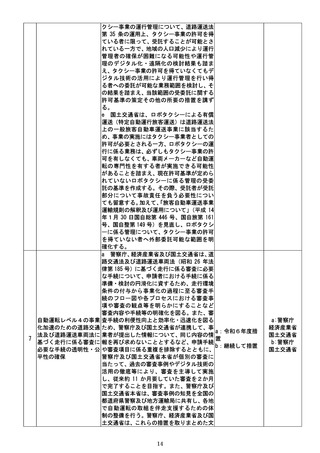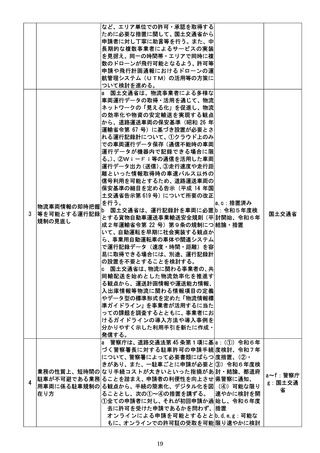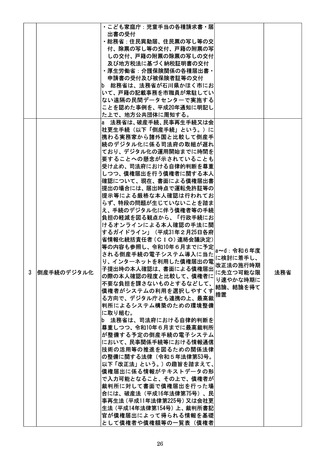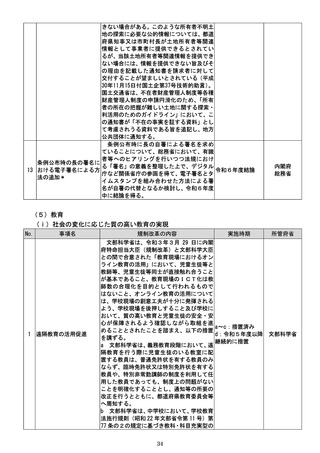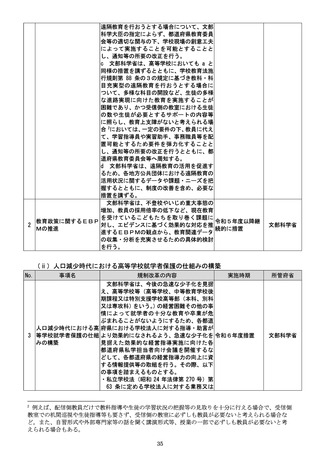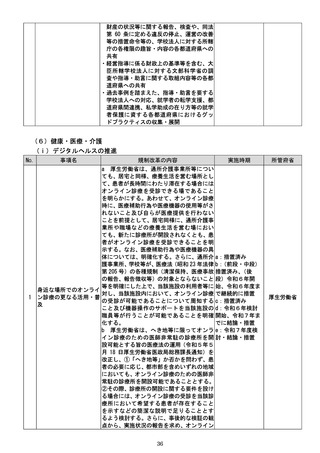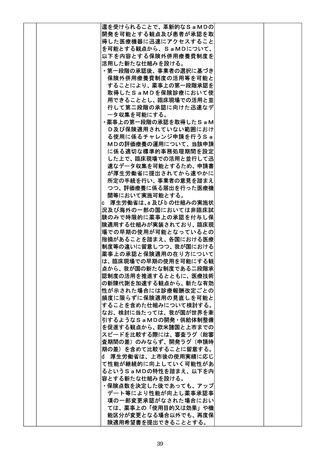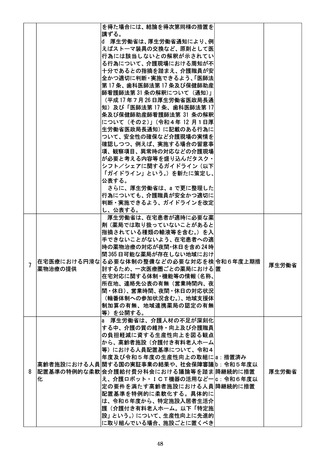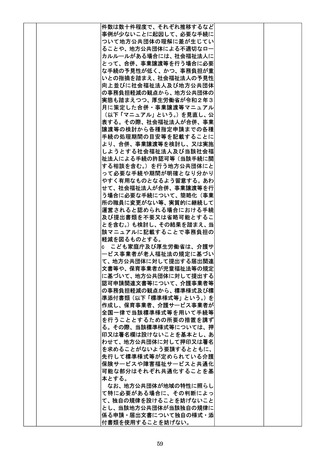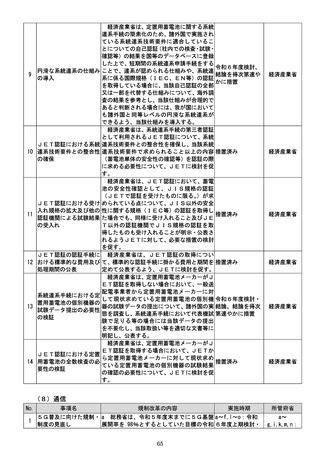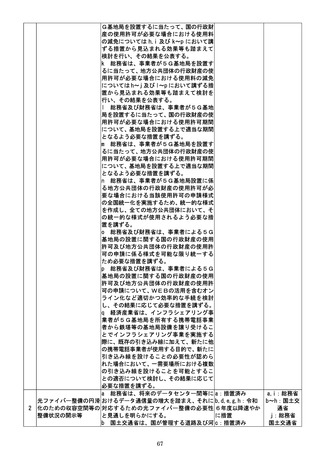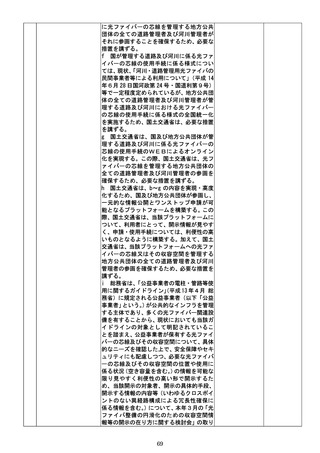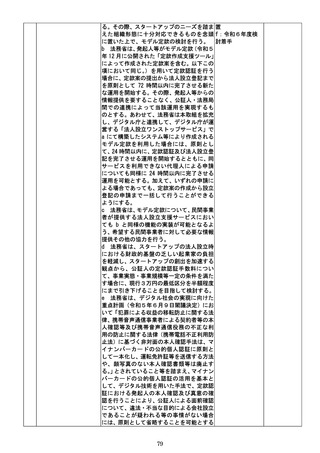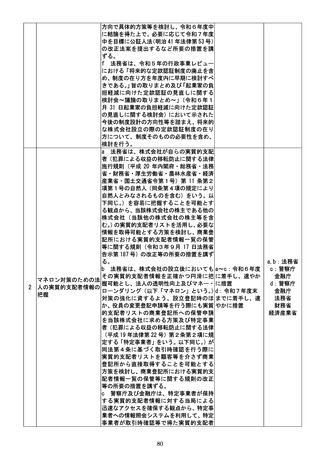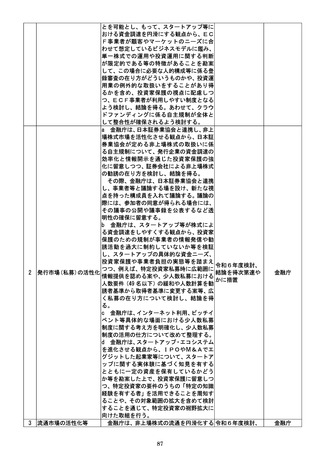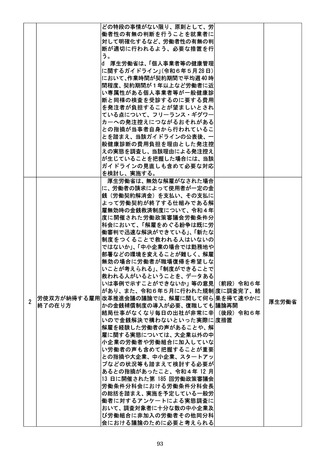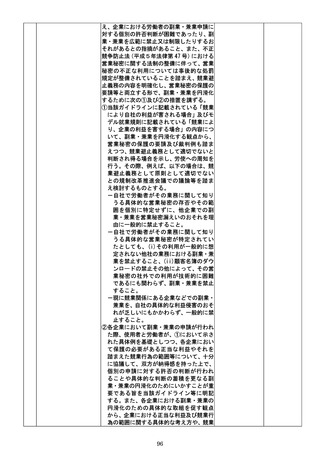よむ、つかう、まなぶ。
『規制改革実施計画』 (97 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
2
どの特段の事情がない限り、原則として、労
働者性の有無の判断を行うことを就業者に
対して明確化するなど、労働者性の有無の判
断が適切に行われるよう、必要な措置を行
う。
d 厚生労働省は、
「個人事業者等の健康管理
に関するガイドライン」
(令和6年5月 28 日)
において、
作業時間が契約期間で平均週 40 時
間程度、契約期間が1年以上など労働者に近
い専属性がある個人事業者等が一般健康診
断と同様の検査を受診するのに要する費用
を発注者が負担することが望ましいとされ
ている点について、フリーランス・ギグワー
カーへの発注控えにつながるおそれがある
との指摘が当事者自身から行われているこ
とを踏まえ、当該ガイドラインの公表後、一
般健康診断の費用負担を理由とした発注控
えの実態を調査し、当該理由による発注控え
が生じていることを把握した場合には、当該
ガイドラインの見直しも含めて必要な対応
を検討し、実施する。
厚生労働省は、無効な解雇がなされた場合
に、労働者の請求によって使用者が一定の金
銭(労働契約解消金)を支払い、その支払に
よって労働契約が終了する仕組みである解
雇無効時の金銭救済制度について、令和4年
度に開催された労働政策審議会労働条件分
科会において、「解雇をめぐる紛争は既に労
働審判で迅速な解決ができている」、
「新たな
制度をつくることで救われる人はいないの
ではないか」
、
「中小企業の場合では勤務地や
部署などの環境を変えることが難しく、解雇
無効の場合に労働者が職場復帰を希望しな
いことが考えられる」、
「制度ができることで
救われる人がいるということを、データある
いは事例で示すことができないか」等の意見 (前段)令和6年
があり、また、令和6年5月に行われた規制 度に調査完了、結
労使双方が納得する雇用 改革推進会議の議論では、解雇に関して何ら 果を得て速やかに
かの金銭補償制度の導入が必要、復職しても 議論再開
終了の在り方
結局仕事がなくなり毎日の出社が非常に辛 (後段)令和6年
いので金銭解決で構わないといった実際に 度措置
解雇を経験した労働者の声があることや、解
雇に関する実態については、大企業以外の中
小企業の労働者や労働組合に加入していな
い労働者の声も含めて把握することが重要
との指摘や大企業、中小企業、スタートアッ
プなどの状況等も踏まえて検討する必要が
あるとの指摘があったこと、令和4年 12 月
13 日に開催された第 185 回労働政策審議会
労働条件分科会における労働条件分科会長
の総括を踏まえ、実施を予定している一般労
働者に対するアンケートによる実態調査に
おいて、調査対象者に十分な数の中小企業及
び労働組合に非加入の労働者その他同分科
会における議論のために必要と考えられる
93
厚生労働省
どの特段の事情がない限り、原則として、労
働者性の有無の判断を行うことを就業者に
対して明確化するなど、労働者性の有無の判
断が適切に行われるよう、必要な措置を行
う。
d 厚生労働省は、
「個人事業者等の健康管理
に関するガイドライン」
(令和6年5月 28 日)
において、
作業時間が契約期間で平均週 40 時
間程度、契約期間が1年以上など労働者に近
い専属性がある個人事業者等が一般健康診
断と同様の検査を受診するのに要する費用
を発注者が負担することが望ましいとされ
ている点について、フリーランス・ギグワー
カーへの発注控えにつながるおそれがある
との指摘が当事者自身から行われているこ
とを踏まえ、当該ガイドラインの公表後、一
般健康診断の費用負担を理由とした発注控
えの実態を調査し、当該理由による発注控え
が生じていることを把握した場合には、当該
ガイドラインの見直しも含めて必要な対応
を検討し、実施する。
厚生労働省は、無効な解雇がなされた場合
に、労働者の請求によって使用者が一定の金
銭(労働契約解消金)を支払い、その支払に
よって労働契約が終了する仕組みである解
雇無効時の金銭救済制度について、令和4年
度に開催された労働政策審議会労働条件分
科会において、「解雇をめぐる紛争は既に労
働審判で迅速な解決ができている」、
「新たな
制度をつくることで救われる人はいないの
ではないか」
、
「中小企業の場合では勤務地や
部署などの環境を変えることが難しく、解雇
無効の場合に労働者が職場復帰を希望しな
いことが考えられる」、
「制度ができることで
救われる人がいるということを、データある
いは事例で示すことができないか」等の意見 (前段)令和6年
があり、また、令和6年5月に行われた規制 度に調査完了、結
労使双方が納得する雇用 改革推進会議の議論では、解雇に関して何ら 果を得て速やかに
かの金銭補償制度の導入が必要、復職しても 議論再開
終了の在り方
結局仕事がなくなり毎日の出社が非常に辛 (後段)令和6年
いので金銭解決で構わないといった実際に 度措置
解雇を経験した労働者の声があることや、解
雇に関する実態については、大企業以外の中
小企業の労働者や労働組合に加入していな
い労働者の声も含めて把握することが重要
との指摘や大企業、中小企業、スタートアッ
プなどの状況等も踏まえて検討する必要が
あるとの指摘があったこと、令和4年 12 月
13 日に開催された第 185 回労働政策審議会
労働条件分科会における労働条件分科会長
の総括を踏まえ、実施を予定している一般労
働者に対するアンケートによる実態調査に
おいて、調査対象者に十分な数の中小企業及
び労働組合に非加入の労働者その他同分科
会における議論のために必要と考えられる
93
厚生労働省